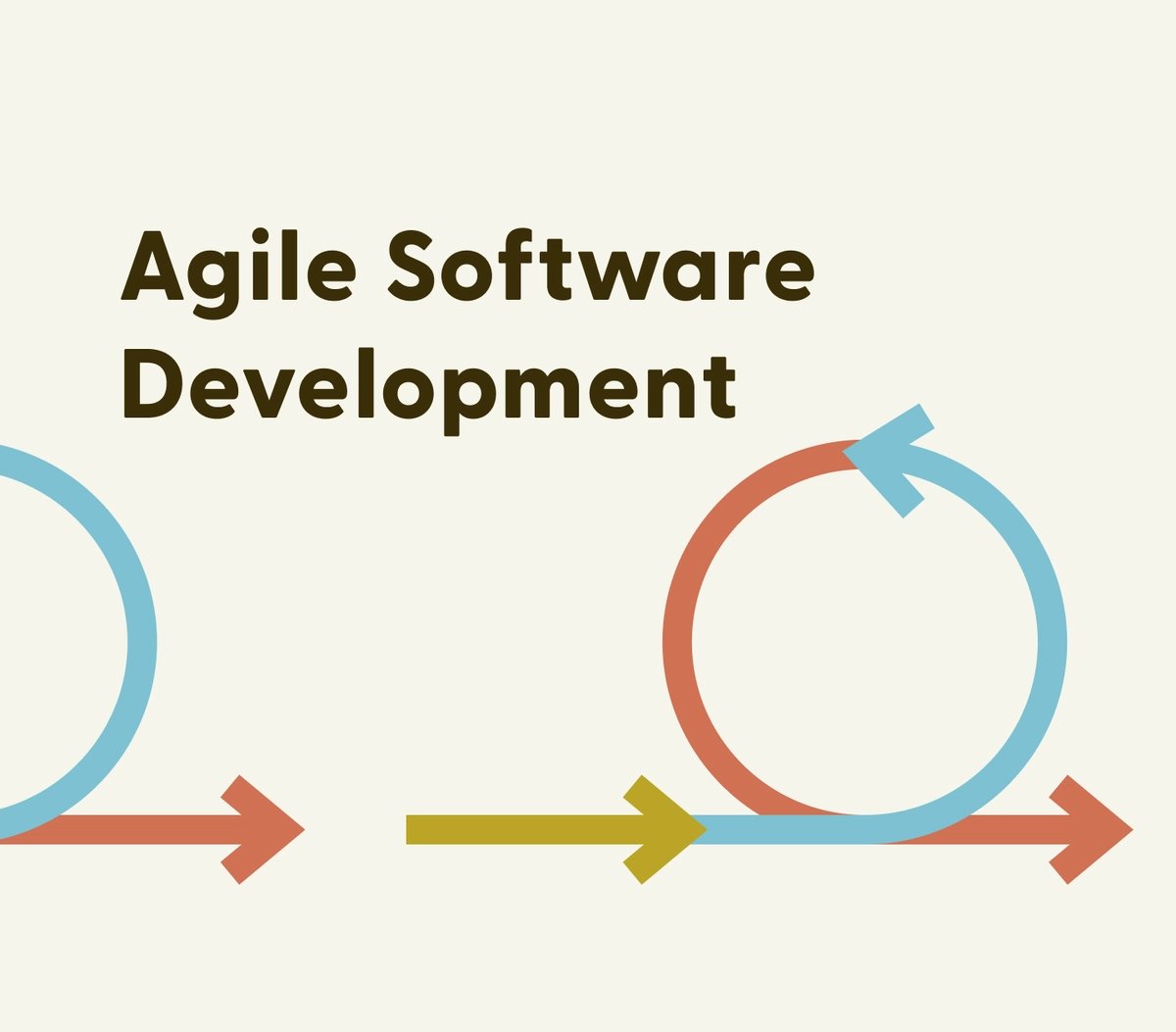
アジャイルとは?
アジャイルとは、もともと「素早い」「機敏な」といった英語からきている言葉で、ビジネスの文脈では、変わりゆく状況や要求に対して迅速に対応する能力や姿勢を指す言葉として使われます。アジャイルのアプローチは、アイデアやソリューションを次々と生み出す必要があるプロジェクトの企画工程や、臨機応変な対応が求められるプロダクトの開発工程などで活用されています。
アジャイルの精神は、計画やプロセスを厳格に固定せず、新たな情報や状況の変化に応じて方向性を調整しやすい環境を提唱しているものです。そのため、変化の激しい現代のビジネスシーンでも、幅広い業種で採用されている考え方となっています。
アジャイルと関連する用語
アジャイルを理解するためには、いくつかの関連用語を押さえておく必要があります。
アジャイル思考
アジャイル組織
ここでは上記2つの用語をご紹介します。
アジャイル思考
アジャイル思考とは、小さな単位での修正を繰り返し、完成度を高めていく考え方です。この思考法の特徴は、短期間でPDCAサイクルを速やかに回し、変化に対して柔軟に対応することです。アジャイルという言葉の元となっている「素早い」「機敏な」という言葉の通り、技術やビジネス環境が急速に変化する現代において、迅速な判断や変革を促すのに役立つ考え方とされています。
アジャイル思考を取り入れることで、プロジェクトやタスクにおけるフットワークの軽さを実現し、積極的なトライ&エラーを通じて解決策を見出すことが可能になります。このアプローチにより、プロジェクトは顧客満足度の高い製品やサービスの提供やスピード感を持って変化に対応する能力、チームの成長促進など、多くのメリットを享受できるようになります。
アジャイル組織
アジャイル組織とは、変化に迅速に対応できる柔軟な組織体系を指します。この概念は、ソフトウェア開発の現場で2000年代以降に広がったアジャイル開発の手法を、組織全体のマネジメントに応用したものです。アジャイルな組織では、変化に柔軟に対応し、ビジネスのプロセスを最適化するための継続的な改善を図ることが特長です。従来のピラミッド型組織と比較し、アジャイル組織は変化への対応速度や従業員の自主性の確保において、優れた特性を持っているとも言えます。
アジャイル組織を実現するには、各従業員が柔軟かつ迅速に動く必要があります。そのため、アジャイル組織ではフラットな組織階層が採用されることも多く、従業員は自律的に業務をおこなうための必要な権限を持つことが一般的です。この組織体系により、企業は市場や社会情勢の複雑な変化に素早く対応することが可能となります。
アジャイル開発とは?
アジャイル開発とは、システムやソフトウェア開発プロジェクトにおいて「素早く」かつ「柔軟に」対応することを目指す手法です。アジャイル開発手法のポイントは、プロジェクトを小さな単位で反復(イテレーション)分割し、各イテレーションごとに計画・開発・テスト・レビューをおこなうことです。このアプローチにより、開発プロセス全体でのリスクを最小限に抑え、変化する顧客ニーズや市場動向に迅速に適応できる柔軟性を確保します。
アジャイル開発では、進行中であっても新たな要求や問題が発生した際に、迅速に調整と改善をおこなうことが可能です。そのため、最終的にローンチする段階では改善を重ねた状態になっており、顧客の真のニーズを捉えている確率が高まります。
また、開発チームは定期的なミーティングを通じて進捗を共有し、問題点を早期に特定して対処する仕組みをとる必要があるため、アジャイル開発ではチームワークとコミュニケーションが重視されます。さらに、フィードバックを柔軟に受け入れて、製品が望む方向へ進むように、顧客とのコミュニケーションも重要です。
アジャイル開発とウォーターフォール開発の違い
アジャイル開発とウォーターフォール開発の違いは、プロジェクト管理と製品開発のアプローチに大きく表れています。
アジャイルは、プロジェクトを短いサイクルのイテレーションに分割し、各段階での優先順位付けと柔軟な対応を通じて、迅速な製品リリースと継続的な改善を目指します。このアプローチでは、変化する顧客の要求や市場の動向に素早く適応することが可能で、利用開始までの時間の短縮が実現できます。
一方、ウォーターフォール開発は、プロジェクト開始時にすべての要件が明確にされ、各段階の活動が詳細に計画される手法です。プロジェクトを連続する段階に分け、ひとつの段階が完了するまで次の段階に進まないよう調整します。そのため、初期段階での詳細な計画立案が必要となり、要件の変更や追加が発生した場合、プロジェクトの遅延やコスト増加につながりや�すいという課題があります。
アジャイルは変化に柔軟に対応し、顧客との継続的なコミュニケーションを重視するのに対し、ウォーターフォールは計画の安定性と予測可能性を優先します。このため、アジャイルは変化の激しいプロジェクトや、顧客の要求がプロジェクト途中で変化する可能性が高い状況に適しており、ウォーターフォールは要件が明確で変更が少ないプロジェクトに向いているとも言えます。
アジャイル開発とリーン開発の違い
アジャイル開発とリーン開発は、開発にあたって重視する思考や目的が異なります。
リーン開発の特徴は「顧客思考」であることです。プロダクトが市場に出る前から、顧客の反応をもとにした最小限の製品(MVP)の開発とリリースをおこなうことが特徴です。つまり、リーン開発は顧客の声を最優先に考えようとするアプローチであり、市場の顧客ニーズから開発することに重点を置いている手法と言えるでしょう。
一方、アジャイル開発は「プロダクト思考」であり、短いサイクルで「計画・設計・実装・テスト」を繰り返しながら開発を促進します。アジャイルでは、変化する顧客の要求に柔軟に対応しながら、継続的な製品の改善と機能の追加をおこないます。
つまり、リーン開発は市場と顧客のニーズにもとづいて価値を最大化することに注力しており、アジャイル開発は製品の迅速なリリースと継続的な改善で優れたプロダクトを作成することに焦点を置いている点に違いがあるのです。
アジャイル手法の種類
アジャイル開発にはさまざまな手法があり、プロジェクトの特性やチームの状況に応じて適切な方法を選択できます。主なアジャイル手法としては、以下のものが挙げられます。
スクラム
カンバン
XP(エクストリーム・プログラミング)
FDD(ユーザー機能駆動開発)
TDD(テスト駆動開発)
ここでは、各手法の詳細な特徴と適用シーンについて解説します。
スクラム
スクラムは、アジャイル開発手法のひとつで、短期間のスプリントと呼ばれる反復期間を中心に、顧客と連携しながら継続的なフィードバックにもとづいた開発を進める手法です。プロダクトバックログと呼ばれる機能リストにもとづき、スプリントごとに開発する機能を決定します。また、スプリントレビューで開発成果を顧客に確認してもらい、フィードバックを得る点が特徴とも言えます。
メリットは、顧客のニーズに迅速に対応でき、変化に柔軟に対応できる点です。デメリットは事前計画が重要になることや、顧客との密接な連携が必要になるためチームメンバーのスキルと経験が��求められることにあるでしょう。
カンバン
カンバンは、タスクの可視化に重点を置いたアジャイル開発手法のひとつです。作業の進捗状況をWIP(Work In Progress)と呼ばれる作業中のタスク数で制限することで、効率的な開発を目指す手法です。具体的には、開発工程のタスクを付箋やカードに書き出し、ボードと呼ばれる可視化ツールに貼り出し、作業の進捗状況に応じてタスクを列間で移動させて管理します。
メリットとしては、チームメンバー全員がプロジェクトの進捗を一目で把握でき、作業の流れがスムーズになることです。また、WIPを制限することで、作業の集中と効率化が図れます。デメリットは、タスクの粒度を誤るとスムーズな運用につながらない点であり、管理者には高い判断力が求められることです。
XP(エクストリーム・プログラミング)
XP(エクストリーム・プログラミング)は、高い品質と生産性を目指すアジャイル開発手法のひとつです。短い開発サイクルと頻繁なリリースを特徴とし、顧客のフィードバックを迅速に製品に反映させます。XPの手法では、ペアプログラミング・テスト駆動開発(TDD)・リファクタリングといった技術を通�じて、コードの品質を維持しながら変更に柔軟に対応します。
メリットは高品質なソフトウェアを開発できる点や、顧客満足度が高くなる点です。しかし、デメリットとして開発コストが高くなりやすいため、すべてのプロジェクトに適しているわけではないといった点が挙げられます。
FDD(ユーザー機能駆動開発)
FDD(ユーザー機能駆動開発)は、ユーザーにとって重要な機能をまず開発し、段階的に機能を追加していく手法です。このアプローチでは、プロジェクトを小さな機能単位に分割し、各機能の設計とビルドを短期間でおこないます。開発プロセスはモデリング、機能リストの作成、機能ごとの計画と開発、ビルドの公開のステップからなります。各機能は個別に開発され、短期間での成果物の提供を目指します。
メリットとしては、保守性の高い手法となるため、とくに大規模なチームや複雑なプロジェクトにも対応できるという点です。デメリットとしては、事前の計画に時間がかかる点が挙げられます。
TDD(テスト駆動開発)
TDD(テスト駆動開発)は、コーディング前にテストケースを��先に書くことから開発を始める手法です。この手法では、まず失敗するテストを作成し、そのテストをパスする最小限のコードを書いてから、コードのリファクタリングをおこないます。このサイクルを繰り返すことで、品質の高いコードの作成と、要件の明確化を同時に進められます。この手法は、継続的な品質保証が求められるプロジェクトに適しています。
メリットとしては、バグの発生を抑制できることや、コードの保守性が向上する点です。デメリットは、テストコードを書くための時間と労力が必要になることが挙げられます。
アジャイル開発に組み合わせるデザイン思考について
デザイン思考とは、デザイナーやクリエイターの手法を応用し、人々のニーズや技術の可能性を探ることで、市場機会を創出する思考方法です。デザイン思考の特徴として、ユーザー中心主義のアプローチであることが挙げられます。デザイン思考では、 ユーザーのニーズや感情に深く共感することで、真の問題を捉えます。また、プロトタイピングやテストを繰り返しながら最適な解決策を探っていく点や、チームメンバーや関係者からの意見を取り入れ、多角的な視点から考えることを大切するという特徴があります。
このデザイン思考とアジ�ャイル開発を組み合わせることで、製品開発はユーザー中心のアプローチとなり、ニーズに沿った開発が可能になります。PDCAサイクルを高速に回しながら、ユーザーの声を直接製品開発に反映させることになるため、よりリアルなニーズにもとづいた製品開発が実現します。また、プロトタイピングとテストを繰り返すことで、製品の品質と顧客満足度を段階的に高めていくことも可能です。
ユーザーファーストなプロダクトや製品を、スピーディ―に市場に投入していきたいケースでは、このデザイン思考とアジャイル開発を掛け合わせた戦略が有効であると言えます。
アジャイルについて学べる書籍紹介
アジャイル開発を深く理解し、実践するためには、基�本から応用まで幅広い知識が必要です。ここでは、初学者がアジャイルの概念を理解するのに適した書籍をピックアップして紹介します。
いちばんやさしいアジャイル開発の教本 人気講師が教えるDXを支える開発手法
SCRUM BOOT CAMP THE BOOK
正しいものを正しくつくる
アジャイル開発に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
いちばんやさしいアジャイル開発の教本 人気講師が教えるDXを支える開発手法
『いちばんやさしいアジャイル開発の教本 人気講師が教えるDXを支える開発手法』は、アジャイル開発をこれから学びたい人や実践のヒントを求める現場の開発者に最適な一冊です。日本のソフトウェア開発現場に即した内容で、アジャイル開発の基本的な概念から実践方法までをわかりやすく解説されています。また、DXを推進する現代において、アジャイル開発がなぜ重要なのか、その必要性と具体的な導入方法が豊富な図とともに紹介されている点が特徴です。アジャイル開発を始めるきっかけを探している人、実践に移したいが具体的な方法がわからない人にとって、とくにオススメの一冊です。
SCRUM BOOT CAMP THE BOOK
『SCRUM BOOT CAMP THE BOOK』は、アジャイルの手法のひとつである「スクラム」をはじめて導入する人々に向けた実践的なガイドブックです。理論だけでなく、架空の開発現場を題材にした実際のプラクティスを詳細に説明することで、スクラムの基礎から応用までわかりやすく解説しています。スクラムを導入したいがうまくいかないと感じている人にも、新たな気づきと解決策につながる情報となるかもしれません。
正しいものを正しくつくる
『正しいものを正しくつくる』は、ソフトウェア開発やデジタルプロダクト制作における新しいアプローチを提案する一冊です。従来の開発プロセスが正解を前提としていたのに対し、この本では不確実性が高い現代の開発現場において、どのように共創を実現し前進していくかを探求しています。アジャイル開発を基盤としながら、エンジニアやデザイナー、クラ�イアントが一体となって正しいプロダクトを創り上げるための考え方や行動指針を、豊富な事例とともに解説しています。
まとめ
本記事では、アジャイルの基本概念から、その多様な手法や実践に役立つ書籍までを網羅的に紹介しました。
アジャイルは「アジャイル開発」という言葉が一般的であることから、エンジニア向け用語として認識されていることもありますが、その概念はデザイナーにとっても重要な思考フレームワークと言えます。デザイン思考との掛け合わせでも解説した通り、より良いものを作るためには、顧客の反応を見ながら繰り返す試行錯誤が必要です。市場に求められるデザイン制作やプロダクト開発をしたい方は、本記事の内容を参考にしていただければ幸いです。












