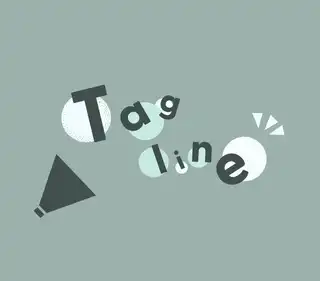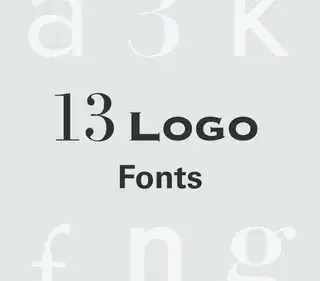ブランディングとは?世界観を作ることで価値を生み出す。
ブランディングは、近年ラグジュアリービジネスのみならず、さまざまなビジネスにおいて重要な戦略となっています。この記事では、ブランディングの基本的な概念やプロセスをはじめ、Webサイトやモバイルアプリなどのデジタルデザインにおけるブランドデザインの考え方について紹介します。
ブランドとは?消費者が特定の企業やサービスから連想するイメージ
ブランドとは、消費者が特定の企業やサービスから連想するイメージのことです。企業はこのブランドを意図的に作り出すことによって、消費者に対して物理的な商品やサービスの提供にとどまらず、企業の発信する「世界観」を体験させることで、競合他社との差別化やファン獲得を狙います。
ブランディングとは?「ブランド」を作り出すためのプロセス
ブランディングとは、この「ブランド」を作り出すためのプロセスのことです。かつては、ブランドというと、ファッション業界のラグジュアリーブランドなどの高級感を演出するような企業で使われるものというイメージがありましたが、さまざまな業界で競合他社との「差別化」が重要となった現在では、高級路線のみならず、「コストパフォーマンス」や「親しみやすさ」など多様なイメージを消費者に与えるための戦略としてブランディングが行われています。
ブランディングデザインとは?視覚的な情報によるブランディング
視覚的な情報はブランドイメージを消費者に伝える上でとても有効な手段です。色彩心理学という分野があることからもわかる通り、色や形などのデザインは人に対して特定の印象を与えることができます。ブランディングデザインとは、このような企業や商品に関する視覚的な情報を操作することを通して、ブランドイメージを消費者に伝える戦略のことを意味します。
実質的な価値以上のものを売る必要性がある時代におけるブランディングの重要性
かつては、「ブランド」というと「高級な時計」「ブランドバッグ」などを連想したかもしれません。これは、ブランディング戦略が「実質的な価値以上のものを売る必要がある場合」に有効な戦略であったからではないでしょうか?例えば、ファッション業界の場合は、実質的な価値である「服・アクセサリー」といった「もの」を販売するだけではなく、そのブランドの発信する「ライフスタイル」という価値を販売しています。
しかし、経済や物流のグローバル化、そしてIT技術の発展によってさまざまな業界で競争が激化した現在では、ファッション業界以外でも「実質的な価値以上のもの」を売る必要性が出てきました。例えば、かつては街に一店舗しかなかったイタリアンレストランが、今やフランチャイズやUberEatsなどの多様な競合他社と顧客を奪い合うような状況になっていますね。もちろん、それぞれのレストランの提供する料理の質にも差はあるでしょう。しかし、ほとんどの消費者の視点からこれらはどれも「��イタリアンレストラン」です。このように似た商材やサービスを扱う企業がごった返す状況で、差別化を図るための戦略が「ブランディング」なのです。
アウターブランディング: 消費者に向けたブランドイメージの構築
このような、一般的にブランディングといった場合にイメージされることが多い、消費者に向けたイメージ戦略のことを、アウターブランディングといいます。競合他社が多い状況で、自社のポジショニングを明確にした上で、そのイメージを消費者に伝える手段として使われるのがアウターブランディングです。
インナーブランディング: 社内関係者にとってもブランディングは重要となる
アウターブランディングが「外向きの」ブランディングであるのに対し、「内向きの」ブランディングである「インナーブランディング」というものも存在します。インナーブランディングとは、企業や商品に関わる従業員に、企業の理念やビジョンを示すことによって、企業理念に寄り添って働いてもらうための戦略です。
近年、企業の方向性と従業員の求める働き方や業務内容のミスマッチによって、高い離職率に悩まされる企業も多いでしょう。日本でも「終身雇用」という考えがなくなり、転職も一般的になった今では従業員に「長く働いてもらう」ことは容易ではなくなりました。もちろん、競合他社と比べて高い給与を出すことで離職率を下げることも考えられるでしょうが、人材獲得競争もグローバル化していく中では、これにも限界があります。そこで、企業としての方向性を明確にすることで、雇用時のミスマッチを回避し、従業員の満足度を上げるような戦略として企業の内部的なブランディングである、インナーブランディングに注目が集まっています。
従業員がその企業で働いていることを誇りに思っているような場合、インナーブランディングがうまくいっている証拠ですね。もちろん、アウターブランディングと同じく発信するブランドイメージに実態がともなっていなくては上手くいきません。高級なイメージでブランディング戦略を行なっても、実際の商品の質が低くては意味がないですよね。インナーブランディングにおいても、実態がともなわないようなブランディングをおこなってしまうと、「やりがい搾取」と言われるような状況に陥ってしまいます。
ブランディングのプロセス
ブランディングのプロセスには大きく分けて2つの重要なフェーズがあります。一つ目は、「ブランドアイデンティティの構築」です。市場調査や自社の現状を分析した上で、競合他社に対するポジショニングや、将来あるべき姿をイメージし、ブランドの核となる「コンセプト」を打ち出します。そしてもう一つのフェーズが、そのブランドコンセプトの「浸透」です。ブランドイメージを決めただけでは、消費者に影響を与えることはできませんよね。この「ブランド浸透」の戦略も業界によってさまざまですが、一夜に成功するようなものではなく、時間をかけて段階的に育てていくようなプロセスとなります。
ブランドアイデンティティ構築の5ステップ
1. 環境分析
ブランドアイデンティティを構築するためにまず必要となるのが、企業やサービス、プロダクトの置かれている状況を明確に把握することです。「ターゲットとなる市場ではどのような競合製品が存在するのか」「消費者のニーズは何か」「今後その市場に起こる可能性のある変化は何か」など多角的に現在の状況を把握しましょう。ここで明確に市場を把握できればできるほど、次のフェーズでの差別化が図りやすくなります。
ブランド戦略における環境分析には主に以下の3つのフレームワークが使われます。
PEST分析: マクロな視点で中長期的な環境�の変化を分析
PESTとは、「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」の頭文字を取ったもので、ビジネスの置かれた環境について多角的に分析するためのフレームワークです。PEST分析でのポイントは、現在の状況をまとめるだけではなく中長期の視点で5年後くらいまでに起こる可能性のある環境変化をリストアップし、それらが自社のビジネスに与える可能性のあるインパクトについて把握することです。ビジネスの内容によっては、「Environmental(地球環境)」と「Legal(法律)」の2つを加えてPESTEL分析とすることもあります。
3C分析: 市場を構成する3要素をそれぞれ分析
3Cとは、「Customer(市場・顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の頭文字を取ったもので、環境分析において重要となる3つの観点を整理・分析するために有効なフレームワークです。まずはこの3つのCについて、収集した情報をポストイットなどで洗い出していくと良いでしょう。
SWOT分析: 自社の戦略の土台となる
SWOTとは、「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」の頭文字をとってもので、PEST分析と3C分析において把握した市場において、自社がどのような状況に置かれているかを明確にするためのフレームワークです。この4つの観点で情報をまとめたら、それぞれの項目を掛け合わせたクロスSWOT分析を行います。例えば、「強み x 機会」で「機会をとらえて強みを最大限に生かす戦略」を考えるといった形で、具体的な戦略につながるようになります。
2. ブランドポジショニング
自社の置かれた状況が明確になったところで、市場における自社の立ち位置を明確にする「ブランドポジショニング」を行います。競合他社に対して自社がどのようなイメージを狙うのかをポジショニングマップを作成して視覚化するとイメージが共有しやすいです。ポジショニングマックのxy軸には、「価格帯」「カジュアル・ラグジュアリー」など、顧客体験にとって重要となる視点を当てはめてみましょう。
また、このブランドポジショニングと一緒に行いたいのがSTP分析で��す。STPとは、「Segmentation(セグメンテーション)」「Targeting(ターゲティング)」「Positioning(ポジショニング)」の頭文字をとったもので、具体的なターゲット市場を定義するためのフレームワークです。前述の3C分析では、広い視点で関連市場の情報を集めますが、このSTP分析では逆に市場を細分化することで狙うターゲット層と自社のポジションを明確に定義します。
3. ブランドコンセプト定義
ここまでで、ブランドがビジネス戦略として目指すべき方向性が明確になりました。ここで改めて、「なぜその市場でサービスを提供するのか」について考えてみましょう。そのサービスを提供することで、顧客に何を与えたいのか、世の中をどう変えたいのかといったストーリーが重要になります。「売りたいから売る」だけのビジネスでは、ブランド戦略で成長するのは難しいです。「なぜ」を明確にした上で「何」をするのかを「ブランドコンセプト」として言葉にしましょう。
Tesla’s mission is to accelerate the world’s transition to sustainable energy.
https://www.tesla.com/about
(世界の持続可能エネルギーへの移行を加速する)
例えば、電気自動車で有名なテスラ社のブランドコンセプトは、「世界の持続可能エネルギーへの移行を加速する」です。もちろん、テスラがビジネス的・経済的な戦略として「電気自動車の開発・販売」に特化することに可能性を見出していることは明らかです。しかし、そのブランドの根幹となるブランドコンセプトとしては、「なぜそれを行うのか」という視点を全面に押し出しています。このブランドコンセプトを浸透させることが一貫性のあるブランドメッセージを伝えることにつながるのです。
4. ムードボード
ムードボードは、言葉としたブランドコンセプトをデザインに落とし込む初めの一歩です。ムードボードとは、デザイン制作において、アイデアやコンセプトをまとめてコラージュしたものを意味します。ムードボードには、画像、スクリーンショット、色、タイポグラフィー、形、イラスト、パターンなど視覚的情報に関するさまざまなものを含めることができます。
ブランディングのプロセスでムードボードを作る際の重要なポイントは、「ブランドコンセプトを視覚的に表現するとどのようなものになるか」を模索することです。例えば、「エレガント」というコンセプトがあっ��たときに、「そのブランドにとってのエレガントを表現する色味は何色なのか」といったように、ブランドコンセプトの表象としてムードボードを作りましょう。デザイン制作の現場では、ムードボードがプロジェクト担当者の「好みのデザインの寄せ集め」のようになってしまうこともあります。意識的にそのような状態を避けるためには、ここでも「なぜその色なのか」「なぜその画像なのか」といった「ブランドコンセプトの繋がり」を意識しながらムードボードを作成すると良さそうです。
5. ブランドアセットの制作
ブランドアセットとは、ブランドのコンセプトを具体的なデザインとして表現する際の土台となるデザインアセットのことです。具体的には、ブランドで使用するロゴ、カラーパレット、スローガン、イラストレーション、タイポグラフィーなどの定義がこれに当てはまります。アプリや広告クリエイティブなど、ブランドと消費者の具体的なタッチポイントとなるものを制作する際に、このブランドアセットに沿った形で制作することとなります。
ブランドの浸透
ブランドコンセプトが定義され、ブランドアセットも揃った段階で、残るはそのブランドを浸透させることです。とはいえ、この浸透プ��ロセスが一番難しく、いくら素晴らしいブランドアセットを持っていたとしても一夜にブランドは浸透しません。
ここで重要となるのが、「組織の内部からのブランドの浸透」です。アウターブランディングの一環として、それぞれの広告クリエイティブやWebサイトのデザインにブランドアセットを当てはめる視覚的なブランド表現ももちろん重要です。しかし、ブランドを浸透させ守っていくためには、内部の人間がそのブランドコンセプトについて深く理解し、共感しているかがとても重要なポイントとなります。ブランドイメージは、サービスと消費者をつなぐ「タッチポイント」すべてを使って表現するべきもので、従業員の振る舞いや企画の方向性などそのブランドに関連した一つ一つの「タッチポイント」がブランドコンセプトを表現する媒体となります。このためには、企業やサービスを支え、ビジネスを実行する一人一人がブランドのストーリーについて深く理解していることが必要不可欠となります。
このブランドの浸透を成功させるために、組織内で共有したい考え方に「ゴールデンサークル理論」があります。ゴールデンサークル理論とは、「Why(なぜ)を語ることが人の行動に最も影響を与える」という理論です。企業活動において、この「なぜ」にあたるのがブランドアイデンティティやコーポレートアイデンティティです。これらを全面に押し出すことが「共感」を呼び、消費者の行動を促すことにつながるのです。
デジタルデザインにおけるブランディング
モバイルアプリや、WebサイトなどのITサービスにおいてもブランディングの重要性は変わりません。WebデザイナーやUIデザイナーも、企業のコーポレートアイデンティティ(CI)やブランドアイデンティティ(BI)をもとに具体的な製品となるアプリなどをデザインすることになります。Webサイトをデザインするときに、ブランドガイドラインを参考にすることもよくあると思います。
デジタルデザインにおけるブランディングの難しさ
しかし、アプリなどのデジタルプロダクトがユーザー体験の中心となるようなビジネスでは、アプリのデザインとしてブランドデザインを表現することはできますが、それだけでユーザーにブランドイメージを伝えることは難しいです。
「ブランドの浸透」で解説したとおり、ブランドイメージを消費者に伝えるためには、一貫性のあるヴィジュアルや言語、体験を提供し続ける必要があります。これらの消費者との接点を「タッチポイント」と呼びます。しかし、モバイルアプリやWebサイトがサービスの中心となるようなビジネスでは、このタッチポイントの数が少ない傾向があり、ブランドイメージの発信がやや難しくなるのです。ここでは、そんなデジタルデザインの分野でブランド浸透を行うための戦略を紹介します。
タッチポイントの細分化
例えば、ユーザーとのタッチポイントがモバイルアプリのみというケースも多々あると思います。�そのような場合には、「アプリ」という大枠でタッチポイントを定義するのではなく、アプリ内の細かなタッチポイントを洗い出して、それぞれにブランドコンセプトを表現できる方法がないか考えてみると良いです。
例えば、
フラッシュメッセージ
オンボーディング
App Storeのレビューへの返信
などは、言語としてブランドコンセプトを発信するための良い機会です。これらのコンポーネントでの言葉遣いについてブランドコンセプトを表現するにはどうしたら良いかなど、検討してみると良さそうです。
他にも、
インタラクション
アニメーション
もブランドコンセプトを伝える良い機会です。「楽しさ」「未来感」「真面目さ」などのコンセプトによって作るアニメーションにも違いが出てきますね。このような細かなタッチポイントを洗い出して、ブランドコンセプトに合った形で再定義することでデジタルプロダクトの中だけでも多様なブランド表現ができることに気づくと思います。
タッチポイントを生み出す
デジタルデザインにおいて、ブランドイメージを浸透させるもう一つの戦略が「タッチポイントを生み出す」ことです。例えば、モバイルアプリの運営をしている場合でも、「電車の吊り革広告」「ファッションブランドとのコラボレーション」「オフラインでのイベント」などをブランド浸透を目的として行うことが考えられます。
ロサンゼルスのeスポーツチームであるインモータルズ・ゲーミング・クラブ(Immortals Gaming Club)は、チームのロゴ入りグッズなどを販売しているものの、これらのグッズの価格設定だと、グッズの販売で利益は上がらないと公式に認めています。これは、インモータルズ・ゲーミング・クラブが収益のためにグッズ販売を行なっているのではなく、ブランド浸透のためにグッズ販売を行なっていることを明確に表しています。
Immortals hopes to leverage this price reduction and other initiatives to help bring younger and less hardcore gamers into its fan base.
https://digiday.com/marketing/why-immortals-gaming-club-is-turning-the-esports-merch-game-on-its-head-with-its-zero-profit-strategy/
他のeスポーツチームが一般的に高価格でのグッズ販売戦略をとる中、インモータルズ・ゲーミング・クラブはそのメインターゲット層となる「気軽にゲームを楽しむ若年層」へのアプローチとして、低価格帯のグッズを購入して同世代にブランドを広めてほしいという狙いがあるようです。
まとめ
この記事では、ブランディングの概念からその目的やプロセスを初め、アプリなどのデジタルデザインにおけるブランディングのポイントまで紹介しました。本記事で述べたように強いブランドには、「なぜ」に答える「ストーリー」があるものです。このようなブランドコンセプトは、企業やサービスのWebサイトのAboutページによく記載されています。私たちが普段利用しているサービスや商品について、そのブランドコンセプトを調べてみても面白いかもしれません。