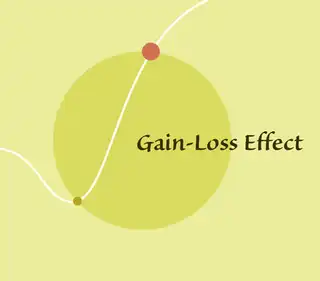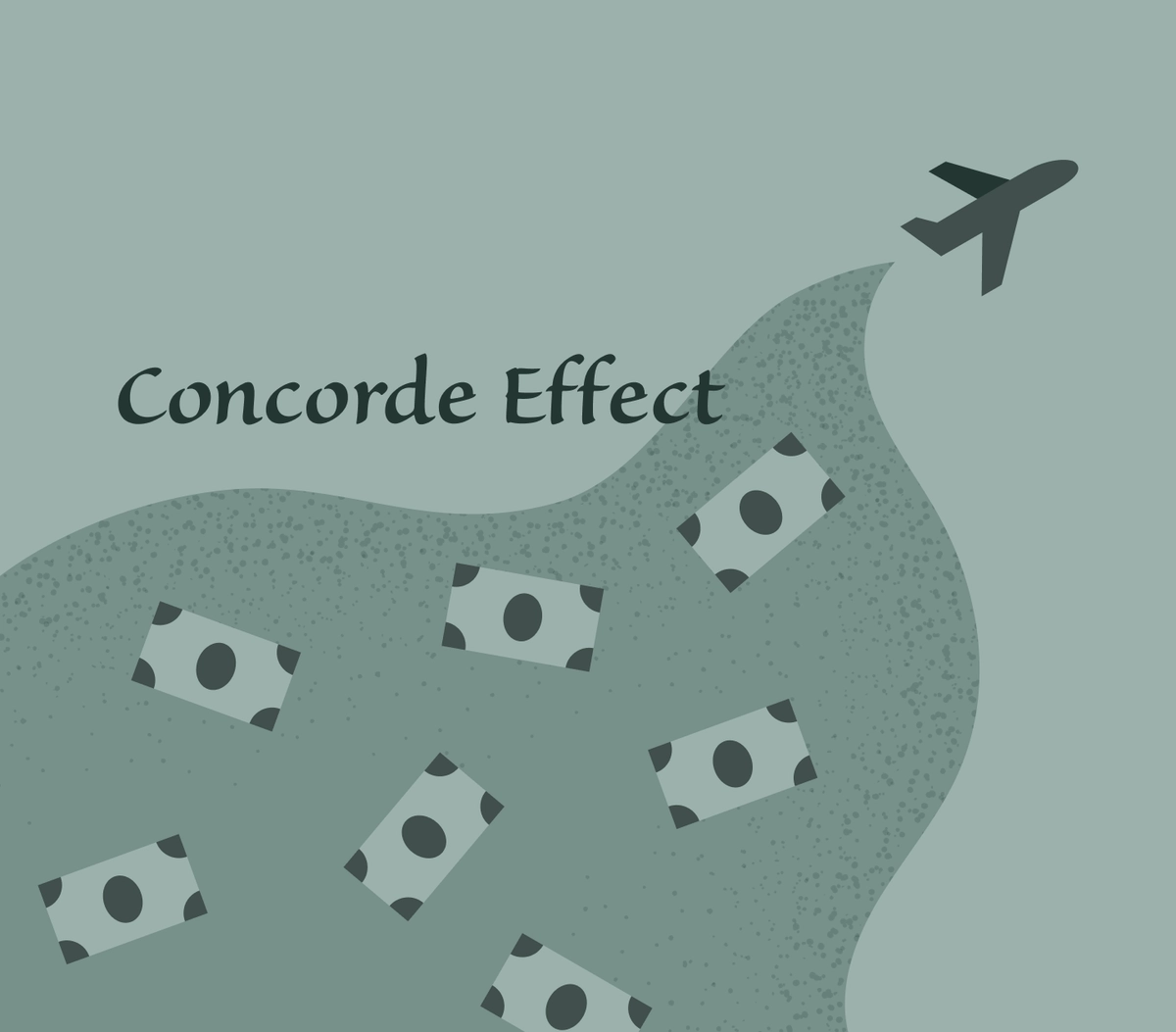
「もったいない」が引き起こすコンコルド効果とは?
コンコルド効果とは、それまでに費やした費用や時間に対して「��もったいない」という心理が働き、合理的な判断ができなくなる心理効果のことです。例えば、投資における「損切り」の難しさが良い例で、コンコルド効果が働いてしまうと非合理的な判断をしてしまい、損失が出ると分かっていてもなかなか投資をやめられません。
その他、身近な例ではゲームのガチャ課金やギャンブルがやめられないのもコンコルド効果が働いている例です。コンコルド効果の名前の由来は、イギリスとフランスが共同開発した超音速旅客機のコンコルドが商業的失敗をしたことで、別名「サンクコスト効果」や「埋没費用効果」ともいわれています。
コンコルド効果の具体例: 投資における損切り
あなたが株式投資を始めることにした場合を例として想定してみましょう。
まず、あなたはどの株に投資しようかとパソコンで検索し始めます。そこで、とある企業の株価が安定しており、将来的な成長も期待されているという情報を見つけ、株を購入します。
最初の数か月は順調で、株価は上昇傾向にありました。しかし、ある日株価が急落してしまいます。そのときあなたは、下記のA・Bどちらの選択肢をとるでしょうか?前提として、この時点であなたは、すでに一定の金額を投資しており、損切りをすることで損失が出る見込みとなっています。
「もう少し待てば、回復するかもしれない」
「投資をここでやめてしまうと、これまでの努力が無駄になってしまうのではないか?」
などと考えてAを選んだ場合、コンコルド効果が働いている可能性があります。
このように、今まで費やした費用や時間が「もったいない」という心理が働き、合理的な判断ができなくなってしまう心理効果のことを、コンコルド効果といいます。
コンコルド効果が起きる3つの心理的な背景
コンコルド効果が起きる心理的な背景を3つ紹介します。
損失回避
楽観主義バイアス
過去のコストに責任を感じている
それぞれの背景を下記で詳しく説明します。
1. 損失回避
コンコルド�効果が起きる主な心理的な背景の1つには、人間の一般的な特性である「損失回避」の影響があります。損失回避は、「何かを失う」ことが「何かを得る」よりも強い心理的影響を与えるために生じるものです。例えば、同じ1万円であっても、1万円を手に入れる喜びよりも、失ったときの落胆のほうが強くなります。
先ほどの株式投資の例をあげると、損失回避の心理的背景があることにより、株価が下落した場合でも、売却せずに保有し続ける傾向にあります。株式を売却すると損失が確定してしまうからです。損失回避の心理的な背景が強くなると、合理的ではない判断を促してしまうのです。
2. 楽観主義バイアス
コンコルド効果の原因となる2つ目の心理的背景は、楽観主義バイアスです。楽観主義バイアスとは、特に根拠がなくても、自分は同じ属性(年代や性別など)を持つ他者よりも、ネガティブな体験に見舞われることは少ないだろうと思い込む心理傾向�のことを指します。
人間の根底にこの楽観主義バイアスがあることで、損失が見込まれる状況でも、
「いつか成功するだろう」
「自分は大きな失敗に見舞われないだろう」
といった考えになり、コンコルド効果がより引き起こされやすくなるのです。
3. 過去のコストに責任を感じている
自分が過去のコスト(費用や時間)に責任を感じている場合、よりコンコルド効果が引き起こされる可能性が高まります。例えば、プロジェクトの発案者や意思決定者など、物事の成否に関わる重要なポジションに置かれている人が過去のコストに責任を感じやすいです。そのため、このような立場に置かれている人は、よりコンコルド効果の落とし穴にハマらないように気をつける必要があります。
ビジネスにおけるコンコルド効果の事例
ビジネスにおいてコンコルド効果が利用されているような事例を4つ紹介します。
契約解除画面
ポイントシステム
一定額購入で送料無料
○点目無料
契約解除画面
サブスクリプションサービスの契約解除画面では、コンコルド効果を引き起こすような工夫がされていることがあります。例えば、契約解除を行う画面で
「未使用のクーポンがあります」
「今契約解除すると、契約更新月までの月割り分の金額は返金されません」
「再登録時には、再度登録料がかかります」
など、顧客にすでにサービスに支払っている費用について意識させることで、「今やめたらせっかく獲得したクーポンが使えなくなってしまう」「登録料のことを考えたら、せっかく登録したしこのまま利用したほうがいいか」などと思わせます。このように、契約解除画面ではコンコルド効果をを引き起こすような工夫がされている事例が多く見受けられます。
ポイントシステム
ポイントシステムもコンコルド効果と関係の深いビジネス施策です。例えば「あと⚪︎日で300ポイントの有効期限が切れます」などという通知が送られてきたことはありませんか?
この通知もコンコルド効果を働かせる方法として有効なのです。通知がくると、顧客は獲得したポイントを失効する前に使おうとし、再度の来店や購買行動を行う可能性があります。
また、「過去に費やしたコストに対して感情的なつながりがあり、それを取り戻そうとする」というコンコルド効果の特性を利用して、ポイントが貯まった際に限定特典が利用できる仕組みが作られることもあります。顧客が限定特典が利用できる仕組みが利用できると、過去に費やしたコストを取り戻せるという心理になる可能性があるからです。
一定額購入で送料無料
一定額を購入すると「送料無料」になる施策も、コンコルド効果が活用されている1つの事例です。この場合、「送料」が埋没費用となり、送料を払うのは損だという心理が働きます。
結果として、本当に必要なもの以外の商品を買ってしまう行動を促され、追加の商品が売れる仕組みができます。このように一人当たりの購入金額を上げる送料無料施策もコンコルド効果との関連性があります。
○点目無料
送料無料と同様に「○点目無料」という施策も、コンコルド効果を活用している事例です。
例えば、大手アパレルブランドであるH&Mの店舗では、子ども服を中心に「3点目無料」と打ち出しています。本来は、1点の洋服を購入する予定だった場合でも、無料の「3点目」が埋没費用となり、2点目も購入したくなるような心理状況になるでしょう。
コンコルド効果の対策をして「選択の質」を高める方法
このように、コンコルド効果は日常の様々なシーンで引き起こされます。知らぬ間に、私たちもコンコルド効果の罠に引っかかっているかもしれません。以下では、コンコルド効果の対策をして「選択の質」を高める方法をご紹介します。
あらかじめ使える金額を決めておく
分岐点では「ゼロベース思考」で判断する
冷静な意見をくれる第三者に相談する
コンコルド効果が起きやすいことを自覚しておく
あらかじめ使える金額を決めておく
コンコルド効果を対策する方法の1つは、あらかじめ使える金額を決めておくことです。見切りをつける金額を決めておき、投資を休止したりやめたりする判断をすることで、埋没費用に執着せずに済みます。投資や事業を開始する前�には、損切りの判断基準になる「使える金額」や「期限」などを決めておくと、合理的な判断ができるでしょう。
分岐点では「ゼロベース思考」で判断する
分岐点に立たされたとき、「ゼロベース思考」で判断することもコンコルド効果の対策になります。ゼロベース思考とは、既存の常識や慣習にとらわれず、現状をゼロの状態から見直し、問題や課題を新たな視点で発見・解析していくアプローチのことです。
分岐点や問題に直面したとき、解決に向けて「どこに課題があるか」を徹底的に把握する必要がありますよね。そのような場合に、ゼロベース思考が有効です。
投資や事業などで、続けるかやめるかの判断の分岐点に立ったときには、これまでの時間や労力などのコストも一旦リセットしてゼロベース思考で判断することも有効です。
冷静な意見をくれる第三者に相談する
冷静な意見をくれる第三者に相談するのもコンコルド効果の対策として有効です。
一人では冷静な判断を下せない場合でも、客観的に相談できる第三者を見つけ��ておくと大きな損失を出す前に引き返せるかもしれません。合理的な判断をしたい場合は、冷静な意見をくれる第三者に相談してみましょう。
コンコルド効果が起きやすいことを自覚しておく
コンコルド効果を対策するためには、コンコルド効果が起きやすいことを自覚しておくことも重要です。
意思決定における感情が、過去のコストに影響される可能性があることを理解しておけば、一度立ち止まって冷静な判断ができる可能性が高まります。コンコルド効果が起きやすいという自覚を持つことで、適切な対策を行い、損失を最小限にできるでしょう。
まとめ
「もったいない」という心理から生まれ、過度な投資や損失を引き起こす心理現象であるコンコルド効果について解説しました。コンコルド効果は、契約解除画面・ポイントシステムなど、さまざまなビジネスシーンでも利用されている心理効果です。
消費者の立場で見れば、私たちも知らぬうちにコンコルド効果に惑わされているかもしれません。ビジネスシーンでも消費者の立場��でも、大きな損失を出さないように、常に冷静な視点を保ちながら最良の選択をしたいですね。