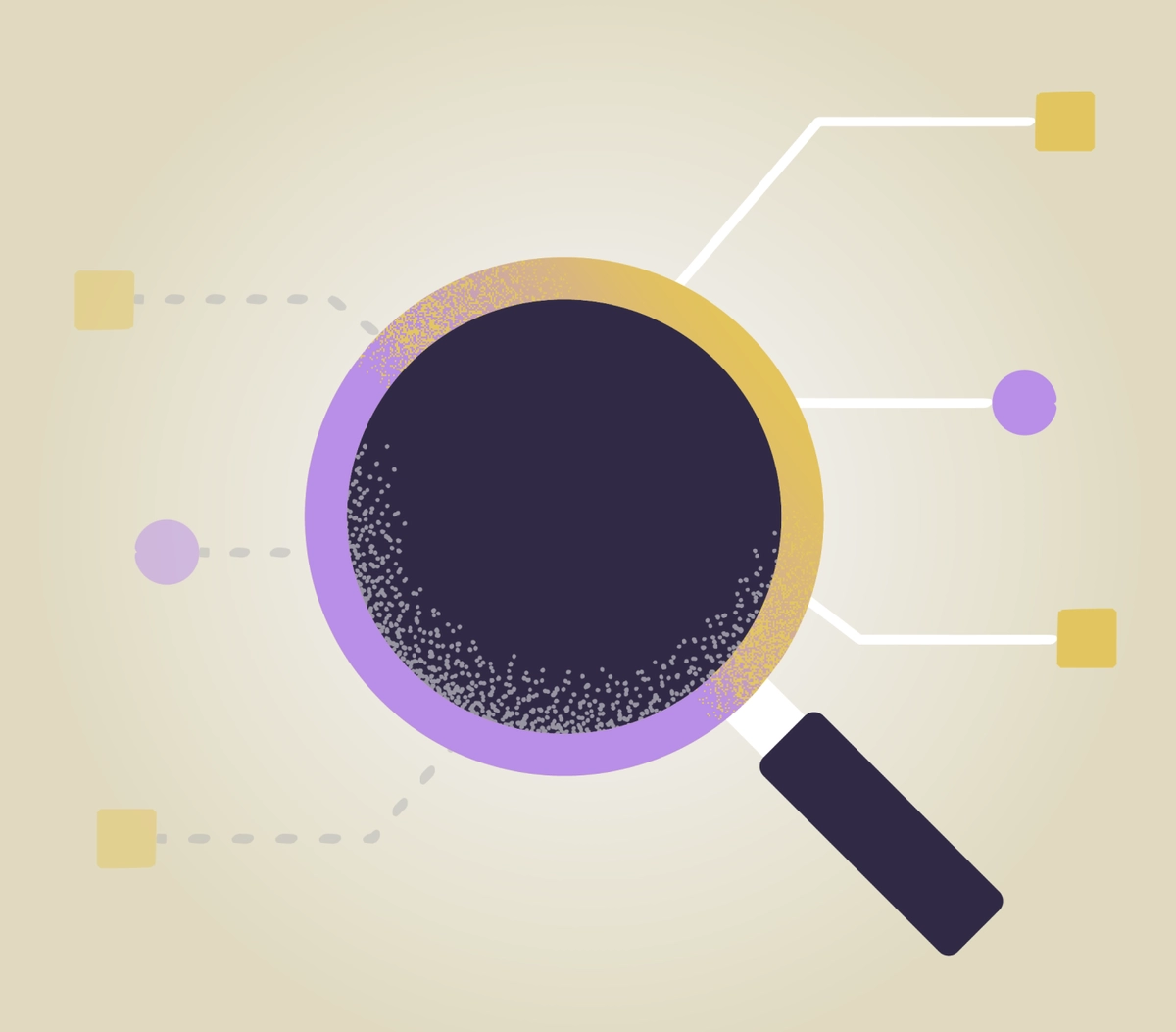
小さなドーパミンヒットを繰り返すSNSアプリの無限スクロールがもたらす心理効果は、薬物中毒に陥った人が麻薬を求め続けてしまう原理と同じだといわれています。ドーパミン中毒による行動は、ギャンブル依存にも当てはまり、そう考えるとSNSの縦スクロール画面をスワイプし続ける行動とスロットを回す行動に恐いくらいの類似性さえ感じますね。次に表示されるコンテンツに対する期待が満たされたり、満たされなかったりする体験が、つい時間を忘れて画面をスワイプし続けてしまうことに繋がり、一度このドーパミンヒットのループにハマるとなかなか抜け出せないのです。
無限スクロールを加速し健康や思想に影響を与え始めた「フィードアルゴリズム」
SNSアプリのフィードをスワイプす�ること自体にお金はかからないので、ギャンブル中毒に陥るよりはまだ良いかもと思えるかもしれません。多くの人が無限スクロールで失われるのは時間くらいだと考えているかもしれないです。
ただ、この無限スクロールによって表示されるコンテンツを制御する「フィードアルゴリズム」の存在によって事態はもっと深刻なものになってきました。ユーザーが見たコンテンツに近いものを表示するアルゴリズムが、時に若者を自殺に追い込んだり、政治的、宗教的思想に影響を与えることが危惧されています。これにより多くの訴訟が起こされたり、法による規制が検討されたりといったことが起こっているのが今現在です。
問題の本質は「スクロールし続けてしまうこと」ではなく、コンテンツを表示する基準が不明であることなのでは?
SNSアプリのフィードは「マスターアルゴリズム」と呼ばれるロジックによって、それぞれのユーザーの嗜好やトレンドを加味しながら「スクロールし続けさせること」を目的に設計されています。
このアルゴリズムは、ユーザーに最適化されて好みに合ったものを表示すると思われていますが、「そのユーザーにとって有益な情報」を届けるわけではなく「そのユーザーが見続けてしまうコンテンツ」を表示するように作られています。つまり、「あなたへのおすすめコンテンツ」は実際のところ、運営企業に利益をもたらすために「あなたが見続けてしまうであろうコンテンツ」なのです。
それらがなんとなくランダムに表示されている感じがするのがSNSのフィードです。そして、ユーザーがスクロールし続けてしまう理由は、自分が好きなコンテンツが流れてくるからではなく、自分が好きなコンテンツが流れてくる”かもしれないから”なのです。そこにはコンテンツがユーザーに有益かどうかという基準は存在しないでしょう。
中毒性ばかり追い求めてきたフィードデザインが変わるかも?STEM教育フィードを公開したTikTokやドゥームスクローリングへの対応を発表したSmartNews
近年多くの批判にさらされるこのフィードですが、 それぞれのサービスはいくつかの方向性を模索していることも伺えます。例えば、若年層に対して有害なコンテンツを配信しているとして批判されるTikTokは「STEM教育フィード」と呼ばれるフィードをヨーロッパとアメリカにて段階的に導入しており、若年層をドーパミン漬けにするサービスというイメージからの脱却方法を模索しています。
また��、SmartNewsは米国版のアプリにてドゥームスクローリングへの対策として、ポジティブな内容のコンテンツをキュレーションした「SmartTake」というフィードを昨年導入しています。
- ドゥームスクローリング(Doomscorolling)とは?
- 「破滅の運命にあるスクロール」という意味で、見ると気分が害されるとわかっていながら不快なコンテンツを次々と見続けてしまう行動のこと。悲劇的なニュースや、自己肯定感を下げるようなコンテンツがユーザーに精神的な悪影響を与えるとして懸念されている。
Instagramも友人との共通の興味関心にもとづいて作られるフィードである「Blend」機能を開発していると報じ��られており、単一のアルゴリズムよって制御されたフィードの提供とは異なる方向性を模索している様子が伺えます。
ユーザーがフィードアルゴリズムを作り、共有するという選択肢
クレジット: Koshiro - stock.adobe.com
そんな中、フィードアルゴリズムに対して全く異なるアプローチを目指しているのが分散型SNSの『Bluesky』です。Blueskyは、このフィードアルゴリズムの不透明性を問題として捉えており、フィードコンテンツを構成するロジック操作をAPIとして公開し、ユーザーがフィードアルゴリズムをプログラミングし、公開することを可能にしたのです。
つまり、ユーザーはどのようなロジックに基づいて自分のフィードが構成されるのかを選択することができるようになるのです。実際にBlueskyのフィード画面ではコミュニティによって作成されたカスタムフィードを検索・利用することができるようになっており、様々なトピックや視点でキュレーションされるフィードが並びます。
Web版Blueskyのフィード選択画面
このようなユーザーによるフィードアルゴリズムの開発や共有は技術的には分散型SNSでなくても実装可能なものであり、TikTokやInstagramといった、その他のSNSがこの流れを一部でも取り入れるような動きにつながれば、現在与えられるがままに消費するしかないフィードにユーザーの選択の余地、そしてそれに伴う責任が生まれ、世の中のフィードに対する見方も大きく変わってくるのではないでしょうか?
スクロールは無限に続くけど、アルゴリズムは民主化できる
一度無限スクロールという体験を手にしてしまった私たちは、今後スクロールし続けること自体に簡単には抗えないかもしれないものの、より”ユーザーが主権を持った無限スクロール”という方向性はありえるのかもしれないです。ユーザーが”選べる”ということは、与えられたものを受け取るだけという行動よりももっと多くの可能性をもたらしてくれるのではないでしょうか?













