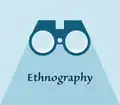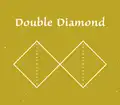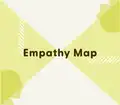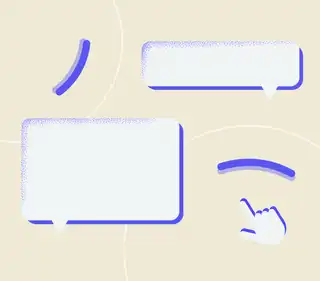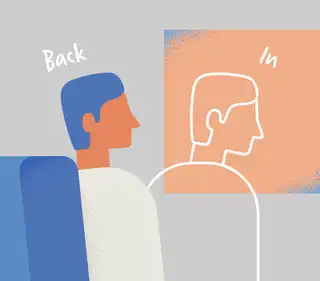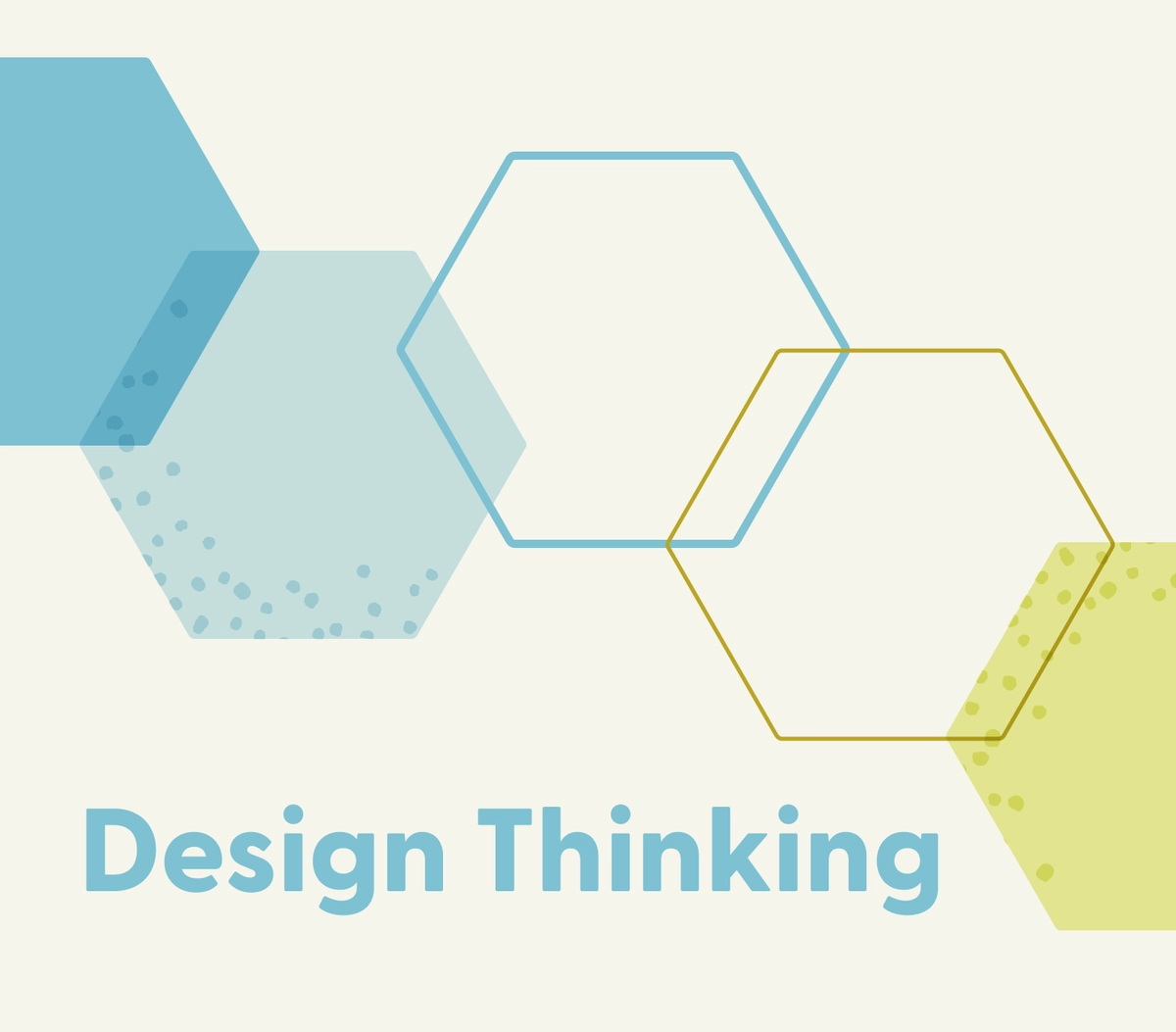
デザイン思考とは?注目を集めるデザイン思考とは一体何なのか?
デザイン思考(デザイン・シンキング)とは、デザイナーによるモノづくりのプロセスを体系化した課題解決のための思考法です。顧客の抱える課題を中心に捉えるという特徴が、ビジネスの現場での商品・サービス開発に効果的であるため広く取り入れられています。
作れば売れる時代ではなくなった。デザイン思考が注目される背景
インターネットや物流が現在ほど発達する前の時代では、商品やサービスを届けることができる範囲がある程度限られていたため、「良いもの作れば売れる」という考え方が一般的でした。市場には様々なチャンスがあり、その穴を埋めるこ�とで利益を上げることができたのです。しかし、現代では消費者は膨大な選択肢からサービスや商品を選択することができます。例えば冷蔵庫を買おうと考えたときにも、インターネットを使って世界中のメーカーの商品から比較検討し、自分のニーズにあったものを見つけて購入することができますよね。
このような状況では、商品を開発する企業の想定する「良いもの」を目指して商品を作ったとしても、同じような商品で溢れている市場においては埋もれてしまい、価格競争に陥ってしまいます。そこで重要となるのが、「顧客の潜在ニーズ」です。「顧客自身も明確には気づいていなかったものの、実は欲していたようなもの」を作ることが求められているのです。このような難易度の高い商品開発において注目されているのが、デザイン思考です。デザイン思考では、ユーザー(顧客)の課題(ニーズ)を起点としてプロダクトを開発するため、ユーザーの潜在ニーズを捉えることができ、競争過多の状況の中で顧客に選ばれる商品を作ることができるのです。
デザイン思考の何が「デザイン」なのか?課題解決という意味のデザインとは?
「デザイン」思考という名前から、なんとなく「おしゃれな見た目」や「クリエイティブな発想」といったものを連想されるかもしれません。しかし、デザイン思考とは見た目が良いモノを作るためのプロセスや、良い外見を重視したモノづくりといった意味ではありません。「デザイン」の本来の意味は「誰かの課題を解決することを目的としたモノの設計」です。確かに、満足感の高い外見もデザインの重要な側面ではありますが、その根本には「ユーザーの課題を解決するためのプロセス」が存在し、そのプロセスは課題を抱えた人への共感を軸とした非常にロジカルなものとなっているのです。デザイン思考は、そのようなユーザーの課題を解決するためのロジカルなプロセスをビジネスなどに応用するための思考法です。
アート思考との違い
デザイン思考とともに知られる思考法に『アート思考』というものがあります。前述した「クリエイティブな発想」をもとした思考はデザイン思考よりはこちらのアート思考に近い考え方です。アート思考とは、「既成概念にとらわれない発想や逆説的な思考によって発想する思考法」です。デザイン思考とアート思考の主な違いは以下のとおりです。
アート的なプロセスは、どちらかというと表現者自身の「自己表現」が主な原動力となりますが、デザイン的なプロセスには常に「目的」が存在し、デザイナーによるものづくりには、必ずアウトプットを使う「ユーザー」の存在があります。この「デザインとは何か?」や「デザインとアートの違い」については、以下の記事でより詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
デザイン思考のフレームワーク
では、デザイン思考のプロセスとはどのようなものなのでしょうか?ここでは、最もよく知られている「デザイン思考の5つのステップ」と「ダブルダイヤモンド」の2つを紹介します。この2つは「デザイン思考のフレームワーク」として良く知られていますが、デザイン思考を取り入れる上で重要な点は、プロセスをなぞることではなく、主軸となる考え方やエッセンスを取り入れることです。ここでは2つの異なるフレームワークを見比べながら、それぞれの共通点に着目してみてください。
デザイン思考の5つのステップ
デザイン思考の5つのステップは、スタンフォード大学のd.schoolによって提唱されたデザイン思考のフレームワークで、問題解決のためのプロダクト開発プロセスを「共感」「課題定義」「創造」「プロトタイプ」「テスト」のわかりやすい5つのステップとして定義しています。
共感(Empathize)
共感のステップは、デザイン思考を特徴づける最初の重要なステップです。共感ステップで行うことは、「課題を抱えるユーザーに共感し、課題の本質をよく理解すること」です。基本的には、課題に関する情報を広く集めていくような作業になりますが、デザインの世界で広く活用されている手法であるエスノグラフィーなどを取り入れるのも大変有効です。エスノグラフィーとは、研究対象の生活環境に身を置いて行動を観察したり、生活を共にすることで、研究対象の行動や課題について深く理解するための手法です。エスノグラフィーを実施できない場合であっても、共感ステップで集める課題に関する情報は、客観性を重視してメンバーの思い込みにとらわれないように気をつけましょう。
課題定義(Define)
課題定義ステップでは、前の共感ステップで集めた情報をもとに「ユーザーが抱える課題」を明確に定義します。ここで定義する課題は、以降のステップの基礎となるためできるだけわかりや�すい形で表現すると良いです。おすすめの定義方法は、海外のデザインチームでよく使われる「How Might We ~?」という形式です。日本語にすると、「どうすれば〇〇できるか?」となり、この「どうすれば」という問いが「こうすれば良いのではないか?」というアクション仮説に繋がりやすく以降のプロセスを進めやすくなります。
創造(Ideate)
創造のステップでは、定義した課題に対して実際に「どうすれば良いのか?」の部分を考えていくようなフェーズとなります。このフェーズでは、できるだけさまざまな可能性を想定してアイデアを集めましょう。チームメンバー内でブレインストーミングを行うのも有効な手段です。効果的なブレインストーミングの方法については、以下の記事で紹介しています。
プロトタイプ(Prototype)
プロトタイプとは、仮説を検証するための試作品です。創造ステップにおいて採用されたアイデアを検証できる最小限の形で実際に作ります。プロトタイプのステップにおいて重要なポイントは、コストをかけすぎないことです。また、デザイン思考はその名の通りデザインのプロセスであるため、このプロトタイプフェーズでは実際のプロダクトに近い形のものを作ることを想像されるかもしれません。しかし、デザイン思考をビジネスなどに応用する場合には、このプロトタイプは物理的な形を持つものにこだわる必要はありません。課題の解決策がユーザーに対して本当に有効かどうかを「検証できる」方法であれば、簡単な代替品やインタビューなどで解決策を検証できる場合も多いです。
テスト(Test)
テストのステップでは、制作したプロトタイプを使って課題解決のアイデアを検証します。課題定義のステップにて定義した「どうすれば〇〇できるか?」の問いに対して、「こうすれば〇〇できる」という答えを見つけることがここでの目的となります。�ここで重要なポイントは、テストの結果をもとにアイデアを修正することです。多くの場合、立てた仮説が一度で立証されることはないと思います。テストを実施する際には、「どのような点に改善の余地があるのか?」という点に注意しながら行うと良さそうです。
「発散」と「収束」に注目したダブルダイヤモンド
デザイン思考の5つのステップとともによく知られているデザイン思考のフレームワークが「ダブルダイヤモンド」です。ダブルダイヤモンドとは、デザイン思考のプロセスを「探索」「定義」「展開」「提供」の4つのフェーズに分けて定義したもので、この4つのフェーズを通して「発散」と「収束」を2回繰り返すという点が特徴です。この発散と収束を繰り返す様子の図が2つのダイヤモンドを並べた形に似ていることから、ダブルダイヤモンドと名付けられました。ダブルダイヤモンドの4つのフェーズは以下のとおりです。定義の仕方は異なるもの�の、前述のデザイン思考の5つのステップとの共通点が見えてくるのではないでしょうか?
1. 探索(Discover)
プロジェクトのコンテキストや課題を理解し、リサーチを行います。この段階では情報を収集し、アイデアを広げることが重要です。デザイン思考の5つのステップでは「共感」にあたる部分ですね。
2. 定義(Define)
リサーチから得られた情報を分析し、問題やニーズを特定、明確化します。この段階では、問題解決のために焦点を絞り込むことが重要です。その名の通り、デザイン思考の5つのステップでの「課題定義」に対応するステップとなります。
3. 展開(Develop)
問題を解決するためのアイデアやコンセプトを生成し、それらを詳細化します。この段階では、再びアイデアを広げ、さまざまな解決策を検討することが重要です。デザイン思考の5つのステップにおける「創造」ステップに対応します。
4. 提供(Deliver)
最も効果的な解決策を選び出し、実装に移します。この段階では、プロトタイプやテストを通じてアイデアを具体化し、最終的なデザインを仕上げます。デザイン思考の5つのステップにおける「プロトタイプ」や「テスト」のステップがこれにあたります。
ダブルダイヤモンドにおける重要なエッセンスは、「発散と収束を繰り返すことによって、目的に近づいていく」という点です。発散のフェーズでは、視野を広げて多くの情報を集め、収束のフェーズにおいてそれらをまとめて定義するという流れの繰り返しを行うことで、多くの可能性を取り込みながら課題解決に取り組むことができるようになります。
デザイン思考の2つのフレームワークに共通するエッセンス
このように、デザイン思考には広く知られた2つのフレームワークが存在します。このように聞くと「どちらのフレームワークを使えば良いの?」といった疑問を抱かれるかもしれません。しかし、デザイン思考はあくまで一つの「思考法」であるため、重要なのはどちらのフレームワークを使用するかや、フレームワークに沿って何かを進めることではなく、その思考法のエッセンスを理解して取り入れることです。ここでは、紹介した2つのフレームワークを通して見えてくるデザイン思考におけるポイントを解説します。
1. ユーザーという存在
まず、デザイン思考において一番重要となるのがユーザーという存在です。デザイン思考のすべてのフェーズにおいて主役はユーザーなのです。つまり、課題を理解する際には実際にユーザーに聞く必要がありますし、アイデアをテストする際には実際のユーザーに使ってもらって検証する必要があります。そして、プロセスを通して「誰の課題を解決しているのか?」という大きな目的からずれないように気をつけることも大切なポイントとなります。
また、大前提としてこの「ユーザー」を正しく定義することも重要なポイントです。プロダクトを開発するときに、ユーザーをあまりに広く定義してしまうと、課題解決のための核心的な情報を集めることが難しくなってしまいます。例えば、「髪のパサつきに悩む女性」の課題を解決したい場合、ユーザーの定義を「20代 女性」のように広く定義して、この条件に当てはまる人から情報を集めようとしても解決したい課題に直接関係するインサイトを得ることが難しいでしょう。
ユーザーの定義は常に「解決しようとしている問題を実際に抱えている人」として、デザイン思考のプロセスの中でもそのような人々から話を聞いたり、プロトタイプを試してもらったりしましょう。
2. 発散と収束
次に重要なポイントは、ダブルダイヤモンドにおいて明確に定義されている「発散と収束」です。どちらのフレームワークに沿って進める際にも、
広く情報を集める
集めた情報をまとめる
という2ステップの繰り返しによって課題解決に近づいていくという点は同じです。ここで、課題解決に取り組むメンバーとして重要となるのが、「今、どちらのフェーズにいるのか?」を正しく把握することです。自由に発想を広げるべきタイミングと、情報の関連性を見出してまとめていくべきタイミングを正しく切り替えながら取り組むことが、効果的にデザイン思考を取り入れるためのポイントとなります。
3. 細かく繰り返す
フレームワークの図を見ると、デザイン思考のプロセスは直線的に見えるかもしれません。しかし、これは図を簡略化するためであり、実際のデザイン思考的なプロセスではステップごとに真っ直ぐ進んでいくことはほとんど想定されていません。実際には、以下のように必要に応じてそれぞれのステップを何回か繰り返すような形で進めていくことになると思います。こうすることで、ユーザーの課題を正しく捉えられているかや、解決策が効果的であるかなどを確認しながら進めていくことができます。
共感
課題定義
(ユーザーの課題に関する情報が足りず、課題を定義できないため「共感」ステップをやり直し)
課題定義
創造
プロトタイプ
テスト
(課題は正しく捉えられていたものの、解決策が良くないため「創造」ステップをやり直し)
創造
このように、単にデザイン思考のフレームワークに沿って一周するのではなく、そのエッセンスを取り入れた上で、それぞれのステ�ップでしっかりと仮説を検証し、プロダクトに反映することが何より重要なポイントとなります。究極的には、ここで紹介したデザイン思考のエッセンスさえ取り入れてしまえば、実際にどのようなステップを踏んでプロジェクトを進めるかはそれほど重要ではないと言っても過言ではないと思います。
デザイン思考のそれぞれのフェーズで役立つ手法
これまで見た通り、デザイナーによるプロセスをもとにしたデザイン思考では、ユーザーへの共感や情報の収束などのデザイナー以外にはあまり身近ではないような表現があったかと思います。これらにいきなり取り組もうとしても「何から始めれば良いのか?」と悩んでしまうかもしれません。ここでは、そんな時に取り入れることができるデザイナーの手法をいくつか紹介します。
ユーザーへの共感ってどうやるの?共感マップやインタビュー、ジャーニーマップといったUXデザイン手法
デザイン思考の起点はユーザーのニーズです。これを的確に捉えるためには、ユーザーがどのような環境でどのような課題を抱えているのか?それはどれほど重要な課題となっているのか?など��、ユーザーに関する様々な情報を集める必要があります。このようなユーザー分析に使える手法の多くは、UXリサーチやUXデザインの世界で多く取り入れられて体系化されつつあります。
ここでは、中でもデザイン思考の初めのステップに役立つ手法として「ユーザーインタビュー」「共感マップ」「ジャーニーマップ」の3つを紹介します。
ユーザーインタビュー
ユーザーについて理解を深める最も重要な方法は、直接話を聞くことではないでしょうか?特に、ユーザーインタビューでは、アンケートなどの他の手法と比べて、ユーザーの行動や考えの裏にある「なぜ?」に迫ることができるという大きな特徴があります。ユーザーインタビューには、ユーザーの潜在ニーズを引き出すためのさまざまなルールや手法があります。しかし、これらを気にしすぎてインタビューを行わないよりは、と��にかくユーザーの声をざっくばらんに聞いてみるような進め方の方がヒントが得やすいかもしれません。その上で、成果を出すための専門的なユーザーインタビューの設計について気になる方は、以下の記事で詳しく解説していますのでそちらも参考にしてみてください。
共感マップ
共感マップもその名の通り、デザイン思考の共感ステップに適したUXデザイン手法です。共�感マップとは、ユーザーの置かれた環境やその中で抱く感情・思考などについて理解するための手法で、ユーザーインタビューで集めた情報をもとにユーザーの環境や心理についてまとめ、チーム内で共有するために役立つフォーマットです。ユーザーの情報を一枚の画像としてまとめることができるため、デザイン思考のプロセスを通してその基礎となる「ユーザーへの共感」を参照したり、見直したりすることができるようになります。
ジャーニーマップ
共感マップがユーザーの基本的な環境や思考をまとめるのに対し、ジャーニーマップではユーザーと課題との関わりを時系列で示すことができます。これによって、課題を抱えたユーザーがどのようなタイミングでどのような行動・思考をするのかを可視化することができるようになります。共感マップとジャーニーマップをそれぞれ作成するとより多角的にユーザーの置かれた状況を理解できるようになるかと思います。
アイデアの発散と収束にぴったり!ブレインストーミングとKJ法の組み合わせ
次に、デザイン思考のプロセスを通して繰り返される「発散」と「収束」を行う際に役立つ手法を紹介します。ブレインストーミングとKJ法は、実はあまり意識しなくても行なったことがあるという人も多いかもしれません。ここでは、改めて効果的にこれらの手法を取り入れる方法を紹介したいと思います。
ブレインストーミング
ブレインストーミングは今やビジネスの現場では大変広く取り入れられており、多くの人が一度は参加したことがあるのではないでしょうか?共感ステップや創造ステップなどの「発散」に集中するステップでも複数人でのブレインストーミングが行われることが多いです。
ブレインストーミングから効果的なアウトプットを得るためのコツは以下の2つです。
ブレインストーミングの目的と背景について参加者に正確に共有すること
ブレインストーミングのスコープを広げすぎないこと
「自由にアイデアを広げる場」というのがブレインストーミングの強みであると同時に、対象とするトピックが広すぎたり、議論が目的からずれてしまうと、あまりにも一般的なアイデアばかり集まってしまったり、本来の目的と関係のない方向にアイデアが広がってしまうことがあります。そのため、上記の2点に注意しながら時にはファシリテーターによる軌道修正も挟みつつ実施すると、効果的にブレインストーミングをすることができると思います。
KJ法
KJ法とは、広く収集した情報をまとめて多角的に分析するための手法で、考案者の人類学者、川喜田二郎氏のイニシャルから「KJ法」と名付けられました。簡単にまとめると、以下のような4ステップで情報をまとめる手法で、使い方がわかれば誰でも簡単に取り入れることができます。
情報の書き出し
情報のグループ化
情報の関係性の視覚化・図解
インサイトを文章にまとめる
KJ法の解説記事では、KJ法の詳しいやり方やポイントについてまとめていますので、詳しくはそちらを参考に��してみてください。
おすすめの本『デザインシンキング・ツールボックス』
最後に、デザイン思考に関�してその他多くの便利な手法をまとめた本を紹介したいと思います。2023年2月に日本語版が出版された『デザインシンキング・ツールボックス』では、世界44カ国でデザインシンキングに携わる2,500名以上もの専門家からとったアンケートにもとづいて、デザイン思考の現場で役立つ手法が48個も紹介されています。中には今回紹介した共感マップなども含まれており、書籍内ではそれぞれの手法に専門家のアドバイスがあるのポイントです。