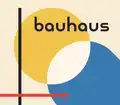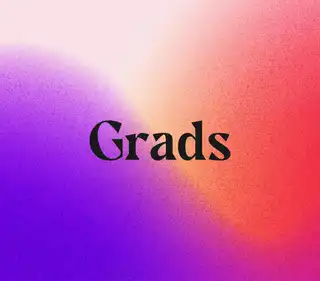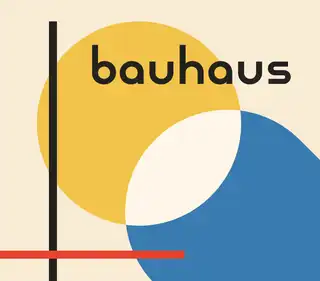デザインとは、「多くの人に配布されることを前提としたモノの設計」である
デザインとは、課題解決や目的達成のための「設計」を意味する言葉です。デザインという言葉が使われる分野は多岐に渡り、グラフィックデザイン、UXデザイン、UIデザインなどがありますが、これらすべてにおいて、デザイナーは「設計者」という役割を持つことになります。デザイナーは、課題を解決するための最適な手段を模索、検証し、最終的な設計図を描くのです。しかし、この「デザイン = 設計」という解説は、現代のデザインの背景にある「大量生産」という前提を踏まえないと理解しにくいです。この記事では、一般的な解説からさらに一歩踏み込んで、デザインの本来の意味「多くの人に配布されることを前提としたモノの設計」について、デザインの歴史やアートとの違いから解説していきます。
「ビジュアルデザイン」も設計!?すべてのデザインが「設計」である理由。
近年の日本における「デザイン」という言葉についての解説では「デザインとは、見た目を整えるだけではなく、設計することである」という説明が多くなされていますね。これには、デザイナーは表面的な表現だけを担うのではなく、目的を持って視覚表現を行うという点を強調してきたデザイン業界の努力が反映されています。この経緯から、近年の日本でのデザインの定義は、
課題解決のための設計
設計されたものの視覚表現の制作
というような2つの側面を持つ言葉として定着しつつあります。ここで言う、「設計」と「制作」を作業工程と結びつけて、上流工程の設計を行うデザイナー、下流工程の制作を行うデザイナーといったような表現も耳にします。確かに、「デザインとは設計である」と言う点は間違っていません。しかし、このようにデザインの定義を「設計」と「制作」という工程に基づいて分ける考え方は、現代のデザインの文脈における「設計」と「制作」が意味する内容を正しく反映できていないのではないでしょうか?
本来デザインが意味する「設計」とは、「設計」と「制作」という2つの工程に線引きをするようなものではなく、デザイナーが設計したものが「生産」されて多くの人の目に触れるというコンテキストにおいての、「設計」に過ぎないのです。つまり、この文脈ではリサーチも視覚表現も等しく「設計」であり、デザインプロセスのそれぞれのフェーズがいかに設計的であるか、または設計的でないかという意味合いは持たないのです。そのため、課題解決や目的達成のための「設計」というデザインの定義が浸透したとしても、人間の五感による知覚の約80%を占める「視覚」に訴える、視覚表現の制作がデザインプロセスにおいて重要な位置にあるという点は忘れてはいけない事実です。
現代のデザインの文脈における「制作(Production)」とは「大量生産」のことである。
現代のデザインにおいて見落とされがちな点が一つあります。それは、「デザイナーが最終的なプロダクトを制作することはない」という点です。
家具デザイナーが作ったプロトタイプはそれ自体が顧客に届けられるのではなく、それをもとに生産された製品が最終的に顧客の課題を解決します。チラシをデザインしたデザイナーはチラシ自体を制作しているのではなく、大量印刷されるための原型を設計しているに過ぎません。Webデザイナーが作ったWebサイトも同じく、ユーザーのブラウザが配布されたコードを解釈することで再生産されたものがユーザーの課題を解決します。これらの例において、デザイナーが行なっている「制作」は、大量生産されるモノの原型を設計する作業となります。つまり、デザイナーの行う作業は見た目の制作でさえ、大きな文脈で見ると「設計」なのです。この「大量に複製され、多くの人に配布される」という大前提が、「デザイン= 設計」という言葉の意味を理解する上で重要なポイントとなります。一般に、デザインが芸術や工芸と区別される点とされるのは、「デザインが生み出したものはオリジナルに存在せず、複製に存在する」という事実です。(FALCINELLI, 2021)
現代的な意味での「デザイン」は印刷技術によって生まれ、大量生産と資本主義によって発展した。
そもそも、現代的な意味でのデザインが誕生したきっかけは、15世紀の活版印刷の発明と言われています。この時代の活版印刷、そしてその後の印刷技術の発展は以下の2つの変化を社会にもたらしました。
同じ書物・絵・図を多くの人に配布することができるようになった。
多くの人が同じ書物を読むことにより、現代的な意味での「大衆」が誕生した。
印刷技術以前の世界は、特定の考えやアイデアを多くの人に広めるという�ことは不可能でした。この前提において、君主制の国家体制が成り立っていたのです。この印刷技術の発展によって、人は「多くの人に見られること」を前提として文章を書き、絵を描くようになりました。そして、それを行う際には常に何かしらの「目的を持っていた」のです。わかりやすい風刺画や文章を用いた書物を大量印刷して、自分の政治的な考えや意見を広めようとしたこと。これが現代的な意味でのデザインの誕生です。
そして、その後の大量生産技術と資本主義の発展はこのデザインという活動をますます加速させます。この時代以降、デザインは政治的な目的だけではなく、商業的な目的を持つようになりました。大衆に向けて便利なものをデザインし、大量生産することは現代の商業の根幹となっていますよね。そして、この「人がお金を払ってでも欲しいもの」を作るということが、現代まで多くのデザイン分野での「デザインの目的」となっています。
このように、大量生産と資本主義という時代背景において、「大量に複製され、多くの人に配布されることを前提としたモノの設計」がデザインの本来の意味です。この前提を踏まえると、「デザインには目的がある」という言葉はもはや当たり前に思えてきますね。目的もなく多くの人にモノを届けても何の意味もないですから。そして、この大量生産という前提によって、人がものを作る時のプロセスも大きく変化しました。例えば、自分一人のためにコップを作る場合と、多くの人のためにコップを設計する場合では考え方もプロセスも大きく異なりますよね。「プロダクトを使う多くの人々」を意識してデザインを行うという、現代まで続くデザインのプロセスが誕生したのです。このようなプロセスを言語化したものが「デザイン思考」などに見られるデザイン的な設計プロセスです。
「デザインが気に入った」という時、ユーザーはプロダクトの設計図を誉めている。
少し話が逸れますが、日常生活で「〇〇のデザインが気に入った」というような表現をすることが多々ありますね。これを私たちが、「〇〇の見た目が気に入った」と同義として捉えていることも、デザインという言葉の意味がわかりにくい原因となっています。では果たして、この文脈では「デザイン = 見た目」なのでしょうか?
ここまでの「デザイン = 大量生産のための設計」という�前提を踏まえると、「〇〇のデザインが気に入った」という表現は、その見た目が気に入っているという意味ではなく、「そのプロダクトの設計が気に入っている」という意味であることがわかると思います。なぜなら、そのデザインは目の前にあるモノに固有の特徴でななく、同等に大量生産された同じ製品すべてに対して言えることだからです。逆に大量生産されていないものに対して、「デザインが気に入った」とは言わないですよね。「モナ・リザのデザインが好き」という人がいたら、違和感を感じると思います。これは、私たちが生活の中で無意識のうちにデザインという言葉と大量生産された製品を紐づけて認識しているからなのです。
デザインとアートの違い。表現者の意図が境界線を作る。
前項で、「モナ・リザ」の話が出ましたが、「デザインとアートの違い」もなかなか明確な回答が得られないモヤモヤとしたトピックではないでしょうか?これについても、「大量生産を意図しているかどうか」という点が「アート的なもの」と「デザイン的なもの」の違いを理解する上で大きなヒントとなります。
まず、モナ・リザはアート的だと多くの人が感じるでしょう。なぜなら、モナ・リザからは大量に複製されることによって目的を達成するという意図は見えてこないからです。つまり、大衆の扇動などといった目的というよりは、「表現」という枠組みに近く見えるのです。その他の「アート」と呼ばれるものに対しても同じようなことが言えると思います。自己表現的なメッセージを持つものがアート的であり、大衆を意識して設計され大量生産されたものがデザイン的であるということです。もちろん、印刷技術や資本主義以降の世界ではこの境界はどんどん曖昧になっていき、純粋なアートとは何かを定義するのは非常に難しくなっています。明確にデザインを定義することはできても、アートの定義はどんどん曖昧になってきています。言い方を変えると、アートがデザイン化してきているとも言えるかもしれません。近年においては、「大衆に理解されること」を目的としていないことが特に明確な現代アートなどが、アート的なものとして取り上げられやすいのにはこのような背景も関係しているのではないでしょうか?
音楽は全て��アートなのか?大量生産による音楽のデザイン化
ここからは、少し踏み込んで複製技術の登場と発展によってアートがよりデザイン化していった経緯を見てみましょう。みなさんは「アート」と聞いて何を思い浮かべるでしょうか?絵画、インスタレーション、写真など様々な分野がありますが、「音楽」は最も身近でアート的なものの一つではないでしょうか?音楽というと、アートというイメージが強いですが、音楽は大量生産されることを意識して設計されているか?という観点で見るとどうでしょうか?
音楽もレコードやCD、そしてMTVなどといった大量生産・消費技術の発展とともに形を変えてきた存在です。個々のミュージシャンを見ると、アート的な思考で音楽を作っているかもしれません。しかし、その音楽を発表するレコード会社は、大衆を意識した音楽とミュージシャンという商品をデザインすることによって成長した極めてデザイン的な産業ではないでしょうか?ミュージシャン自身がアート的な思考で音楽を作っていたとしても、その曲を発表するレコード会社による編曲やプロモーションによって、それがデザイン的な制作プロセスに組み込まれることも少なくないでしょう。特に現代のヒットチャートに乗るような音楽は、初めから産業的な成功を強く意識して「設計」されているものも多いですね。ある種、音楽の大量生産によって、近年は音楽においてもデザイン的な性格が強くなってきているのかもしれません。
大量生産されないアートはアートとしてのみ存在するのか?インターネットとSNSによる大量生産。
では、大量生産することのできないようなアートについてはどうでしょうか?例えば、一点ものの絵画やオブジェなどです。自己表現的なメッセージを持つものがアート的であり、大衆を意識して設計され大量生産されたものがデザイン的であると述べましたが、アーティストが一点ものの絵画を制作する時にはそれをコピーして売り出すことはあまり考えなさそうですね。では、絵画は純粋にアートなのでしょうか?これは現代において難しい問題です。なぜなら、インターネットが浸透した現代では、一点ものの絵画であっても、その画像コピーがSNSなどで拡散されて大量に消費される可能性があるからです。無名の画家がネットで一夜にして有名になるなどということもあるかもしれません。このようなことが容易に想像することができるような現代においては、ネッ�トという大量拡散装置をアーティスト自身も無視することは難しいでしょう。もし、アーティスト自身が、作品の画像(複製)がネットによって拡散されて、多くの人に好まれることを意識してその作品を「設計」したのであれば、それはある意味デザイン的なプロセスと言うこともできるかもしれません。それがアート的かデザイン的かは、制作者の意図によるものですが、制作者もネットによる大量拡散の可能性を無視できないような現代においては、あらゆるものが無意識のうちにデザイン化しつつある世界とも言えるでしょう。


まとめ
今回は、近年「設計」としての意味合いが定着しつつある「デザイン」という言葉について、さらに一歩踏み込んだ「多くの人に配布されることを前提としたモノの設計」という考え方について紹介しました。デザインが誕生し発展した背景や、アートとデザインの違いに目を向けると、デザインには大量生産され、多くのターゲットに届けられると言う前提が存在していることがわかると思います。多くの人にその「設計」にもとづいて作られたモノを届けることによって、人の行動や思考を変えようとするのがデザインです。そして、大量生産されるという前提において、すべてのデ�ザイン分野において重要なのはもちろん、ターゲットにそのデザインを通して「何を届けたいのか」という点です。この「目的」という観点を緻密に分析した上で、解決策を設計することが良いデザインを作るための重要なポイントとなります。
参考文献
リッカルド・ファルチネッリ (2021). 『ビジュアルデザイン論』 クロスメディア・パブリッシング