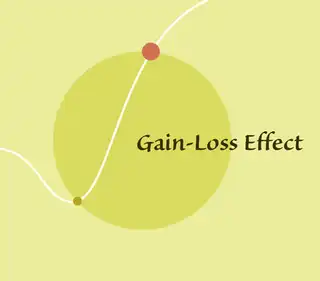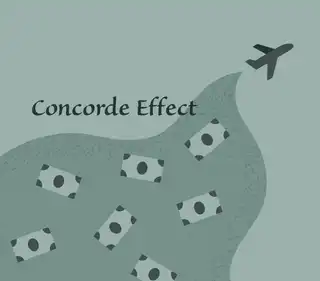ディドロ効果とは?
ディドロ効果(diderot effect)とは、新しく購入した商品やサービスによって理想的な価値を得たとき、その価値に合わせてこれまでの生活環境や身の回りのものを一新したくなるような、連鎖的な消費喚起を生じさせる心理現象のことです。
たとえば何か新しいものを購入したとき、その商品に合わせてほかのものも一緒に買い替えたという経験は��ありませんか。これまでもっていなかったような少し高価なソファが気に入って新しく購入してみたところ、今まで部屋にあったカーテンやほかの家具が急に見劣りして見えてきてすべて買い直したくなり、新しいソファのテーストやグレードに合わせて買い直してしまったというようなことはないでしょうか。行動経済学では、このようにひとつの購入品をきっかけに所有物のトーンを統一させたり、一貫性をもたせようとするような購買行動のことをディドロ効果と呼んでいます。
購買行動が加速してしまう怖い現象
このディドロ効果は1988年に、文化人類学者であり、カナダのグエルフ大学の准教授でもあるグラント・マクラッケンによって提唱されました。マクラッケンはフランスの『百科全書』を編纂した18世紀の哲学者のドゥニ・ディドロがエッセイの中で初�めてこの効果について述べたことに着目してディドロ効果を提唱しました。
ディドロがエッセイ『私の古いガウンを手放したことについての後悔』に記述したのは下記のような内容でした。
書斎で生活していたディドロはある日、知人から贈り物として高価なドレッシングガウンをプレゼントされます。彼はそのガウンをとても気に入りました。当初は単純に喜んでいたディドロですが、もらったガウンと自分の書斎を改めて見比べてみたところ、高品質でエレガントなガウンと比較するとディドロのこれまでの持ち物や家具は地味で野暮ったく見え始め、新しいガウンにマッチしていないことに不満を抱くようになったというのです。
そこでディドロは部屋に統一感や一貫性をもたせたいと考え、たとえば古い藁椅子をモロッコ革張りのアームチェアに、古い机は高価な新しいライティングテーブルに買い直したり、愛用していた版画をより高価な版画に新しく買い直していくなどの購買行動を始めました。
美しく高価なドレッシングガウンを手に入れたことをきっかけに、ディドロは最終的には借金を背負うまでモノを買い続けたといいます。ディドロはこの経験について「私は古いガウンの絶対的な主人であったが、新しいガウンの奴隷となった。貧乏人は見栄を張らずに気楽に過ごせるが、金持ちはいつも緊張の中にいる」と自己分析したそうです。
ディドロのエッセイを読んだ前述の文化人類学者のグラント・マクラッケンは、ディドロの購買行動から、“所有物と環境の調和を求めて次々に物を消費する心理”を見出し、これをディドロ効果と定義しました。
ディドロ効果を誘発する顕示的な消費行動
ディドロ効果が生じる心理的な背景は諸説あり、主に以下のような説があげられています。
人は本質的に統一感や一貫性を求める心理傾向をもっている → 人間のもつ基本的な心理のひとつに一貫性の原理というものがあり、人は自分の行動や信念などに一貫性をもたせたい傾向がある
生活に何かひとつ高いレベルのものが導入されると、生活レベル全体が影響を受ける傾向がある → たとえばひとつブランド品を手に入れると、自分の価値も高まったような自我拡張感が得られて、その後の選択が自然と影響されてしまう
購買や所有されるものが社会的なステータスの高いものであるほど顕示的な消費行動を誘発しやすい → たとえばハイブランドの洋服や高級車、ブランド品の腕時計など人の目に見えやすいアイテムは社会的ステータスを示すアイコンとしても機能し、顕示的な消費につながりやすい
人は購買行動や所有物によって自己顕示をする傾向があり、それを他者に伝えやすくする機能としてディドロ効果が発動する → 特別な意味のあるものの購買や所有はアイデンティティや自己の存在価値の形成につながりやすく、ディドロ効果を誘発しやすい
社会学者であり経済学者であるジュリエット・ショアは、1992年に著書の『浪費するアメリカ人—なぜ要らないものまで欲しがるか』の中でディドロ効果につながる顕示的消費のメカニズムについて触れました。
たとえば高級腕時計を購入したら自然とその腕時計にみあう洋服を購入したいと考えるように、ステータスや人の目を意識した競争的な消費は、自己をとりまく様々な情報からも影響を受けてしまいます。たとえば、周囲の身近な人々のライフスタイルがセルフイメージの比較対象になったり、マスメディアからの情報が階層を越えて個人の消費基準や意思決定に影響をもたらしたりするといった具合です。
SNSが普及している今日では消費や購買の情報はコミュニケーションのひとつであり、ステータスを示すアイコンとしても機能することを改めて認識させられます。
まとめ
新しい商品やサービスを購入すると、ほかの物もその商品のグレードに合わせて買い直したくなる心理現象、ディドロ効果についてまとめました。ディドロ効果はビジネスの多岐に渡る場面で使用されており、たとえば次のようなマーケティング施策に応用されています。思わず全品揃えてしまいたくなるような世界観のあるブランディング施策、未収集のアイテムが気になってしまう魅力的なシリーズコレクション、セットで所持することで魅力が倍増するコーディネート提案等々。ただし、持続可能な経済活動などの文脈においてはディドロ効果に否定的な意見も少なくなく、決して時流ではない部分もあるといえるでしょう。


参考文献
Diderot effect『Wikipedia the free encyclopedia』(最終閲覧日2023年9月29日)
Grant McCracken『Wikipedia the free encyclopedia』(最終閲覧日2023年9月29日)
ドゥニ・ディドロ『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(最終閲覧日2023年9月29日)
一貫性の原理『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(最終閲覧日2023年9月29日)