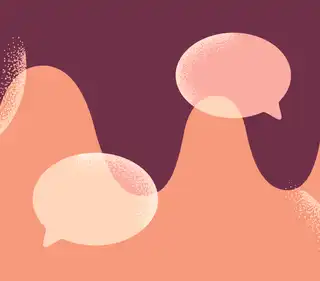点字と文字を組み合わせた新しい書体から、オンライン上で顔だけを使って楽しむスポーツまで、ユニークな作品を次々と生み出している「発明家」の高橋鴻介さんは、現在オランダを拠点とし、国際的に活動の場を広げています。そんな高橋さんが発明をはじめたきっかけは、会社の業務の傍らで進めていた「マイプロジェクト」。「ちょっとでもいいから、マイプロジェクトに時間をかけた方がいい」という高橋さんに、その極意を伺いました。
電通時代に��1日1発明、「接点の発明」にたどり着く
発明家・高橋鴻介さん
―― 「発明家」としてご活躍されるまでの経緯は?
僕は生まれが秋葉原で、小中学校からずっとモノづくりにすごく興味がありました。当時の将来の夢はロボットのエンジニアでしたが、高校の文化祭でパンフレットを作ったとき、デザインってめちゃくちゃ面白いと思って。慶応義塾大学の湘南藤沢キャンパスに進学して、デザインとエンジニアリングの両方を学びました。
大学卒業後はいろんなことができそうな電通に就職して、広告の仕事をしていました。そこでは先輩と業務日誌を交換する制度があったんですけど、僕の先輩には「基本的に言いたいことがあれば直接言えばいい。その代わりに1日1個アイデアを考えて俺にプレゼンしろ」と言われました。それで1日1個発明していたら、そっちの方が楽しくなっちゃって(笑)。
―― 「1日1発明」は業務とは関係のないことでよかったのですか?
そうです。普段はクライアントワークで顧客の依頼に応える仕事をしていましたが、「1日1発明」では自分が好きなもの、作りたいものを書いていました。その中からいくつかは実際に形になりました。
いちばんの転機になったのは、点字と文字を組み合わせた「Braille Neue(ブレイルノイエ)」という書体を作ったことです。視覚障害のある人と出会って、点字の歴史の話をしていたときに、実は点字はもともと目が見える人が見えにくいときに読めるよう発明されたかもしれないという��話を聞いて。その人に「高橋君も点字が読めたら暗闇で本が読めるようになりますよ」と言われて、興味を持ち始めたのがきっかけです。
Braille Neue ©Kosuke Takahashi
当時、僕は全く点字が読めなかったので、「目の見える人も見えない人も同じものを共有できる書体があれば素敵だな」と思って、文字と点字が一体となった書体をデザインしてネットにアップしてみたら、結構反響があって。渋谷区役所のユニバーサルサインの中に、その書体を入れてもらえることになりました。
それまで発明は趣味でやっていたんですけど、「仕事になるやん、これ!」と思った瞬間でした。
―― 「ブレイルノイエ」のほかにはどんな発明がありますか?
その後はプロジェクトに誘ってもらえる機会が増えて、全国盲ろう児教育・支援協会の支援を受けつつ、触覚で楽しめるゲームを作りました。
たくさんの触覚カードの中から同じ触覚の2枚を見つけ出す「たっちまっち」とか、カードの指示に合わせて、複数のプレーヤーが指で棒を支える「YUBIBO」とか、盲ろう者はもちろんのこと、年齢、国籍、障害などに関係なく楽しめるシンプルなゲームです。遊びには言葉とか障害とかを楽しく乗り越える力があるんですよね。
2025年のダッチ・デザイン・ウィークにて。「YUBIBO」を楽しむ来場者たち。©Kosuke Takahashi
自分の作品を見返してみると、そういうコミュニケーションのギャップが埋まっていく瞬間が僕は嬉しいんだな、というのを感じて。そこから、「接点の発明」という自分のテーマが生まれました。
フリーランスになって海外に出たのも、言葉の通じない海外にこのテーマを持って行くとどんなことが起きるかな、と考えたのが理由のひとつです。一昨年、オランダの「ダッチ・デザイン・ウィーク」を訪れて、未完成で、実験的なプロジェクトがたくさんあるのが気に入って、昨年ワーキングホリデーのビザを利用してオランダに来ました。
―― オランダではどんな活動をされていますか?
来た当初はなんのプランもなく、なにをしていいか分からなかったのですが、ロッテルダムの財団である「V2_」がアーティストを支援してくれるというので申し込んだら、運よく受かって。オーストリアに住みながらプロジェクトをはじめる機会を得ました。
そのとき取り組んだのは、顔の筋肉を使って競い合う「Facial Sports(フェイシャルスポーツ)」です。日本にいるときに車いすユーザーの友人と話していて、車いすの人とそうでない人が一緒に遊べるスポーツって意外とないなって言う話になって。そこから着想を得てオンラインで顔にエフェクトをつけるフィルターを使って、顔の動きを得点化するスポーツを作りました。
「眉毛リフティング」といって、眉毛を上げ下げするスポーツとか、口を動かすとデジタルの風船が膨らんで、最初に破裂させた人が勝ちの「チューチューバルーン」とか。子どもからお年寄りまで、みんな対等に遊べるのが特徴なんですよ。
オーストリアでの「Facial Sports」展示の様子 ©Kosuke Takahashi
―― 面白いですね!これはどこかにアクセスすれば遊べるんですか?
これは今、アプリ化を進めているところで、まずはイベントで運用してもらうところから始めようとしています。ロッテルダムのチームとは、世界中の美術館にアプリを送って繋いでもらって、世界大会をやろうという企画も挙がっています。
あとは今、新しい発明として、佐賀県の肥前吉田焼とのコラボレーションで器を作っています。器の底についている「高台」の部分をネジの形にして、3Dプリントしたパーツなどをねじ込むことで、器自体をいろんな形にハックできるものです。
2月の半ばに開催される「OBJECT Rotterdam」という展覧会でまず完成品を発表して、その後は「Bambu Lab」という中国の3Dプリンターの会社と組んで、ユーザーのコミュニティで自分の好きなパーツを作ってもらうという、デザインコンペみたいなものを企画しています。
Co-rcelain ©Kosuke Takahashi
「興味の鉱脈」を発見する。
―― 高橋さんの作品は、会社の仕事以外で進めていた「マイプロジェクト」から生まれていますが、自分のテーマはどのように決めればいいのでしょうか?
自分がやりたいことは最初から見つかるわけではないと思います。僕も毎日毎日アイデアを書いてプロジェクトをやってきましたが、「これは違うな」と、消えていくアイデアがほとんどです。ブレイルノイエも、100個、200個と�出してきた中で淘汰されて生き残ったアイデアだったりします。
テーマがまだわからない人は、ラフでいいから、いろんなアイデアをまず書いてみて、それを見て自分の心が動くかどうか試してみるといいかもしれません。やりたいことがあるからアイデアが出るというよりは、アイデアを出すことでやりたいことが見えてくるイメージなんですよね。
それを続けていると枯れちゃうアイデアもあれば、ちゃんと育ち切るアイデアもあるし、ふとしたきっかけで新しいアイデアが芽吹いたりもする。ひとつひとつのアイデアに毎日ちょっとずつ水をあげていく感じで、プロジェクトを進めていくのが一番いいのかな、と思います。
―― でも、アイデアを毎日考えるというのは、結構大変ですよね。
最初からアイデアを考えなくてもよくて、例えば展示会を見に行ったり、映画を見たり、本を読んだりしたときに、ちょっとずつ出会う「いいな」と思ったことをどこかに書き留めたりすることからはじめてみるのもいいと思います。その結果、自分の興味が見えてくる。
やりたいことが最初からみんなちゃんとあると思っている人が多いけど、実はそうじゃなくて、自分を研究しないと出てこないものです。「この辺かなあ」と、自分という山をカンカン掘っていたら、「あ、ここだったか!」みた��いに、興味の鉱脈を発見するんですね。
僕も毎日アイデアをストックする中で、意外とこんなことに興味があったんだって、後から気付く瞬間がすごく増えてきました。自分のことって、自分がいちばん分かっていなくて。だから自分をちゃんと研究する時間を取ることですね。
Facial Sports ©Kosuke Takahashi
―― 私たちは普段、どうしても人から頼まれた仕事を優先させてしまって、自分のことは後回しになりがちですよね。
人と仕事をすると、約束とか、責任とか、義務とかが増えて、時間がなくなりがちですが、そこをちょっと踏ん張って、自分の時間をもうちょっと大切にしてあげることが僕は大事だなと思います。
僕はクライアントワークをずっとやっていたときに、自分の感覚よりクライアントとか社会の感覚を優先するようなっていまし�た。それは悪いことじゃないんですけど、それをずっと続けていると、だんだん自分がいなくなってくる感じがあって、それがいちばんしんどかったんですよね。そのときに心を救われていたのが「1日1発明」で、自分が何をいいと思っているかを考えて、形にするという行為だったんですよ。
自分が好きなものとか、自分が心をこめて「いい」と言えるものを自分が知っていると、クライアントに提案するときも自信を持って「いいものだ」と言える。クライアントワークとか、人となにかをやるときにもすごくいい影響があるのを実感しました。それがマイプロジェクトをやる一番の効能じゃないかな、と思います。
オンラインで「眉毛リフティング」を競う仲間たち ©Kosuke Takahashi
デジタルデザイナーの「マイプロジェクト」の進め方
―― 自分の好きなものを週末にちょっと作ってみるというデザイナーは多いかもしれませんが、デジタルデザインだとプログラミングを伴いますよね。「フェイシャルスポーツ」とか、高橋さんのデジタルプロダクトはご自分でプログラミングされているのですか?
僕はもともとフィジカルなプロダクトデザイン畑出身なので、あまりプログラミングが得意じゃなくて、エンジニアの友達と一緒にやっています。
フェイシャルスポーツもエンジニアの友達と話していたら、「面白そう!一緒にやってみよう」となって。夜な夜な部活動みたいに集まって作りました。お互いに価値観が揃うと、お金とかじゃなくて、本当に仲間として楽しくできる。
不思議なことに、うまく進むプロジェクトって、ちょうどいいタイミングで良い人との出会いがあるんですよね。来たるべきときに出会いがあるのは、僕がたぶんいろんな人に話しているからだと思います。面白いな、と思うアイデアがあったら、誰かと会ったときに「口に出してみる」というのが一番速い。そうすると、いつのまにか仲間ができたり、共感者が出てきたりして、めちゃめちゃ大きな力になると思います。
ダッチ・デザイン・ウィークでの展示を手伝ってくれた友人たちと。 ©Kosuke Takahashi
―― 仲間と「得意」を持ち寄ってプロジェクトを進めるのはいいですね。でも、デジタルプロダクトデザインだと、どうも「役に立つツール」に価値が置かれがちで、ピュアに趣味的なものが作りにくいと感じている人も多いようです。
僕はむしろ、便利だけじゃなくて「テクノロジーをこんなムダなものに!」みたいなことも大事にしてほしいと思います(笑)。ともすれば冷たく感じられるデジタルデザインにこそ、体温のあるユーモアが効くなと思っていて。僕の作ったフェイシャルスポーツもそうなんですけど、「くだらないけど、面白そう!」みたいな。
「くだらない」といっても、そこに価値を見出してくれる人は絶対いて、世界中の人にワンアイデアでリーチできるのがデジタルデザインのすごく面白いところです。フィジカルなプロダクトを売ろうと思うと、モノを送ったりお金がかかったりしますけど、デジタルプロダクトだといちば�んコストが低く、世界中の人に使ってもらえます。それはやっぱり強みですよね。そういう意味でデジタルデザイナーの人たちは、下駄を履いていると思って良いと思いますよ。
―― なるほど、デジタルプロダクトこそ世界中で共感者を見つけやすいんですね。
そうですね。日本のデジタルプロダクトデザイナーの人たちがすぐできることとしては、とりあえず英語に翻訳して発信するということかもしれません。オランダに来てからすごく思うのは、日本の面白いクリエイターが世界に知られていないのがすごくもったいないということです。今はAIですぐに日本語のアプリを英語にしてもらえるから、ぜひ自身のプロダクトを英語対応してみることをお勧めします。
X、Facebook、Instagram、ブロックチェーンを使ったアート市場など、置き場所もいろいろあります。自分の作品が知らない文化で急に広がったりするから、デジタルは面白いんです。
ブレイルノイエも Xにあげてみたら、実はいちばん最初に記事化してくれたのは、ブラジルの人だったんですよ。そういう意味で、「アイデアはすごいパスポートだな」っていつも思いますね。ぜひ自分のアイデアをいろんなところで口に出して、発信してみてください。
フリーランスライター。日本、中国、マレーシア、シンガポールで主にライター・編集者として活動した後、2004年よりオランダ在住。同国の生活・教育・イノベーション・デザインを雑誌やオンラインメディア、ラジオなどで紹介するほか、オランダと日本を結ぶさまざまな活動を手がける。著書に『週末は、Niksen。』(大和出版)。
https://www.yamantextfactory.com/