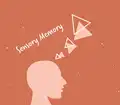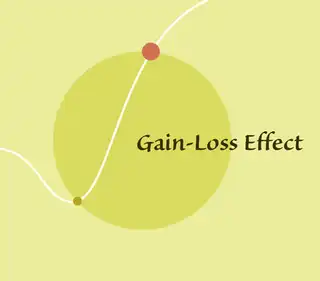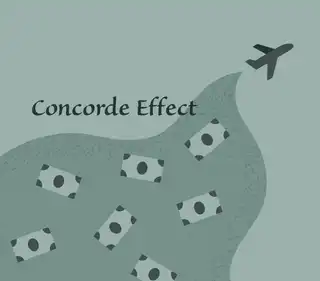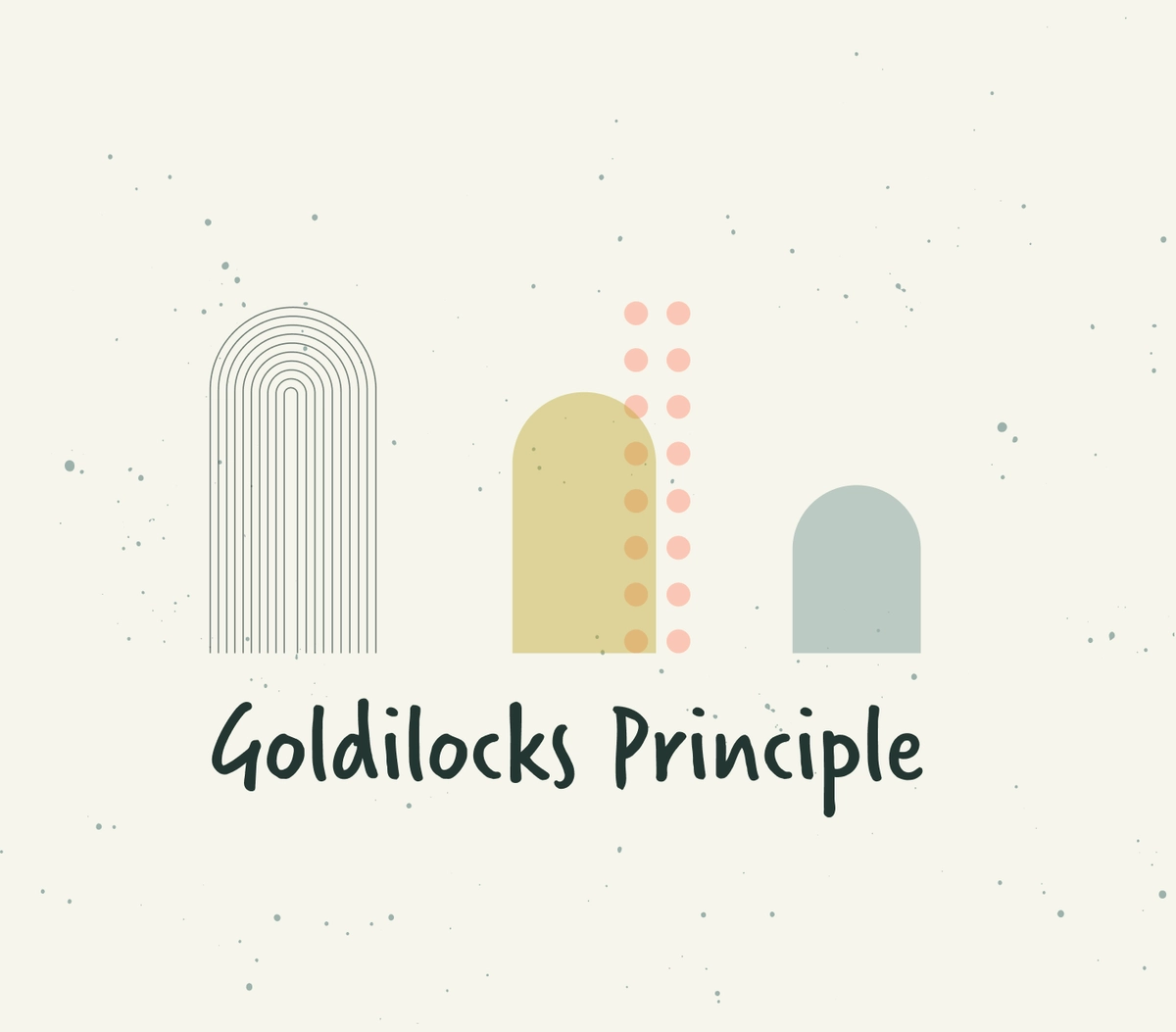
ゴルディロックス効果とは?多くの人が無意識のうちに真ん中の選択肢を選んでしまう傾向
ゴルディロックス効果とは、選択肢が3つあった場合、多くの人が無意識のうちに真ん中の選択肢を選んでしまう傾向があるという心理現象のことです。たとえば同じ商品を異なる3つの価格帯で販売すると、真ん中の価格帯の商品が最もよく売れる傾向があります。1500円、1200円、980円と3つの価格のお弁当が並んでいたとしたら、いちばんよく出るのは真ん中の1200円になります。
日本ではゴルディロックス効果は「松竹梅の法則」と呼ばれています。松竹梅の法則とはマーケティング業界などで用いられる用語で、松・竹・梅と3種類のグレードの商品が用意されていた場合、消費者の多くは竹を選ぶであろうという推論にもとづいて活用されています。
童話『ゴルディロックスと3匹のくま』
このゴルディロックスの心理効果の原理は、『ゴルディロックスと3匹のくま(Goldilocks and the Three Bears)』という童話に由来しています。イギリスに古くから伝わる昔話『3びきのくま』を、イギリスの詩人ロバート・サウジーが散文で記したことで広く知られるようになった童話です。
物語の主人公はゴルディロックスという少女です。少女は3匹の熊が住む家に留守中に入り込んでしまい、そこで3種類のお粥や椅子やベッドを試すのですが、熱すぎるのも冷たすぎるのもいやだし、固すぎるのもやわらかすぎるのも気に入らない。最終的にはいずれも真ん中の「ちょうどよい」温度や大きさや固さのものを選んだというストーリーです。この物語から、「ゴルディロックス=ちょうどよい程度」という概念やイメージが広まり、心理学や行動経済学などの領域で研究が重ねられるようになりました。
選択肢が3つであることにも意味があります。2択の場合はどうしても、価格が安いほうの選択肢が選ばれやすくなります。選択肢を4つ以上に増やしてしまうと、逆に選ぶことが難しくなります。人は選択肢が多すぎると選びきれなくなり、答えを出すことを諦めてしまう傾向をもっているからです。これらのことから、選択肢は多すぎても少なすぎても適切な選択をすることができなくなるという側面が指摘され、選択肢を提案する際にはバランスや中庸が意識されるようになりました。
ゴルディロックス効果の心理学的な背景
ゴルディロックス効果の根拠を心理学や行動経済学の観点から見てみましょう。類似的な心理傾向としては以下の3つが挙げられています。
社会的比較「相対的な価値で判断する傾向」
人は正確な自己評価をするために、自分と他者を比較することで自己評価をしたり、自己を定義づけるとされています。これはアメリカの社会心理学者のレオン・フェスティンガーが社会的比較理論の中で指摘しました。この、判断するために比較するという心理的な傾向から、人は絶対的な価値ではなく相対的な価値で判断する傾向も合わせもつことが示唆されています。そのため、意思決定の際には判断材料が必要であり、アンカリング効果やフレーミング効果のように、先に提示された情報と比較したり心理的な枠組みをもとに比較検討しながら意思決定を行っています。その際に選択肢の中で真ん中のものが適切に見える可能性が高いことが、多くの研究から指摘されています。
極端と損失を回避する心理
人のもつ基本的な心理の中に、利益より損失のほうを大きく感じてしまう損失回避があります。行動経済学者のダニエル・カーネマンと心理学者エイモス・トヴァスキーがプロスペクト理論の中で提唱しました。彼らの研究の中で、人は基本的に損をしたくない気持ちが強いことが示されています。選択肢を選ぶ際も“失敗して損をしたくない”という心理が働いて、極端な選択肢ではない、無難な“真ん中”を選ぶ可能性が高まるのだとされています。
認知的負荷の影響
人の情報処理能力には限界があります。情報を保管する脳にはキャパシティがあり、たとえば、人が15秒から30秒の間にワーキングメモリに正しく記憶できる項目の数は、平均的に7±2の範囲におさまることがアメリカの認知心理学者ジョージ・ミラーの研究「マジカルナンバー7±2」により知られています。そのため人は複雑な判断は回避するという傾向があり、選択肢が多い場合には様々な理由から選びやすい真ん中を選択することで、認知的な負荷の軽減を求めることがあると示唆されています。
購買決定におけるゴルディロックス効果の検討
学生を対象に行われた、購買決定にまつわる実験・調査をまとめた論文があります。名古屋文理大学の学生に対して行われたアンケート調査の中から、ゴルディロックス効果についての調査結果部分をご紹介します。
フードビジネス学科の学生81名に、カフェに入ったときに3つの価格帯のランチメニュー(Aランチ1100円、Bランチ900円、Cランチ700円)があったら、どれを選ぶか回答してもらう
約63%の学生が、真ん中の価格帯であるBを選択
いつも学食でワンコインで昼食をとっている大学生たちが最低価格のCではなくBを選んだということは、所得制約要因よりもゴルディロックス効果が強く作用したと推察できる
(関川 靖 (2015). 「比較を基準にした購買決定」より)
上記の結果から、“隣りに並んだ価格が、支払ってもよいと思う価格に対する意思決定の基準になっている”“失敗したくない気持ちが無難なものを選ぶという行動を起こさせ、3つの価格帯の真ん中を選ぶことになる”という仮説が証明されました。
まとめ
人は無意識のうちに真ん中の選択肢を選んでしまう傾向をもっているという、ゴルディロックス効果についてまとめました。人の認知は、常に目安や基準となる対象や情報を求めています。選択肢が多すぎれば混乱し、少なすぎる選択肢から選ばなければならないと満足感が損なわれます。選ぶことを楽しめるような工夫がサービスとなる時代です。


参考文献
ゴルディロックスの原理��『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(最終閲覧日2023年7月31日)
ダニエル・カーネマン・村井章子(訳)(2012). 『ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか?(上)(下)』 早川書房
真壁昭夫 (2019).『行動経済学 見るだけノート』宝島社
服部雅史・小島治幸・北神慎司(2022). 有斐閣ストゥディア『基礎から学ぶ認知心理学人間の認識の不思議』 有斐閣
鹿取廣人(編)・杉本敏夫(編)・鳥居修晃(編)・河内十郎(編)(2020).『心理学 第5版 補訂版』 東京大学出版
関川 靖 (2015). 比較を基準にした購買決定 名古屋文理大学紀要(16) , 5-11
3びきのくま『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(最終閲覧日2023年7月31日)
ロバート・サウジー『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(最終閲覧日2023年7月31日)
社会的比較理論『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(最終閲覧日2023年8月3日)