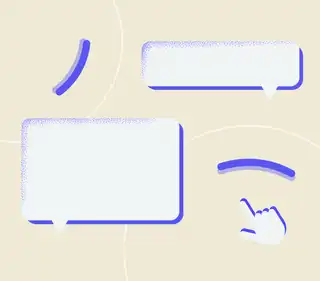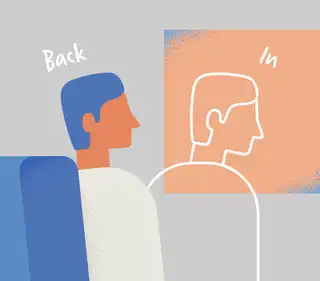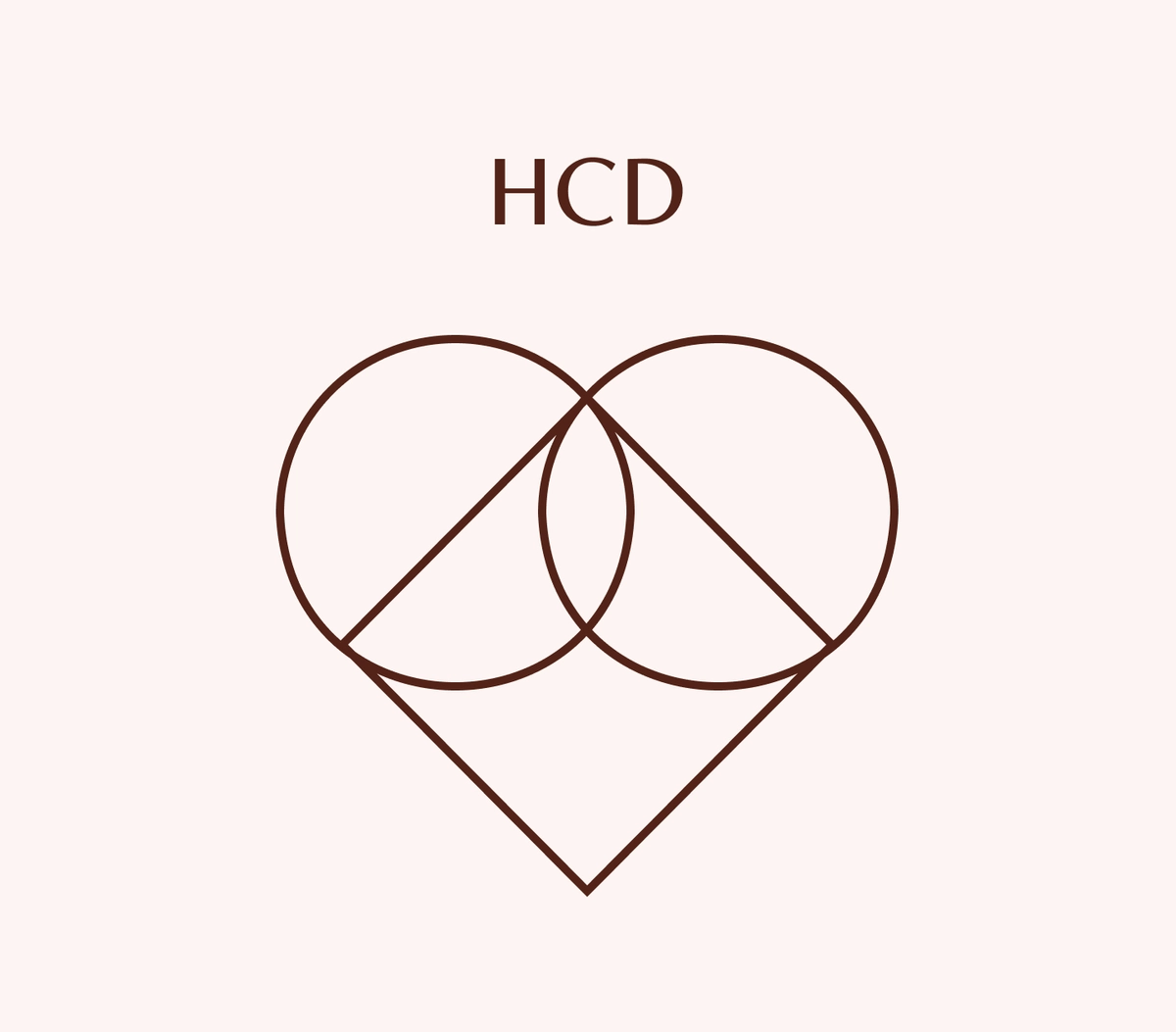
人間中心設計(HCD)とは?
人間中心設計(Human-centered design)とは、人間(ユーザー)を中心としたモノづくりのことで、人間がそのプロダクトを利用する際の体験を念頭に置いたプロダクトデザインのフレームワークです。
ISOによる人間中心設計の定義
ISO(国際標準化機構)の国際規格であるISO9241-210の定義によると人間中心設計とは以下のように定義されています。
人間によるシステムの利用体験に焦点を当て、人間工学及びユーザビリティの知識と手法とを適用することによって、システムをより使いやすいものにすることを目的としたシステム設計へのアプローチ
https://www.iso.org/standard/77520.html
ISOの定義では、「ユーザー」中心設計ではなく「人間」中心設計として理由として、いわゆる「エンドユーザー」以外にも�利害関係者が存在する場合を考慮してより広い意味を持つ「人間」を採用しているとのことです。
人間中心設計とUXデザインの違い
人間中心設計と似た言葉に、UXデザインがあります。UX(ユーザーエクスペリエンス)デザインとは、「ユーザーがサービスや製品を通して得られる顧客体験」の設計を意味する言葉です。人間中心設計が、ユーザーとプロダクトのインタラクションに注目するのに対し、UXデザインはより広い意味でのユーザー体験の設計のことを指します。
また、人間中心設計が「使いやすい」システムを作ることを目指すのに対し、UXデザインは常に「ビジネス面での利益」につながるようなユーザー体験の改善を目指すことにも特徴があります。
人間中心設計(HCD)の6つの原則
前述のISO9241-210の定義によると、人間中心設計には6つの原則があります。
ユーザー、タスク及び環境に対する明確な理解に基づいた設計
デザインと開発のプロセスへのユーザーの参加
ユーザーの評価に基づいた設計と改良
評価と改善のプロセスの反復
ユーザー体験全体(UX)を考慮した設計
多分野のスキルや視点を持ったデザインチームの編成
1. ユーザー、タスク及び環境に対する明確な理解に基づいた設計
人間中心に使いやすいデザインを作るというと、単純に聞こえますが「使いやすさ」とはとても主観的な概念で、「誰にとっても」使いやすいものを作るというのは実はとても難しいことです。また、ユーザビリティテストを行うにあたっても、無作為に集めた人を対象にテストを行うとあまりにも多種多様なフィードバックが集まってしまい、プロジェクトの目指す方向性がわからなくなってしまいます。
そこで人間中心設計の原則では大前提として、ユーザー、タスク、環境への理解が必要だとしています。言い換えると、
誰が
何を
どのような状況で
サービス及び、プロダクトを利用するのかを明確に理解・定義することが重要となります。この3つの��状況設定を把握することで、プロジェクトのスコープが明確になり、施策の優先順位づけや取捨選択が可能となります。極端な言い方をすると、「10代向けのアプリをデザインしている時に、50代のユーザーにとっても使いやすいかを考える必要はない」ということです。
2. デザインと開発のプロセスへのユーザーの参加
実際にデザインや開発しているものが、人間中心的な設計になっているかどうかを判断する一番の近道は、想定している利用者に実際に意見を聞くことです。プロジェクトの要所でユーザーの意見を取り入れながら進めることで、小さな軌道修正をしながら最適なプロダクトをデザインすることを可能にします。
また、ユーザーにプロトタイプを試してもらう場合などは、前項の「どのような状況で」にも注意を払うと良いでしょう。実際にユーザーがプロダクトやサービスを使う状況は、会議室やインタビュールームとは大きく異なります。できるだけユーザーがプロダクトを使う実際の状況に近い状態でプロトタイプに触れてもらうことが、有用なフィードバックをもらう重要な鍵となります。
3. ユーザーの評価に基づいた設計と改良
プロジェクトの設計と改良を行う際の優先度付けとタスクの取捨選択の指標は、ユーザーにとっての重要度をもとに考えるべきという考え方です。プロジェクトチームの想像や予測に頼るのではなく、ユーザーによる評価をもとにデザインを行うことが人間中心設計には欠かせません。
逆に、人間中心的ではない設計の良い例が、ビジネス上の利害関係者からの要望に基づく設計や改良です。ユーザーからは要望はないものの、ビジ��ネスの担当者からの要望で設計を変更しなくてはならない場合は、人間中心設計の原則から外れてしまうことに気をつけましょう。
4. 評価と改善のプロセスの反復
アプリやソフトウェアのデザインや開発は、リリースまでで完了するものではなく継続的に続くプロセスです。サービスの公開後も常にユーザーからのフィードバックを得られる状態を保ち、評価と改善のプロセスを継続的に行いましょう。
サービスのリリース後にどんなに評判が良くても、市場の状況は常に変わります。自社製品に変化がなくても、競合製品やトレンドの変化によって常にユーザーの評価は変わります。例として、モバイルアプリであればApp Storeのレビュー機能などを活用して、常にユーザーからの評価が届くような状態を保つと良いでしょう。
5. ユーザー体験全体(UX)を考慮した設計
前述したように、UXは人間中心設計よりも広い意味での「全体のユーザー体験」を意味します。「使いやすい」プロダクトであると同時に、「使いたい」プロダクトになっているかにも目を向けて設計を行いましょう。
6. 多分野のスキルや視点を持ったデザインチームの編成
人間中心設計はデザイナーだけのチームで行うものではありません、エンジニア、データアナリスト、マーケターなど多様な分野からの視点を取り入れながら取り組むことで、より広い視野を持ってプロダクト開発を行うことができます。
人間中心設計の基本プロセス
人間中心設計は4つのプロセスからなります。この4つのプロセスを繰り返すことで、段階的に製品の質を上げることができるというPDCAサイクルにも似た手法でデザインを行うことが推奨されています。
調査:利用の状況の把握と明示
分析:ユーザーの要求事項の明示
設計:解決策の作成
評価:要求事項に対する設計の評価
1. 調査:利用の状況の把握と明示
人間中心設計6つの原則の1つ目である、「ユーザー、タスク及び環境に対する明確な理解に基づいた設計」の根幹となる部分です。まずは、明確に「誰が」「何を」「どのような状況で」プロダクトを利用するのかに対する理解を深める必要があります。
具体的には、ユーザーインタビューやアンケートを通して明確なペルソナとカスタマージャーニーの把握ができるまでユーザーとの対話を繰り返しましょう。さらに、5W1Hのフォーマットに落とし込んでユーザーの行動心理を深掘りしていくと、後のプロセスでの施策考案に役立ちます。
5W1H
When = いつ
Where = どこで
Who = だれが
What = 何を
Why = なぜ
How = どのように
2. 分析:ユーザーの要求事項の明示
「1. 調査:利用の状況の把握と明示」で定義したユーザーがこのサービスやプロダクトを通して、「何を成し遂げたいのか?」「何を求められているのか?」を要求事項として定義します。ここで定義した要求事項は、後のフェーズでデザインに対するチェックリストとしても機能することになる重要な指標です。また、可能であればこの段階で要求の優先度を把握できるとさらに良いでしょう。
コーヒー1杯分に最適なマグカップが欲しい
食器棚に収納した際にかさばらない (優先度: 10)
熱い飲み物を入れた際に持ち手が熱くならない (優先度: 6)
片手で持ちやすい重さ (優先度: 8)
食洗機で洗える (優先度: 3)
3. 設計:解決策の作成
「2. 分析:ユーザーの要求事項の明示」で明確になったユーザーの要求事項に応えることができるデザインを作成します。多くの場合は、成功率を高めるために初めはプロトタイプとして作成し、本当にユーザーの要望を解決できるかを検証しながら最終的なデザイン決定に至ります。
4. 評価:要求事項に対する設計の評価
デザインした解決策を実際のユーザーに見てもらい、ユーザーの要求に的確に応えることができているかについてフィードバックをもらいましょう。「もっとこうだったら良いのに」というような視点を沢山引き出して、サービスの更なる改善を目指しましょう。
人間中心設計の資格、人間中心設計専門家とは?
日本には、人間中心設計の推進を目指す人間中心設計推進機構(HCD-Net)という非営利活動法人があります。このHCD-Net提供する認定資格に「HCD-Net認定 人間中心設計専門家」というものがあります。簡単に言うと、人間中心設計に関する資格です。
2種類の人間中心設計専門��家資格
HCD-Netは以下の2種類の資格を設けており、
人間中心設計専門家(認定HCD専門家)
https://www.hcdnet.org/certified/about/post_1.html
HCDに関わる実務経験を5年以上持ち、HCD実践の基礎、マネジメント、研究、組織開発に関わる一定水準の能力を有する人材。3年ごとに資格を更新する必要がある。
HCD-Net認定人間中心設計スペシャリスト(認定スペシャリスト)
https://www.hcdnet.org/certified/about/post_1.html
HCDに関わる実務経験を2年以上持ち、HCD実践の基礎に関わる一定水準の能力を有する人材。3年ごとに資格を更新する��必要がある。
要求される実務経験の長さからも分かる通り、人間中心設計専門家の方が認定の難易度が高い資格となります。
人間中心設計専門家の試験内容
人間中心設計専門家の試験内容は、一般的な資格試験とは異なり、書類審査で合否が決まります。また、以前に人間中心設計専門家、及びスペシャリストの認定を受けた方が、新たな受験者の認定審査を行なっている点も特徴です。
まとめ
本記事では人間中心設計の基本をはじめ、その原理やプロセスを紹介しました。サービス提供者からユーザーの顔が見えにくいITサービスでは、特に人間中心設計的な考え方が重視されており、いかにユーザーの意見を汲み取りながらサービス開発を行うかがビジネス成功の鍵となっています。まず何から始めて良いか迷った場合は、今回紹介したプロセスの1ステップ目からでも手を出してみてはいかがでしょうか?ユーザーについて理解が深まるだけで、ビジネスの抱えている課題を解決するための施策のイメージが湧いてくるかもしれません。