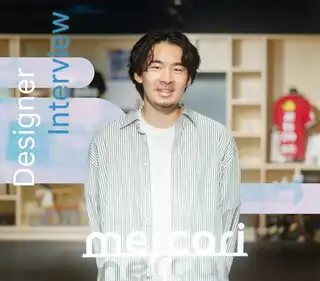2024年5月、集英社は縦読みマンガアプリ「ジャンプTOON(トゥーン)」をリリースした。同社が築いてきた「週刊少年ジャンプ(以下、ジャンプ)」、及びマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」のブランド力を武器に、近年盛況な縦読みマンガ市場へ参入したという。
「ジャンプTOONには、どんな狙いがあり、競合他社のサービスとどうUI・UXの差別化を図っているのか。同アプリの統括編集長 浅田貴典氏と開発を担当したサイバーエージェント社の開発チームに取材した。
サムネイル:(左)©ジャンプTOON/集英社、(右)『ラスボス少女アカリ~ワタシより強いやつに会いに現代に行く~』©岸馬きらく・酒ヶ峰ある/集英社
「作家の視点」を第一に、ビジネスモデルを決定
「ウェブトゥーン」とは「web」と「cartoon」を組み合わせた造語で、画面の小さなスマートフォン上でも読みやすいデジタルコミックの形態の一つだ(日本経済新聞参照)。 ただし、日本で「ウェブトゥーン」はNAVER WEBTOON Ltd.の登録商標であるため、日本では縦スクロールのマンガは「縦読みマンガ」と呼ばれる。
インプレス社の調査によると、2022年度の電子書籍市場規模は前年比9.4%増の6026億円で、そのうちの約1割が縦読みマンガの市�場規模にあたると見られる。世界的にも縦読みマンガの市場が拡大しており、グローバルインフォメーションの調査によると、2023年の40億9,300万米ドルから2030年には54億8,420万米ドルに成長すると予測されている。
2024年5月、集英社は成長市場の縦読みマンガ市場に参入した(©ジャンプTOON/集英社)
集英社では、若手社員による縦読みマンガ市場参入の提案を受けて参入を決定。ビジネスモデルについて社内で多くの議論が勃発したという。
まずは、自社でメディアを持つか否か。縦読みマンガの作品だけを制作し、既存の縦読みマンガアプリや書店に卸すことも考えたが、収集できるユーザーデータが非常に限定的になることから、自社でメディアを持つことにした。
続いて検討したのはウェブサイトにするか、アプリにする��か。ウェブメディアはアダルトなど大人向けの作品が多い傾向があり、作品の系統が限定される懸念があった。加えて、課金の仕組みを考えたとき、クレジットカード決済がメインとなるウェブメディアよりキャリア決済を活用できるアプリのほうが17歳以下の幅広いユーザーを獲得しやすい。広範囲のユーザー動向を把握したい狙いがあり、アプリを開発することに。ユーザーの裾野を最大限に広げるために、アプリと同様のサービスをウェブサイトでも展開している。
「ジャンプTOON」統括編集長の浅田貴典氏(集英社提供)
さらに、「ジャンプ」の名称を使用するか否かも議論した。作家の視点に立ったとき、ジャンプで積み重ねてきた信頼を活かせることがメリットになると考え、「ジャンプTOON」という名称とした。その背景には、SNSの浸透などにより膨大な数のマンガが世の中に存在する現代において、消費者に気づいてもらうためのPRやマーケティングのコストが増大している事情があるという。
「当社では、作家の先生方に『集英社と一緒に作品を作りたい』、『集英社のメディアで作品を描きたい』と思っていただけることが最も重要だと考えています。どれだけ先生方に良いものを提供できるかを総合的に判断し、『ジャンプTOON』の名称でアプリサービスとする方針が決定しました」(浅田氏)
開発方針の策定まで、約6ヵ月かけて議論した
ビジネスモデルの決定後、サイバーエージェントがジョイン。2社の役割の棲み分けとして、掲載する作家・作品の選定やそのクオリティに関しては集英社が見極め、アプリの開発・運用・マーケティングは、集英社の意見を取り入れながらサイバーエージェントが担っている。
左から、サイバーエージェントのプロデューサー 竹内恒平氏、クリエイティブディレクター 山幡大祐氏、デザインチームマネージャー 室橋秀俊氏(サイバーエージェント提供)
開発チームは、主に企画・デザイン・アプリ・ウェブ・バックエンドの担当者で構成されている。サイバーエージェントがプロジェクトにジョインしてから約6ヵ月間は仕様やデザインの方向性を決定するための議論に当てたという。
「本プロジェクトでは、ロゴや全体のデザインの雰囲気が伝わるモックアップを制作し、仕様面も含めて総合的に議論を交わしたうえで開発をスタートしています。サービストップや作品に関わる画面など重要度の高い仕様やユーザーが目にするUIは上流のタイミングで集英社さんと議論して、開発前に両者の意見を着地させました。現在は運用フェーズに入っていますが、大きな仕様のアップデートやUIは集英社さんと壁打ちしながら決定しています」(サイバーエージェント・竹内氏)
2社の議論で方針を決定後、約1年間の開発期間を経てリリースした(©ジャンプTOON/集英社)
本格開発前の議論で確定したのは、「作家、及び新作を読者にしっかり届けることを大事にしたい、そのためにも印象に残るようなUIを採用する」という方向性だ。
「マンガアプリの特徴は、主に2種類に分かれます。新作を世の中に広く届けることを主眼に置いたものと、既存作品を中心にして多くの読者を呼び込み、多く課金してもらうことを重要視したものです。ジャンプTOONは前者に当たり、作家や新作の魅力を届けることを最大の目的としています」(浅田氏)
ベースの機能は標準化、「作品の見せ方」や「操作性」で差別化
ジャンプTOONは、既存のマンガアプリと併用することを踏まえ、一般的な仕様から大きく逸脱しないものの、ところどころに独自性を盛り込ん��でいる。
課金システムなどベースとなるUXは、標準的な仕様に沿っている(ランキングは記事執筆時点、(左)『伝説の暗殺者、転生したら王家の愛され末娘になってしまいまして。』©ストレートエッジ/集英社、(中・右)©ジャンプTOON/集英社)
課金システムは、「最初の3話は無料、4話以降は待てば無料」とい��う既存のマンガアプリと同様であり、検索や本棚の機能、人気ランキングによる訴求も一般的な仕様に寄せている。一方で、「サービストップ画面」や「作品トップ画面」、「ビューワー」などは独自性を意識した。
コンセプト、及びサービストップ画面のデザインを担当したクリエイティブディレクターの山幡氏は、「ロゴ」について以下のように説明した。
ジャンプTOONのロゴ(©ジャンプTOON/集英社)
「ジャンプブランドのサービスなので、ユーザーが『ジャンプ』だと認識できることは大事にしています。その上で、縦読みマンガというジャンルの新規性や、これから方向性を柔軟に模索していくという意味合いを込めて、既存のジャンプのロゴよりも線を細く、造形をシンプルにするなど、より懐の広いブランドになるよう意識しました。カラーもジャンプを連想する「赤」を採用した上で、画面上の「ライトモード」と「ダークモード」どちらと組み合わせても、コントラスト比がアクセシビリティチェックの合格ラインに到達する赤としました。
またサービストップ画面では、縦読みマンガならではの画面を大きく使ったインパクトのある画角を最大化するため、作品をグリッド上にいくつも並べるのではなく、横幅いっぱいに1枚の絵を見せるなど大胆なレイアウトを採用しています。キャラクターが迫ってくるような画角を意識しました」(山幡氏)
デザインチームマネージャーの室橋氏は、作品の魅力を伝えていく作品トップ画面における独自のこだわりに触れた。
作品トップ画面(左)とマンガのレイアウト(『史上最強の魔法剣士、Fランク冒険者に転生する タテマンガ版』©柑橘ゆすら・亀山大河・金丸栄一・SHINE Partners/集英社)
「スマホのサービスではありますが、“雑誌らしさ”を残すデザインを意識しています。作品トップ画面では、ジャンプTOONの世界観ではなく、作品ひとつひとつの世界観の表現にこだわりました。作家さんが扉絵として描いた画像をサービストップ画面に合わせて使用し、雑誌で新連載を開始する時に表紙に載せるようなキャッチフレーズも添えています。その文字を載せる帯の色は、各作品から抽出するシステムを採用しました」(室橋氏)
ビューワーは自社開発しており、スクロールの位置にもこだわった(『レンタル努力』©ストレートエッジ・TOON CRACKER/集英社)
作品の魅力訴求に加え、スムーズに閲覧できるような配慮もされている。「読む」というボタンを作品タイトルのすぐ下に配置したり、作品トップ画面にエピソードのリストが見えるようにレイアウトを工夫したり。
さらに、ビューワー(コンピューターで画像・動画・電子書籍などを閲覧するためのソフトウエア)は自社開発し、スクロール時にストレスがないようにした。スクロールバーの開始位置を画面の一番上ではなく、ビューワー画面に対してやや下に配置することで、片手で持った時に親指が無理なく届く。タップの感度などの細かい挙動も計算しながら仕上げたそうだ。
作品やサービスの成熟度に応じて、UI・UXを柔軟に変えていく
リリース後の反響をたずねると、ダウンロード数などの数字情報は非公開だが、「期待通りに推移している」と浅田氏は明かした。
「大きな広告費をかけて派手に打ち出すのではなく、あえてスモールスタートとしていて、それを踏まえて計算通りの反響ですね。アプリ自体の機能性もリリース当初はマンガを楽しく読めるところにとどめており、リリース後にフィードバックを得て改修を進めています」(浅田氏)
現状の改修については、既存のマンガアプリが備えている機能を追加していく、いわゆる「標準化」が中心だが、サービストップ画面やビューワーなど、より作品を魅力的に見せるためのブラッシュアップも必要だと考えているという。
ジャンプTOONは、サービストップ画面もブラッシュアップさせていく方針だという(©ジャンプTOON/集英社)
ジャンプTOONでは、毎日4作品以上の最新話が更新されるほか、数ヶ月に1度の頻度で新連載が追加される。ハイペースで作品や話数が増加することに加え、押し出していく作品も頻繁に変わる。ベースとなる方針はあるが、それが全ての道筋を決めるものではなく、サービスの成熟度や作品展開に応じてUI・UXも柔軟に変化していくことが求められている。そうしたサービス特性に対して、山幡氏、室橋氏は「常に変化していく戦略に対して開発チームの足並みをそろえていく点は難易度が高い」と言及した。
「例えば、ホーム画面は基本的にデザインが変わらない普遍的なものだと考えがちですが、ジャンプTOONはもっと柔軟に、その時々でマッチするような提案が必要です。そうした変更に対応できる体制を整えることや、タイミングごとの戦略に応じたUI・UXを模索し続ける点は難しさだと感じます」(山幡氏、室橋氏)
現状のユーザー層は、既存のジャンプや少年ジャンプ+のファンも多い印象だという。幅広い層に向けたオールジャンルの作品を扱うため、作品ごとにファン層のバラつきがあるのは想定内だが、意外な動きも見えているとか。
「具体的な作品名は出せないのですが、意外な組み合わせで併読されている方が見られるなど興味深いデータが取れています。これはオールジャンルを扱うサービスならではで、媒体としての色がハッキリしているマンガ雑誌とは異なる光景なのかなと考えています」(竹内氏)
「私は紙の雑誌でキャリアをスタートさせているので、マンガアプリには驚かされることばかりです。どのページで離脱したかなど詳細なデータが取得できるので、それを担当編集者にも共有して作品のブラッシュアップに活かしています。まずは、ユーザーに満足いただける作品をオールジャンルでどんどん制作していきます」(浅田氏)
ベースとなる戦略は存在しつつも、「変わっていくこと」を前提に開発されているジャンプTOON。成長市場の新規サービスにおける「標準化」と「差別化」のバランス、細部におけるUI・UXの追求など多くのデザイナーにとって発見が多かったのではないだろうか。ジャンプTOONのさらなる発展もまた気になるところだ。
「自由なライフスタイル」に憧れて、2016年にOLからフリーライターへ転身。2020年に拠点を北欧に移し、デンマークに6ヵ月、フィンランド・ヘルシンキに約1年長期滞在。現地スタートアップやカンファレンスを多数取材する。2022年3月より拠点を東京に戻し、国内トレンドや北欧・欧州のイノベーションなどをテーマに執筆している。
https://love-trip-kaori.com/