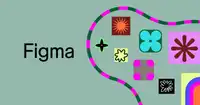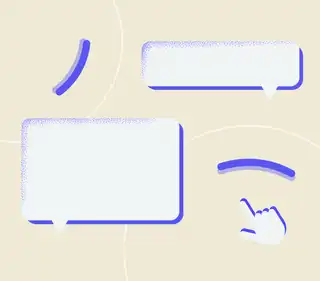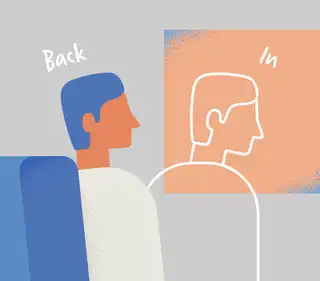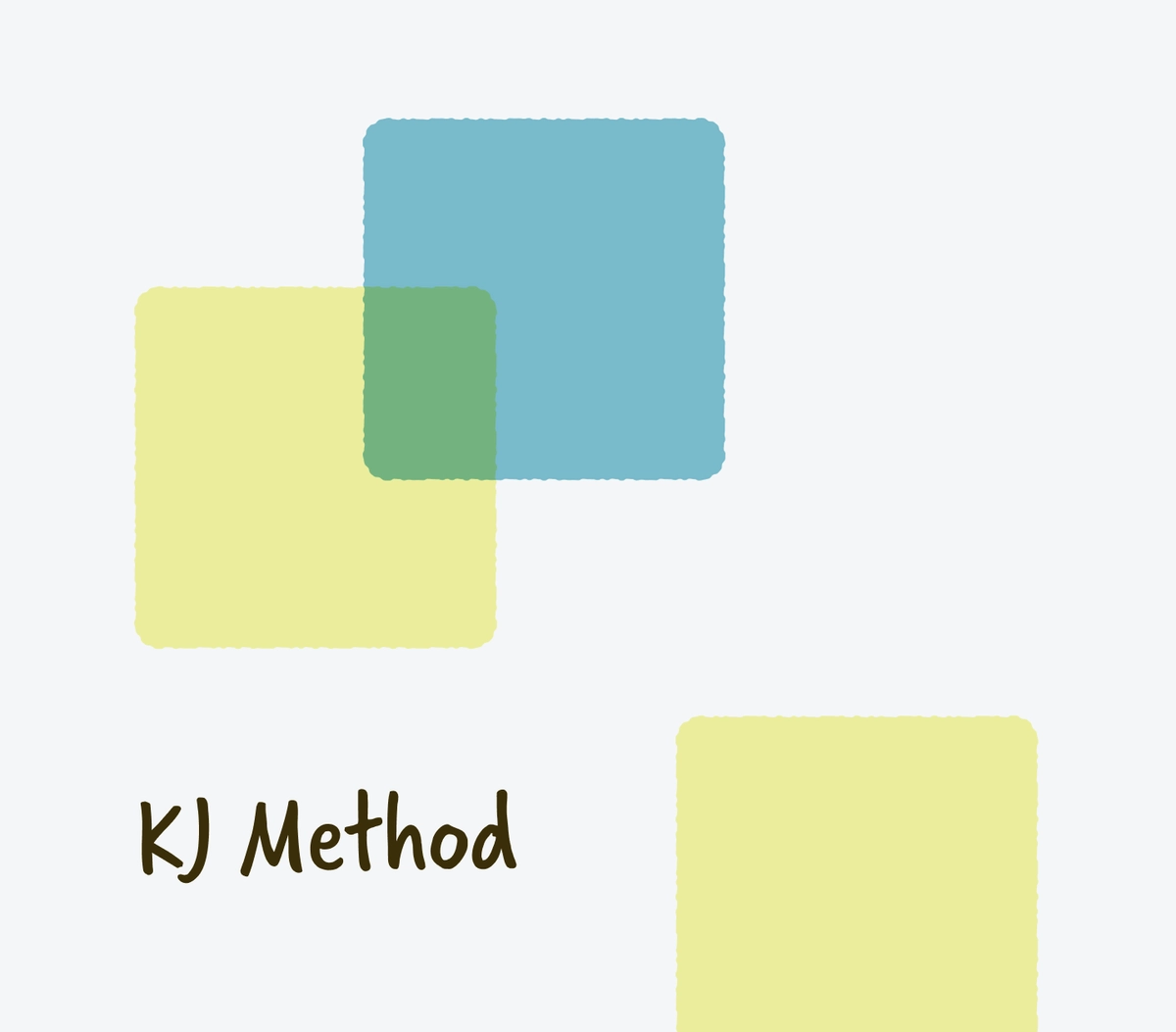
KJ法とは?アイデアを整理して図解化するための手法
KJ法とは、集まった情報やアイデアを整理、グループ化、そして図解化するための手法です。雑多な情報を多角的に分析して意味を見出すために最適な手法で、近年では特にミーティングやブレインストーミングなどで集まったアイデアを整理、分析するための手法としても広く取り入れられています。このKJ法という名前は、考案者である人類学者、川喜田二郎氏のイニシャルに由来し、海外でもよく知られています。また、人類学で研究成果を論文にまとめるための手法(エスノグラフィ)として生まれたKJ法は、ユーザー行動の観察・分析を行うUXリサーチの分野でもユーザーインタビューやユーザーテストによって得られた情報を構造的、多角的に分析する手法として用いられています。
情報を「グループ化する」だけでなく「分析する」という視点が大切
KJ法は、「情報をグループ化」するための手法としてよく知られていますが、「情報をグループ化する」というと、ただまとめ作業をして終わりというような印象を抱くかもしれません。実際、KJ法的な手法は、ミーティング後に単なる情報のグループ化作業として行われているような例もあるかもしれません。しかし、KJ法における最大の目的は、「雑多な情報の論理的な関係性を図解化して、多角的に分析すること」です。これを一般的に「まとめる」として表現されているのですが、どちらかというと「分析する」という視点を持って取り組むとより効果的にKJ法を使いこなせるかと思います。
KJ法が役立つタイミング
KJ法は、「拡散(情報の洗い出し)」と「収束(情報のまとめ)」を繰り返すデザイン思考的なプロセスにおいて、「収束」を効果的に行うための手法です。そのため、拡散的な作業であるブレインストーミングや、ユーザーインタビュー、ユーザーテストなどの後に、集まった情報やアイデアをまとめるためにも使われます。近年は、複数人でのブレインストーミングの後に、出てきたアイデアをまとめることを目的とした使い方が注目されているため、複数人で行う作業であると思われがちですが、UXリサーチャーが一人で情報をまとめ、分析する際にも有効な手法です。「目の前に雑多な情報があり、そこから有意義な情報を抽出する必要がある」といった場面で特に効果を発揮する手法です。
KJ法の4つのメリット
KJ法の主なメリットとしては、以下の4つが挙げられます。必要な道具として、付箋とペンがあればできるというのも大きなメリットです。最近では、MiroやFigJamなどのオンラインホワイトボードツールが登場し、複数人でオンラインで行うことができるようになり、さらにKJ法を活用する機会が増えたのではないでしょうか?
情報を集める段階では自由に情報を集めることができる
情報を体系的に図解化できる
情報を多角的に分析できる
情報の関連性から新たなアイデアを導くことができる
KJ法のデメリット
KJ法のデメリット(というより注意点)は一点、「最終的な質は、集めた情報に左右される」という点です。KJ法は、情報を分析するために大変役立つ手法ですが、あくまで情報を集めるのはその前段階のブレインストーミングやユーザーテストです。この段階で有意義な情報が集められないと、いくらKJ法を使って分析しても表面的な内容しか得られないことがあります。この問題に対する解決策として、ブレインストーミングのポイントを後ほど紹介します。


KJ法のやり方を具体例に沿って解説
では、早速KJ法のやり方について解説していきます。
1. 情報をカードに書き出す
まずはブレインストーミングやリサーチで集まった情報を一つずつ付箋やカードに書き出しましょう。ブレインストーミングを行う場合は、会議の中で参加者に直接アイデアを書き出してもらう場合も多いです。ここでのポイントは、集まった情報をカードに書き出す際に内容が変わらないように注意することです。できるだけ集めた情報や発言をそのままカードに記載することが、書き出す人のバイアスがかかることを防ぎます。
また、UXリサーチの現場ではユーザーインタビューなどの定性調査から得られた情報をまとめる方法として、KA法もよく利用されています。KA法は、KJ法との相性もよく合わせて使うことができます。KA法のやり方については、以下の記事でわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
2. カードのグループ化
次に、カードを類似性や近似性に沿ってグループ化します。この時、それぞれのグループに名前をつける様にしましょう。また、グループ同士は境界線がはっきりしたものではなくても大丈夫です。関連性のありそうなものを近くに配置していき、エリアごとに名前をつけるというようなイメージで作業すると良いでしょう。
また、類似性に沿ってグループ化するといっても、情報を見る視点によって出来るグループは異なります。例えば、「猫」「車」「鉛筆」という情報がある場合、「動くもの・動かないもの」というグループに分けることもできますし、「動物・人工物」というグループに分けることもできます。ここでの分類の基準によって見�えてくる全体像が変わってくるため、「情報のグループ化」の段階ではさまざまな分類の基準を模索して多角的に情報を分析すると新しい発見に繋がりやすいです。UXリサーチにおいてKJ法を使う際には、サービス内での「ユーザージャーニー」「ユーザーセグメント」「AARRRファネル」や「関連機能」などを分類の基準として使うことが多いです。
3. 情報の関係性を図解化
次に、グループ化したカードのグループ同士、またはそれぞれのカード同士の関係を書き込んでいきます。それぞれのカードを線で結んでいくイメージで進めるとやりやすいです。その際に、以下のような関係性に注意して進めると良いでしょう。
前後関係(時間の前後)
相反関係(対立、矛盾)
因果関係(原因と結果)
相関関係(影響し合う)
包含関係(全体と一部)
ここでも、「カードのグループ化」ステップと同じく、情報を見る視点や基準によって見えてくる関係性も異なります。そのため、複数の観点から新たな関係性を見つけるように意識して進めると良いでしょう。
4. 分析内容や発見を文章にまとめる
前のステップで可視化された情報の関係性をもとに、今回の分析の目的に沿ったインサイトを書き出します。この際に、それぞれのインサイトの重要性を、分析の目的と照らし合わせて評価していくと良いでしょう。
KJ法で有意義な情報を得るためのブレインストーミングのポイント。「なぜ行うのか?」を共有することの大切さ。
ブレインストーミングなど、複数人での自由なアイデア出しを行い、挙がったアイデアをKJ法でまとめるというのは、ビジネスにおいてKJ法が最もよく使われる場面ではないかと思います。しかし、KJ法をいくら使いこなしたとしても、ブレインストーミングで挙がったアイデアの内容によっては、あまり有意義な関係性が見出せず、結局アイデアをグループ分けして終わりといった事態になってしまうことも少なくありません。ここでは、KJ法の前段階として、ブレインストーミングで質の高い発想を集めるための方法を紹介します。
ブレインストーミングの原則として一般的に、
アイデアの否定や判断をしない
ユニークなアイデアを歓迎する
質より量を重視する
アイデアを組み合わせる
の4つが挙げられます。この4原則はもちろん守った上で、さらに有意義な発想を集めるためのポイントが2つあります。それが、
参加者全員が目的・背景を明確に理解していること
スコープを絞ること
です。例えば、「新しい収益チャネルを考える」というブレインストーミングを行うとします。ブレインストーミングの目的を「新しい収益チャネルを考えること」だと全員が理解したとします。しかし、この内容でブレインストーミングを行うと、あまりにも一般的な施策や、そもそも試して上手くいかなかった施策など必要以上に広範囲な意見が集まってしまいます。もちろん、「質より量を重視する」というブレインストーミングの原則から考えれば決して間違ってはいません。しかしながら、限られた時間内でこの様なアイデアまで出していると、本当に役に立つアイデアが多く出ることはなく、後にKJ法でまとめる際にも情報の関係性があまりないような薄い内容となってしまいます。
では、この様なブレインストーミングのどこに問題があるのでしょうか?それは、「何をするか?」のみをブレインストーミングの目的と捉えてしまっていることです。これでは、深いインサイトに基づいたアイデアはなかなか出てきません。ブレインストーミングの目的としては、「なぜ行うのか?」という背景を含めて具体的に目的と背景を共有する必要があります。
例えば、「ターゲティング広告に対する規制により、動画広告経由の収益が低下している。次年度、新たな収益チャネルを確保するために、インハウスで行うことができる施策案が必要」などです。「5W1H」を含めた形で目的を参加者に共有することで、参加者に当事者意識が芽生えるだけでなく、自然とスコープが絞られることで、ブレインストーミングで発想されるアイデアの関連性も高�まるでしょう。この様なブレインストーミングで挙がったアイデアであれば、KJ法を使った分析によってさらに関連する有意義なアイデアが生まれてくることも少なくありません。「なぜ?」を語ることで人を動かすことができるという考えは、ゴールデンサークル理論として知られており、ビジネスにおいてもさまざまな分野で応用されています。
ブレインストーミングの方法については、以下の記事でより詳しく解説しています。ぜひこちらも参考にしてみてください!
KJ法は誰が行うべき?
近年、KJ法は主にブレインストーミングのまとめ作業として紹介されることが多いため、KJ法を使った分析作業もブレインストーミング後にワークショップの一環として参加者全員で行うことがあります。参加者全員がトピックについて深い理解を持っている場合などは、この方法でも良いでしょう。しかし、KJ法は「収束的」手法であると同時に、ある意味集まった情報をもとに新たな発見を模索する「拡散的」手法でもあります。前項で紹介したように、見る視点を変えて何度もグループ化したり、情報の関連性を組み替えてみたりといったプロセス自体に大きな意味があります。そのため、KJ法による分析はワークショップの時間に縛られて行うべきではなく、「参加者が個別に行い、後で照らし合わせる」「リサーチャーが一人で行う」といった方法も検討すると良いでしょう。
KJ法を行うときに役立つFigmaテンプレート
unprintedオリジナルのKJ法テンプレートは、Figma Communityからコピー可能なFigmaファイルとして配布しています。登録やメールアドレスの入力は不要。個人・商用に関わらず自由に使用することができます。Figmaをお使いの場合は、ぜひ利用してみて下さい!
KJ法に役立つリモートミーティングでも使えるアプリ紹介
KJ法は、ペンとカード(付箋)というアナログなツールを道具として想定していますが、PC上で作業をしたり、リモートミーティングにて複数人で行うといった場合にはアプリやWebサービスを利用すると便利です。ここでは、「共同作業が可能」という観点でKJ法に使えるアプリを2つ紹介します。
1. Miro
https://miro.com/
Miroは「オンラインホワイトボード」と呼ばれるサービスの一つで、ホワイトボードで行える作業全てをオンラインでも行える様にするという目的のもと開発されているWebアプリです。ブラウザ上で動作し、複数人でお互いのカーソルを見ながら作業することができます。KJ法に必要な付箋や矢印といったツールも揃っているため、すぐにでも使えるおすすめのツールです。
2. FigJam
https://www.figma.com/figjam/
FigJanはUIデザインツールのFigmaの提供するオンラインホワイトボードです。Miroと同じく付箋などのツールが使え、共同作業者とリアルタイムにKJ法を使った作業ができます。機能面ではMiroと大きな違いはありませんが、デザイナーにとってはデザインツール内でリサーチ作業もできるというのは大きな利点となります。デザイナー同士でブレインストーミングやKJ法での分析を行う際にはぜひ使ってみてください。
まとめ
今回は、UXリサーチやブレインストーミングの際に活用されている分析手法であるKJ法について紹介しました。一見すると、情報をまとめるだけのように見えてしまうKJ法も、今回の記事で紹介したような重要なポイントを押さえて取り組むと、思考が整理され、新たな発見にもつながる強力なツールとなります。雑多な情報を整理・分析する必要がある際には、ぜひKJ法の手法を試してみてはいかがでしょうか?