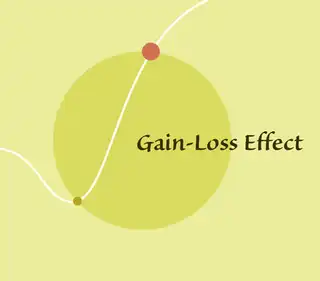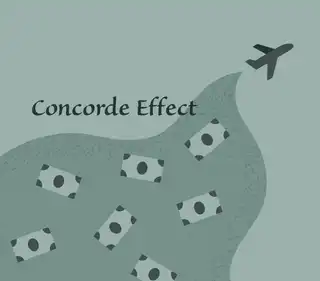クレショフ効果とは?
クレショフ効果とは、同じものでも前後に繋がる映像情報の違いにより、生じる印象や解釈が変わるという心理効果のことです。前後の情報に直接的な繋がりがなかったとしても、無意識に関連づけてしまうという人の心理にもとづいています。全ロシア映画大学で、映画作家・理論家であるレフ・クレショフが実験内で示したため、クレショフ効果と呼ばれています。
クレショフ効果の実験
レフ・クレショフは、認知心理学の視点からクレショフ効果を研究しました。実験では、ロシアの俳優イワン・モジューヒンのアップの映像を使い、この映像を下記3つの背景と組み合わせて、参加者に見せました。
背景1: スープ皿
最初の映像では、モジューヒンのクローズアップの前に、スープ皿のクローズアップを配置。被験者はこのシーンを見た後、「空腹を感じる」と回答しました。
背景2: 棺
2番目の映像では、スープ皿の代わりに棺(ひつぎ)の中に遺体を配置。被験者は、この場面では「悲しみを感じる」と回答しました。
背景3: ソファに横たわる女性
3番目の映像では、棺の中の遺体の代わりに、ソファに横たわる女性を配置。観客はこのシーンを見た後、「欲望を感じる」と回答しました。
上記の実験から明らかになったのは、まったく同じ俳優の表情でも前後の映像情報が俳優の感情の解釈に影響を与えるということです。このように視覚的な要素の組み合わせが、映像を見た人の感情や認識に強い影響を与えるという現象がクレショフ効果です。
クレショフ効果の具体例
枕を対象としたクレショフ効果の例を紹介します。同じ枕でも、組み合わせる画像が異なるとマッチするターゲット層も大きく変わります。
まず初めに、下記の画像のように枕を小さな子どもと組み合わせるとどうでしょうか。
小さな子どもとセットで枕を見ると、不思議と安心感がありませんか?枕がファミリー向けで、素材にこだわった「安心・安全」であることをアピールしたい場合は、上記のような方法が活用されます。
他にも、友人たちとパーティーしている様子の画像と組み合わせるとどうでしょう?
旅行を楽しむ人たち向けのホテルの枕のイメージであったり、持�ち運びできる枕などのイメージが湧きやすいかと思います。
最後に、キャンドルと組み合わせてみると......?
快眠・リラックス効果の高い枕といったイメージになるのではないでしょうか。
以上のように、同じ商品であっても、組み合わせる画像によって与える印象が大きく変わるのがクレショフ効果です。
クレショフ効果とモンタージュ理論の関係
クレショフ効果は、モンタージュ理論において重要な概念の1つと言えます。モンタージュ理論とは、映画の視覚的な表現の中での「編集」の重要性を強調する理論で、関係性のない映像でも編集でつなぐことで、映��像に関連性を持たせることができるという理論です。
モンタージュ理論の中では、「モンタージュ」という言葉が中心的な役割を果たしています。モンタージュとは、映画技法の1つで、複数の断片的なシーンを連続的に組み合わせて1つのシーンを作る方法です。
クレショフ効果は、映像を単独でなく「系列全体」として捉え、組み合わせることで新たな情報や感覚が引き出されるという理念に基づいています。つまり、クレショフ効果はモンタージュ理論の一環であり、映像の組み合わせによって生まれる新しい意味や印象に焦点を当てた効果です。
クレショフ効果と似ている心理効果
クレショフ効果には、似ている心理効果が2つあります。
プライミング効果
プライミング効果とは、プライマーと呼ばれる「先行刺激」によって、刺激を受けた後の行動や判断が変わる心理効果です。
例えば、身近なプライミング効果としては以下のようなものがあります。
海外旅行の特集番組を見た後に海外旅行に行きたくなる
事故や火災のニュースを見た後は安全に気をつけようとする
最新のファッション雑誌を読んだ後、洋服やスタイリングに気を使うようになる
以上のように、先行刺激を受けたことにより行動が変わる心理効果を「プライミング効果」と言います。クレショフ効果は、前後の視覚的な違いが印象を変える効果である一方で、プライミング効果は、先に見た情報が後の行動や考えに影響を与える心理効果です。
文脈効果
文脈効果とは、環境や文の続き方によって印象・内容が変わったり、理解しやすさが変わる効果です。ジェローム・ブルーナーが1955年の論文で提唱しました。
例えば、以下のような順番で文字が並んでいると、真ん中は「13」に見えませんか?
しかし以下のような続きになると、
同じ文字でも、真ん中が「B」に見えるのではないでしょうか。以上のように、周囲の環境や文の続き方によって印象・内容が変わ�ることを「文脈効果」と言います。
クレショフ効果を活用する方法
クレショフ効果の活用方法を2つご紹介します。
結びつけたいイメージと並べてブランディング
オンラインの打ち合わせに活用する
結びつけたいイメージと並べてブランディング
1つ目は、結びつけたいイメージと並べてブランディングする方法です�。例えば、伊藤園の「毎日1杯の青汁」は、青汁の商品と野菜を並べたPR画像をホームページ上で紹介しています。
このように、商品やサービスと結びつけたいイメージと並べることでクレショフ効果が働き、効果的なブランディングができます。
オンラインの打ち合わせに活用する
2つ目は、オンラインの打ち合わせに活用する方法です。Zoomなどのツールを使ったオンライン会議では、背景やカメラの角度を工夫することで相手の印象を変えられます。
例えば、ターゲット顧客に落ち着いた印象を与えたいなら、ヴィンテージ雑貨やダークブラウンを基調とした背景にすると効果的です。一方で、明るく爽やかな印象を持ってもらいたいなら、植物を配置したり、背景の色調を明るくすると良いでしょう。
自分の印象自体を変えるのは難しいですが、背景に映るものを変えることでクレショフ効果を利用し、ターゲットに与える印象をうまくコントロールできます。
クレショフ効果を活用するまでの流れ
クレショフ効果をマーケティングで活用するまでの流れは以下の通りです。
消費者にどのようなイメージを持たせたいか決める
与えたい印象に関連した「モノやヒト」を決める
「モノやヒト」と商品を紐づける
1. 消費者にどのようなイメージを持たせたいか決める
まず、自社の商品やサービスを消費者にどう印象付けたいかを決めます。クレショフ効果を最大限に生かすためには、伝えたいイメージを具体的に定義しなければなりません。
例えば、商品の「安心感」をアピールしたい場合、先ほど紹介したように「小さな子ども」や「真面目なイメージのある俳優」など、安心感があるイメージの具体的なキーワードや特徴を検討しましょう。制作する広告やコンテンツの中でクレショフ効果を最適に活用するためには、明確��な目標を作っておくことが大切です。
2. 与えたい印象に関連した「モノやヒト」を決める
次に、選んだイメージに適する「モノやヒト」を選びます。例えば、「安心感」をアピールするなら、日本人がよく目にする「富士山」「伝統文化」や、可愛くて真面目なイメージのある俳優、または信頼性のある専門家の姿も良いでしょう。
「健康」をアピールするなら「野菜」「果物」、または健康的なイメージのある俳優を起用することなどが考えられます。このステップで選ばれた「モノやヒト」は、全体のコンセプトを統一して効果的にメッセージを伝えるための鍵となります。
3. 「モノやヒト」と商品を紐づける
最後に、選ばれた「モノやヒト」と商品やサービスを紐付けます。選ばれた対象が、商品やサービスのイメージにピッタリとフィットするようなシーンを構築しましょう。
例えば、家族とのほっこりとしたシーンは安心感を引き立て、消費者に印象づけられます。青空の下で汗をかいているシーンは、健康的なイメージを引き立てるでしょう。このステップでクレショフ効果が発揮され、消費��者に受け取って欲しいメッセージを伝えることができます。
まとめ
クレショフ効果は、効果的に活用することで商品やサービスをイメージ通りにブランディングできる心理効果です。視覚的な組み合わせを行うことで、商品を単なるモノではなく、ストーリー性を持った体験として捉えてもらいやすくなります。