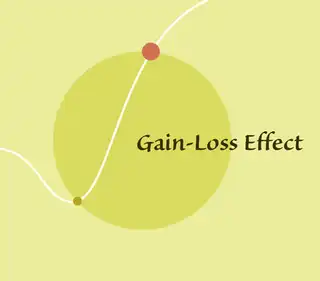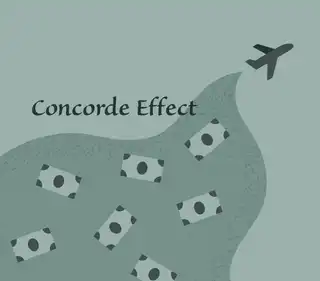ピーク・エンドの法則とは?
ピーク・エンドの法則とは、人間がある出来事を記憶する際には、感情が大きく動いた「ピーク」と全体の終わり「エンド」が最も強く印象に残り、ほとんどそれらだけでその出来事の全体の印象が形作られるという法則です。1999年にダニエル・カーネマンが提唱しました。
「終わりよければすべてよしの理論」ともいわれることがあります。ピーク・エンドの法則をうまくビジネスに活用すれば、顧客の記憶に残りやすくなり、良い印象を残すヒントとなりそうです。
ちなみに、ピーク・エンドの法則はポジティブな印象だけに当てはまる法則ではありません。どちらかというと、もとは苦痛の体験にフォーカスした法則でした。実際に、提唱者のダニエル・カーネマンの大腸内視鏡検査の実験では、苦痛が残るネガティブな体験に着目した実験となっています。
ピーク・エンドの法則を証明した実験
ピーク・エンドの法則を証明した代表的な2つの実験を紹介します。
冷水に手をつける実験
この実験は、被験者に「終わり」と言われるまで冷水に手をつけてもらう実験です。
実験は、以下のA・Bの2つのパターンに分けて行われました。
A:60秒経ってから「終わり」
B:90秒経ってから「終わり」ただし、最後の30秒は水温が1度高い冷水に手をつける
AとBを両方経験した人に、もう一度体験するならどちらがいいかを問うと、8割の人が「B」と答えました。合理的に考えると、苦痛の「ピーク��」はAもBも同じであり、水温が1度が上がったとは言え、Bの方が苦しい時間が長いはずです。しかし、AよりもBの「エンド」のほうがましだったという記憶が強く残るため、Bを選ぶ人が多かったのでしょう。
以上のことから、ピーク・エンドの法則は、経験の「長さ」ではなくピークとエンドの平均で快・不快の評価が決まり、最後の印象で最終的な記憶が形作られることがわかります。
大腸内視鏡検査の実験
大腸内視鏡の検査をしている被験者2人に、検査中の痛みを10段階で評価してもらい、検査後に、それぞれの記憶に基づいてどちらの患者がより苦痛だったかを評価する実験です。
患者A:検査時間は8分。ピークの数値は「7」でエンドの数値は「8」。平均値は「7.5」
患者B:検査時間は24分。ピークの数値は「8」でエンドの数値は「1」。平均値は「4.5」
結論としては、患者Aのほうが、より強い苦痛を感じていました��。冷水の実験と同様に、苦痛を感じている時間の長さは関係なく、ピークとエンドの平均値で快・不快の評価がされ、最後の印象で記憶が決まることが分かります。
ピーク・エンドの法則の具体例
ピーク・エンドの法則は、日常の至るところで起こっています。例えば以下の3つです。
遊園地での事例
飲み会での事例
UXデザインでの事例
遊園地での事例
遊園地のアトラクションに乗るために、何度も行列に並んだ経験がある方もいるのではないでしょうか。アトラクションに乗れる時間はたった数分にも関わらず、最後の快感を体験するために、数��時間行列に並びますよね。この事例においても、ピーク・エンドの法則が働いていると考えられます。
待っている時間の苦痛が長かったとしても、最終的に飛び抜けて「楽しかった」印象が残るため、結果的には高い満足度の記憶が残るのです。
飲み会での事例
楽しい飲み会だったのに、最後の10分間で酔った上司に説教され、全てが嫌な思い出になってしまったという経験がある方もいるのではないでしょうか。この事例も、楽しい思い出が長い時間あったとしても、「エンド」にそれを超える嫌な経験をした場合、嫌な記憶しか残らなくなるというピーク・エンド効果の例です。
UXデザインでの事例
MailChimp社が提供するメール配信ツール「MailChimp(メール・チンプ)」でも、ピーク・エンドの法則が働いているような場面があります。
MailChimpは、「メールマーケティングを効果的に行いたい」人や企業に向けたツールで、さまざまなメールデザインテンプレートが用意されており、簡単にメールマガジンの作成ができます。それだけでなく、メール作成後に「送信ボタン」を押すと、以下のようなイラストが表示されるといったユーモアが満載です。
上記の画像が出てくる瞬間が「エンド」となり強く印象に残るので、良いユーザー体験として認識されやすくなるのです。
まとめ
ピーク・エンドの法則とは、経験全体の中での「ピーク」と「エンド」が最も記憶に残りやすく、その印象が全体の評価を左右する法則です。具体的な事例や実験からもわかるように、経験全体の「長さ」や「ピークの強度」よりも、「ピーク」と「エンド」の平均値で印象が決まることが分かりました。顧客の記憶に残り、リピートしてもらえるような体験を提供したいときには、ぜひピーク・エンドの法則の活用を検討してみてください。
参考文献
ダニエル・カーネマン (2014) 『ファスト&スロー(下) あなたの意思はどのように決まるか?』早川書房
ピーク・エンドの法則『Wikipedia the free encyclopedia』(最終閲覧日2023年12月22日)