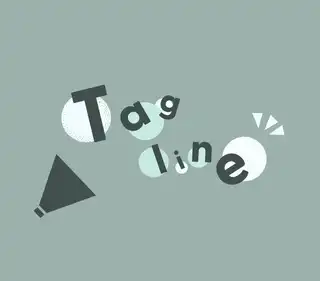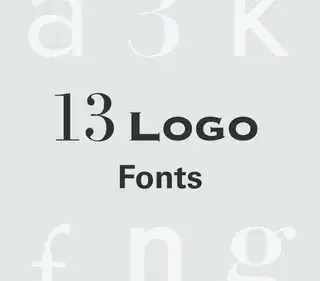数ヶ月前、私の同僚であるクロエが、デザイナーのスキルアップワークショップで、パーソナルブランドに関する興味深いワークショップを主催してくれました。そのワークショップでは、クロエのプレゼンやチームの意見��を聞くことができ、私はパーソナルブランディングが非常に重要な要素であることを学びました。
それまで、フリーランスのデザイナーが自身のブランドを持つことの重要性は理解していましたが、私のような企業で働くデザイナーにとっても、自身のブランドを構築することで、社内外での仕事の機会を広げることができ、またより深い自己理解を得ることができるのだと気付いたのです。
さらに、現代の社会ではSNSの影響力が非常に強いため、雇用主はソーシャルメディア上でも採用候補者を評価することが一般的になっています。私たちの会社もLinkedinなどを活用し、デザイナーを探すことががますます増えています。
Nokoです。メルボルン在住のプロダクトデザイナーで、リモートで仕事をしています。 過去8年間は、ブランド戦略、エクスペリエンスデザイン、ビジュアルデザイン、モーションおよびイラスト、アクセシビリティデザインなどのデジタルデザインの様々な分野で仕事をしてきました。現在は、Two Bulls/DEPTでシニアプロダクトデザイナーとして、様々な国際的なデザインプロジェクトに取り組んでいます。
なぜ、今のポートフォリオサイトではダメなの?
もともと、自身の作品を載せているだけのポートフォリオサイトがありました。しかし、それは非常にシンプルで、ミニマルで、一般的なものでした。ミニマル・イズ・ザ・ベストと言って、白いバックグラウンドに作品だけを載せているサイトに満足していると思っていましたが、今考えると、特別には思っていませんでした。その証拠に、あまり積極的にポートフォリオサイトのリンクをシェアするようなこともなかったように思います。
そのような中で、次に転職するときにでも作り直そうと漠然と考えていたものの、結局時間だけが過ぎていきました。しかし、同僚のクロエによる今回のワークショップをきっかけに、今すぐ時間と労力をかけてちゃんと作るべきだと思うようになりました。そこで、仕事でよく使用して、慣れ浸しんでいるSquarespaceを使って、もう一度ポートフォリオサイトを作り直すことにしました。
パーソナルブランド再構築までの道のり
その後、私は自分の個人ブランドを作ろうとしましたが、なかなかハマらない日々が続きました。なぜかというと、私は気分屋で、いつも考えが変わってしまうからです。そして、もともとビジュアルデザイナーなので、ビジュアルアイデンティティから考えてしまう癖があります。最初は「赤をメインカラーにして、やる気や情熱を伝えてみよう!」と思ったり、次の日には、「やっぱりもっと落ち着いた、洗練された感じの紺色を基調として、藍染のような日本をイメージできる色合いがいいかも」と思ったり… とにかく迷走して、時間だ�けがどんどん過ぎて行きました。でも、幸か不幸か、Squarespaceでサブスク代を払わなくてはいけなくなったことが、私のやる気を引き出してくれました。
その後、パーソナルブランドに関する記事を読み、そのステップや賢い作り方を学びました。そして、私たちがプロダクトを制作する時と同様、しっかりと自分のビジョンや、特性を理解することから始めるのが大切だったと気づきました。自分自身を知り、自分のユニークな特徴を理解し、何が提供できるのかを考える必要がありました。自分が本当にやりたいことは何かを考え続け、自分自身にどんな価値があるのかを一人ワークショップを通して考えてみました。
本当は何をしたいのか?まずは自分のことを知ることから
自己理解のための一人ワークショップを通して、
得意なこと
楽しいと感じる瞬間
興味があること
をリストアップしました。さらに、最近よく使っているデザインツールやプラットフォーム、好きなプラグインなども挙げました。その中で、例えば「私はアクセシビリティに関連するプラグインを多く使用しているため、アクセシビリティに深い関心を持っている」といったようなことに気がつくことができました
また、ここ数年メディカル系のプロジェクトに関わる機会が増え、アクセシビリティ、インクルーシビティ、ニューロダイバーシティについて学びました。そのため、シンプルで使いやすく、誰にでもアクセス可能なインクルーシブなデザインを目指しています。
また、私が楽しいと感じる瞬間は、子供向けのデザインを手がける時です。鮮やかな色彩や可愛らし��いイラストを使ってデザインするとワクワクします。
また、最近同僚のトバイアスからESGについて学びました。ESGは、環境(Environment)、社会(Social)、およびガバナンス(Governance)の頭文字を組み合わせた用語です。ESGは、企業や投資家が持続可能性と責任投資を評価するための指標となる要素を指しています。これらは将来的にますます重要になってくると考え、ESGのこともちゃんと考慮したデザインを心がけることがこれからの未来大切になってくるとも考えています。
それから、次に考えをまとめるために履歴書を作り直すことから始めました。外資系企業や海外企業に応募する際に同封するカバーレターを書き直すことで、自分の考えが明確になると思ったからです。
カバーレターでは、ワークショップによる自己分析からわかった内容をもとに、以上のように自分が目指している方向性を大まか��に紹介した上で自分自身のユニークなスキルを挙げてみました。
私の価値とは?「違い」はブランド作りにとって大切な要素
「違い」はブランド作りにおいてとても重要な要素です。なぜかというと、他の人が提供していない特別な価値を私だけが提供できるからです。
私は海外で働くデザイナーとして、自身が「日本人」であることも私のユニークなアイデンティティの一部だと考えています。例えば、デザイナーの同僚たちは私が細部への注意を払う傾向があるとよく指摘します。これは日本人の特性の一つではないかと思います。
また、多様性に富んだ職場においても、私自身が外国人と位置付けられるために、異なる文化や背景を持つ同僚の気持ちを理解し、異なる文化間の共通点や違いに気付くことにも長けていると感じます。
私は英語が母国語ではないため、マクロコピーの作成やコンテンツ作成が苦手だと思っていました。しかし、逆に言えば私は自然にシンプルで分かりやすい文章を書くことができ、分かりにくい表現を避けることができるのだと思うようになりました。
このように自分が苦手だと思っ��ていた分野でも「違い」に着目し、自分独自の視点や強みとして活かすことで、新たな発見や成長をすることができます。
最後に、「他の人から褒められたこと」について振り返ってみました。私のパフォーマンス評価でよく言われるのは、仕事が早いということです。私はクライアントや、チームメンバーのアイデアを積極的に取り入れたいと思っているので、たくさんの意見を聞くようにしています。また、テンプレートやデザインツールの使い方をスピーディに検索するので、それぞれの要素が組み合わさって、仕事を素早く進めることができると評価されているようです。次に考えたこと、それは「一体誰と仕事がしたいのか?」についてです。
誰と仕事がしたいのか?自身のビジョンをもとにターゲット層を設定する
パーソナルブランドを構築する上で、自分のビジョンがはっきりとしてきました。私は、教育、持続可能性、平等、または二酸化炭素排出の削減に関心を持っている人と仕事がしたいと思っていることに気がつきました。これらをもとに、自分がアピールしたいターゲット層を設定しました。
以下は、私が一緒に仕事をしたい人や組織のリストです:
サステナブルなブランド: 環境に配慮し、倫理的な製造方法や材料を使っているブランド
教育に関わること: 人々のスキルや知識を向上させ、成長の促進を目指すプラットフォームなど
B-Corp認証を取得している企業とのコラボレーション: 世界中の人々の生活を改善するために、具体的なプロジェクトや取り組みを行っている企業のインパクトプロジェクトなど
非営利団体(NPO): 社会の問題に取り組み、社会を良くするために活動しているグループや会社
これらの活動に関心を持っている方々と一緒に仕事をすることは、私にとって非常に意義深いものとなります。
ビジュアルアイデンティティの方向性を決定する
なんとなくターゲットが見えてきたので、次は自分自身のビジュアルアイデンティティの方向性を決定しました。
ロゴ
パーソナルブランドを考える上で、ロゴは自分のアイデンティティを示す大切なものです。自分の顔のシンプルでユニークなイラストや、自分の名前の頭文字を使ったロゴなどがあります。私は、ロゴに膨大な時間を費やしてしまうのを懸念して、今回は10分以内で作ったロゴをプレースメントとして使うことにしました。
カラーパレット
色の選定においては、一番に、自分の好みやアイデンティティに合った色を選ぶことは重要です。最近の流行で、ネオンカラーなどでハイライトされているデザインを見ると、ドキッとときめきますが、ずっと気に入っているのはAESOPのような秋色で落ち着いている色合いが好きです。それと同時に自分のビジョンにも適応できる色を選ぶことが最適だと考えました。これにより、ターゲット層にも響くブランドを作り上げることができるのではないかと思いました。
https://www.aesop.com/
例えば、私が興味を持っている分野に焦点を当てると、持続可能性や環境への貢献、教育などがあります。そのため、自然を表現するために色合いを選びました。プライマリーカラーとしては、森林をイメージした深緑を選定しました。また、この色がアクセシビリティテストでWCAG AAAにも適合することも確認しました。さらに、明るく楽しげで教育にもつながるため、4色の配色を取り入れたカラーパレットを作りました。このパレットは、Webサイトの制作後、どんどんと増えていきました。
フォント
フォントについては、プライマリーのフォントとしてはオープンソースのモダンでシンプルで読みやすいものを選びました。セカンダリーのフォントには、フレンドリーで上品ながら少し個性的なセリフフォントを選びました。通常はサンセリフフォントをよく使用しますが、今回はセリフがありつつも丸くてフレンドリーなフォントを選びました。
画像やイラストレーション
私の場合、環境に関連したテーマに焦点を当てたので、抽象的な木のイラストやシンプルな花のイラストを使用することを考えました。また、子供の教育にも関わりたいと思っているので、積み木や折り紙の要素を取り入れました。さらに、楽しげな雰囲気を出すために、ちょっとしたアニメーションや、モーションインタラクションも取り入れたいと考えています。
最後に、ブランド名は、自分自身の名前をブランド名にすることにしました。主な理由はドメインが残っていたから!ですが、ドメイン名やSNSアカウントの名前を検討することも重要です。
個人のWebサイトを最適化しよう
ブランドの基礎部分が決まってきたら、��早速Webサイトの制作にかかりました。なぜかというと、私はブランドの要素がちゃんと機能するかは、何か制作してみないとわからないからです。その点Figmaは最適なブランド制作ツールだと思います。一度スタイルを設定すれば、少しづつそれらをアップデートしながらブランドを構築できるからです。
最初に取り掛かったのは、「ABOUT」ページです。今回はこのページをメインにしたいと思いました。今まではABOUTページにそれほど重点をおくことはなかったのですが、ブランドを構築する上で、自分の中で一緒に働きたい人には「しっかりと自分のことを理解してから仕事を依頼して欲しい」と思ったからです。
私自身についての大切な情報に加えて、一見どうでもいいような、ほっこりとするような情報も提供したいと思いました。そして私の個性と興味、それから教育や将来に対する思いについても記載して、私のユニークなスキルと、興味があることもわかりやすく伝えたいと思いました。
次に重要なページは「WORK」セクションですが、実はまだコンテンツが充実していないため、あまり多くの作品を掲載することができません。これまでケーススタディを作成することが非常に面倒で、なかなかコンテンツを作成することができませんでした。しかし、今はChatGPTを利用して簡単にケーススタディを作成できそうなので、逆にワクワクしています。「WORK」には、自分のやりたいビジョンに沿っているものだけをセレクトして載せたいと考えています。
また、「ホームページ」にはお客様の声のような、一緒に働いたことのある人からの声というセクションも設けたいと思いますが、これは、ちゃんとWebサイトが出来上がってから、リンクを提供してお願いしたいと思っています。
オンラインプレゼンスの構築
Webサイトは徐々に形になってきているのですが、気が付いてしまったことがあります。
それは、ソーシャルメディアの画像やアイコンに統一感がなく、バラバラなデザインになってしまっていることです。このままでは一貫性がなく、プロフェッショナルな印象を与えられないのではないかと心配になってしまったので、一旦、バグだらけのWebサイトの作業は休憩して、現在、ソーシャルメディアTwitter、Instagram、Note、Dribbble、Behanceなどのデザインを統一するためにバナーやアイコンの制作を進めています。
ソーシャルメディアの画像は、各プラットフォームに合わせてデザインを調整する必要があります。例えば、私はロゴに自分のイニシャルの「N」を使用していますが、LinkedInやFacebookでは顔写真を使用する方が良いと考えました。そのため、3週間後にプロの写真家にプロフィール写真を撮ってもらうことにしました。この期間にダイエットして、顔がもう少しスッキリするように心がけたいです。
ソーシャルメディアのコンテンツにも統一感を
Noteのロゴとバナー、それからカテゴリー部分のカバー画像も変えたのに、統一感が出ず、バラバラに見える?なぜかというと、コンテンツに統一感がないからです。私の場合、以前は違ったカラーパレットとデザインスタイルを使用していました。そのため、ごちゃ混ぜに見えてしまいます。このように、コンテンツを発信する場合にはコンテンツ用の画像テンプレート�なども制作しておくと便利だと思います。
これらのステップを踏んで、自分自身をブランド化してきましたが、私はまだまだ苦戦中です。ブランドの構築には時間がかかります。忍耐力とコミットメントが必要です。私も、この記事を書こうと思うまで、なんとなくダラダラと時間がすぎてしまいました。
最後に、無料のリソース提供を通した広告戦略について
ここ数年で、無料のコンテンツの考え方が変わってきました。
というのも、ここ数年はパッシブインカムを作ることだけを考えていたからです。ちょっとだけでもキャッシュフローができればと、画像素材やテンプレートを制作したときに無料にするという考えがなかったのです。
しかし最近になって、価値があり本当にに役立つ無料コンテンツを提供することは、私が専門知識を持っていることを示すことができ、人々から信頼を得ることができるということがわかりました。考えてみると、私も無料でダウンロードできて高品質な画像を提供してくれるクリエーターには、信頼感を持っていつも感謝しています。クリエーター名もしっかりと覚えています。このように、無料でのリソース提供は多くの人に自分を知ってもらうきっかけとなるため、優れた広告戦略になるのです。私も、今後Figmaのコミュニティや、自身のWebサイトのリソースページで、テンプレートやガイドを無料で提供したいと考えています。
まとめ
現在、私のWebサイトはまだ完成しておらず、改善が必要な部分がたくさんあります。しかし、最近、フリーランスの仕事の依頼が増えてきました。メッセージには、依頼主が私の会社の理念やビジョンに共感しているという言葉が添えられており、おそらくWebサイトを見てくださっているのだと感じています。
今後、デジタル時代においては、パーソナルブランドの価値がますます高まってくるかと思います。皆さんもパーソナルブランドを構築してみてはいかがでしょうか?時間と労力はかかりますが、自分自身についてより理解し、自分の知識やスキルを明確にしてブランドを構築することで、キャリアアップや成功に向けて準備することができると思います。
Nokoです。メルボルン在住のプロダクトデザイナーで、リモートで仕事をしています。 過去8年間は、ブランド戦略、エクスペリエンスデザイン、ビジュアルデザイン、モーションおよびイラスト、アクセシビリティデ�ザインなどのデジタルデザインの様々な分野で仕事をしてきました。現在は、Two Bulls/DEPTでシニアプロダクトデザイナーとして、様々な国際的なデザインプロジェクトに取り組んでいます。
https://nokowashiyama.com/