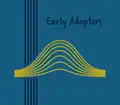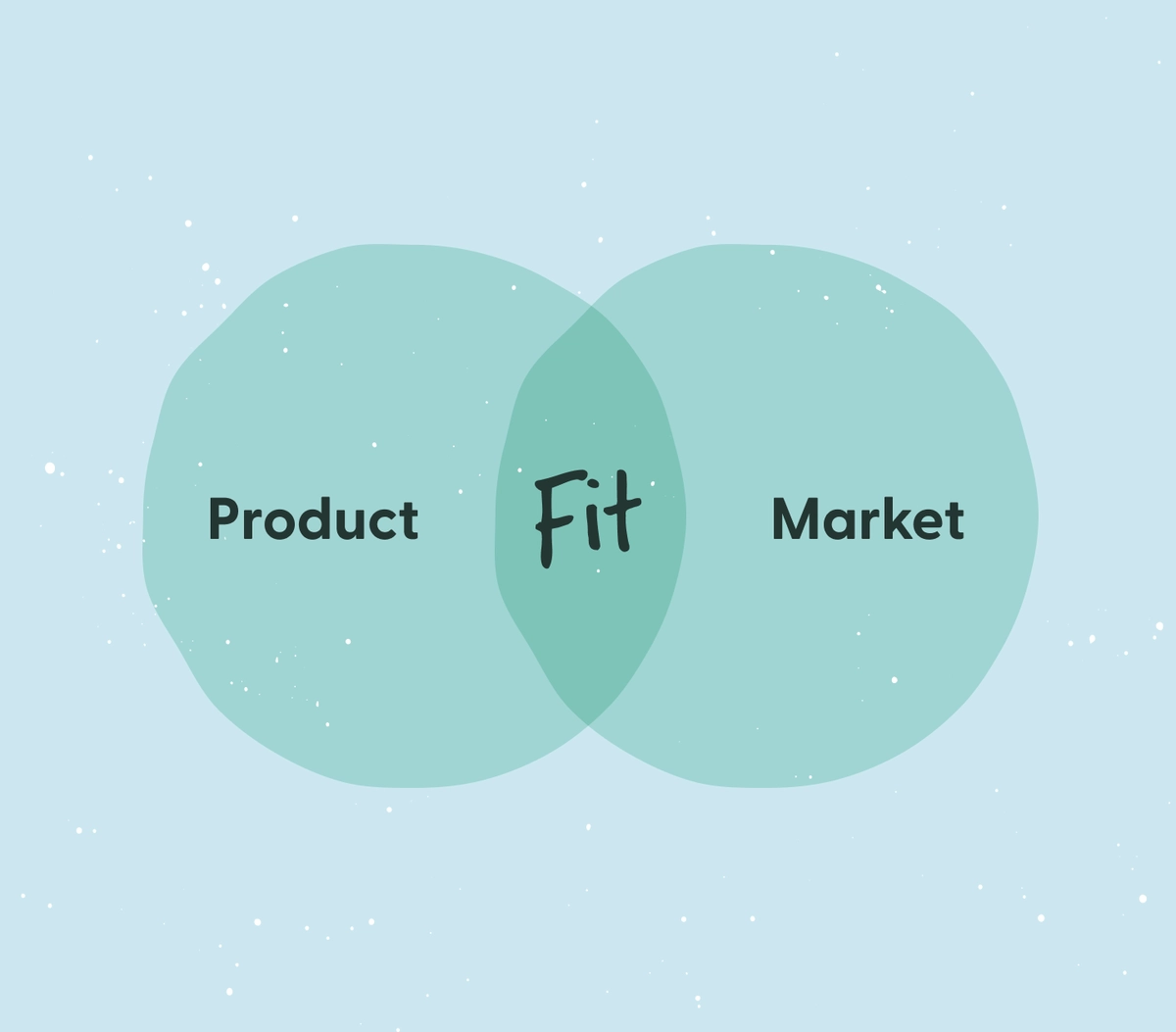
PMF(プロダクトマーケットフィット)とは?新規事業がまず達成するべき重要指標。
PMF(Product Market Fit)とは、その名の通り、製品が市場のニーズに合っている状態のことを表す言葉です。新規事業の初期段階において重要なビジネス指標とされ、事業継続の判断基準としても使われます。また、スタートアップのように市場が存在するかどうかさえ不明確なビジネスを行う場合にも、このPMFを一つの初期目標としてプロダクト改善に取り�組むことになります。PMFを達成していることは、スタートアップがベンチャーキャピタルから投資を受ける際の条件となる場合も多く、このような場合、数的根拠を持ってPMF達成を証明する必要性も出てきます。このようなスタートアップのプロダクト開発手法としては、MVPの継続的な改善を通して市場の反応を探りながらPMFを目指すリーンスタートアップが有名です。
また、スタートアップにおいては、プロダクトのUXをどんなに改善したとしてもビジネス目標を達成できない場合も多く、そのような場合はビジネスのPMFを確認し、そもそも「プロダクトが提供しようとする価値に対してお金を払いたいと感じる人が十分な数いるのか」という問いに立ち返りましょう。PMFがうまくいかないのであれば、ピボット(路線変更)することも一つの選択肢となります。
PSF(プロブレムソリューションフィット)とPMFの違い。プロダクトと市場の存在。
PMFと一緒によく聞く言葉に、PSF(Problem Solution Fit)があります。PSFとは、ビジネスが解決しようとしている課題に対して、「正しい解決策を提示できている」状態です。PSFを測るためには、必ずしも実際の製品は必要ないため、新規事業において製品開発に取り掛かる前段階の「事業企画」や「市場調査」において用いられる指標となります。
例えば、「病院の待ち時間が長い」という課題に取り組む際に、考え得る解決方法は一つではありません。
医者の数を増やす
病院に来る患者の数を減らす
看護師でも対応できる処置を見分ける
予約時間を最適化する
など、さまざまな解決策が考えられますね。
PSFとは、「この解決策が本当に課題を解決できる」と言えるような状態のことをいいます。そして、PSFを検証するためには、実際にプロダクトやサービスを作る必要はありません。上記の例であれば、課題を抱える患者や、病院の経営者などのステークホルダーへのインタビューを行ったり、実証実験としてそれぞれの解決策を試してみたりといった方法で課題に対してどの解決策が有効であるかという問いに対する答えを導くことができます。
PSFを達成したのち、「その解決策をプロダクトとして顧客に販売できるか?」の検証を行うのが、PMFを目指す次のフェーズとなります。つまり、PSFとPMFの大きな違いはPMFにおける「プロダクト」と「市場」の存在です。PSFでは解決策の有効性を検証すれば良いのに対し、PMFでは、実際の製品(プロダクト)を開発し、それに対して顧客がお金を払ってでも欲しいと思えるか(市場性)という点を検証する必要が出てきます。
PMFの重要性: 事業拡大前にプロダクトに対するニーズがあることを確認
スタートアップが失敗する要因で一番多いのが、「プロダクトに対するニーズがなかったこと」です。極端な言い方をすると、「誰も欲しくないものを作っていた」ということです。このような状態にならないためにも、ピボット(路線変更)することを視野に入れた上でPMFを検証し続けることが重要になります。路線変更するのであれば、判断のタイミングは早ければ早いほうが良く、需要のないプロダクトのために多くの資金と時間を費やすようなことを避けることができます。
また、初期段階のスタートアップのプロダクトを試してくれるユーザーは、プロダクトが解決しようとする課題に対する熱量が特に高い人たちです。イノベーター理論では、この層のことを「イノベーター」と「アーリーアダプター」と呼び、「機能や新規性を重視するユーザー層」であると定義しています。そして、アーリーアダプターにプロダクトが浸透した��後に求められるのが「一般ユーザーへの浸透」です。つまり、熱量の高い一部のユーザーに認められたとしても、そのプロダクトが一般ユーザーにまで受け入れられるとは限らないのです。一般ユーザーはアーリーアダプターよりも保守的で、実績や価格など機能面以外の項目を考慮した上でお金を払うため、この段階でのPMFはさらに難易度が上がります。逆に、初期段階でPMFが達成できないということは、課題に対する熱量が高い「アーリーアダプター」にも受け入れられていない状況ということになり、その後の成長は見込めないという客観的判断をされてしまうのです。
PMFのためには何をすれば良いのか?
では、PMF達成のためには何をすれば良いのでしょうか?PMF達成のためには、「市場があること」を証明する必要があります。つまり、1日�や2日ではPMFは達成されません。PMFのために行えることはただ一つ、「実験と検証」です。PMF達成とはどのような状態なのか、それぞれのプロダクトに合った定義を打ち立て、プロダクトの機能やUI、料金形態について仮説を持って戦略を実行し、実際に効果があったかどうかを一つずつ検証するのです。この実験と検証の繰り返しによってプロダクトが改善され、PMFを証明できるようなデータが集まり始めます。
PMFを検証するための指標
では、PMFを数的に検証するためにはどのような指標が使われているのでしょうか?プロダクトの内容やビジネスモデルによって使われる指標はさまざまですが、ここでは多くのモバイルアプリやWebサービスで使われるPMF指標を紹介します。
PMF検証のためにふさわしくない「虚栄の指標」
PMF検証に適した指標を理解するためには、逆に「PMFを検証するための指標としてはふさわしくない指標」を理解することが近道となります。この「ふさわしくない指標」には、リーンスタートアップが提唱する構築・計測・学習のループにおける「計測」についての指南書である、「リーン・アナリティクス」において「虚栄の指標(vanity metrics)」として定義されているものが該当します。
例えば、「リリースしたプロダクトが1週間目から100万ダウンロードを達成した」などといった話もよく聞きます。この場合は、PMFを達成達成したと言えるのでしょうか?答えは、ほとんどの場合「いいえ」です。ダウンロード数という数値は、プロダクト自体の魅力を純粋に表す指標ではなく、広告キャンペーンや話題性などといった多くの外部要因に影響されています。また、サービスによっては時期的な影響を受ける場合もあります。このような指標は、どんなに見栄えが良くても次のアクションに関するヒントは与えてくれない上、期間を跨いで客観的に比較することもできません。
虚栄の指標とは、見栄えが良いものの、プロダクトの実際の評価や戦略策定には役に立たない数値のことで、上記のダウンロード数の他に「ユーザー数」や「ページビュー数」などもこの例に該当します。ユーザー数という絶対数だけでは、「主な流入経路何か?」「再訪ユーザーの割合は?」「ユーザーの滞在時間は?」といったプロダクトの改善施策につながるような情報を得ることができません。PMFのための指標としては、プロダクトの状態を客観的に判断できる上、次の戦略・アクションに導いてくれるような指標(actionable metrics)を取り入れることが望ましいです。
SMART Goals(スマートゴールズ)
PMFに適した指標を定義するためには、「SMART Goals(スマートゴールズ)」と呼ばれるKPI指標の選択基準が有効です。SMARTとは、指標の評価基準となる要素の頭文字からなる言葉で、
Specific: 具体的である
Measurable: 計測可能で��ある
Attainable: 現実的に達成可能である
Relevant: 全体戦略に沿っている
Time-based: 長期を跨いで計測・比較できる
という5つの要素によって定義されます。これらの条件を満たす指標は多くの場合、絶対数ではなく割合で表現され、期間を跨いで長期的に成長を測定することができます。これらのSMART Goalsの条件を満たし、PMFの指標としてよく使われるものを紹介します。
利用開始翌週の継続率(リテンション)
リテンションレートとは、プロダクトやサービスを初めて利用したユーザーが、一定期間継続して利用してくレているかという指標です。モバイルアプリなどでは、初回利用日から計算して次の週に再度アプリを使ってくれたユーザーの割合を継続的に計測することが多いです。この数値は「ユーザーが初めてサービスを使ったときに魅力的に感じたか」を直接的に示す指標となるため、PMFのためにまず重視される指標です。平均的なサービスだと、インストール後1週間のリテンションは20%前後となる場合が多く、ユーザーのニーズにマッチしているアプリだと50 ~ 60%を超える数値となります。
チャーンレート
チャーンレートは、「解約率」や「顧客離脱率」を意味する用語で、一定期間内にサービスを使わなくなったユーザーの割合となります。サブスクリプションサービスなどの、継続利用を前提としてサービスでよく使われる指標で、この数値を低く保つことがPMFの達成を目指す際に重視されます。「サービスに対する満足度が高ければ解約せず使い続けてくれるだろう」という前提のもと、この数値が高いと「ユーザーはお金を払ってまでそのサービスを使い続けたいと思っていない」と見なされてしまいます。
NSP(ネット�プロモータースコア)
PMFを測る指標として、もう一つ有効なのが「ユーザーに満足度を直接聞く」ことです。これを定量的に評価できるようにしたものが、NPS(ネットプロモータースコア)です。NPSとは、「あなたはこのプロダクトを友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」という質問に対して、ユーザーに0 ~ 10の11段階で評価してもらい、9~10点を付けたユーザーの割合から0~6点をつけたユーザーの割合を引いて求めることができる数値です。NPSはユーザーの主観的な評価に基づくため、対象ユーザーの文化的背景や市場、対象年齢に大きく左右されます。そのため、そのスコア自体に注目するのではなく、継続的に数値を取得して、前回計測時と比較して向上したのかどうかを評価すると良いでしょう。
PMFの次は?PMFが達成されたら
PMFが達成される頃には、溢れる顧客のニーズへの対応にオペレーションが追いつかなくなると言われています。スタートアップであれば、この段階で数億円規模の「シリーズA」と言われる投資ラウンドでの調達を行うことが多いです。資金を調達し、事業の拡大に向けて動き出すフェーズとなります。この、事業を拡大するフェーズになると、ターゲットのユーザー層が変化してくることが多々あります。前述したキャズム理論における、「一般ユーザーへの浸透」フェーズです。それまでプロダクトを支持してくれていたユーザー層とは思考パターンが異なるユーザーへのアプローチが必要となるため、事業を拡大しながら、新たなターゲット層に対するPMFを検証していくことが主な活動となります。
まとめ
今回は、新規事業にとって重要なゴールとなるPMFについて、その重要性や主な指標を紹介しました。PMFを達成しているかどうかは、新規メンバーとして事業に参加する際にも、その事業の状況や目指す方向性を確認するためにも有効な指標となります。