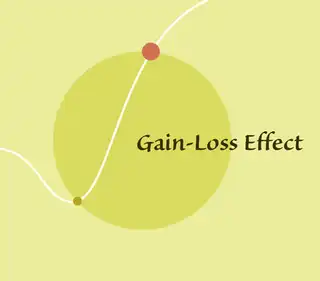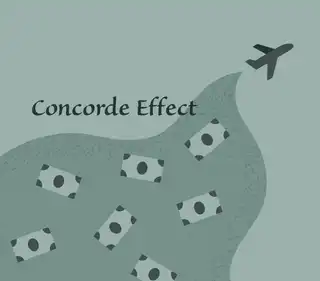行動経済学の基礎・プロスペクト理論とは?
プロスペクト理論(Prospect theory)とは、「富をめぐる人の心理」について分析した意思決定理論で、行動経済学の基礎に位置づけられる有名な研究です。プロスペクトは英語で見込みや可能性を意味する言葉で、人は不確かなリスクのある状況下では利益や損失に対する意思決定に認知のバイアスがかかりやすくなることが指摘されています。私たちは「利益��はできるだけ早く確定したい」と願う一方で、「損失は先送りしたい」と考える傾向をもっており、得をしたときよりも損をしたときのほうが2〜3倍重く感じてしまうことが示されたのです。
この理論を提唱したのはアメリカの行動経済学者のダニエル・カーネマンで、1979年にイスラエルの心理学者エイモス・トベルスキーとの共同研究として論文「プロスペクト理論:リスクがある環境下での意思決定の分析」が発表されました。のちにカーネマンは人の心理に関する研究から得た知見を経済学に結びつけた功績から、2002年にノーベル経済学賞を受賞しています。経済における意思決定にある程度共通する人の行動パターンを見出して、人の心理や感情がどのように行動に結びついて経済を動かすのかについて分析した研究が評価されたのです。
行動経済学の具体例としては、たとえば「気持ちよく晴れた日には株価が上昇するけれど、なんとなくうっとおしさを感じる曇りの日には株価が低調になる」「良いことが起きても悲しいことが起きても、人は感情が動いたときに飲みに出かける」などがあります。人の感情の動きがどのような行動を生み出し経済を動かすのかを理論化・解明することが行動経済学の役割です。
カーネマンらがプロスペクト理論を導くために行った実験は「一つだけの質問による心理学」と呼ばれる心理学��者のウォルター・ミシェルが用いた手法を参考に行われました。たとえば以下のような設問が提示されます。
問題1 あなたはどちらを選びますか?
確実に900ドルもらえる
90%の確率で1,000ドルもらえる
問題2 あなたはどちらを選びますか?
確実に900ドル失う
90%の確率で1,000ドル失う
(ダニエル・カーネマン・村井章子(訳)(2012).『ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか?(下)』 早川書房より)
彼らの調査では、問題1では多くの人々が「リスクを回避して利益を優先�する」ことを選び、人は利益はできるだけ早く確定したいと考える傾向をもつことが示されました。また問題2では「損失回避のためリスクをとる」ことを選ぶ人が多数であることがわかりました。これらの結果からカーネマンは「人は確実に利益を得られる場合にはギャンブル性のある選択肢を嫌うが、確実に損をするとわかっている場合にはリスクを承知しながら損失の出ない確率に望みをたくす人が多い」という考察を導きました。
さらに、利益が出ている局面と損失が出ている局面を比較した場合には、人は利益が出たときの喜びよりも損失が出たときの精神的なダメージのほうをより重く捉えることから「損失はできるだけ先送りしたい」と考えることも示されました。前述したように人の心には、同じ金額でも「得をしたときよりも損をしたときのほうが2〜3倍重く感じてしまう」という不合理な受け止め方をする傾向があることが明らかになったのです。
プロスペクト理論を可視化するグラフ
損失は2〜3倍重く感じることを示す「価値関数グラフ」
前述した現象を説明するために��、カーネマンとトベルスキーは「価値関数」のグラフを用いました。人が何かに価値を感じるとき、その感じ方に実際の価値とはズレやゆがみが生じることを数値化して関数で示したものです。
Kahneman and Tversky(1979)より
価値関数グラフは利益や損失に対する主観的な価値(感情)を評価するため、タテ軸で心理的な価値をはかり、ヨコ軸は金額を示します。タテ軸とヨコ軸が交わる点は数字のゼロではなく、判断の基準となる「参照点」として設定されているのが特徴です。
心理的な価値の軸は上方向がプラスで下方向はマイナス、金額の軸は右方向が利益で左方向は損失を示し、いずれも参照点を境に切り替わります。よってグラフの右上の象限は利益、左下の象限は損失に対する心理的な価値の大きさを表します。どちらも参照点からプラスに評価するのか、マイナスに評価するのかという相対的な判断をするのが特徴で、その評価は曲線で示されます。
たとえば「利益の額」と「損失の額」が同じ100ドルだった場合、参照点をはさんだ左右のヨコ軸に同じ幅でポイントされます。しかし感情を示す曲線に向かってそれぞれタテに線を伸ばしてできる四角形を比較してみると、100ドルを得る喜びの大きさよりも、100ドルを失う悲しみのほうが、より大きな長方形として表示されることが見てとれます。金額の価値は同じでも損をした悲しみやがっかり感のほうが2〜3倍程度重く感じられることが可視化示されています。
小さな確率を過大評価する心理が見える「決定の重みづけのグラフ」
プロスペクト理論を可視化するグラフはもうひとつあります。「決定の重みづけのグラフ」と呼ばれる「確率加重関数」のグラフです。こちらは確率に対する感じ方にズレやゆがみが生じることを数値化して関数で示したものです。
Kahneman and Tversky(1979),Tversky and Kahneman(1981), 友野(2006)より作成
このグラフのヨコ軸は「客観的な確率」、タテ軸は「主観的評価による確率」を示しています。実線が点線を上回っているときは過大評価されている状態で、下回っている場合は過小評価されている状態であると読み解きます。カーネマンらによれば、35%以下の確率は高い確率であるかのように過大評価をされ、35%以上の確率は実際よりも低く見積もられて過小評価されてしまうことがわかりました。
たとえば「得に関する確率」について宝くじを例に説明すると、宝くじが当たる確率は実際には極めて小さいにもかかわらず、人は「もしかしたら当たるかもしれない」と過大な評価による期待感をもって購入する行動を起こします。
「損失に関する確率」については、自動車よりも飛行機による事故件数のほうが少なく安全である確率が大きいことが示されていても、その大きな確率を過小評価して飛行機事故のほうをより恐れる傾向があると説明されています。
マーケティングにおけるプロスペクト理論
人の行動は心の動きに影響されるため、経済における意思決定に感情が大きな影響を及ぼすことについて、これまでにさまざまな研究が蓄積されてきました。行動経済学では経済は人の心が動かすことを重視しています。そのためプロスペクト理論はFXや株式投資の場で語られるだけでなく、消費者行動研究のフィールドでも応用されています。
「損失回避の心理」を応用した施策例
リミット内に使わないと損をしてしまう
期間限定の割引キャンペーンやクーポンのプレゼント
今だけ送料無料サービス
ポイントの期限通知メール
使ったり入手しておかないと損をしてしまう
特典が付与されるサービス
希少性の高い貴重な品
損失回避の心理は、裏を返せば「得を逃したくない心理」ともいえます。そのため人は限定感やお得感のあるフレーズに接すると「逃すと自分だけ損をしてしまう」という損失回避の心理が刺激されることが少なくありません。じっくり検討してみれば理屈にあわない選択でも、損失を避けようと反射的にアクションを起こしてしまう傾向をもっているため、上記のようなフレーズが定番として効力を発揮するのです。
まとめ
経済における重要な意思決定理論、プロスペクト理論に�ついてまとめました。マーケティングに多用される「損失回避の心理」ですが、たとえばZ世代はタイムパフォーマンスを重視する世代であることが知られています。パッと見ただけで時間的なコストを損失しそうな印象を与えてしまうと、そのことが敬遠や回避をされてしまう理由になるかもしれません。ユーザーフレンドリーな工夫がより評価される時代も加速しています。
参考文献
ダニエル・カーネマン・村井章子(訳)(2012).『ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか?(下)』 早川書房
真壁昭夫 (2019).『行動経済学 見るだけノート』宝島社
八島明朗 (2008). マーケティングにおけるプロスペクト理論研究のレビュー マーケティングジャーナル. 28(1),101-113
プロスペクト理論 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』 (最終閲覧日2023年4月15日)
ダニエル・カーネマン フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』 (最終閲覧日2023年4月15日)