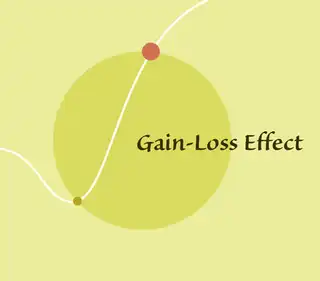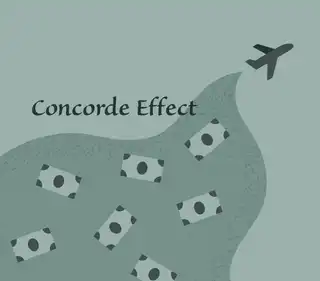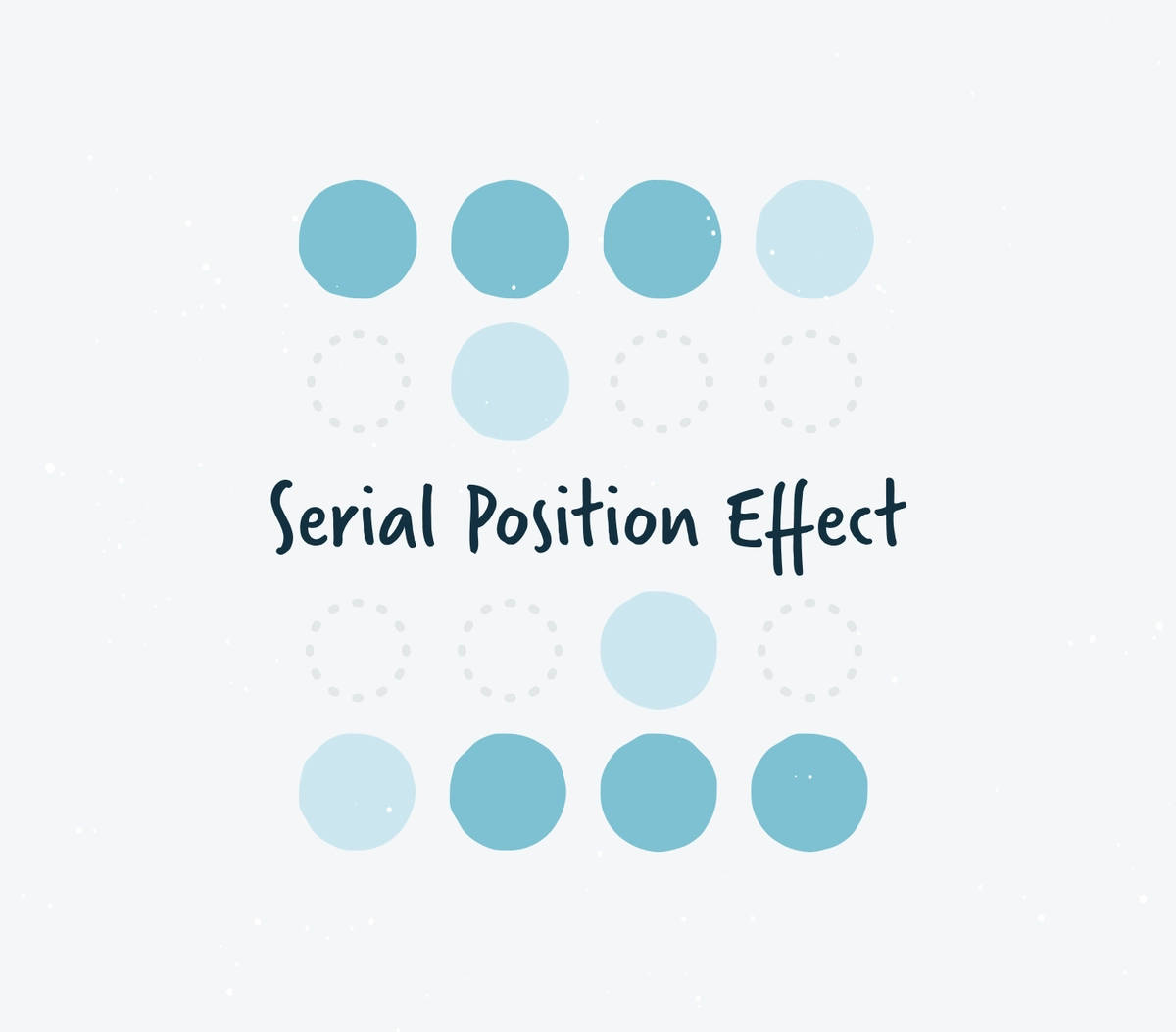
系列位置効果とは?
系列位置効果(Serial position effect)とは、記憶の残りやすさにまつわる現象です。人が複数の項目を提示された順番で記憶しようとするとき、覚えた順番によって記憶の再生に差が出てくるというものです。最初のほうに提示された項目と、最後のほうに提示された項目は記憶に残りやすく、中間の記憶は忘れてしまいやすい傾向があるとされています。系列位置効果という名称は1990年代にドイツの心理学者、ヘルマン・エビングハウスによって名付けられました。
エビングハウスは記憶に関する実験的研究の先駆者であり、忘却曲線を発見した人物でもあります。しかし彼の記憶研究は自分自身を唯一の研究対象としていることに限界があり、系列位置効果は他のさまざまな心理学者の研究に受けつがれ、初頭効果や新近効果によって理論づけられました。
系列位置効果の実験
系列位置効果は心理学者のグランツァーとカニッツ(Glanzer & Cunitz,1966)による実験が代表的で、以下のような手順で検証されています。
実験参加者に意味をなさない無意味な15語の単語リストから、2秒間隔で単語をひとつずつ呈示して記憶してもらう
呈示した直後に順番は自由に思い出してもらう「直後自由再生テスト」と、少し時間がたってから順番は自由に思い出してもらう「遅延自由再生テスト」を行った
その結果、全体的に最初のほうに提示された項目と、最後のほうに提示された項目は回答の成績が良く、全体を曲線として見た場合にU字型を描くような結果が得られた
系列位置効果を�理論づける2つの効果
1) 初頭効果(Primacy effect): 最初に提示された項目が記憶に残りやすい理由とは?
初頭効果とは、ポーランド出身の心理学者ソロモン・アッシュが定義した、人は最初に与えられた情報が印象に強く残りやすいという現象です。アッシュは2つのグループに対して、架空の人物の特徴についていくつかの単語を読み上げるという実験を行いました。人物の特徴についての単語は、良い印象から始まって途中から悪い印象の単語に変わっていくように並べました。
最初のグループに対しては単語のリストを頭から読み上げ、次のグループに対しては順番を逆から読み上げて、印象がどのように変わるかを調査したのです。その結果、意味は逆だったにもかかわらず、�どちらのグループも「冒頭に読み上げた単語」から架空の人物の第一印象を回答したのです。アッシュは情報を提示する順序によって異なる印象が形成されることから、初頭効果を見い出しました。そして、人物やものごとの第一印象が長期間に渡って残るのは初頭効果の影響であると理論づけています。
2) 新近効果(Recency effect): 最後に提示された項目が記憶に残りやすい理由とは?
新近効果とは、アメリカの心理学者ノーマン・アンダーソンが提唱した、人は最後に与えられた情報や直前に与えられた情報がより強く印象に残りやすいという現象です。直近の新しい記憶のほうが短期記憶に残りやすく、再生率も良いというもので、「新近性効果」とも呼ばれています。アンダーソンは、人の関心は前半に得た情報よりも後半に得た情報のほうに向けられやすい傾向があると考察しています。
ちなみに前述したグランツァーとカニッツの実験結果によれば、初頭効果は単語を呈示した直後に行う「直後自由再生テスト」と、時間を置いてから行う「遅延自由再生テスト」の両方で変わらずに発生し、新近効果は「直後自由再生テスト」のみで発生しました。このことから、同じ系列位置効果といっても、初頭効果は長期記憶、新近効果は短期記憶に残りやすいことが導かれ、長期記憶と短期記憶は記憶の質が異なるのではないかと考察されています。
記憶のメカニズム: 記憶のモデルは多重構造
入ってきた情報を一瞬で忘れる「感覚記憶」として保管
注意を向けた情報は海馬に運ばれ、1分程度の「短期記憶」として保管
くり返し復唱することで「中期記憶」として最長1か月保管
重要な記憶は「長期記憶」として長期にわたって定着


まとめ
人が複数の項目を提示された順番で記憶しようとするとき、覚えた順番によって記憶の再生に差が出てくるという、系列位置効果についてまとめました。たとえばプレゼンテーションや動画などでは、重要なテーマは最初と最後に置くことで相手の記憶により長くとどまることが期待されます。
参考文献
鹿取廣人 (編)・杉本敏夫 (編)・鳥居修晃 (編)・河内十郎 (編) (2020). 『心理学 第5版 補訂版』 東京大学出版
服部雅史・小島治幸・北神慎司 (2022). 有斐閣ストゥディア『基礎から学ぶ認知心理学 人間の認識の不思議』 有斐閣
ヘルマン・エビングハウス 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』 (最終閲覧日2022年12月1日)
Glanzer, M., & Cunitz, A. R. (1966). Two storage mechanisms in free recall. Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior, 5, 351–360.