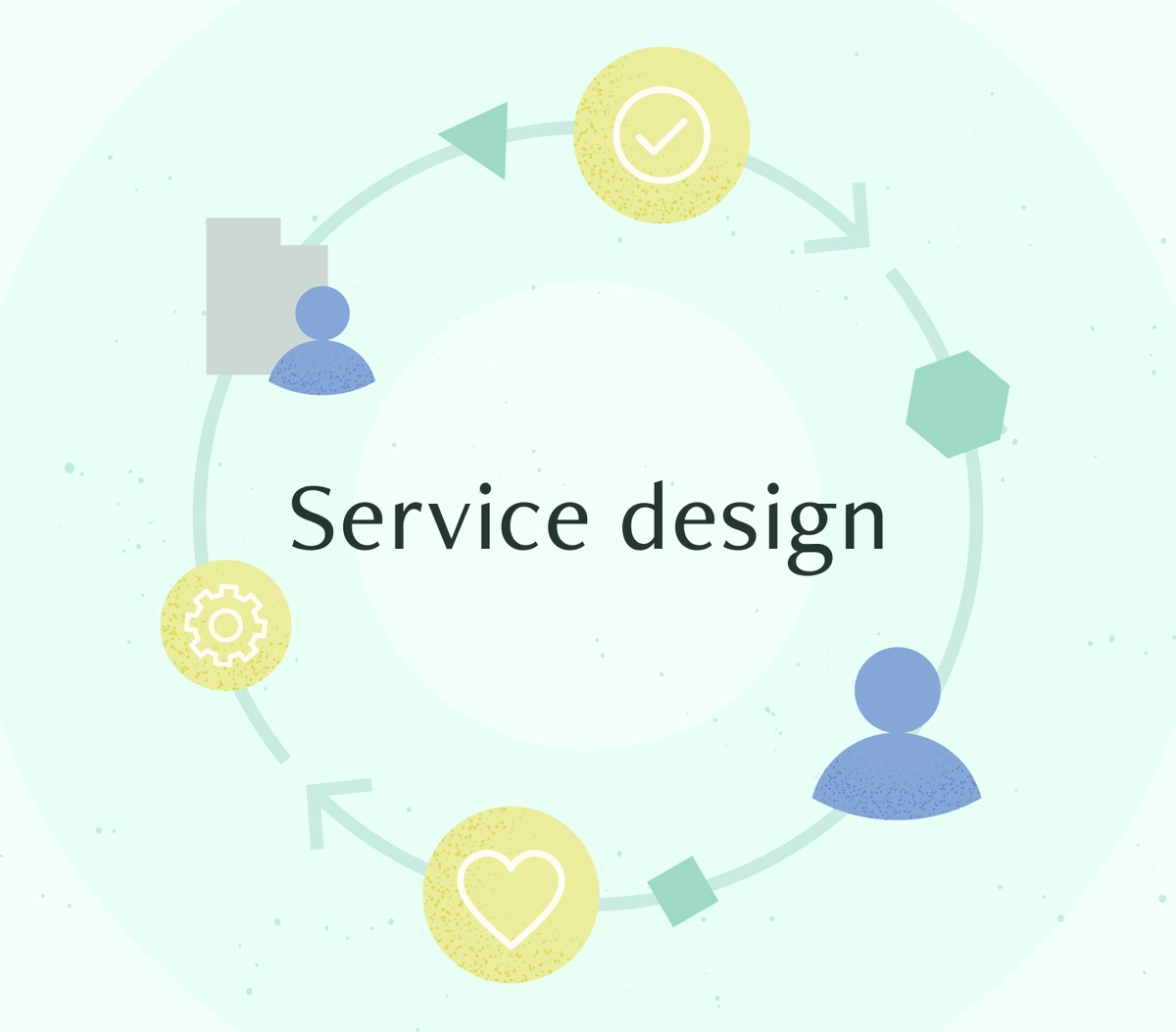
サービスデザインとは?
サービスデザインとは、顧客に提供��するサービス全体の体験をデザインし、改善するプロセスを指します。このアプローチは、顧客が直接触れる製品やサービスだけでなく、店舗のレイアウトやWebサイトの使いやすさ、顧客サポートの質など、関連するすべての接点を考慮に入れます。
また、経済産業省の資料では、サービスデザインの概要を以下のように示しています。
サービスデザインは、顧客にとって望ましい連続的な“体験”を提供するための仕組みとして“サービス”を構想し、実現するための方法論であり、その特徴は、「人間中心」、「共創」、「包括的」といったキーワードで表すことができます。
サービスデザインをはじめるために|経済産業省
サービスデザインの目的は、顧客にとって価値のある体験を提供し、顧客満足度を向上させ、ロイヤリティを強化をすることで、ビジネスを成長させることにあります。
サービスデザイン思考とは
サービスデザイン思考とは、従来のビジネスやサービスの開発プロセスにデザインの方法論を取り入れ、人間中心の視点からサービス��全体を考え直すサービスデザインの思考方法です。この思考は、単に見た目を整える「デザイン」にとどまらず、利用者の体験やサービスの提供方法に深く関わります。利用者がどのように振る舞い、どのように感じるかを重視し、それに基づいてサービスを全体的にデザインすることが特徴です。
具体的には、利用者の実際のニーズや課題を発見し、それを解決するためのアイデアを創出し、プロトタイピングとテストを繰り返しながらサービスを改善していくプロセスを含みます。このプロセスを重ねることで、利用者にとってより価値のあるサービスを生み出すことが可能になります。また、内部プロセスの効率化や、新たなビジネス機会の発見にもつながるため、多くの組織や企業で積極的に採用されています。
サービスデザインとUXデザインの違い
サービスデザインとUXデザインの違いは、重点を置く対象とその範囲にあります。UXデザインは、ユーザーが製品やサービスを使用する際の体験に焦点を当て、その使いやすさや満足度を高めることが目的となります。一方サービスデザインは、サービスや商品を提供するための仕組みの設計までおこなうことが大きな特徴で、多角的なアプローチでサービス全体の構造をデザインし、顧客の体験価値向上を目指します。
サービスデザインの対応範囲には、ロジスティクスやバックヤードの設計、フルフィルメントのフロー構築など、バックステージの設計も含まれます。顧客体験に重点を置いたUXデザインとは異なり、サービスデザインの良し悪しによって、提供する事業者サイドへも影響が生じるといった点にも違いがあるといえるでしょう。
サービスデザインとCXデザインの違い
サービスデザインとCXデザインの主な違いは、対象範囲の広さにあります。サービスデザインは、顧客体験を継続的に実現するための組織や仕組みを含め、サービス提供全体をデザインするアプローチです。一方CXデザインは、顧客が商品やサービスに接触する前の認知段階から使用後までの全体的な顧客体験に焦点を当てます。
CXデザインでは、購入前後のサポートやアフターサービスも重要な要素です。つまり、サービスデザインはサービス提供の背後にある組織やプロセス��も考慮に入れるのに対し、CXデザインは顧客との直接的な接点に重きを置いているという点も異なります。
サービスデザインが重要視されている背景
市場にモノがあふれる現代においては、モノのみによる差別化が難しくなっていることから、体験(=コト)が重要視される傾向があります。情報技術の進化とともに、顧客は単なる製品やサービスの機能性だけでなく、その利用過程での体験価値を重視するようになりました。
このため、企業は顧客一人ひとりのニーズに応える柔軟なサービス提供が求められ、それを実現するためにサービスデザインのアプローチが重要視されています。また、競争が激化する市場において差別化を図り、持続可能な成長を達成するためにも、サービスデザインは欠かせない戦略となっているのです。こうした背景もあり、一連の顧客体験を向上させるための方法論として、サービスデザインが重要視されています。
経済産業省によるサービスデザインの推進
経済産業省は、サービスデザインの推進を通じて、企業や公共サービスの質の向上を目指しています。この取り組みは、顧客体験の向上とビジネスプロセスの革新を図ることで、日本経済の持続的な成長を支えることを目的としています。
具体的には、サービスデザインを活用して新たなサービスやビジネスモデルを創出し、既存のサービスの改善にも取り組んでいます。また、企業間のコラボレーションや異業種間の連携を促進することで、新たなイノベーションの創出にも貢献しています。
経済産業省によるこのような推進策は、日本のサービス業の競争力を高めるとともに、国際市場における日本のプレゼンスの強化にもつながると期待されています。
デジタル・ガバメント実行計画における「サービス設計12 箇条」
政府はデジタル・ガバメント実行計画において、「サービス設計12箇条」を策定し、公共サービスの質の向上を図ることで市民に寄り添ったサービスの提供を目指しています。設定されているサービス12 箇条は以下の通りです。
第1条 利用者のニーズから出発する
第2条 事実を詳細に把握する
第3条 エンドツーエンドで考える
第4条 全ての関係者に気を配る
第5条 サービスはシンプルにする
第6条 デジタル技術を活用し、サービスの価値を高める
第7条 利用者の日常体験に溶け込む
第8条 自分で作りすぎない
第9条 オープンにサービスを作る
第10条 何度も繰り返す第
第11条 一遍にやらず、一貫してやる
第12条 システムではなくサービスを作る
サービス設計12箇条は、行政機関がITを活用したサービスや業務を提供する際、従来の提供者中心のサービス設計から脱却し、利用者本位のサービス・業務設計を目指すことを奨励しています。この取り組みは、政府情報システムの使い勝手を向上させるだけでなく、サービスそのものを利用者に満足して使ってもらえるものに再設計することを意味します。
デジタル・ガバメントの取り組みは、民間企業においても参考にされており、顧客中心のサービス開発への意識も高まっている状況です。この12箇条に沿ったサービス設計と改革が、公共サービスの質の向上と効率化に大きく貢献することが期待されています。
サービスデザインに必要な6つの原則
経済産業省がまとめるサービスデザインの概要の中でも、サービスデザインに必要な6つの原則として、以下の内容が紹介されています。
サービスデザインに必要な6つの原則
1. ⼈間中⼼
サービスの影響を受けるすべての⼈のエクスペリエンスを考慮する。
2. 共働的であること
サービスデザインのプロセスには多様な背景や役割を持つステークホルダーが積極的に関与しなければならない。
3. 反復的であること
サービスデザインは、実装に向けた探索、改善、実験の反復的アプローチである。
4. 連続的であること
サービスは相互に関連する⾏動の連続として可視化され、統合されなければならない。
5. リアルであること
現実にあるニーズを調査し、現実に根差したアイデアのプロトタイプを作り、形のない価値は物理的またはデジタル的実体を持つものとしてその存在を明らかにする必要がある。
6. ホリスティック(全体的)な視点
サービスはサービス全体、企業全体のすべてのステークホルダーのニーズに持続的に対応するものでなければならない。
これらの原則を適用することで、サービスデザインは利用者中心のアプローチを保ちながら、全体的な視点からサービスを改善し、実装することが可能になります。サービスデザインは単なる一時的なプロジェクトではなく、継続的におこなっていくプロセスです。これらの原則はそのプロセスをガイドするための重要な要素です。
サービスデザインのプロセス
サービスデザインのプロセスは、以下のようなステップで構成されます。
事業計画設計
リサーチ
アイディエーション
プロトタイピング
テストマーケティング
サービスの実装
このプロセスを通じて進めることで、利用者の真のニーズを理解し、顧客満足度の高いサービスを�開発することが可能になります。
STEP1:事業計画設計
サービスデザインの第一歩は、明確な事業計画の設計から始まります。この段階では、サービスの目的・目標市場・提供する価値を定義します。また、事業のビジョンやミッションを明確にし、それを達成するための戦略も策定します。
事業計画設計は、サービスデザインプロセスの基盤を築き、次のステップに向けた方向性を明確にする役割を担います。この段階での洞察と戦略は、後続のリサーチやアイディエーションにおいて重要なガイドラインとなります。
STEP2:リサーチ
サービスデザインのプロセスにおいて、リサーチは不可欠なステップです。この段階では、定性的/定量的の両面でリサーチをおこないます。対象となる市場や顧客の深い理解を得るために、広範なデータ収集と分析が求められます。
具体的には、利用者インタビューやアンケート、フォーカスグループなどを通じて実際の声を聞き、利用者の体験を理解することが重要です。市場のトレンドや顧客の行動パターン・ニーズ・課題を把握することで、サービスが解決すべき具�体的な課題が明確になります。
STEP3:アイディエーション
アイディエーションとは、アイデアを生み出すために、思いついた思考を具体化することです。このフェーズでは、リサーチを通じて得た洞察を基に、サービスの概念やサービスによる解決策、新しいアイデアを生み出します。具体的には、ブレインストーミング・マインドマップ・スケッチなどで参加者が自由に思考を広げ、多様な視点からアイデアを出し合うことが奨励されます。
このプロセスは制約が少なく、可能性を広げることに重点が置かれ、最終的にはサービスの革新や改善につながる実現可能なアイデアへと絞り込まれます。
STEP4:プロトタイピング
プロトタイピングは、アイディエーションで生まれたアイデアを具体的な形に落とし込むステップです。この段階では、アイデアの実用性や実現可能性を試すため、初期の概念モデルやモックアップを作成します。プロトタイプの形は、紙のスケッチからデジタルモデル、さらには機能するミニマム・プロトタイプまでさまざまです。
ここで重要なことは、速やかに構築・テストすることで、アイデアが実際に機能するか、ユーザーにとって価値があるかを確認することです。プロトタイピングを通じて、デザインチームは迅速にフィードバックを得られ、サービスの方向性を適切に調整できます。
STEP5:テストマーケティング
テストマーケティングとは、開発されたプロトタイプを実際の市場環境で試験的に展開することを意味します。このステップでは、限定された範囲内でサービスを提供し、実際の利用者の反応やフィードバックを収集します。テストマーケティングの目的は、サービスの概念が市場での実際のニーズに適合しているかを評価し、必要に応じて調整を加えることです。
テストマーケティングを通じて、利用者の期待とサービスの実際のパフォーマンスのギャップを特定することで、最終的なサービス提供前にリスクを最小限に抑えられます。
STEP6:サービスの実装
サービスの実装フェーズでは、プロトタイピングとテストを経たアイデアが具体的な形として現れます。このステップでは、選ばれたソリューションを実際の運用環境に導入し、利用者に提供する準備を整えます。実装プロセスには、必要な技術開発やUIの最終決定、サービス運用のロジスティックの設定などが含まれます。
この段階で重要となるのが、チーム間の連携とコミュニケーションの強化です。すべての関係者が目標とするサービスのビジョンと利用者のニーズを理解し、それに沿って行動することが、成功の鍵を握ります。
サービスデザインに活用できる分析手法
サービスデザインを成功に導くためには、効果的な分析手法が不可欠です。ここでは利用者のニーズや行動を深く理解するために活用できる、以下の手法を紹介します。
KA法
カスタマージャーニーマップ
ユーザーテスト
サービスブループリント
KA法
KA法は、定性的なデータを基にユーザーのニーズやインサイトを明らかにする手法です。とくに、UXデザインやUXリサーチの現場でよく利用され、ユーザーの声や行動、体験から質的データを分析・モデリングします。
KA法のポイントは、分析の過程をさかのぼれるため、モデリング時の試行錯誤がしやすく、複数人での分析時も議論を活性化させやすいことです。KAカードをもちいて、定性調査から得た気づきを出来事ごとに整理し、ユーザーの潜在ニーズを明らかにします。
カスタマージャーニーマップ
カスタマージャーニーマップは、顧客がサービスや製品と接触する一連の経験を、時系列で可視化するツールです。カスタマージャーニーマップを使うことで、顧客がサービスを利用する際にたどるステップが明確になり、各接点での顧客の思考や感情、問題点などが詳細に捉えられます。
カスタマージャーニーマップの例
カスタマージャーニーマップの作成プロセスは、ユーザーインタビューや行動データ分析などを通じて、ユーザーの行動や心理を深く理解することから始まります。そしてその情報を基に、サービス体験の各ステージにおけるキータッチポイントを識別し、顧客が経験する可能性のある障壁を特定します。
ユーザーテスト
ユーザーテストは、製品やサービスがユーザーの要求や期待にどの程度応えているかを評価するために実施されます。このテストでは、ユーザーの満足度や製品に対する感情的な反応、使用状況における製品の適合性などが重視されます。実際の利用者による直接的な体験から得られるデータを基に、サイトやアプリの使いやすさを向上させるための改善策を導き出します。
ユーザーテストは、ユーザビリティテストと混同されがちですが、ユーザビリティテストが使いやすさや効率性に焦点を当てるのに対し、ユーザーテストは製品がユーザーの期待に応えるかどうかを評価する点が異なります。
サービスブループリント
サービスブループリントは、サービスの提供に関わるプロセスや接点などを体系的に可視化する手法です。サービスブループリントを作成することで、サービス提供の背後にある複雑なプロセスを理解しやすくなり、チーム内でのコミュニケーションを促進します。
サービスブループリントの例
とくに、顧客との直接的な接点だけでなく、舞台裏でおこなわれるサポートプロセスも明確にし、サービス運用の全体像を把握できます。これにより、顧客体験の向上だけでなく、運用効率の改善や問題の早期発見にもつながります。
サービスデザインを学ぶためのオススメの本・PDF
ここでは、サービスデザインについて学べる書籍・PDFを紹介します。より知識を深めたい方は、参考にしてみてください。
サービスデザイン実践ガイドブック
『サービスデザイン実践ガイドブック』は、内閣官房情報通信技術が提供する、サービスデザイン思考に基づくサービス・業務改革を進めるための指南書です。概要解説だけでなく、ペルソナやジャーニーマップなどの手法を通じて進めるための具体的な方法まで紹介されています。行政だけでなく、民間企業でも実際の改革プロジェクトに役立てられる指南書として、サービスデザインを取り入れようとする多くのビジネスパーソンに必要なまとめです。
サービスデザインの教科書
『サービスデザインの教科書 共創するビジネスのつくりかた』は、「価値提供から価値共創へ」をキーワードとして、サービスデザインの概念を解説する入門書として紹介される一冊です。本書では、「モノのビジネスからコトのビジネスへ」という現代のビジネスシフトを踏まえ、サービスデザインの重要性とその実践方法について詳しく解説しています。サービスやデザインの新たな定義を理解し、ビジネスに取り入れたいと考える方にはオススメです。
THIS IS SERVICE DESIGN THINKING.
『THIS IS SERVICE DESIGN THINKING.』は、サービスデザイン思考を体系的に学べる入門書です。プロダクトとサービスの境界が曖昧になりつつある現代において、従来のマーケティングやビジネスモデルに対する考え方を整理するための知識が提供されています。サービスデザイン思考での基礎概念から実践に役立つ25の思考ツール、具体的な導入事例まで、豊富な図解とともに詳細に説明しています。
This is Service Design Doing
『This is Service Design Doing』は、サービスデザインを「実践」するための包括的な書籍です。ビジネスだけでなく、政策や公共サービス領域においても高まるサービスデザインの重要性を背景に、リサーチ・アイディエーション・プロトタイピング・実装だけでなく、組織への根付かせ方まで、数々の手法と事例を示しながら詳細に解説しています。UX/CXや新規事業開発に関心のあるビジネスパーソンにオススメできる一冊です。
まとめ
この記事では、サービスデザインの概要から近年サービスデザインが重要視されている背景、サービスデザインに活用できる分析手法やオススメの書籍などを紹介しました。
サービスデザインは、経済産業省も推奨する新たな時代のビジネスフレームワークとして、モノがあふれる現代の市場にとっても重要な概念です。新規事業を進める経営者の方や、UI/UXに取り組むデザイナーなどにとっても大��切な考え方ですので、新たなプロダクト開発の際などには、ぜひ参考にしていただければと思います。




















