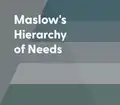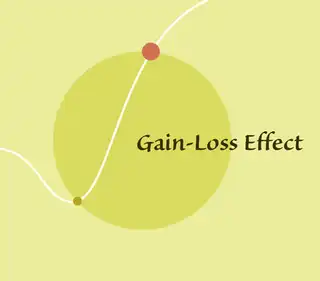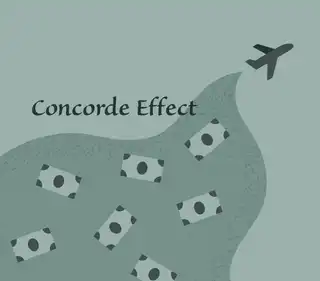スノッブ効果とは?
スノッブ効果(snob effect)とは “他の人が持っているものと同じモノは欲しくない”という心理から、大勢の人が所有するモノに対して個人の購買意欲や需要が減少してしまうという現象です。主に行動経済学やマーケティングの領域で用いられている用語です。
提唱したのは、アメリカの理論経済学者であるハーヴェイ・ライベンシュタインです。彼が1950年に発表した論文「消費者需要理論におけるバンドワゴン効果、スノッブ効果、及びヴェブレン効果(Bandwagon, Snob and Veblen Effects in the Theory of Consumers' Demand)」の中で、表題にある3つの概念を提示し、スノッブ効果はその中のひとつとして定義されました。
ここではスノッブ効果の背景にある人の購買行動に影響を与える心理や、ライベンシュタインが論文で提示した3つの概念についてあわせて紹介していきます。
私たちの購買行動は他者に影響を受けている
行動経済学では、消費者が購買行動を起こす際に�は、他者に大きな影響を受けることが指摘されています。私たちが何かモノを購入するときには、身近な他者の購買行動や口コミが影響する場合が多い傾向にあるのです。
その背景として、古来から人は基本的にひとりではなく、社会の中で助け合い、影響を与えあいながら生活していく生き物であることが要因のひとつになっているといえるでしょう。基礎心理学的な観点からみると、たとえばアメリカの心理学者アブラハム・マズローの欲求5段階説では、人間は他者と関わり、集団に帰属したいという基本的な欲求をもっているとされています。また、社会や組織の中では人は無意識か意識的なのかを問わず、周りの雰囲気に合わせることで集団の中で逸脱しないように気を配る、同調と呼ばれる心理状態が生じることもあります。
一方で、伝統的な経済学では経済を動かすのは 「欲しい」や「うらやましい」などの個人の欲求に根ざす感情であるとされており、その感情にもやはり、身近な他者の存�在が影響しているといわれています。
前述のライベンシュタインは、人は“周囲との同質化”による、仲間と同じようなものを購入したいとする欲求と、自分はその他大勢の人から乖離した特別な存在でありたいと考える、“周囲との差別化“という、相反するふたつの感情から購買行動の意思決定を下していることに着目しました。そこで“他者の購買に影響を受けて自らも購買したくなる現象”をバンドワゴン効果、反対に、“他者の購買に影響を受けて自らは購買を控えてしまう現象”をスノッブ効果と定義したのです。
ヴェブレン効果については、ライベンシュタインが19世紀から20世紀初頭期のアメリカの経済学者であり社会学者である、ソースティン・ヴェブレンの著書『有閑階級の理論』(1899年)の中で、有閑階級の人々が“自分が目立つため”だったり “人に見せびらかす顕示性が高い商品”ほど高額であっても購入するという現象を衒示的消費(げんじてきしょうひ)と論じたことに着目して命名されました。
3つの効果の心理的背景
では、3つの効果についてさらに詳しくみていきましょう。
他者との同質化願望から生じるバンドワゴン効果
バンドワゴン効果(bandwagon effect)とは、ある商品に多くの需要がある場合、人々がその商品に対して“人が持っているから自分も欲しい” などの心理が生じる現象です。バンドワゴンとはサーカスなどで用いられる華やかな四輪車のこと。バンドワゴンの後を追って大勢の人が行列をつくる背景には、他者との同質化願望がうかがえます。人の心は個人の判断より世間の流行りや周囲の評判に惑わされてしまう傾向があり、トレンドやヒット商品にはバンドワゴン効果が影響していると考えられます。
他者との差異化願望から生じるスノッブ効果
スノッブ効果(英語表記前出)が生じる背景にあるのは、人が持っていない珍しい商品や高価な商品、ユニークな商品を所有したいという心理です。そこには他者との差異化願望があり、希少性や限定性が大きな意味や価値をもちます。たとえば大量に流通する同じ絵柄のトレーディングカードよりも、簡単には入手できない数量限定のレアなカードのほうが人気が集まり需要が増すといった現象が生じます。バンドワゴン効果とは反対に、他者の消費が増えるほど需要が減少するのです。特定の分野のコレクターはスノッブ効果に悩まされる傾向があるといえます。ちなみにスノッブの語源は“俗物“です。スノッブ自体は、周囲と自分を差別化することで優越感を抱いたり、教養人を気取るような態度をとる人の俗称としての意味ももちます。
自己顕示的な感情から生じるヴェブレン効果
ヴェブレン効果(veblen effect)とは、通常の需要の法則とは反対に、商品の価格と希少価値が高いほどそれを手に入れること自体に特別な消費意識や欲求が生まれる現象で、高額商品を購入する人の心理といえます。アメリカ史において成金趣味の時代として知られる”金メッキ時代”の有閑階級たちの生活様式に特徴的だった、自分は他人からいくらに見られているかという社会的な効用をもつ“見せびらかし”の消費に由来しており、ヴェブレンは著書で “有閑階級は、自分が生きていくのに不必要な消費が可能であることを顕示するためにのみ、様々な消費を行う”と、批判的な指摘をしました。他人にどう見られるかを意識したヴェブレン志向の消費傾向を、ライベンシュタインは価格が高いほど顕示的消費が増加する現象であると注目したのです。
日本における興味深い実験
人の購買行動が何によって影響を受けるのかについての研究は日本でも蓄積されています。バンドワゴン効果とスノッブ効果は、同じ人物の中に並存しているのではないかという可能性から仮説をたて、そのメカニズムの解明を目指した実験の概要を紹介します。
東京都の10代から50代に質問表調査を行った
第1段階の質問表を用いて、被��験者にブランド品を想定したバンドワゴン志向とスノッブ志向についての設問に回答してもらう
第2・第3段階の質問表を用いて、被験者にタブレット端末を想定した設問、バンドワゴン閾値とスノッブ閾値についての設問に回答してもらう
バンドワゴン志向とスノッブ志向は、同じ人物の中に並存していることが示された
言い換えれば、人は、両方の志向がどちらも強く周囲の購買に影響されやすい者と、両方の志向がどちらも弱く周囲の購買に影響されにくい者という形で、2種類に分類できることが示唆された
(同一消費者内で発生するバンドワゴン効果とスノッブ効果より)
上記の論文では、同じ人物の中にバンドワゴン効果とスノッブ効果の両方の志向が共存していることが示された結果について、何かを購入する際に、周囲の人たちと同じような人気ブランドを求める一方で、色やデザインといったディテールにおいては周囲との重複を避けようとする、という具体例をあげて考察していました。
さらに、消費者は孤立した存在ではないという観点から、社会ネットワーク分析を用いて「消費者間ネットワークと購買行動」について調査した研究もあります。実施した実験から、ブランド品などの顕示性の強い財においては「消費者同士が実際に友人知人関係にある場合にスノッブ効果が働く」という興味深い報告がありました。
まとめ
他者の購買に影響を受けて自らは購買を控えてしまう現象、スノッブ効果を中心に、バンドワゴン効果、ヴェブレン効果についてもまとめました。スノッブ効果においては、日常生活の中で“限定版”や“特別版”、“会員限定機能”や“プレミアム会員特典”などと称した製品やサービスにその活用をみることができます。人の心はさまざまな刺激から影響を受けて反応する、一定ではない動きをもっています。実験や観察など多様な観点から実証を重ねることで、心の不思議が解き明かされていきます。
参考文献
Snob effect『Wikipedia the free encyclopedia』(最終閲覧日2023年9月30日)
ハーヴェイ・ライベンシュタイン『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(最終閲覧日2023年9月30日)
ソースティン・ヴェブレン『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(最終閲覧日2023年9月30日)
バンドワゴン効果『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(最終閲覧日2023年9月30日)
ヴェブレン財『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(最終閲覧日2023年9月30日)
真壁昭夫 (2019).『行動経済学 見るだけノート』宝島社
渋谷昌三 (2021).『決定版 面白いほどよくわかる!心理学の本』 西東社
新垣優樹・呉シンエ・柴山優奈・鈴木愛恵・服部拓真・鷲田和宣(2012). 同一消費者内で発生するバンドワゴン効果とスノッブ効果 中央大学商学部 結城祥研究会研究論文
桑島由芙(2008). 消費者間ネットワークと購買行動 ―スノッブ効果とバンドワゴン効果 ― 赤門マネジメント・レビュー, 7(4),185-204