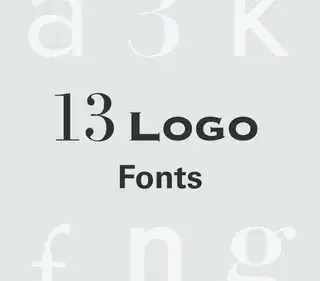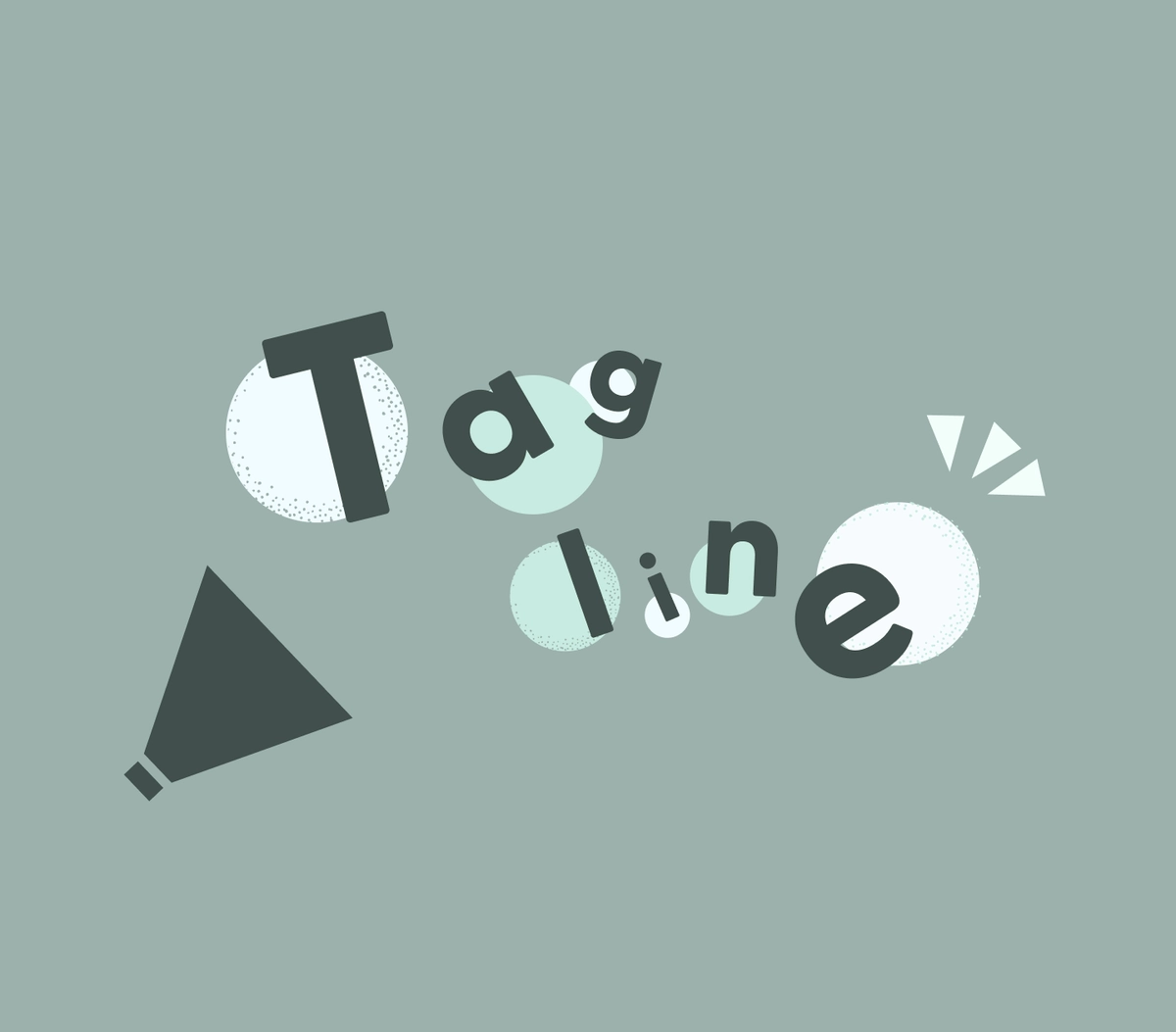
タグラインとは?ブランドや商品の第一印象にもつながる重要なメッセージ
タグラインとは、企業やサービスのアイデンティティを短く、印象的に伝えるためのブランドメッセージです。タグラインのタグは「札」で、ラインは「一筆」などを意味するため、直訳すると「識別するための一筆」となります。
タグラインは、消費者がブランドや商品を思い浮かべる際の第一印象を形成する要素となることから、マーケティングにおいて非常に重要な役割を果たします。以下のような有名なタグラインであれば、一度は見聞きしたことがありますよね。
株式会社ニトリ 「お、ねだん以上。」
ライオン株式会社「今日を愛する。」
Nike Inc. 「Just Do It.」
インパクトのあるタグラインが作成できれば、消費者から企業やサービスを想起してもらいやすくなるため、競合に負けない存在感を示せるようになります。
タグラインの必要性
タグラインは、サービスやブランドが持つ価値を短時間で伝えるために必要なワードです。とくに競争が激しい市場において、他のブランドや商品との差別化を図る上で、キャッチーなフレーズは重要です。
記憶に残るタグラインがあれば、消費者が商品やサービスを選択する際の判断材料としても機能します。そのため、ネットやSNSなど情報収集先が多様化する現代において、想起されるための有用なツールにもなります。
タグラインとセットで使われる「ステートメント」とは
ステートメントとは、タグラインを補足するために添えられる一言です。コーポレートステートメントやブランドステートメントとも呼ばれるもので、企業やブランドの核心を伝える機能を持っています。
たとえばX(旧:Twitter)のタグラインは『「いま」を見つけよう』です。そしてコーポレートサイトには以下のステートメントが添えられています。
⼈⽣で⼤事なのは、何の仕事をするかではなく、何を⽬的にするかです。真の変化は会話から始まると、私たちは信じています。だからこそ、あなたの声が重要なのです。あなたらしさを存分に発揮して、「会話と議論に開かれた場を提供する」ため、何が簡単にできるかではなく、何が正しいことなのかを私��たちとともに考え、成し遂げましょう。
https://about.twitter.com/ja
Twitter Inc.は、イーロン・マスク氏の保有するX Corp.と合併されたため、企業としての存在は消滅していますが、そのサービスの根幹はステートメントに現れていると言えます。多くの人が、今起こっていることを見つけ、議論できる場を提供したいという思いが読み取れますね。
タグラインと似た言葉
タグラインはブランディングの中心となる言葉ですが、似たような言葉として「キャッチコピー」や「スローガン」があります。これらの言葉は一見似ているように感じるかもしれませんが、実際にはそれぞれ異なる役割や特��徴を持っています。ここでは、これらの違いについて詳しく見ていきましょう。
タグラインとキャッチコピーの違い
タグラインとキャッチコピー、どちらもブランドや商品をアピールするための言葉として使用されますが、その目的や使われる場面には明確な違いがあります。
キャッチコピーは、短期的なキャンペーンや商品の特徴を伝えるためのもので、消費者の購買意欲を引き出すことが目的です。タグラインは一貫性を持ち続けることが求められるのに対し、キャッチコピーは時期や商品に応じて変わることもあります。
タグラインとスローガンの違い
スローガンも短い言葉で構成されることの多いコピーではありますが、その目的は、企業やサービスの使命を表明しているという点にあります。
タグラインが消費者に向けて、ブラ�ンドの価値をアピールしているのに対し、スローガンは企業理念やモットーなどを示します。企業としての理念はもちろん、商品やサービスが作られた目的や、それらで社会をどのように変えていきたいのかなど、提供する側の思いが込められているコピーがスローガンです。
IT・Web系企業のタグラインを一覧で紹介
IT・Web系の企業は、独自のブランドイメージを強く打ち出すためにタグラインを活用していることが多くあります。ここでは、以下のIT・Web系企業がどのようなタグラインを使用しているのか、具体的な例を通して紹介していきます。
note
STUDIO
Wantedly
LINE
SmartHR
弁護士ドットコム
FiNC
note「つくる、つながる、とどける。」
https://note.jp/
「note」は、クリエイターの表現と創作をサポートするメディアプラットフォームとして、多くのユーザーに利用されているサービスです。noteはタグラインにある通り、さまざまな形式でクリエイターがコンテンツを「つくり」、それを手軽に「とどける」ことで、多くのユーザーと「つながる」機能を搭載しています。
クリエイターを支援することを目的としているため、従来のブログ投稿サイトなどにはなかった記事の販売や、投げ銭機能でマネタイズが可能です。また、ハッシュタグの仕組みがあり、Google検索以外からのアクセスも得られる仕組みになっていることが特徴のサービスです。
STUDIO「Web制作を、ノーコードで。」
https://studio.design/ja
「STUDIO」は、誰もがアイデアや想いをWebサイトとして形にするためのノーコードWebデザインプラットフォームです。
従来のWebサイト制作には、デザインやコーディング、ドメイン取得やサーバー設定など、多くのスキルや知識が必要でした。しかし、ノーコートツールのSTUDIOを用いることで、それらの専門的なプロセスを一新し、手軽に誰でもWebサイトを制作することが可能となりました。
Webサイトを作りたいけど技術的な障壁で断念していた方に向けて、課題が解消できることがわかるシンプルなタグラインと言えます。
Wantedly「はたらくを面白く。」
https://www.wantedly.com/
このタグラインを掲げる「Wantedly」は、個人の情熱や価値観を共有する企業とのつながりを強化するプラットフォームです。
Wantedlyは、企業のミッションや価値観を前面に押し出し、求職者との真のつながりを築くことを目指しています。興味を持った企業と手軽にカジュアル面談できるようになっており、新しい形の就職活動ができると多くのユーザーに支持されています。
また、Wantedlyのステートメントには以下のように記載されています。
Wantedlyは、350万人のプロフィール・37,000社の募集と出会い、つながり、つながりを深めるシゴトのSNS。あなたの人生の3分の1以上を占める「はたらく時�間」を、Wantedlyでもっと充実したものにしてみませんか?
https://www.wantedly.com/
従来の転職サイトなどとは異なり、企業とつながる手軽さや面白さを表現するため、「シゴトのSNS」と表現していることも、サービスの特徴を表しています。
LINE「いつもあなたのそばに。」
https://line.me/ja/
「LINE」は、単なるメッセンジャーアプリを超え、新しいコミュニケーションツールの形として世間に浸透したサービスです。
LINEでは、「LINE NEWS」「LINEドクター」「LINE Pay」「LINE MUSIC」など、日常生活の中で身近に感じられるようなさまざまな機能が提供されています。これらのサービスは、人々の生活をより便利で豊かにすることを目的にしており、ユーザーの日常に近い場所に存在しています。
タグラインからも、日常的にLINEを想起してもらいたいという想いが感じ取れますね。
SmartHR「社員に、いい。」
https://smarthr.jp/
「SmartHR」はクラウド人事労務ソフトとして、人事・労務の業務効率化だけでなく、働くすべての人の生産性向上を目的に掲げているサービスです。
SmartHRの導入により、書類の回収やチェック作業の工数が大幅に削減され、データの一元管理が可能となります。また、蓄積されたデータを活用することで、効果的なマネジメントや組織のパフォーマンス向上が期待できます。
弁護士ドットコム「弁護士をもっと身近に。」
https://www.bengo4.com/
「弁護士ドットコム」は、一般ユーザーと弁護士をつなぐプラットフォームとして、多岐にわたるサービスを提供しています。
その中でも、弁護士向けの情報収集や交流の場、集客支援ツールなどが特徴的です。また、国内最大級の弁護士検索サイトを活用した依頼獲得のための集客サービスや、案件対応に必要な法律や実務ノウハウ、案件ナレッジ情報をクラウド環境で提供する「弁護士ドットコム 業務システム」、さらには弁護士向け法律書籍のサブスクリプションサービス「弁護士ドットコム LIBRARY」など、多様なニーズに応えるサービスを展開しています。
弁護士に依頼するのは抵抗があると感じられる消費者の心理に対し、相談しやすい環境を整えており、それらの内容をタグラインで簡潔にまとめています。
FiNC「カラダのすべてを、ひとつのアプリで。」
https://finc.com/
健康管理に必要なカラダの記録を一元管理できるアプリ「FiNC」は、最先端の人工知能を搭載したパーソナルトレーナーが、毎日の体重や睡眠、運動データを分析し、ユーザーの悩みに合わせた美容・健康メニューを提供します。
誰もが気になる身体・健康について、ひとつのアプリで管理できるという最大のメリットが直感的にわかるタグラインと言えます。


デジタルサービスのタグラインについての考察
近年、多くの企業やサービスが独自のタグラインを採用し、ブランディングの一環として活用しています。ここではその中でも、デジタルサービスのタグラインにある傾向から、意図や戦略について考察してみます。
短い文章で末尾に句点を打つケースが多い
デジタルサービスのタグラインにおいて、「短い文章 + 句点」という形式を採用するケースは多くあります。
たとえば上でご紹介したnoteの「つくる、つながる、とどける。」のように、多くのサービスで末尾に句点を打つスタイルが見受けられます。このような形式を選ぶ背景には、Web上の情報過多な環境でユーザーの目を引き、印象に残りやすくするという狙いが考�えられます。
ABEMAの「TV for the Future」というタグラインのように、一部例外的に句点が含まれていないものもありますが、短い文章は読み手の記憶に残りやすく、ブランドやサービスのイメージを強化する要因となります。また、一つの完結したメッセージとして伝えられ、親しみやすさを表現する効果も期待できます。
このように、タグラインの形式選びには、ユーザーへのインパクトを最大化するための戦略が反映されていると言えます。
定期的に変更される
デジタルサービスのタグラインは、時代やトレンド、ユーザーのニーズに応じて変わることがあります。長期間にわたって同じタグラインを継続して使用するケースは少なく、一定の期間ごとに変更されることが多いようです。
Webマーケティングでは、リスティング広告など定期的に測定が必要な施策が多くあります。 効果改善のためには、都度コピーも変えていくため、その中でタグラインも一緒に変更するというケースがあるのです。
オフラインビジネスでは「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のように、ロゴデザインと組み合わせてタグラインがデザインされるケースが見られますが、デジタルサービスにおいてはそのような手法は少ない傾向にあります。上記のような背景もあり、デジタルサービスでは長期間タグラインを固定することを想定せず、柔軟に変更することができる余地を残してロゴデザインには組み込まないような決定をしているのではないでしょうか?
タグラインの作り方
効果的なタグラインを作成するためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。ここでは、タグラインを作成する際のステップや考慮点を解説していきます。
企業やサービスのビジョンを明確にする
企業やサービスの強みを言語化する
顧客に想起してもらいやすい言葉を整理する
覚えやすい表現を精査する
企業やサービスのビジョンを明確にする
タグライン作成の一歩目は、企業やサービスのビジョンを明確にすることです。ビジョンとは、企業が目指す未来の姿や理念のことを指し、これがタグラインの土台となります。
明確なビジョンを持つことで、ターゲットとなる顧客に対してどのような価値を提供したいのか、どのような存在でありたいのかを伝えられます。また、ビジョンを元にしたタグラインは、社内のメンバーに対しても方向性を示す指標になります。
企業やサービスの強みを言語化する
企業やサービスの強みを明確に言語化することも重要です。強みは競合他社との差別化要因となり、顧客に選ばれる理由となります。
たとえば、迅速な配送を売りにする物流企業、高品質な素材にこだわるアパレルブランドなど、業種や業界独自の強みを言語化できると効果的です。この強みを言葉にすることで、タグラインの魅力や説得力が上がります。
顧客に想起してもらいやすい言葉を整理する
タグライン作成の際の重要なポイントとして、顧客に想起してもらいやすい言葉を整理することも挙げられます。
タグラインは、短い言葉の中��に企業やサービスのエッセンスを凝縮するものです。日常生活でよく使われるフレーズや、業界特有のキーワードなど、ターゲットとなる顧客が馴染み深い言葉を取り入れることで、タグラインの認知度を高められます。たとえば、上述した弁護士ドットコムの「弁護士をもっと身近に。」では、「身近に」という言葉で弁護士と手軽につながるためのサービスとして、想起を得られています。
言葉の選び方一つでブランドのイメージが変わるため、顧客の心に響く言葉を選ぶことで、ブランドの価値を高める効果も期待できます。
覚えやすい表現を精査する
タグラインは、短い言葉の中に企業やサービスの魅力を詰め込むため、覚えやすい表現を選ぶことも重要です。
覚えやすさは、リピート利用や口コミ拡散のキーとなる要素です。そのため、直感的にわかりやすく、シンプルでありながらもインパクトのある言葉を選ぶ必要があります。たとえばFiNCのタグラインである「カラダのすべてを、ひとつのアプリで。」では、身体に関することをFiNCひとつで管理できることが直感的に理解できる表現になっていますよね。
また、類似のサービスや商品と差別化を図るためにも、独自性のある表現を追求することが求められます。タグライン作成時には、多くの候補をリストアップし、その中から最も魅力的で覚えやすいものを選ぶ作業を繰り返すことで、最適な表現を見つけ出せます。
まとめ
この記事では、デジタルサービスのタグラインの特徴やその作り方について解説しました。基礎的な知識やトレンドを押さえることで、新たなタグラインを考案する際の参考として、具体的なアクションを起こすためのヒントや方針を得られます。
タグラインは企業やサービスの顔とも言えるものです。多くの思いや戦略が込められていることを再認識し、効果的なブランディングの一環として活用していきましょう。