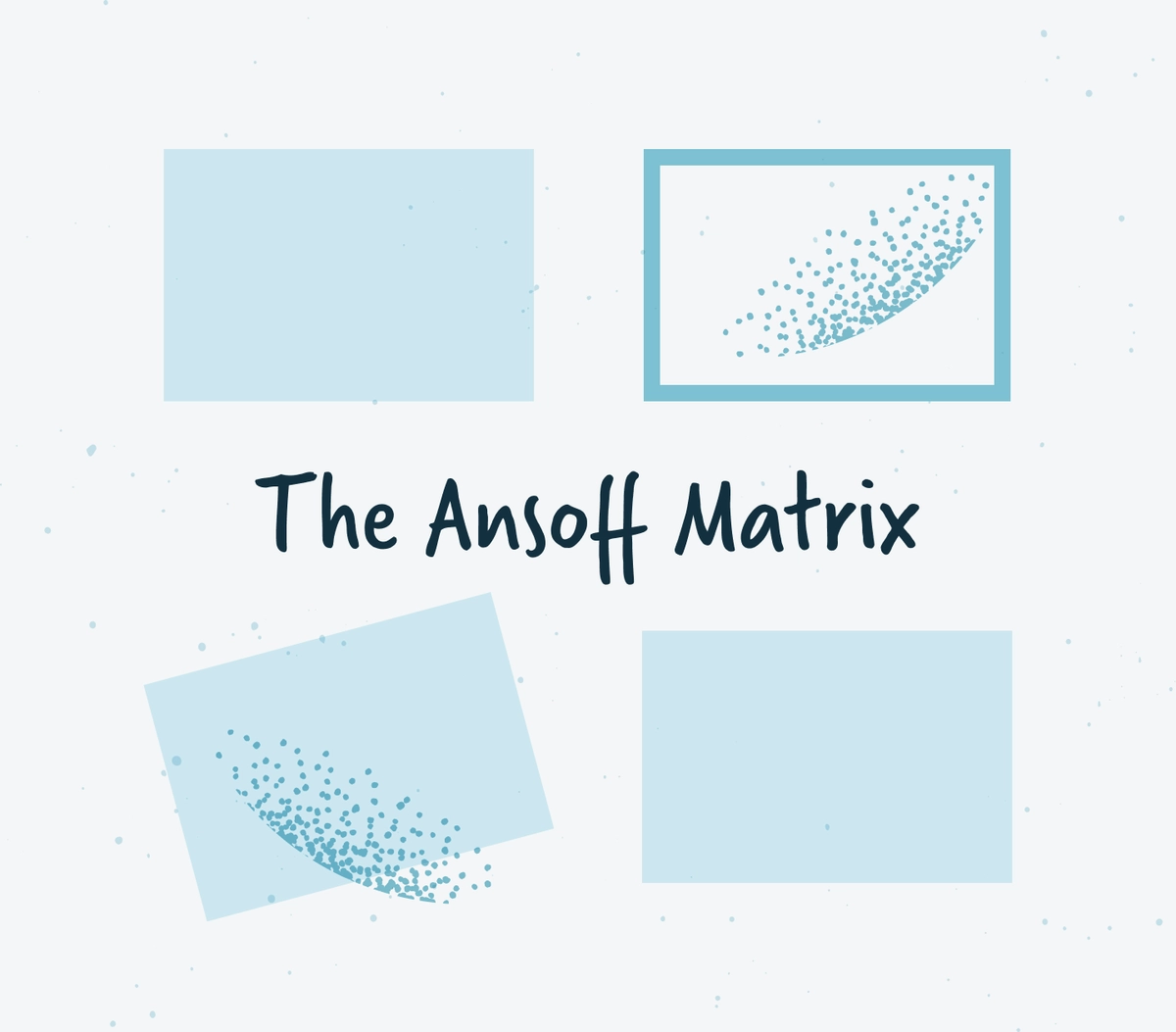
アンゾフの成長マトリクスとは?
アンゾフの成長マトリクスは、戦略的経営の父と呼ばれた経営学者イゴール・アンゾフが唱えたフレームワークで、ビジネスの成長戦略を考える際の有効なフレームワークとして知られています。
アンゾフの成長マトリクスでは、成長戦略を「製品」と「市場」の2軸で考え、それぞれを「既存」と「新規」に分けて考察しています。具体的には、既存の製品を既存の市場で展開する「市場浸透戦略」、新しい製品を既存の市場で展開する「製品開発戦略」、既存の製品を新しい市場で展開する「市場開拓戦略」、新しい製品を新しい市場で展開する「多角化戦略」の4つです。
1965年に提唱されたフレームワークですが、競争が激しい現代のビジネスでも活用できるものとなっています。それぞれの組み合わせによるシナジーを理解し、適切に活用することで、企業は成長の方向性を明確にし、より効果的な戦略を策定できるようになるのです。
アンゾフの成長マトリクス4つの戦略
アンゾフの成長マトリクスは、企業が取るべき成長戦略を明確にするためのフレームワークとして、「製品」と「市場」の2つの要素を基に、4つの異なる戦略を提案しています。
市場浸透戦略
市場開拓戦略
製品開発戦略
多角化戦略
上記4つの戦略を適切に選択できれば、企業は市場での競争力が高まり、思い描く理想の成長に近づきます。それぞれの概要について解説します。
市場浸透戦略(既存市場 × 既存製品)
「市場浸透戦略」とは、企業がすでに提供している製品やサービスを、現在の市場でさらに深く展開するための戦略です。具体的には、既存の顧客に対して製品の購入頻度を増やす、新たな顧客層を獲得する、または競合他社の顧客を取り込むといったアプローチを考えます。
この戦略のメリットは、新しい製品の開発や新市場への進出といったリスクを伴わないという点です。既存の顧客基盤やブランド力を最大限に活用し、効果的なマーケティングやプロモーションを行うことで、市場シェアの拡大や売上の増加を目指せます。
市場開拓戦略(新規市場 × 既存製品)
「市場開拓戦略」とは、企業が現在提供して�いる製品やサービスを、まだ進出していない新しい市場や顧客層に展開するための戦略です。具体的には、地域的な拡大や異なるターゲット層へのアプローチなどが考えられます。
たとえば、国内でのビジネスが安定してきた企業が、海外市場への進出を検討する場面でこの戦略が取り入れられることが多いです。また、異なる年齢層やライフスタイルを持つ顧客層への展開もこの戦略の一部となります。市場開拓戦略を成功させるためには、新しい市場のニーズや文化を深く理解し、適切なマーケティング戦略を策定することが不可欠です。
製品開発戦略(既存市場 × 新規製品)
「製品開発戦略」とは、企業が現在展開している市場に、新しい製品やサービスを導入するための戦略です。この戦略の背景には、顧客のニーズの変化や技術の進化、競�合との差別化を図るための取り組みなどがあります。
スマートフォンの進化にともない、新しいアプリケーションや機能を開発して市場に投入する戦略や、環境問題への対応としてエコフレンドリーな新製品を開発する戦略などが該当します。製品開発戦略を採用する際には、市場のトレンドや顧客の声をしっかりとキャッチし、継続的な研究開発活動を行うことが大切です。
多角化戦略(新規市場 × 新規製品)
「多角化戦略」とは、企業がまったく新しい市場に、新しい製品やサービスを導入する戦略です。この戦略は、企業のリスクを分散させるためや、新しい収益源を確保するために採用されることが多いです。
たとえば、自動車メーカーがエネルギー事業やIT事業に進出する場合などが��考えられます。多角化戦略を成功させるためには、新しい市場や製品に関する深い知識や経験が必要です。また、企業の経営資源や技術を最大限に活用し、新市場での競争力を確立することが求められます。逆に資金力がないスタートアップの企業であっても、新しい製品を開発してビジネスを始める場合、多角化戦略で臨むケースも多いです。
この戦略は高いリスクをともないますが、成功すれば大きなリターンを得られるというメリットがあります。
「多角化戦略」はさらに細分化できる
競争の激しい現代のビジネスにおいて、既存の製品や既存の市場だけを主戦場としていても、売上が保証され続けることはありません。そのため、新たな製品開発や新たな市場へのチャレンジが求められるケースは多いです。
水平型多角化
垂直型多角化
集中型多角化
集成型多角化
新規市場×新規製品の「多角化戦略」には、さまざまなアプローチや方向性が存在しますが、具体的には上記の4パターンにわけられます。企業が取るべき方向や、どのような市場・製品に進出するかによって戦略は細分化されるのです。
それぞれの戦略には、特有の特徴や目的、そして取り組むべきポイントがあります。このセクションでは、それぞれの細分化された戦略の特色や適用シーンについて詳しく解説していきます。
水平型多角化
水平型多角化は、企業が現在の主力市場と同じ、または類似した市場に新しい製品やサービスを導入する戦略です。このアプローチの魅力は、既存の顧客基盤やブランド力を活用して、新しい製品やサービスを効果的に市場に展開できる点にあります。
たとえば、アパレルブランドが服だけでなくアクセサリーや化粧品を展開する場合などが考えられます。水平型多角化を成功させるためには、市場のニーズやトレンドを把握し、既存のリソースやノウハウを最大限に活用することが重要です。また、新しい製品の開発やマーケティング戦略の策定にも注力する必要があります。
垂直型多角化
垂直型多角化は、企業が既存製品と関連性の低い製品を開発し、既存の市場に投入していく戦略です。
垂直型多角化戦略では、既存顧客や既存の取引先へのアプローチがしやすい点がメリットとなります。
例として、輸入豆でコーヒーショップを展開している企業が、自社でコーヒー豆の農園栽培までおこない、農園で栽培した食物の販売業に着手するようなケースが挙げられます。水平型多角化戦略と比べ、元々持っているノウハウが少ない分、リスクは高いです。そのため、垂直型多角化を採用する際は、新たに着手する開発領域で成功している事業者からノウハウを集積することや、既存事業の売上を落とさないような経営リソースの配分が求められます。
集中型多角化
集中型多角化とは、企業が自身の核となる事業や技術をもとに、新しい市場へ進出する戦略です。この戦略の魅力は、企業が持つ独自の技術やノウハウを活かしながら、新しいビジネスチャンスを探求できる点にあります。
たとえば、革製品を使った高級財布やカバンの製造販売を営む企業が、小学生向けのランドセルを製造販売するようなケースが該当します。集中型多角化を成功させるためには、自社の強みや技術の特性を深く理解し、それを最大限に活用する方向性を持つことが重要です。また、新しい市場への適応力や、変化に柔軟に対応する経営体制の構築も求められます。
集成型多角化(コングロマリット型)
集成型多角化(コングロマリット型とも呼ばれる)とは、従来��の製品や参入していた市場とは異なる領域へ参入する戦略です。この戦略の背景には、リスクの分散や安定した収益の確保、さらには新しいビジネスチャンスの探求といった目的があります。
たとえば、電機メーカーが食品事業や不動産事業に進出するケースなどが考えられます。多様な事業を適切に管理し、効果的に統合することは容易ではありません。多角化戦略の中でもっとも既存事業とのシナジーが薄い戦略となるため、リスクは高いと言えます。そのため、経営資源の適切な配分や、各事業間の連携を強化する取り組みが不可欠となります。


アンゾフの成長マトリクスを活用した事例
富士フイルム株式会社
https://www.fujifilm.com/jp/ja
富士フイルムは、写真フィルムという主力商品の需要が減少する中、新しいビジネスモデルへの転換を迫られていた中で、アンゾフのマトリクスを活用した多角的成長戦略を策定しました。
既存市場x既存製品の「市場浸透戦略」では、インスタントカメラ「チェキ」の成功がありました。チェキはデジタルカメラの販売台数を逆転し、年間500万台の売上を記録したことで、カメラメーカーとしての市場浸透を成功させています。
また、新規市場×既存製品の「市場開拓戦略」では、レーザー内視鏡や医療用画像情報ネットワークシステムなどの技術を医療業界の市場へ提供したことで、競合に負けないポジショニングを築きました。
さらに、フィルム製造技術や光学レンズ技術を基に、液晶用フィルムや携帯電話用プラスチックレンズの提供を開始するなど、富士フイルムは技術と市場の双方を最大限に活用できる戦略を展開しています。
イケア・ジャパン株式会社
https://www.ikea.com/jp/ja/
IKEAは、北欧スウェーデンを起源とする世界最大の家具メーカーで、独特の家具デザインと手頃な価格で知られています。
日本に本社を置くイケア・ジャパン株式会社では『新市場開拓戦略』を採用し、スウェーデンと文化的に近いヨーロッパ市場への進出を皮切りに、アジア市場へと拡大してきました。日本においても、当初は知名度が低い状態でしたが、新聞や雑誌などのPR活動を通じて、店舗オープン日には約3.5万人という来店客の獲得に成功しました。
IKEAの成功は、顧客のニーズを的確に捉え、独自の価値提案��を持ち続けることに起因しています。自社のブランディングをぶらさずに、各国に商品力で勝負し続けた結果、家具業界におけるリーダー的存在としての地位を築いています。
株式会社セブン&アイ・ホールディングス
https://www.7andi.com/
セブン&アイ・ホールディングスは、国内外の多岐にわたるビジネスを展開する大手総合小売業者で、国内最大手のコンビニチェーンであるセブンイレブンを展開しています。
小売事業として確固たる地位を築いていましたが、多角化戦略の一環として、セブン銀行というサービスで銀行業界へ参入しています。セブン銀行は、セブンイレブンを利用する顧客へのサービスを深化させる手段として、商品の販売だけでなく、ATMを提供することでより買い物しやすい店舗環境を提供しました。
小売事業と金融業(銀行サービス)は一見別物のようですが、事業のシナジーをうまく活用した戦略と言えます。
アンゾフの成長マトリクスを取り入れる際のポイント
アンゾフの成長マトリクスを効果的に活用するためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
市場の変化を意識する
ターゲットを明確に設定する
費用対効果を意識する
ここでは上記3点について解説します。
市場の変化を意識する
ビジネスにおいて、常に変動している市場の変化を正確に捉えることが事業を成功させる鍵です。とくに現代のビジネス環境では、テクノロジーの進化や消費者の価値観の変化が急速に進行しています。企業が成長戦略を考える際、過去のデータや経験だけに頼るのではなく、現在の市場の動向をしっかりと分析し、未来のトレンドを予測する能力が求められます。また、競合他社の動きや新たな技術導入や新サービスの売れ行きなどをチェックすることも重要です。
アンゾフの成長マトリクスは、上記のような市場分析ができているうえで成り立つフレームワークであると理解しておきましょう。
ターゲットを明確に設定する
事業の成功のためには、ターゲットとなる顧客層を明確に特定し、そのニーズや期待に応える製品やサービスを提供することが不可欠です。ターゲットを明確に設定することで、マーケティング活動や製品開発の方向性が鮮明になり、リソースの無駄を抑えられます。また、明確なターゲット設定は、顧客とのコミュニケーションを深化させ、ブランドの魅力を高める助けとなります。とくに新市場への参入や新製品の開発時には、ターゲットの特性やニーズを詳細に分析し、それに基づいた戦略を策定することが必要です。
ターゲット設定をする際には、マトリクスに照らし合わせ、具体的かつ実現可能な目標を立てることが求められます。
費用対効果を意識する
ビジネスでは投資によって得られるリターンを常に考慮することも必要です。費用対効果を意識することで、企業は最適なリソース配分が可能となり、効率的な事業展開が実現します。アンゾフの成長マトリクスを利用して新市場や新製品の開発を検討する際、期待される収益とそれにかかるコストを比較し、もっとも効果的な戦略を選択することが重要です。
とくに多角化戦略などの挑戦的な戦略に取り組む場合は、企業の目的やビジョンに合わせて、適切な投資判断を行い、長期的な視点での成功を追求することが求められます。
アンゾフの成長マトリクスと組み合わせて使えるフレームワーク
アンゾフの成長マトリクスは、企業の成長戦略を考える際の基盤として非常に有効ですが、アンゾフの成長マトリクスだけでは十分な戦略を練れない場合もあります。そこでオススメなのが、他のフレームワークと組み合わせる方法です。
ファイブフォース分析
SWOT分析
バリューチェーン分析
ここでは上記3つのフレームワークを紹介します。いずれもアンゾフのマトリクスとの相性が良く、組み合わせるこ��とでより詳細かつ具体的な戦略策定が可能となります。
ファイブフォース分析
ファイブフォース分析は、マイケル・ポーターによって提唱された業界分析のフレームワークです。この分析手法は、業界の競争構造を5つの要因で評価し、企業が直面する競争の強度や業界の魅力を把握するのに役立ちます。
競合他社の脅威
新規参入の脅威
買い手��の交渉力
売り手の交渉力
代替品の脅威
具体的には上記5つの項目を分析します。これらの要因を詳細に検討することで、自社の位置や戦略の方向性を明確にします。アンゾフの成長マトリクスと組み合わせることで、市場の動向や競争環境をより深く理解し、適切な成長戦略を策定できるようになります。
SWOT分析
SWOT分析は、企業やプロジェクトの新たなチャンスを見つけるために用いられるフレームワークです。
強み(Strengths)
弱み(Weaknesses)
機会(Opportunities)
脅威(Threats)
上記4つの要素を評価する手法で、それぞれの頭文字をとってSWOT分析と呼ばれています。
それぞれのプラス要因とマイナス要因を組み合わせることで、組織の内部環境と外部環境を総合的に把握し、戦略の方向性を明確にできます。明確にした戦略をもとに、アンゾフの成長マトリクスと組み合わせることで、成功確率の高い市場を発見できる可能性が高まります。
バリューチェーン分析
バリューチェーン分析は、企業の活動を一連のプロセスや活動に分解し、それぞれの付加価値がどのように連鎖するか評価できるフレームワークです。
バリューチェーン分析を大別すると、「主活動」と「支援活動」のふたつに分けられます。主活動とは、原料の調達や製品製造・販売、アフターサービスに至るまでの一連の流れで、支援活動は主活動を進めるために必要な人事や労務管理などの業務です。それぞれの段階でのコストや付加価値を詳細に分析することで、企業が提供する製品やサービスの価値を最大化するためのキープロセスを特定できます。
アンゾフの成長マトリクスと組み合わせることで、市場展開や製品開発の方向性をより具体的に策定する�際の参考として活用することが期待されます。
まとめ
本記事では、アンゾフの成長マトリクスとその活用事例、さらに関連するフレームワークについて詳しく解説しました。
アンゾフの成長マトリクスは、経営者やマーケティング担当者、新規事業を検討している方々にとって、市場や製品の展開戦略を考える際の有力な手法として役立つフレームワークとなります。
本記事で紹介した情報をもとに、自社のビジネス戦略の策定や見直しを行う際の参考にしていただければと思います。また、新たな市場や製品の可能性を探る際のステップとしても役立ていただけると幸いです。











