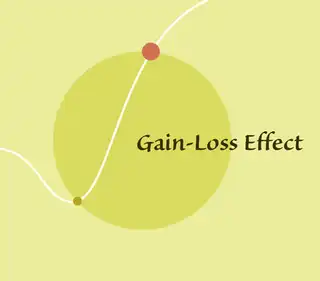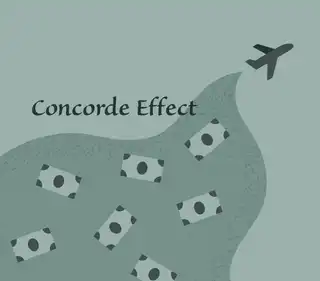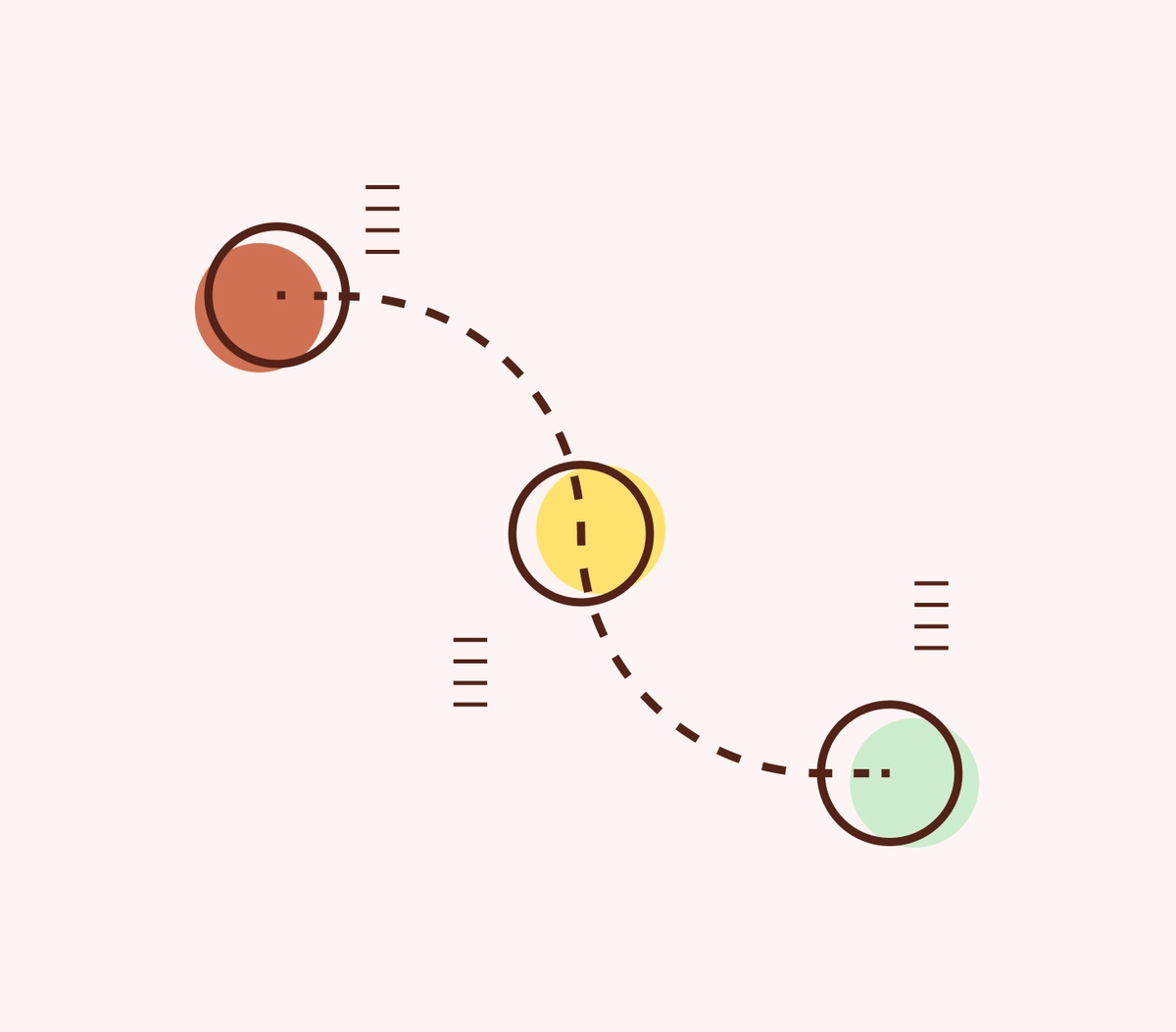
アンダーマイニング効果とは?
アンダーマイニング効果とは、やりがいや楽しさといった内発的な動機づけが、報酬などの外発的な動機づけを与えられることによって、逆に低下してし��まうという現象をさします。UXデザインのプロセスにおいて、ユーザーの価値観や本音を把握するための「ユーザーインタビュー」を効果的に行いたいときに大きく影響しそうな心理です。教育心理学や認知心理学を専門とする、村山 航教授(イギリス・レディング大学)の論文「労働の動機づけにおける金銭的報酬と非金銭的報酬の役割」による定義は以下のとおりです。
アンダーマイニング効果の生物学的根拠
たとえば、それまで自発的に行っていたボランティア活動が、途中から成果報酬(金銭的報酬)が発生する有償の活動に変化してしまったとき。心理学の研究では、当初は自分が誰かの役に立てるという純粋な喜びから 「楽しさ」や「やりがい」(内的報酬)を得ていた行動が、知らず知らずのうちに金銭的報酬(外的報酬)目的の行動にすり替わってしまうことが指摘されています。労働には適切な報酬が必要です。しかし成果報酬が強調された場合は、報酬が思うように得られなくなってしまったときに、モチベーションやその行動に対する関心や意欲が、下がったり薄れてしまう場合があることがわかっています。
「動機づけ」は人の行動を喚起するための大切な要因であり、モチベーションの大きな源です。人はモチベーションによって心に変化が生じて、それが行動にも移されます。 「報酬にまつわる逆効果な動機づけ」をはらんでいるのが、アンダーマイニング効果の注意したいところです。このアンダーマイニング効果は、脳の反応からも実証されています。前述の村山教授の論文から、被験者の脳画像を用いた興味深い実験をご紹介しましょう。
ストップウォッチ課題
実験の目的
アンダーマイニング効果と脳の働きを調べる
方法
実験参加者を、課題に対する金銭的報酬を約束された報酬群と、報酬の約束をしない統制群(非報酬群)にランダムに分ける
報酬群の最初のセッションは、報酬を約束された中で行った
報酬群の2回目のセッションは、報酬が約束されない中で行った
セッションとセッションの間には、休憩時間が設けられた
休憩時間中、自主的に課題に取り組んだ人数は統制群のほうが多かった
実験は機能的磁気共鳴画像法(functional magnetic resonance imaging. fMRI)を用いて、参加者はfMRIスキャナの中で課題を実施した
2つのグループの脳の画像について、比較分析を行った
結果
課題に対する金銭的報酬を約束された��報酬群の2回めのセッションは、約束されなかった非報酬群よりも、内発的動機が低下していることがわかった
(Murayama et al. (2010). 「アンダーマイニング効果の神経基盤を調べるための実験」より)
実験参加者たちには、ストップウォッチを時間通りに止めるという課題が与えられました。パフォーマンスに応じた金銭的報酬を約束された「報酬群」と、非報酬である「統制群」の2グループに分かれて、それぞれ2回のセッションを実施しました。2回目は「報酬群」にも報酬が約束されないことが伝えられました。「報酬群」と「統制群」の「休憩時間中の行動」も調査しました。さて、結果はどうなったのでしょうか? 上記のように、報酬群の内発的動機は低下したことが示されました。注目したいのは、報酬を約束されない統制群(非報酬群)のほうが、休憩時間中も自主的に課題に取り組んだ人数が有意に多かったという報告です。人の意欲や好奇心は、報酬よりも大きくモチベーションに影響するのです。
また、報酬群のモチベーションの減少は、脳の活動からも明らかであることがわかりました。fMRIスキャナで撮影された被験者たちの脳の画像を、脳の動機づけや報酬を司る部位である線条体に注目して画像分析を行ったその結果、「報酬群」の2回目の画像は、報酬が約束されていた1回目の画像と比べて、線条体の活動が活性化されなかったことが示されたのです。つまり、動機づけを司る脳の反応が維持されなかったということです。対照的に、非報酬の統制群の画像では、線条体の活力が維持されていました。アンダーマイニング効果が生じる条件が脳の働きからも確認された、意味深い実験結果といえるでしょう。
アンダーマイニング効果を意識したユーザーインタビューの被験者リクルーティング
このように、アンダーマイニング効果は報酬に対する人の心理を左右する重要な要素です。UXデザインにおいて、このアンダーマイニング効果を意識すると、以下のような点でメリットがあります。
主体的なインタビュー協力者の掘り起こし
協力者の良質なモチベーションの維持
サービスへの関心の高い層へのリーチ
定量調査と比較した際のユーザーインタビュー��の利点は、ユーザー行動の背景や心理に迫ることができるという点です。つまり、ユーザーが「なぜそのサービスを使うのか?」または「どのような点に魅力を感じているのか?」といったインサイトを得られることがユーザーインタビューの強みとなります。この利点を最大限に活かすためには、サービスへの関心が高いユーザーにインタビューすることが求められます。なぜなら、あまりサービスに関心をもっていない被験者からは表面的な反応しか得られないからです。みなさんも、自分が興味・関心をもっていないトピックに関して、「どう思う?」と聞かれても深い話はできないですよね?
では、サービスに関する有益なフィードバックが得られそうな「主体的な調査協力者」を集めるためには、どのような点に気をつける必要があるのでしょうか?主体的な調査協力者とは、ふだんからサービスをよく使っていて、改善のために協力したい」といった考えをもつユーザーのことです。このようなユーザーは報酬を設定しなくてもインタビューに協力してくれる可能性が高いです。そして、このような内的モチベーションをもったユーザーを集めるためには、報酬を設けないほうが効果的な場合があります。なぜなら、金銭的な報酬を設定することにより、ユーザーの調査協力に対する自発的な動機や関心が低下してしまうという、アンダーマイニング効果が起こる可能性があるからです。「せっかくサービス改善のために協力しようと思ったのに、お金で釣られている感じがして嫌だな」と、意欲が下がってしまう�のです。つまり、アンダーマイニング効果が発現する可能性がある場合は、あえて報酬を設定しないという選択ができるようになります。
また、「お礼にAmazonギフト券を差し上げます」と一律で提示をしてしまうと、その調査は潜在的に「Amazonギフト券」目的であるユーザーを集めてしまうことになってしまい、サービスの改善点に関する本質的なインサイトが得られにくくなってしまいます。この点は、調査会社のパネルから被験者を集める際のデメリットともなっています。報酬を提示しないことは、インタビューに対する能動的なマインドや「良質なモチベーションを維持すること」にもつながります。設問数やインタビュー時間が多かったり、長かったりする場合にも、こちらの深掘りに根気よく協力的なスタンスでつきあってくれるかもしれません。これから始まるサービスやプロジェクトに協力したいという「関心の高い層」が集まることで、より有効な調査結果をつくり上げる可能性も見込めます。
ただし、このアンダーマイニング効果は金銭的報酬自体が引き起こしているのではないことが、前述の村山教授の論文でも示されています。「自分は報酬のためだけに課題を行っている」「報酬に統制されている」といった知覚がアンダーマイニング効果のメカニズムであることが指摘されています。
調査によっては、「主体的な調査協力者」が明確に定義できず、インタビューを報酬なしで実施することが難しいと予測さ��れる場合もあるでしょう。その際には、金額は伏せた上で「謝礼あり」と記載するなどの工夫で、成功報酬の側面を強調しすぎないように募集するとよいかもしれません。
まとめ
UXデザインのプロセスにおけるユーザーインタビューにおいて大切な視点である、アンダーマイニング効果。アンダーマイニング効果を意識することは、主体的で熱心なインタビュー協力者を集めたいときに有効な知識でもあります。今回紹介したような観点を用いて、まずは今取り組んでいるユーザー調査がどのような条件で設計されているか、チェックしてみてはいかがでしょうか。
参考文献
村山 航 (2020). 労働の動機づけにおける金銭的報酬と非金銭的報酬の役割 日本労働研究雑誌, 719, 46-55.
渋谷昌三 (2010). 『面白いほどよくわかる!心理学の本』西東社