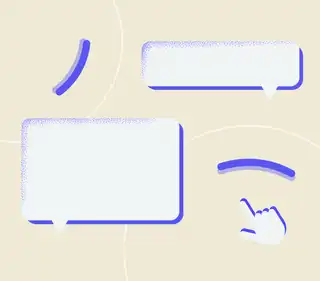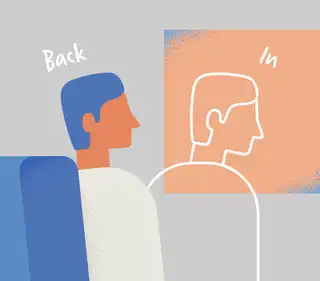ユーザビリティとは?「ユーザビリティ = 使いやすさ」ではない?
ユーザビリティ(Usability)とは、英語で「使いさすさ」を意味する言葉です。IT業界でも、一般的に「使いやすさ」や「操作性」という意味合いで使われることが多いですね。バグや設計ミスがなく「使うことが可能」なものを作る必要があることは誰にとっても明確だと思います。しかし、「使いやすさ」に関してはユーザーの経験や年代、目的によっても大きく判断が異なり、客観的な判断が難しいのではないでしょうか?
実は、UXデザインの世界ではユーザビリティは単なる「使いやすさ」を意味する言葉ではありません。UXデザインの文脈で一般的に受け入れられている定義は、ISO(国際標準化機構)の国際規格であるISO 9241-11に基づくものであり、
ユーザビリティとは��、製品やサービスの対象となる利用者が特定の目的を達成する際の有効さ、効率、満足度の度合いである。
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-2:v1:en
と定義されています。
ここで重要な点は、UXデザインにとってのユーザビリティとは「誰にとっても操作性が良いもの」ではないということです。UXデザインの文脈からユーザビリティについて考える際には「誰のためのデザインか」と「ユーザーに何をさせたいか」の2つを明確する必要があります。例えば最近よく耳にする、「シンプルで使いやすいUI」について考えてみましょう。これは、対象のユーザーが特定の目的を達成するまでのステップが簡素であり、余分な動線や機能を削ぎ落とした状態であると言えます。逆に、「シンプルな見た目であれば操作性がよくなる」という意味ではない点で注意が必要です。
ユーザビリティには必ず「ゴール」が存在する
つまり、UXデザインに取り組む上ではそのプロジェクトのビジネス的なゴールを明確に意識することがとても大切となります。「ユーザーに何をさせたいか」をいくつかのゴールとして設定し、ユーザーが特別な助けを必要とせずにそれらのゴールを達成できる状態が「ユーザビリティが良い状態」となります。
特定のタスクに関するUXを改善したい場合は、そのタスク達成をゴールとして設定することができます。また、サービス全体のユーザビリティを評価する場合は、そのサービスのコンバージョンイベントやKPIに関するユーザーアクションをゴールとして設定することが多いです。
ユーザビリティの良いデザ��インを作るには?ユーザビリティを向上させるための5つのチェック項目
では、ユーザビリティの良いデザインを作るにはどのような点に気をつけると良いのでしょうか?
UXデザイン分野の代表的なコンサルティング会社であるニールセン・ノーマン・グループ(Nielsen Norman Group)では、ユーザビリティの良いデザインの構成要素を以下のように定義しています。
学習しやすさ = 初めて使う際にも問題なく目的を達成できるか?
効率の良さ = 操作を覚えた後、効率的に再度同じ操作を行えるか?
記憶しやすさ = しばらく使わなくても、操作方法を思い出せるか?
エラー頻度の低さ = 目的達成までにエラーが頻繁に起こらないか?
満足度 = 目的達成までのプロセスはユーザーにとって満足度の高いものか?
出典: https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/
ユーザビリティの良いデザインを作るためには、これらを念頭に置いた上でデザインを作成し、実際にそれぞれの項目に沿っているかをチェックリスト形式で評価すると良いです。また、それぞれの項目は目的達成までのプロセス全体に関わるものとなるため、平面的なデザイン上での確認だけではなく操作可能なモックアップなどでの検証を行うと良いでしょう。


1. 学習しやすさ
学習しやすさとは、ユーザーが初めてそのデザインを見たときに「使い方を理解できるか」という観点です。これは、一般的にユーザーの過去の記憶や体験から使い方を連想できるようなデザインを提供することで解決できます。例えば、iOSアプリにおいて戻るボタンが常に左上に表示されているのは、様々なアプリでのそ��れまでの体験から「左上にある矢印は戻るボタンである」というメンタルモデルが形成されているからです。これを左下などにおいてしまうと、ユーザーそれまでに経験したことのない操作となり、初見のユーザーは使い方に戸惑ってしまうでしょう。また、どうしても他のアプリと異なる操作感にしたい場合など、ユーザーが見たことのないUIを提供する場合には、ユーザーに使い方のヒントを与えることでこの「学習しやすさ」を向上することができます。簡単なものだとコーチマークを用いた使い方の説明や、高度なものだとアニメーションを使って操作方法を示唆するなどの手法があります。
2. 効率の良さ
効率の良さとは、ユーザーが一度操作方法を覚えたら、迷うことなく効率的に再度同じ操作を行えるかという観点です。これには、それぞれの操作UIのデザインだけではなく、流れとしてのユーザーフローが最適化されていることが重要となります。効率よく操作が行えるユーザーフローを作るためには、
無駄な操作がなく必要なステップが最低限であること
使い方によって操作フローが変わらないこと
の2点が重要なポイントとなります。
一つ目の「無駄な操作がなく必要なステップが最低限であること」については、実際は一回の操作で完結できるものを、複数の操作を行わせることで複雑化してしまっていないかといった点に注意すると良いでしょう。二つ目の「使い方によって操作フローが変わらないこと」に関しては、ユーザーの操作によって操作フローの分岐が起こらないような設計にすることがポイントです。
3. 記憶しやすさ
記憶しやすさとは、ユーザーがそのサービスを一度使った後、しばらく使わなくても操作方法を思い出せるかという観点です。「しばらく使わなくても」というのは、必ずしも長期間である必要はありません。3日 ~ 4日程度、日が開くだけでもユーザーは操作方法を忘れてしまうものです。ここで重要になるのが、初めて使った時と、二回目以降使ったときで操作方法が同じであるという点です。これには、前述の「使い方によって操作フローが変わらないこと」という点が同じくポイントとなります。何回、どのように使っても使い方が変わらないUIというのが記憶しやすいUIとなります。
また、よくあるモバイルアプリのオンボーディングで、初回のみ特別なフローでユーザーが簡易的にタスクを完了できるようにするというものがあります。確かに、初回でタスクを達成させることは、その後のユーザー継続率に大きく影響するため有効なデザイン施策です。しかし、この初回のみの特別フローをあまりにも通常のユーザーフローと異なるものにしてしまうと、1回目のアプリ操作でユーザーが操作方法を学習することができず、2回目以降のユーザビリティの低下を招いてしまうことがあります。オンボーディングでタスクの簡略化を行う場合は、通常フローと大きく異なるデザインとならないように��注意する必要があります。
4. エラー頻度の低さ
エラー頻度の低さとは、目的達成までにエラーが頻繁に起こらないかという観点です。エラーというと、システムのバグのようなものを思い浮かべるかもしれません。もちろん、バグのないシステムというのはユーザビリティにとって重要なポイントです。しかし、バグ以外にもユーザーがエラーとして認識するものがあります。例えば、入力フォームのバリデーションなどです。電話番号を入力するときに、入力して送信した後に「ハイフンなしで入力してください。」というエラーが表示されるのを見たことがある人は多いと思います。これは、システムのエラーではないものの、ユーザーの操作に対して不正な情報としてエラーを返しているパターンですね。ユーザビリティの向上のためには、サービス内でこのようにユーザーにエラーを表示する可能性のあるポイントを洗い出し、何かし�らの方法でこれを回避できないかを模索することが必要です。先ほどの電話番号のバリデーションの例では、ユーザーがハイフン入りで入力したとしても、システム側で自動的にハイフンを追加して登録してしまえば、エラー頻度を下げることができますね。
5. 満足度
満足度とは、目的達成までのプロセスはユーザーにとって満足度の高いものかという観点です。満足度はユーザーの主観的な感覚であるため、ユーザーヒアリングなどを通して実際のユーザーの声を集めると改善の手がかりが見つかるかもしれません。モバイルアプリの場合は、アプリストアのレビューが総合的な満足度を測るための大変有効な指標となります。レビューを通して寄せられる意見や要望にしっかりと耳を傾けて必要なものはプロダクトに反映していくと良いでしょう。
ユーザビリティテストはペルソナに近い人物で行う。
前述のユーザビリティの説明を踏まえると、ユーザビリティテストとは「使いやすさの検証」ではなく、「対象のユーザーが目的を達成できるか」の検証となります。ユーザビリティテストの重要性は、この対象のユーザーを被験者として行う点にあります。理想的には、そのプロダクトが解決しようとしている課題を抱えている人に対してテストすることが望ましいです。
ユーザビリティテストのよくある失敗としては、性別・年齢などの属性情報のみで被験者を集めてしまうことです。属性情報がペルソナと一致していたとしても、ランダムに集められた被験者たちは多くの場合、プロダクトの解決しようとしている課題について「どうでも良い」と感じている場合がほとんどです。この、プロダクトに対して無関心の人で、プロダクトの「使いやすさ」を検証したところで、レイアウトのわかりやすさなどの一般的なフィードバックしか集めることができません。そのプロダクトを実際に使う可能性のある人を被験者としてテストすることで、実際のユースケースに沿ってプロダクトが有効なのかどうかを検証することができるようになります。実際にサービスのターゲットユーザーやペルソナに近い人物でユーザビリティテストを行うことで初めて、「対象のユーザーが目的を達成できるか」を検証することができるのです。
まとめ
今回は、UXデザインにおいてとても良く使われる言葉「ユーザビリティ」について解説しました。ユーザビリティにおいて重要なポイントは、「ユーザビリティ = 誰にとっても使いやすいこと」ではなく、「ユーザビリティ = 想定しているターゲットユーザーにとって良い製品であること」です。今回紹介した、ユーザビリティを向上させる5つのチェック項目を使ってプロダクトを改善しながら、ターゲットユーザーへのユーザビリティテストを繰り返すことが、ユーザビリティの高いプロダクトを作るための近道となります。