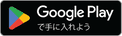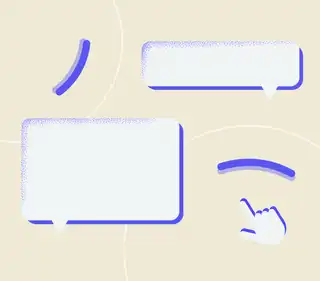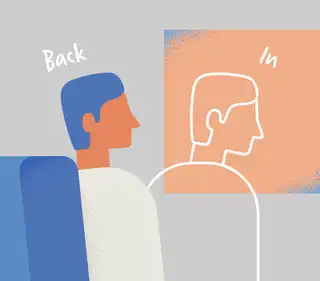UX(ユーザーエクスペリエンス)とは?
UXとは、ユーザーエクスペリエンス(User Experience)の略称で、「利用者がサービスや製品を通して得られる顧客体験」を意味します。個々の顧客に対して、直接サービスを提供する企業が「顧客体験」といった言葉を使う一方、個々の利用者を「ユーザー」と定義した上で、ソフトウェアを通して自動化されたサービス提供を行うIT業界で主に使われている言葉です。
UXとCX(顧客体験)の違い。UXという言葉の2つの使われ方
でもUXという言葉、イマイチわかりにくくないですか?
実際にIT業界で仕事をしてい�ると、
「アプリ全体のUXを改善したい」
「スクロール時のUXが悪い」
「リピート顧客のUXを改善したい」
など、幅広い文脈でUXという言葉を聞きますよね。それぞれ意味が少しづつ違うため、混乱しそうです。
これは、「従来、CXと呼ばれていたもの対してもUXという言葉が使われ始めている」と考えるとわかりやすいです。幅広く使われているUXという言葉の定義について、CX(顧客体験)とUX(ユーザー体験)の関係性を意識するとスッキリ理解できると思います。
CX(顧客体験)とは?ITサービスではUXとの境界線が曖昧に
CX(顧客体験)とは、商品を購入する前から、購入した後までのすべての体験を意味します。
例えば、新型のiPhoneを購入する顧客のCXを考えてみましょう。
テレビで新型iPhoneの広告を見て、利用シーンをイメージする
Appleストアに行って、未来感のある店舗の空間デザインを体験する
丁寧な店舗スタッフの説明を受けてiPhoneを購入
家に帰って購入したiPhoneの箱を開封する
iPhoneを利用する
使い方についてカスタマーサポートに助けを求める
購入したiPhoneについてInstagramにストーリーを公開する
これら全てを含めてCXと呼びます。
顧客の体験すべてを意味するので、IT業界以外でも広く使われる言葉です。
本来、UXはサービスを「利用」しているときの体験のことを意味するので、UXは顧客体験全体としてのCXの一部として考えることができます。しかしながら、IT業界では顧客のことを「ユーザー」と呼ぶことが一般的となったため、今までCX(全体的な顧客体験)と呼ばれていたようなものに対しても、UXという言葉が使われることが多くなりました。
ちなみに、顧客のことを「ユーザー」と呼ぶのはIT業界と違法ドラッグ産業だけなんて話もあります。
UIとUXの違い。UI/UXデザインって?
UXと一緒によく聞く言葉にUI(ユーザーインターフェース)があります。UIとはボタンやスイッチなど、ユーザーとの「接点」のことを意味する言葉で、サービス利用体験であるUXを最適化する上でとても重要な要素となります。
UI(ユーザーインターフェース)とは?Instagramアプリをもとに解説
UIとは、ユーザーと製品とのすべての「接点」のことです。接点と言うとわかりにくいですが、ユーザーはサービス利用時に大きく分けて「インプット」と「アウトプット」という2つの動作をおこなっています。このインプットとアウトプットを行う接点となるのがUIです。ユーザーはアプリなどのサービスを利用する際には、このインプットとアウトプットの繰り返し(インタラクション)を行っているのです。
例えば、インスタグラムのフィードを見ている場面を考えてみましょう。
画面一番上に表示されている投稿の画像を見る
画面をスクロールするとさらに投稿があることに気付く
画面をスクロールする
気になる投稿を見つける
気になった投稿をタップする
この一連の動作でユーザーが見た画像や説明文、ボタンなどのすべてがUIです。
インスタグラムのようなモバイルアプリは、ユーザーが「操作」することを前提としたサービスなので、画面内のすべての要素がUIであるということができます。そのため、アプリをデザインするデザイナーは一般的に「UIデザイナー」と呼ばれています。一方、広告デザインやデジタルアートなどのユーザーが「操作」しないものはUIとは呼ばれません。
IT業界では、UIをどのようにデザインするかが製品のUXに大きな影響を与えるため、デザイナーはUIをデザインする際にUXを常に意識する必要があります。このようにUIとUXが密接に関係しているIT業界では、アプリのデザインをする際にUI/UXデザインとしてまとめて語られることが多いです。そのため、IT業界の求人情報を見ても、「UIデザインを通して、最適化されたUXを提供するデザイナー」という意味合いで、UI/UXデザイナーとしてデザイナーを募集していることが多いです。
UXデザイナーが解説!UXデザインのプロセスとUX最適化のポイント
個々のUIデザインがUXに大きな影響を与えることはわかりましたが、一体UXが良い製品とはどのように作られるのでしょうか?アプリやWebサイトのUXを改善することを主な職務としているUXデザイナーの実際の作業プロセスを紹介しながらUX最適化のポイントを解説します。
UXデザインの5つのプロセス
UXデザインに求められるのは、「何かを作ること」ではなく「課題を解決すること」です。そのため、具体的な課題解決の方法だけではなく、そのプロセスも非常に重要となります。UXデザインは問題の発見、解決案の模索、解決案のテストの小さな繰り返しとなるため、UXデザイナーはデザイン思考のプロセスでUX課題に取り組むことが多いです。
デザイン思考のプロセス
共感
問題定義
創造
プロトタイプ
テスト
1. 共感
UX最適化の第一歩として、まずはそのサービスや商品を使う「ユーザー」について理解し、共感することが重要となります。ユーザーのサービス利用シーンを洗い出し、どの部分に課題を感じているか仮説を立ててみましょう。
また、よく「ユーザーの気持ちになって考えるべき」と言われることも多いですが、自分がターゲットペルソナに当てはならない場合は、想像に任せるのではなく、ユーザーインタビューやアンケートで実際のユーザーの��声を聞くことが重要となります。
2. 問題定義
共感ステップで集めた情報をもとに、解決するべき問題を定義します。ここで定義する問題は、「私たちは、どうすれば〜できるか?」と簡潔にまとめることで、その後のステップで目的を見失うことがなくなり、チームメンバーとゴールの認識を共有する上でも役立ちます。この問題定義の問いのことを、海外では「How Might We Question」と呼び、多くのUXデザインチームで取り入れられています。
3. 創造
定義した問題を解決するための方法を模索します。何かを作ることのみにとらわれず、自由な発想で解決策を考えることが重要となります。UXデザインの課題は、ちょっとした文言の変更や、ボタンの入れ替えだけで大きく改善することも多いです。ここで課題解決策を出すためのUXの考え方については、次のUX最適化のための5つの観点で詳しく解説します。
4. プロトタイプ
「プロトタイプ」とは、試作品という意味です。考案したUX改善策を実際のサービスに反映する前に「試作品」を少数のユーザーやユーザーテストの被験者に体験してもらうことで、効果検証を行うステップとなります。試作品というと大袈裟に聞こえますが、紙に書いたモックアップでのテストや、ちょっとしたイン�タビューだけでも立派なプロトタイプと言えます。ここで重要なことは、定義した問題である「私たちは、どうすれば〜できるか?」に対する解決策、「こうすれば良いのではないか?」をユーザーが体験できる形で準備することです。
5. テスト
準備したプロトタイプを使って、実際のユーザーの反応を検証しましょう。ここで重要なのは、問題解決策が実際のユーザーに効果的かどうかをできるだけ少ないコストで実験することです。もちろん、初回のプロトタイプですぐに解決策が見つからない場合もあります。小さな失敗�を繰り返しながら、プロトタイプとテストを繰り返すことがUX最適化に最も重要なプロセスとなります。
UX最適化のための5つの観点
UX最適化には、プロトタイプとテストを繰り返すことが重要だとお伝えしました。しかし、実際にUX課題を解決するための案はどのように見つけたら良いのでしょうか?ここでは、良いUXを形作る5つの観点をUX最適化のポイントとしてまとめました。UX課題の定義ができたらこの5つの観点に照らし合わせて現状を評価し、改善できる部分がないか確認してみてください。
使えるか?
信頼できるか?
使いやすいか?
便利か?
心地よいか?
この5つの観点からUX課題を診断して、改善策のプロトタイピングとテストを繰り返すことがUX最適化のポイントとなります。
1. 使えるか?
サービスや機能が問題なく使える状態であるかとういう点です。「問題なく使える」というのは、特別な環境の準備やバグによるやり直しなどを必要としない状態を表します。これが、良いUXを提供するための最低ラインとなります。
2. 信頼できるか?
見た目のデザインや表記の言葉遣いなどを通して、サービスに安心感を与えましょう。使用感に影響を与えないようなレイアウトの崩れであっても、この「信頼できるか?」という観点で見ると悪影響を与える可能性があります。信頼感のない商品だと、使いやすさの評価以前の段階でユーザーに避けられてしまいます。
3. 使いやすいか?
「使いやすいか?」は「ユーザービリティ」とも呼ばれ、UX関連で一番良く検討されている観点かもしれません。これについては、
学習しやすさ
効率性
記憶しやすさ
エラー発生率
満足度
といった、さらに細かい観点に分けて考えることができます。何度も同じ動作を繰り返させるようなUIでは、一度使えるかだけではなく、反復して同じ動作をストレスなく行うことができるかまで考えてUXを設計・テストする必要があります。
4. 便利か?
「便利か?」は、ユーザーがそのサービスや機能を使った上で、自分にとって役に立ったと感じるかどうかという観点です。ユーザーの役に立つものを作ることはもちろん、ユーザーがそのサービスや機能のメリットを実感として感じられるような工夫をすることもUXデザインには重要な観点となります。
5. 心地良いか?
「心地良いか?」はユーザーの主観的な感覚として、そのサービス・機能を使った後に「なんとなくまた使いたい」や「誰かに紹介したい」と感じてもらえるかという観点です。使いやすく、便利であるといった観点をクリアした上で、さらなる一歩として心地良さを提供できるようなUXデザインができると良いですね。サービスや機能を使うときに、ユーザーはある程度の期待値を持っているため、その期待を満たした上で、「意外性」や「おどろき」といった感情につながるような何かを提供することが求められます。
もう一つの重要な観点「使いたいか?」
実はもう一つ、見落とされがちな重要な観点があります。それは、「使いたいか?」です。ユーザーに対してある体験を提供することを前提とするUXデザインの観点からは少しずれますが、そもそも「ユーザーがそのサービスや商品、機能を欲しがっているか」、また「どれくらい欲しがっているか」という点はとても重要です。
UX最適化を目指してプロトタイピングとテストを何回も繰り返しても効果が上がらないといったケースもよく見かけます。その場合、そもそもユーザーがあまりその機能自体を使いたいと思っていない場合が多いです。どんなに優れたUXであってもそもそもユーザーが必要としない価値を提供していては、何の意味もありま�せん。サービスを提供する企業側がサービス価値を信じるあまり、UX最適化以前の根本的な問題に気づいていないといったこともあります。
特にスタートアップなどの、まだユーザーニーズが不明確なビジネスの場合、UX最適化と並行して、サービスが提供する価値自体の検証も繰り返し行えると良いでしょう。
UberEatsのストーリー機能。優れたUXによってユーザーの課題を解決した事例
フードデリバリーサービスであるUberEatsは、コロナ禍でもレストランの食事を楽しめる手段として実際に利用されている方も多いのではないでしょうか?今回は、UberEatsのプロダクトデザイナーであるFemkeさんのYoutubeチャンネルfemke.designで紹介されている「UberEatsがストーリー機能を実装した際のケーススタディー」からUXデザインの実例を紹介します。
ストーリー機能とは?
UberEatsは、2021年4月に「ストーリー」機能をリリースしました。「ストーリー」とは、スライドショーのような形式で画像や動画が投稿できる機能です。Instagramが2016年に始めたのをきっかけに、Facebook, Airbnb, LinkedInなどの多くのサービスが似た形式でこの機能を取り入れました。
IT業界では「最近どのサービスもInstagramを真似してストーリー機能を実装している」なんて話を聞くこともありますね。しかし、実際にUberEatsでこのストーリー機能実装に携わったプロダクトデザイナーの話を通してわかるのは、UberEatsが安直に流行りの機能を取り入れたわけではなく、解決したい課題に対するアプローチとして検討を重ねた結果、ストーリー機能の実装に至ったということでした。
「機能を実装することを目的とするのではなく、問題を解決することを目的とする」という点はUXデザインにとってとても重要です。今回のケーススタディを紹介しているFemkeさんも、「検討初期段階には、ストーリー機能として実装する予定はなかった」と言っています。
UberEatsのストーリー機能: https://merchants.ubereats.com/jp/en/technology/reach-customers/stories/
UXデザインの最初のステップ「共感」。UberEats出店レストランが抱えていた課題
では、UberEatsのプロダクトチームが持っていた問題意識とはどのようなものだったのでしょうか?動画内で、Femkeさんはこのプロジェクトの出発点となった問題提起は以下のようなものであったと述べています。
- プロジェクトの問題提起
- 出店しているレストランは、顧客に直接情報を届ける手段を求めているものの、UberEats上にはそのような要求にあった機能がなく、レストランと顧客の関係性が無機的なものになってしまっているのではないか?
レストランを始めとした飲食業界は、顧客に食を通した喜びを届けることを目指している業界です。実店舗をもつレストランでは「店舗」が顧客との重要なタッチポイントとなっており、従業員の振る舞い、店頭のポスターや店舗の空間デザインなど、さまざまな方法で顧客にメッセージを届けることで顧客体験を形作っています。
しかし、コロナ禍の影響でフードデリバリーへのシフトが進む中で、UberEatsは食事を注文するユーザーには数タップで食事が届く利便性の高いサービスを提供している一方、出店レストランに「金銭の対価として食事を提供する無機的な顧客関係」を強いてしまっているのではないかという問題意識が生まれていました。
問題に関する仮説の検証。ユーザーによる機能の”ハッキング”とは?
UXデザインの「共感」ステップでは、ユーザーが感じているであろう課題に関する仮説を打ち出し、その仮説を検証することが重要となります。一般的には、ユーザーインタビューやデータ分析などを通して仮説の検証を行うことができます。しかし、今回のUberEatsチームの持っていた仮説は面白い形で実証されることとなりました。「出店店舗がUberEats上の既存機能を駆使して、顧客にメッセージを伝える方法を模索していた」のです。
具体的には、¥0のメニューを作成して説明欄に最新のキャンペーン情報を載せるなど、何らかの方法で顧客にメッセージを伝えようとする出店レストランが多く見受けられたそうです。このように、「ユーザーが別の手段を駆使して自分のニーズを満たそうとしている」という状況はサービス提供者にとっては新しい機能やサービスを提供するための大きなヒントとなります。
ちなみに、今回の動画内で表現されているように、ユーザーが本来と異なる使い方で既存機能使うことで自身のニーズを満たしている状況を、英語圏のプロダクトデザイナーは「ユーザーが機能をハッキングしている」と呼びます。
UberEatsチームが「問題定義」ステップで設定したHow Might We Question
ユーザーの課題を明確に把握したUberEatsのプロダクトチームは、このプロジェクトで解決したい問題を表現する「How Might We Question (私たちは、どうすれば〜できるか?)」を以下のように定義しました。
- UberEatsチームの問題定義
- 私たちは、どうすればレストランに関する最新情報の提供を通して、食事を注文するユーザーの需要を高めることができるか?
ここでは、「顧客への情報発信」という出店店舗のニーズに寄り添った「共感」から始まったプロジェクトでも、「食事を注文するユーザーの需要を高める」という根本的なビジネスゴールを見失うことなく問題定義していることが重要です。仮に「私たちは、どうすれば出店レストランに情報発信ができる機能を提供できるか?」と問題定義してしまうと、ユーザーのニーズは満たせてもビジネス的なメリットの少ない施策に陥ってしまう可能性があります。UXデザインでは、ユーザ体験を最適化することが主なミッションとなるものの、解決策がビジネス面でのゴールに沿っている事も忘れてはいけません。その点で、問題定義の段階でビジネスゴールを意識することはプロジェクトの軌道がビジネスゴールに沿ったものとなることを担保する上でもとても有効だと言えます。
様々なアイデアを自由に検討する「創造」ステップに最低限のルールを設ける
次の「創造」ステップでは、UX最適化のための5つの観点を意識しながら問題の解決策を検討することとなります。UberEatsのプロダクトチームは、具体的な解決案のデザインに取り掛かる前に、UXが最適化されていることを担保するための4つのルールを設けました。
ユーザーが、受け取る情報の取捨選択権をできること
メッセージの量と頻度が多過ぎないこと
機械的なメッセージを送信しないこと
出店店舗が簡単にメッセージを作成できること
解決策を模索するフェーズでは、自由な発想を元にさまざまなアイデアを検討することになります。その中でも効率良く問題に沿ったアイデアを導き出すためには、目指す方向性を示したルールやガイドラインを設けることは大変有効です。
UberEatsチームが検討したアイデア
Push通知
店舗詳細にステータス情報表示
メニューへの追加情報表示
ストーリー
UberEatsのプロダクトチームは、ストーリー機能に辿り着く前に他にも様々な解決案を検討していました。しかしながら、Push通知はユーザーの状況とは関係なく送信されてしまう。店舗ページやメニューへの追加情報表示は、その画面を開いたユーザーにしかアプローチできないなど、それぞれの案は主に「情報を提供する文脈が最適ではない」という理由で却下となりました。
そんな中、「ユーザーが食事を選んでいる」という文脈にフィットするフィード画面に表示できる上、ユーザーが他のアプリを通して見慣れているであろう「ストーリー機能」という形で検討を進めることとなりました。
余談ですが、近年のモバイルアプリでは、ユーザーがコンテンツを選択する際に多角的に探すことができるよう「フィード」画面を設けることが多いですね。AppStoreやNetflixなどのアプリでもこのフィード画面と相性の良いUX施策が多く見受けられます。
プロトタイピングとテスト。MVPによる効果検証と段階的リリース
今回の動画では詳しく紹介されていませんが、ストーリー機能のデザインは100パターン以上作成したと述べられており、膨大なパターンのプロトタイプを作成しながら最適なデザインを模索したことが見て取れます。また、機能の検討開始から6ヶ月後にはオーストラリアでのMVPテストが開始され、2021年5月にはアメリカ、カナダでのリリースに至ったとのことから、UberEatsのチームがMVPでの効果検証を通して機能のテストと最適化を繰り返したことがわかります。
ストーリー機能開発ロードマップ
2020年5月 検討開始
2020年12月 オーストラリアでのMVPテスト
2021年5月 アメリカ、カナダでのリリース
ストーリー機能がUberEatsにもたらした成果
具体的な数字は伏せられていますが、ストーリー機能を使ったレストランの1ユーザあたりの注文数の上昇、ストーリー機能導入後のUberEats全体の売り上げの上昇といった成果が計測されており、今回のUX改善が成功に終わったことが述べられています。また、2022年現在には日本のUberEatsでもストーリー機能が実装されていることを見ると、全世界的に効果を上げている機能となっていることがわかります。
まとめ
UberEatsの例からも分かるように、UXの改善はアプリやソフトウェアがユーザーとの主なタッチポイントとなるITビジネスにとって重要な施策となります。UX改善を成功に導くためには、当てずっぽうや感覚で新しい機能を考えるのではなく、正しい問題定義とデータに基づいた仮説検証の繰り返しが鍵となります。UX改善をどのように進めてよいかわからない場合は、今回紹介したような一般的なプロセスを参考に進めてみてはいかがでしょうか?