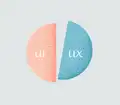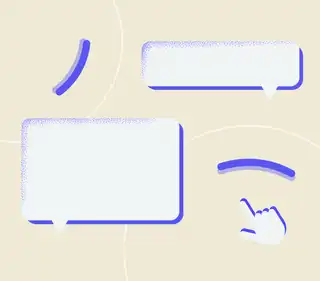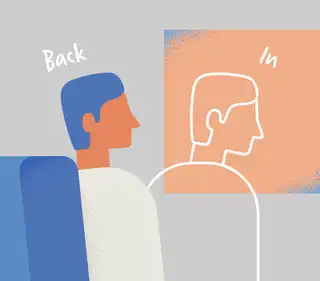UXデザインとは?
UX(ユーザーエクスペリエンス)デザインとは、「ユーザーがサービスや製品を通して得られる顧客体験」の設計を意味します。ITサービスをはじめ、人と人の直接的な交流の範疇を超えてサービスが提供されるようになった現代においては、「ユーザーとサービスの接点を最適化すること」がUXデザインの主な課題となっています。
「UX = すべての顧客体験」なのか?
近年では、UXデザインを「すべての顧客体験の設計」と定義する場面も多く見受けられます。しかし、例えばホテルや旅館などの宿泊業での顧客体験設計について、UXデザインと呼ぶことはあまりありません。では、顧客体験設計の中でもUXデザインと呼ばれるものにはどのような特徴があるのでしょうか?
一つの指標として、顧客を「ユーザー」と呼べるかどうかで判断することができます。UXデザインは、その名前が示す通り、顧客を「�ユーザー」として定義する業界で主に使われている言葉です。逆に、顧客を「ユーザー」とは呼ばない、宿泊業や実店舗での小売業では「CX = 顧客体験」という言葉が使われることが多いです。
UXデザイナーとは?UXデザイナーの業務内容
このUXとCXの違いが、UXデザイナー業務内容を理解する上でもわかりやすい指標となるかと思います。
UXデザインが注目されるようになった背景には、ITサービスや物流の発達によって「サービス提供者と利用者の間に距��離が生まれたこと」があります。前述の宿泊業のような「顧客の顔が見える」伝統的なビジネスでは、顧客の要望を取り入れてサービスを改善することに特別な技術は必要ありませんでした。しかし、「顧客の顔が見えない」ビジネスが増えた現代では定量的・定性的なデータを集め、ユーザーとの接点を改善するために特別な技術・手法が求められるようになりました。これを担うのが、UXデザイナーの業務となります。
ユーザーリサーチ
プロトタイピング
ユーザーテスト
といった手法を使って、顔の見えない大多数の顧客の体験を最適化することがUXデザイナーのミッションです。
UI/UXデザイナーとは?
UXデザインと共によく聞かれる言葉に「UI�デザイン」があります。「UI/UXデザイン」としてまとめて語られることも多く、IT企業の求人を見てもUI/UXデザイナーとしてデザイナーを募集している企業もありますね。UIデザインはUXデザインにとって重要な「ユーザーとの接点」を担う部分となっており、UIデザインはUXデザインにとって重要な要素の一つであると考えることができると思います。
この2つの分野をまとめて同じデザイナーが担当する場合、UI/UXデザイナーといった職種で定義されることが多いです。
UIデザインとは?
UXデザインとは、「利用者とサービスの接点を最適化すること」と述べましたが、モバイルアプリやWebサービスにおいてその「接点」となるのがUI(ユーザーインターフェイス)です。UIとは、ボタンやスイッチなど、ユーザーとの「接点」のことを意味する言葉で、サービス利用体験であるUXを最適化する上でとても重要な要素となりま�す。このような「接点」のデザインをUIデザインと呼びます。
UXデザインとUIデザインの違い
UXデザインとUIデザインのそれぞれの定義は、
UXデザイン = 「ユーザー体験の設計」
UIデザイン = 「ユーザーとサービスの接点の設計」
と言えます。UXデザイナーが主にリサーチやプロトタイピング、ユーザーテストを通してユーザー体験の設計を担当するのに対し、UIデザイナーは実際にユーザーが操作する画面の具体的なデザインの作成を担当します。
UXデザインのプロセス
UXデザイナーに求められるのは、「何かを作ること」ではなく「ユーザーの課題を解決すること」です。そのため、具体的な課題解決の方法だけではなく、そのプロセスも非常に重要となります。UXデザインは問題の発見、解決案の模索、解決案のテストの小さな繰り返しとなるため、UXデザイナーはデザイン思考のプロセスでUX課題に取り組むことが多いです。
1. 共感
UX最適化の第一歩として、まずはそのサービスや商品を使う「ユーザー」について理解し、共感することが重要となります。ユーザーのサービス利用シーンを洗い出し、どの部分に課題を感じているか仮説を立ててみましょう。
また、よく「ユーザーの気持ちになって考えるべき」と言われることも多いですが、自分がターゲットペルソナに当てはならない場合は、想像に任せるのではなく、ユーザーインタビューやアンケートで実際のユーザーの声を聞くことが重要となります。
2. 問題定義
共感ステップで集めた情報をもとに、解決するべき問題を定義します。ここで定義する問題は、「私たちは、どうすれば〜できるか?」と簡潔にまとめることで、その後のステップで目的を見失うことがなくなり、チームメンバーとゴールの認識を共有する上でも役立ちます。
3. 創造
定義した問題を解決するための方法を模索します。何かを作ることのみにとらわれ�ず、自由な発想で解決策を考えることが重要となります。UXデザインの課題は、ちょっとした文言の変更や、ボタンの入れ替えだけで大きく改善することも多いです。
4. プロトタイプ
「プロトタイプ」とは、試作品という意味です。考案したUX改善策を実際のサービスに反映する前に「試作品」を少数のユーザーやユーザーテストの被験者に体験してもらうことで、効果検証を行うステップとなります。試作品というと大袈裟に聞こえますが、紙に書いたモックアップでのテストや、ちょっとしたインタビューだけでも立派なプロトタイプと言えます。ここで重要なことは、定義した問題である「私たちは、どうすれば〜できるか?」に対する解決策、「こうすれば良いのではないか?」をユーザーが体験できる形で準備することです。
5. テスト
準備したプロトタイプを使って、実際のユーザーの反応を検証しましょう。ここで重要なのは、問題解決策が実際のユーザーに効果的かどうかをできるだけ少ないコストで実験することです。もちろん、初回のプロトタイプですぐに解決策が見つからない場合もあります。小さな失敗を繰り返しながら、プロトタイプとテストを繰り返すことがUX最適化に最も重要なプロセスとなります。
UXデザインの代表的な手法5つ
UXデザインのプロセスは、小さな仮説検証の繰り返しとなることがわかりましたね。では、具体的にはどのような手法を使ってUX改善のための仮説立案と検証を行うのでしょうか?実は、UXデザインにはとても沢山の手法があり、プロジェクトのフェーズや規模に合わせて異なる手法を取り入れることが多いです。ここでは、おそ�らく最も使用頻度が高い代表的な手法を5つ紹介します。
競合分析
「競合分析」と聞くと、マーケティングや経営分野の手法のように聞こえますが、UXデザインの初期段階で行う業務はマーケティング分野でよく知られた3C分析とよく似ています。マーケティング分野での競合分析が資金力、ブランド認知などの広い視点から「企業」を分析するのに対し、UXデザイナーの行う競合分析では、「サービス・プロダクト」のユーザー体験を分析することが多いです。
競合サービスの状況を把握することは、UXデザイン施策の優先度付けや、施策効果の予測をする際に重要となります。特に、UX面で競合に対して圧倒的な優位性を得るために必要となる「鍵」を理解することで、UXデザインプロジェクトの方向性を明確にすることができます。
ユーザーインタビュー
ユーザーインタビューはUXデザイナーの最大の武器と言っても過言ではないでしょう。なぜなら、「ユーザー体験」を設計するためにはユーザーの行動心理を理解することが欠かせないからです。最近では、サービス内のユーザー行動データの分析に基づいてサービスのUXを改善することも多くなりましたが、データ分析ではどうしてもユーザー行動の「なぜ」を理解することはできません。なぜそのサービスを使うのか?または、なぜそのサービスを使わないのか?といった、サービスの提供価値に対するユーザーの反応を理解するには、ユーザーインタビューによって直接聞くことが最適です。
ユーザーインタビューを行う際に重要となることが一つあります。それは、「適切なインタビュー対象者を選ぶ」ということです。例えば、既存サービスの改善のためにターゲットユーザーと同じ性別・年代の人を集めて質問したとしても、その人がサービスに関�心を持っていなければ多くのインサイトを得ることはできません。ユーザーインタビューの対象者を探す際には、できるだけ細かく条件を設定して、サービスを利用する可能性のある人の心理を探れるようにする必要があります。
インタビューの対象者を適切に設定できていれば、5 - 10人程度へのインタビューでもインタビューの内容から明確なユーザーの行動心理パターンを見出すことができます。
ユーザビリティテスト
ユーザビリティテストとは、実際のプロダクトやプロトタイプをユーザーに操作してもらい、操作性上の問題を発見したり、新しいUIの操作性を検証する手法です。サービス内でのユーザの行動を実際に「観察」することでユーザーがサービスをどのように使っているかについての理解を深めることができます。ユーザビリティテストを行う際には、ユーザーには考えていることを実際に声に出しながら操作をしてもらうと、特定の操作を行なった理由や、画面を見て感じた印象を理解することができます。ユーザービリティテストは、プロジェクトのさまざまなフェーズで取り入れることができ、それぞれ
ユーザー行動心理の理解
操作性上の問題の発見
新しいUIの操作性の検証
といった効果を期待できます。特に、UXデザインのプロセスで紹�介した「プロトタイプ」の段階では、さまざまなアイデアをユーザビリティテストで検証することで、リリース前に施策の成功率を上げることができます。
ペルソナ
ペルソナとは、サービスや商品の典型的な利用者の定義です。ペルソナに似た言葉に、「ターゲットユーザー」がありますが、ペルソナはその「ターゲットユーザー」に当てはまるユーザーの人物像を細かく定義したものとなります。行動パターンや、思考まで明確に定義すること�で、プロジェクトの要所で施策がユーザーのニーズに沿っているかを再確認することができます。また、プロジェクトのステークホルダー(利害関係者)に施策内容の説明をする際にも、「誰のための施策か」を明確にすることができ、共通認識を形成することに役立ちます。
ペルソナを作成する際に重要となるのが、ターゲットユーザー層がサービスを利用する際の心理や行動パターンをペルソナの定義に含めることです。ここで、ユーザーがサービスを利用する際の5W1Hを明確に定義できていることが、具体的なUXデザイン施策を考える際の絶対条件となります。そのような人がなぜ使っているかわからないような状態では、サービス改善施策も空振りに終わってしまいます。
5W1H
When = いつ
Where = どこで
Who = だれが
What = 何を
Why = なぜ
How = どのように
つまり、ペルソナは想像で作って良いものではなく、ユーザーインタビューやデータ分析による強い根拠に基づいたものである必要があります。リサーチによって明らかになったユーザー性質まとめた集合体として考えても良いと思います。
とはいえ、サービス立ち上げの初期段階など、まだデータに基づいた明確なユーザー像がわからない場合もありますね。そういった場合には、簡易的なペルソナである「プロトペルソナ」として作成して、チーム内での合意形成に役立てる場合もあります。
カスタマージャーニーマップ
カスタマージャーニーマップとは、ユーザーがサービスを利用する際の行動と心理を時系列にまとめたものです。カスタマージャーニーマップを作成する目的は、「ユーザー行動の可視化」と「合意形成」です。ペルソナと同じく、ユーザーインタビューやデータ分析からわかった典型的なユーザーのサービス利用時の行動を時系列にまとめることで、ユーザーのペインポイントや、サービス目指す方向性を明確に定義することができます。
カスタマージャーニーマップには大きく2種類あり、リサーチからわかった現状のユーザー体験は「AS-IS(現状)カスタマージャーニーマップ」としてまとめ、UX改善により目指すべき理想のユーザー体験を「TO-BE(あるべき姿)カスタマージャーニーマップ」としてまとめます。
また、カスタマージャーニーマップ作成時によくある失敗が一つあります。それは、「カスタマージャーニーマップを作ること自体が目的となってしまう」ことです。カスタマージャーニーマップはあくまでもユーザー分析から得られた情報をわかりやすくまとめる「フォーマット」です。UXデザイナーが注力すべきは、ユーザー分析によってUXデザイン施策に役立つインサイトを得ることです。リサーチ段階で明確なインサイトが得られている場合は、カスタマージャーニーマップは自ずと出来上がってきます。逆に、カスタマージャーニーマップ作成時に迷うことがある場合は、もう一度ユーザー分析を行なって情報を集めることが必要となります。カスタマージャーニーマップを作ることが目的化してしまうと、UX改善に役立たない情報や想像に基づいた情報ばかりが書き込まれた、UXデザイン施策を考える際に役に立たないカスタマージャーニーマップとなってしまいます。
ウィキペディア上の不正な情報編集の発見を簡易化。ウィキペディアのUXデザインプロジェクトの事例。
開かれた情報コミュニティとして、非営利でウィキペディアを運営するWikimediaのデザインチームによるUX改善プロジェクトを例に、UXデザインの実際のプロセスを紹介します。
プロジェクト背景
一般的なWebサービスがユーザーによるコンテンツの投稿や編集のためにはアカウント作成を要求するのに対し、ウィキペディアではアカウント作成なしでページの編集が可能となっています。これは、誰でも気軽にウィキペディアの編集への参加ができるようにするためのもので、実際に小さな誤字脱字の編集などはとても簡単に行えるようになっています。
しかし、アカウント登録なしで編集を許可するということは、悪意のある編集や悪戯を行うユーザーも簡単にページの内容を編集できるということを意味します。ウィキペディアでは、この問題に対してボランティアでコンテンツの不正な改ざんを監視するユーザーたちがおり、このようなユーザーたちがサイト内をパトロールすることでコンテンツのクオリティを担保しています。
このようなパトロールを行うユーザーは、アカウント登録のないユーザーによる悪意のあるページ編集を見つけた場合、編集者の情報などをもとに問題の重要度を判断して対策を講じます。今回のプロジェクトは、このような「手作業での監視作業のUXを改善できないか?」という課題が出発点となりました。
ユーザーリサーチ
ウィキペディアのチームはまず、実際にパトロールを行なっているボランティアユーザーへのインタビューを行いました。インタビューを通して、ボランティアユーザーがどのようなプロセスを経て不正な編集に対する対応を行なっているのかをカスタマージャーニーマップとして可視化しました。
https://design.wikimedia.org/blog/2021/11/17/patrolling-unregistered-editors-on-wikipedia.html
リサーチを通して、パトロールを行うユーザーが編集者のIPアドレス情報をもとに、ユーザーの情報を特定する外部サービスを利用して悪意のある編集であるかどうかを推測していることがわかりました。
ウィキペディアのチームはこのユーザーインタビューを通して、パトロール時のUX改善を行う必要性を感じると同時に、必要以上の投稿者情報をウィキペディア内で開示することで、一般の編集者の投稿意欲を削がないように気をつける必要があるという結論に至りました。これらを元に、チームは今回のプロジェクトの課題を以下のように定義しました。
IPアドレスに基づいてサイト内で開示する情報の性質をユーザーに理解させるにはどうしたら良いか?
IPアドレスに基づいたユーザー情報を誰に開示するべきか?
ユーザー登録をしないでウィキペディアを編集した場合、IPアドレスが開示されることをユーザーにどのようにして伝えるか?
プロトタイピン��グとユーザビリティテスト
定義した問題を解決するためのUIデザインのプロトタイプを作成し、開示するべき情報の内容が最適であるかの検証を重ねました。また、小さなポップアップに表示する情報と詳細ページに表示する情報がカスタマージャーニーのそれぞれのステップで必要となる情報に沿っているかを実際のユーザーへのヒアリングを通して確認しました。
具体的なUIの検討時にユーザーへのヒアリングやユーザビリティテストを行うことで、ユーザーが抱えている課題を解決できているかの確認を繰り返し行うことができました。
https://design.wikimedia.org/blog/2021/11/17/patrolling-unregistered-editors-on-wikipedia.html
https://design.wikimedia.org/blog/2021/11/17/patrolling-unregistered-editors-on-wikipedia.html
機能のリリース
2022年4月現在、ベータ版ウィキペディアにて機能の最終テストを行なっており、機能的な問題がなければ近日正式にリリースされる予定となっています。
まとめ
ウィキペディアの実例を見てわかる通り、最終的な成果物としては「サイト内に表示する情報を少し追加するだけ」であっても、その裏側ではUXデザインのためのリサーチや検証が繰り返し行われており、効果を上げるUX施策を行うためにはユーザー�の行動心理に対する深い理解と効果の検証が重要であることがわかります。そのため、UX課題解決のための仮説検証プロセスとその手法を熟知したUXデザイナーが、近年のITサービスやビジネスにとっては欠かせない、大変重要な役割となってきています。