#インタビュー
「インタビュー」に関連する記事一覧
 Article・2025.04.17「無色透明」のUIで“書籍”を主役に。124万人が利用する本の要約サービス「flier」のデザイン原則を聞いた1冊10分で読める本の要約を提供するサービス「flier(フライヤー)」。1日1冊以上のペースで要約を配信し、テキストと音声で利用できる。会員数は、個人・法人をあわせて累計124万人超え(2025年4月現在、無料会員を含む)。運営するフライヤー社(東京都千代田区)は2025年2月に東京証券取引所グロース市場へ新規上場したばかりと、勢いに乗っている。コスパ・タイパの意識が高い現代人に好まれているflierだが、どんな体験設計やデザインが心地よさや利便性につながっているのか。デザイナーの筒井大尊氏に
Article・2025.04.17「無色透明」のUIで“書籍”を主役に。124万人が利用する本の要約サービス「flier」のデザイン原則を聞いた1冊10分で読める本の要約を提供するサービス「flier(フライヤー)」。1日1冊以上のペースで要約を配信し、テキストと音声で利用できる。会員数は、個人・法人をあわせて累計124万人超え(2025年4月現在、無料会員を含む)。運営するフライヤー社(東京都千代田区)は2025年2月に東京証券取引所グロース市場へ新規上場したばかりと、勢いに乗っている。コスパ・タイパの意識が高い現代人に好まれているflierだが、どんな体験設計やデザインが心地よさや利便性につながっているのか。デザイナーの筒井大尊氏に Article・2025.04.08会員数143万人のプロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」 PdMに聞くサービスの強みヌーラボ社(福岡市)が提供する「Backlog」は、チームで働く全ての人をターゲットに、「親しみやすい操作性」や「多機能」を追求。「このチームで仕事ができてよかった」と思えるツールを目指している。2005年のβ版のリリースから早20年。今やエンジニアやデザイナーなど143万人が利用する人気のプロジェクト・タスク管理ツールとなった。国内外での受賞歴があり、海外のユーザー拡大も狙う。なぜ、Backlogはこれほどの支持を得られたのか。プロダクトマネージャー(PdM)の吉澤 毅氏に、「サービスの強み」
Article・2025.04.08会員数143万人のプロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」 PdMに聞くサービスの強みヌーラボ社(福岡市)が提供する「Backlog」は、チームで働く全ての人をターゲットに、「親しみやすい操作性」や「多機能」を追求。「このチームで仕事ができてよかった」と思えるツールを目指している。2005年のβ版のリリースから早20年。今やエンジニアやデザイナーなど143万人が利用する人気のプロジェクト・タスク管理ツールとなった。国内外での受賞歴があり、海外のユーザー拡大も狙う。なぜ、Backlogはこれほどの支持を得られたのか。プロダクトマネージャー(PdM)の吉澤 毅氏に、「サービスの強み」 Article・2025.04.03情報発信のハードルが高いと感じるデザイナーには、「今の自分をプロトタイプで表現する」と考えてほしい活発に情報発信をする企業として知られる株式会社マネーフォワード。当初は「採用」のための認知を目的に始まったnoteでの発信は、「今ではデザイナーの暗黙知を形式知化する取り組みへと発展している」とCDOの伊藤セルジオ大輔さんは話します。KPIを設けずにメンバーの自由な発信を大切にしていることや情報発信を始めるときのアドバイスについて、伊藤さんに聞きました。―― マネーフォワードのデザイン組織において、情報発信を始めたきっかけや目的を教えてください。2019年頃、マネーフォワードの事業や組織が拡大す
Article・2025.04.03情報発信のハードルが高いと感じるデザイナーには、「今の自分をプロトタイプで表現する」と考えてほしい活発に情報発信をする企業として知られる株式会社マネーフォワード。当初は「採用」のための認知を目的に始まったnoteでの発信は、「今ではデザイナーの暗黙知を形式知化する取り組みへと発展している」とCDOの伊藤セルジオ大輔さんは話します。KPIを設けずにメンバーの自由な発信を大切にしていることや情報発信を始めるときのアドバイスについて、伊藤さんに聞きました。―― マネーフォワードのデザイン組織において、情報発信を始めたきっかけや目的を教えてください。2019年頃、マネーフォワードの事業や組織が拡大す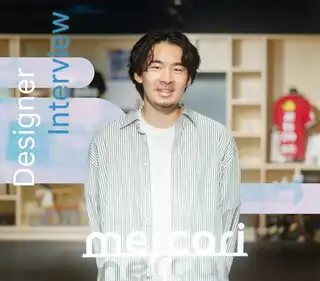 Article・2025.01.22メルカリ唯一のUXライターが語る「ブランド体験とわかりやすさをロジ�カルに追求するUXライティング」近年「UXライター」という肩書きを目にすることが増えたが、実際にUXライターがいる企業はまだ少数。多くの企業では、デザイナーやプロダクトマネージャーが感覚を頼りにUXライティングを担っているのが現状だ。今回はメルカリ唯一のUXライター・小川洸生さんに、UXライティングで自社らしさを出すコツや、UXライティングガイドライン策定の背景について話を伺った。編集プロダクションなどで、編集者・ライターとして働いていた小川さんは、2019年エディターとしてメルカリに入社した。当初の仕事は、アプリの使い方や出
Article・2025.01.22メルカリ唯一のUXライターが語る「ブランド体験とわかりやすさをロジ�カルに追求するUXライティング」近年「UXライター」という肩書きを目にすることが増えたが、実際にUXライターがいる企業はまだ少数。多くの企業では、デザイナーやプロダクトマネージャーが感覚を頼りにUXライティングを担っているのが現状だ。今回はメルカリ唯一のUXライター・小川洸生さんに、UXライティングで自社らしさを出すコツや、UXライティングガイドライン策定の背景について話を伺った。編集プロダクションなどで、編集者・ライターとして働いていた小川さんは、2019年エディターとしてメルカリに入社した。当初の仕事は、アプリの使い方や出 Article・2025.01.16「現実の枠内で考えよ!」サーキュラー建築のパイオニア、トーマス・ラウ氏が説く、クリエイティブな発想の作り方大阪・関西万博のオランダパビリオンをデザインした建築家のトーマス・ラウ氏は、イノベーションを生み出す思想家としても知られています。照明や家電などを貸し出す「サービスとしての製品(Product as a Service)」や、資材を循環させる「サーキュラー建築」など、彼のアイデアは業界を超えて広がり、限りある資源を図書館の本のように回すサーキュラーエコノミーへのムーブメン��トを作りました。数々の画期的なアイデアはどのように生まれたのでしょうか。また、そのアイデアを形にするにはどうすればいいのでしょ
Article・2025.01.16「現実の枠内で考えよ!」サーキュラー建築のパイオニア、トーマス・ラウ氏が説く、クリエイティブな発想の作り方大阪・関西万博のオランダパビリオンをデザインした建築家のトーマス・ラウ氏は、イノベーションを生み出す思想家としても知られています。照明や家電などを貸し出す「サービスとしての製品(Product as a Service)」や、資材を循環させる「サーキュラー建築」など、彼のアイデアは業界を超えて広がり、限りある資源を図書館の本のように回すサーキュラーエコノミーへのムーブメン��トを作りました。数々の画期的なアイデアはどのように生まれたのでしょうか。また、そのアイデアを形にするにはどうすればいいのでしょ Article・2025.01.14Z世代がハマる「Jiffcy」の開発者に聞く ― コアなユーザー体験を突き詰めLINEにない価値を創出2021年末に誕生したテキスト通話アプリ「Jiffcy(ジフシー)」の注目度が上昇している。電話のように相手を呼��び出した後、リアルタイムでテキストのやり取りをするというシンプルな機能性だが、「これまでにない体験ができる」としてα・Z世代を中心に利用者が増えているのだ。2024年10月にはロゴ・アイコン・アプリデザインを刷新、かつ機能性をシンプルに絞り込むリブランディングを実施。2024年11月1日発売の「日経トレンディ2024年12月号」では、「2025年ヒット予測ベスト30」で10位にランクイ
Article・2025.01.14Z世代がハマる「Jiffcy」の開発者に聞く ― コアなユーザー体験を突き詰めLINEにない価値を創出2021年末に誕生したテキスト通話アプリ「Jiffcy(ジフシー)」の注目度が上昇している。電話のように相手を呼��び出した後、リアルタイムでテキストのやり取りをするというシンプルな機能性だが、「これまでにない体験ができる」としてα・Z世代を中心に利用者が増えているのだ。2024年10月にはロゴ・アイコン・アプリデザインを刷新、かつ機能性をシンプルに絞り込むリブランディングを実施。2024年11月1日発売の「日経トレンディ2024年12月号」では、「2025年ヒット予測ベスト30」で10位にランクイ Article・2024.12.19ケーキ職人からCDOへ ― 納得感と貢献感を軸に異なる領域へ挑戦し続けるデザイナーのキャリア進化の速いデジタルプロダクト領域のCDOのキャリアを深掘りします。今回はケーキ職人からデザインの道へ、そして現在は株式会社プレイドでCDOという異色のキャリアを切り拓いた鈴木健一さんに、これまでのキャリア変遷とキャリア形成のヒントを伺いました。デザイナーの方はもちろん、これからデザイナーを目指したい方もこの記事を読んでご自身のキャリアの参考にしてみてはいかがでしょうか?―― 現在はCDOとしてどのようなお仕事をされていますか?CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」などのプロダクトを通して
Article・2024.12.19ケーキ職人からCDOへ ― 納得感と貢献感を軸に異なる領域へ挑戦し続けるデザイナーのキャリア進化の速いデジタルプロダクト領域のCDOのキャリアを深掘りします。今回はケーキ職人からデザインの道へ、そして現在は株式会社プレイドでCDOという異色のキャリアを切り拓いた鈴木健一さんに、これまでのキャリア変遷とキャリア形成のヒントを伺いました。デザイナーの方はもちろん、これからデザイナーを目指したい方もこの記事を読んでご自身のキャリアの参考にしてみてはいかがでしょうか?―― 現在はCDOとしてどのようなお仕事をされていますか?CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」などのプロダクトを通して Article・2024.11.26インクルーシブデザインを実現するには? 豊富な実績を持つ「CULUMU」に制作手法を聞いたイギリス・ロンドン発祥の「インクルーシブデザイン」�は、障がいがある人や多様なバックグラウンドを持つ人、高齢者など従来の製品やサービスから排除されてきた人たちをデザインプロセスの上流から巻き込み、共創する手法とされる。現在はより広義な意味合いで使われており、身体的、認知的、感覚的、言語的、文化的な多様性に考慮するデザインプロセスやそのデザイン自体、サービスを社会実装する際の配慮なども含めて「インクルーシブデザイン」と呼ぶそうだ。インクルーシブデザインの重要性は認識していても、いざデザインに落とし込
Article・2024.11.26インクルーシブデザインを実現するには? 豊富な実績を持つ「CULUMU」に制作手法を聞いたイギリス・ロンドン発祥の「インクルーシブデザイン」�は、障がいがある人や多様なバックグラウンドを持つ人、高齢者など従来の製品やサービスから排除されてきた人たちをデザインプロセスの上流から巻き込み、共創する手法とされる。現在はより広義な意味合いで使われており、身体的、認知的、感覚的、言語的、文化的な多様性に考慮するデザインプロセスやそのデザイン自体、サービスを社会実装する際の配慮なども含めて「インクルーシブデザイン」と呼ぶそうだ。インクルーシブデザインの重要性は認識していても、いざデザインに落とし込 Article・2024.11.21ジャンプのタテマンガアプリ 「ジャンプTOON 」 の開発秘話を聞く。"大胆な作品訴求"や"世界観の演出"で差別化2024年5月、集英社は縦読みマンガアプリ「ジャンプTOON(トゥーン)」をリリースした。同社が築いてきた「週刊少年ジャンプ(以下、ジャンプ)」、及びマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」のブランド力を武器に、近年盛況な縦読みマンガ市場へ参入したという。「ジャンプTOONには、どんな狙いがあり、競合他社のサービスとどうUI・UXの差別化を図っているのか。同アプリの統括編集長 浅田貴典氏と開発を担当したサイバーエージェント社の開発チームに取材した。サムネイル:(左)©ジャンプTOON/集英社、(右)『ラ
Article・2024.11.21ジャンプのタテマンガアプリ 「ジャンプTOON 」 の開発秘話を聞く。"大胆な作品訴求"や"世界観の演出"で差別化2024年5月、集英社は縦読みマンガアプリ「ジャンプTOON(トゥーン)」をリリースした。同社が築いてきた「週刊少年ジャンプ(以下、ジャンプ)」、及びマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」のブランド力を武器に、近年盛況な縦読みマンガ市場へ参入したという。「ジャンプTOONには、どんな狙いがあり、競合他社のサービスとどうUI・UXの差別化を図っているのか。同アプリの統括編集長 浅田貴典氏と開発を担当したサイバーエージェント社の開発チームに取材した。サムネイル:(左)©ジャンプTOON/集英社、(右)『ラ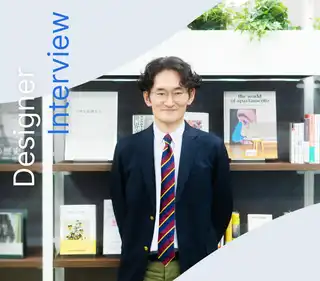 Article・2024.10.09元フリーターでバンドマン。異色の経歴をもつデジタル庁プロダクトデザイナーが描く未来2024年9月1日で、設立3年を迎えたデジタル庁。「誰一人取り残されない、人にやさしいデジタル社会の実現」を目指し、「Visit Japan Web」「ワクチン接種証明書アプリ」「マイナポータル」などの行政サービスを手がける。今回話を聞くのは、金成奎(きん・せいけい)さん。デジタルサービスのデザインやユーザー体験の設計に携わるプロダクトデザイナーだ。30歳からデザイナーとして歩み始め、民間企業でビジュアルデザインやアートディレクションを手がけていた金さんは、なぜデジタル庁に入庁したのか。これまで
Article・2024.10.09元フリーターでバンドマン。異色の経歴をもつデジタル庁プロダクトデザイナーが描く未来2024年9月1日で、設立3年を迎えたデジタル庁。「誰一人取り残されない、人にやさしいデジタル社会の実現」を目指し、「Visit Japan Web」「ワクチン接種証明書アプリ」「マイナポータル」などの行政サービスを手がける。今回話を聞くのは、金成奎(きん・せいけい)さん。デジタルサービスのデザインやユーザー体験の設計に携わるプロダクトデザイナーだ。30歳からデザイナーとして歩み始め、民間企業でビジュアルデザインやアートディレクションを手がけていた金さんは、なぜデジタル庁に入庁したのか。これまで Article・2024.09.06「働きがいのある会社」を受賞、フィンランド発「Reaktor Japan」が実践する、“北欧流”の働き方2000年にフィンランドで創業したテクノロジーコンサルティングファームReaktor(リアクター)。その日本支社として2014年に誕生したのが、Reaktor Japanです。同社では、フィンランド本社で導入しているアジャイル開発や自律性の高い組織体制をベースに、日本の商習慣にフィットするようアレンジして日本市場のクライアントへの提供価値最大化を推進すると同時に、社員の「働きがい」を追求。2024年には、世界最大級の意識調査機関であるGreat Place To Work®が発表した「働きがいの
Article・2024.09.06「働きがいのある会社」を受賞、フィンランド発「Reaktor Japan」が実践する、“北欧流”の働き方2000年にフィンランドで創業したテクノロジーコンサルティングファームReaktor(リアクター)。その日本支社として2014年に誕生したのが、Reaktor Japanです。同社では、フィンランド本社で導入しているアジャイル開発や自律性の高い組織体制をベースに、日本の商習慣にフィットするようアレンジして日本市場のクライアントへの提供価値最大化を推進すると同時に、社員の「働きがい」を追求。2024年には、世界最大級の意識調査機関であるGreat Place To Work®が発表した「働きがいの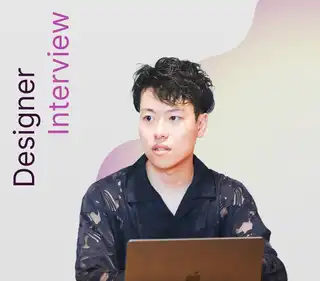 Article・2024.08.14生成AIとデザイナーの向き合い方。「自己否定を受け入れる」大切さ生成AIはUXデザイナーにとってどんな存在たりうるのか? 今回はAI戦略や体験設計も担当するエクスペリエンス・デザイナー・川村将太(しょーてぃー)さんに、「生成AIとデザイン業界」についてインタビューし、デザイン業界への生成AIの影響や向き合い方についてお話を伺いました。デザイナーの集まるコミュニティ「Designer's HYGGE」の運営にも携わっている川村さん。こちらの記事では「デザイナーとコミュニティ」についてたっぷりお話いただいてます。―― デザイン業界での生成AIの活用状況はいかがで
Article・2024.08.14生成AIとデザイナーの向き合い方。「自己否定を受け入れる」大切さ生成AIはUXデザイナーにとってどんな存在たりうるのか? 今回はAI戦略や体験設計も担当するエクスペリエンス・デザイナー・川村将太(しょーてぃー)さんに、「生成AIとデザイン業界」についてインタビューし、デザイン業界への生成AIの影響や向き合い方についてお話を伺いました。デザイナーの集まるコミュニティ「Designer's HYGGE」の運営にも携わっている川村さん。こちらの記事では「デザイナーとコミュニティ」についてたっぷりお話いただいてます。―― デザイン業界での生成AIの活用状況はいかがで Article・2024.08.08受賞歴多数の「Garden Eight」 国際的に評価される表現はどのように生まれるのか。CEO・野間寛貴氏に聞く前身のウェブ制作会社「レターズ」を経て、2011年から活動しているデジタルデザインスタジオ「Garden Eight」。国際的にすぐれたウェブサイトを表彰するAwwwardsやFWAなど多くの受賞歴があり、業界内で注目度の高い企業の一つです。創業当時から現在も7名と少数精鋭を貫く同社は、どのようにして国内外で評価される実績を輩出してきたのか。下北沢にあるオフィスを訪ね、CEOの野間寛貴氏にインタビューしました。―― 現在の運営体制を教えてください。創業当時からメンバーは、ほぼ変わりません。現在は
Article・2024.08.08受賞歴多数の「Garden Eight」 国際的に評価される表現はどのように生まれるのか。CEO・野間寛貴氏に聞く前身のウェブ制作会社「レターズ」を経て、2011年から活動しているデジタルデザインスタジオ「Garden Eight」。国際的にすぐれたウェブサイトを表彰するAwwwardsやFWAなど多くの受賞歴があり、業界内で注目度の高い企業の一つです。創業当時から現在も7名と少数精鋭を貫く同社は、どのようにして国内外で評価される実績を輩出してきたのか。下北沢にあるオフィスを訪ね、CEOの野間寛貴氏にインタビューしました。―― 現在の運営体制を教えてください。創業当時からメンバーは、ほぼ変わりません。現在は Article・2024.07.31デザイナーが横のつながりをつくるには?コミュニティ運営を続けて気づいた「居心地と知識」の壁今回は、デザイナーの集まるコミュニティ「Designer's HYGGE」の運営に携わる川村将太さんに、「デザイナーとコミュニティ」についてお話を伺いました。デザイナーにとってコミュニティは必要なのか? 参加するための課題とは? たっぷりお話いただいてます。「Designer's HYGGE」はデザイン好きが集まって会話を楽しむコミュニティ。経験や年齢は一切不問で、デザインにまつわる雑談を楽しむ集まりです。毎月末、20時からオンラインワークスペース「Nework」上で開催されており、テーマごとに
Article・2024.07.31デザイナーが横のつながりをつくるには?コミュニティ運営を続けて気づいた「居心地と知識」の壁今回は、デザイナーの集まるコミュニティ「Designer's HYGGE」の運営に携わる川村将太さんに、「デザイナーとコミュニティ」についてお話を伺いました。デザイナーにとってコミュニティは必要なのか? 参加するための課題とは? たっぷりお話いただいてます。「Designer's HYGGE」はデザイン好きが集まって会話を楽しむコミュニティ。経験や年齢は一切不問で、デザインにまつわる雑談を楽しむ集まりです。毎月末、20時からオンラインワークスペース「Nework」上で開催されており、テーマごとに Article・2024.07.29「タイミー」のプロダクトデザイナーが公開した「自分の取扱説明書」。 社内における自己開示の大切さとは?新しい環境に身を置く際、自身の仕事の進め方が周囲と合わなかったり、 顔合わせの度に自己紹介を繰り返したりとストレスを感じる方も多いかもしれません。スキマバイトアプリ「タイミー」でプロダクトデザインのマネージャーとしてご活躍中の横田泰広さんは、22項目にわたる「私の取扱説明書」を作成。コミュニケーション・態度効率化・プロセス改善過去に受けたフィードバックなど、自身の仕事に対する姿勢や進め方などをまとめています。「取扱説明書」を開示することによる反響は? なぜ「取扱説明書」の作成に至ったのか? 自己
Article・2024.07.29「タイミー」のプロダクトデザイナーが公開した「自分の取扱説明書」。 社内における自己開示の大切さとは?新しい環境に身を置く際、自身の仕事の進め方が周囲と合わなかったり、 顔合わせの度に自己紹介を繰り返したりとストレスを感じる方も多いかもしれません。スキマバイトアプリ「タイミー」でプロダクトデザインのマネージャーとしてご活躍中の横田泰広さんは、22項目にわたる「私の取扱説明書」を作成。コミュニケーション・態度効率化・プロセス改善過去に受けたフィードバックなど、自身の仕事に対する姿勢や進め方などをまとめています。「取扱説明書」を開示することによる反響は? なぜ「取扱説明書」の作成に至ったのか? 自己 Article・2024.06.24ゆっくり、確かに夢に近づく。デザイナーの暮らしをつくる「ファイリング」の妙器や家具、身の回りのモノにこだわって丁寧に暮らしたいけど、仕事や子育て、その他にとにかく時間がなくて、なかなか環境が整えられない。仕事も子育ても大事。でも自宅を居心地よく整えたりオン・オフをうまく切り替えられたりする時間も大切だと思うのです。京都在住のデザイナー・朝倉由美さんは、デザイナーの視点を生活に活かして活動を続けられています。美しい写真で構成されるブログに綴られるのは、丁寧にモノを選ぶプロセス。リビングにも馴染むオフィスチェアーを探してITOKIの「vertebra03」にたどり着いてか
Article・2024.06.24ゆっくり、確かに夢に近づく。デザイナーの暮らしをつくる「ファイリング」の妙器や家具、身の回りのモノにこだわって丁寧に暮らしたいけど、仕事や子育て、その他にとにかく時間がなくて、なかなか環境が整えられない。仕事も子育ても大事。でも自宅を居心地よく整えたりオン・オフをうまく切り替えられたりする時間も大切だと思うのです。京都在住のデザイナー・朝倉由美さんは、デザイナーの視点を生活に活かして活動を続けられています。美しい写真で構成されるブログに綴られるのは、丁寧にモノを選ぶプロセス。リビングにも馴染むオフィスチェアーを探してITOKIの「vertebra03」にたどり着いてか