#心理学
「心理学」に関連する記事一覧
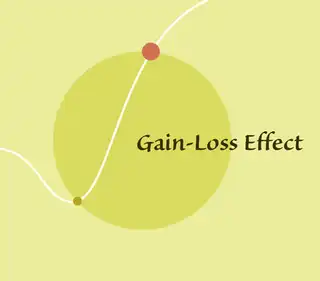 Article・2024.02.11ゲインロス効果とは?人に対する評価の変動が印象形成に与える影響ゲインロス効果とは、相手に対して初めにネガティブな印象を与えた上で、後からポジティブな印象を与えると、最終的な評価が強くポジティブなものになりやすいという現象です。1965年に、エリオット・アロンソンとダーウィン・リンダーが発見しました。具体的には、怖く見える人と話してみたら、実は優しい人だったことが分かって、好感度がぐっと高まることなどが挙�げられます。いわゆる「ギャップ萌え」のようなものと紹介されることが多いです。ただし、もともとゲインロス効果は、他者からの評価の変動に着目した実験が起源となっ
Article・2024.02.11ゲインロス効果とは?人に対する評価の変動が印象形成に与える影響ゲインロス効果とは、相手に対して初めにネガティブな印象を与えた上で、後からポジティブな印象を与えると、最終的な評価が強くポジティブなものになりやすいという現象です。1965年に、エリオット・アロンソンとダーウィン・リンダーが発見しました。具体的には、怖く見える人と話してみたら、実は優しい人だったことが分かって、好感度がぐっと高まることなどが挙�げられます。いわゆる「ギャップ萌え」のようなものと紹介されることが多いです。ただし、もともとゲインロス効果は、他者からの評価の変動に着目した実験が起源となっ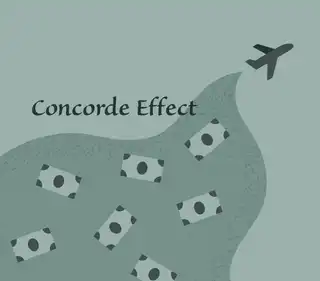 Article・2024.02.11コンコルド効果とは?ビジネスにおける4つの事例を紹介コンコルド効果とは、それまでに費やした費用や時間に対して「もったいない」という心理が働き、合理的な判断ができなくなる心理効果のことです。例えば、投資における「損切り」の難しさが良い例で、コンコルド効果が働いてしまうと非合理的な判断をしてしまい、損失が出ると分かっていてもなかなか投資をやめられません。その他、身近な例ではゲームのガチャ課金やギャンブルがやめられないのもコンコルド効果が働いている例です。コンコルド効果の名前の由来は、イギリスとフランスが共同開発した超音速旅客機のコンコルドが商業的失敗
Article・2024.02.11コンコルド効果とは?ビジネスにおける4つの事例を紹介コンコルド効果とは、それまでに費やした費用や時間に対して「もったいない」という心理が働き、合理的な判断ができなくなる心理効果のことです。例えば、投資における「損切り」の難しさが良い例で、コンコルド効果が働いてしまうと非合理的な判断をしてしまい、損失が出ると分かっていてもなかなか投資をやめられません。その他、身近な例ではゲームのガチャ課金やギャンブルがやめられないのもコンコルド効果が働いている例です。コンコルド効果の名前の由来は、イギリスとフランスが共同開発した超音速旅客機のコンコルドが商業的失敗 Article・2024.02.19ピーク・エンドの法則とは?ユーザーの記憶に残る具体的な事例を紹介ピーク・エンドの法則とは、人間がある出来事を記憶する際には、感情が大きく動いた「ピーク」と全体の終わり「エンド」が最も強く印象に残り、ほとんどそれらだけでその出来事の全体の印象が形作られるという法則です。1999年にダニエル・カーネマンが提唱しました。「終わりよければすべてよしの理論」ともいわれることがあります。ピーク・エンドの法則をうまくビジネスに活用すれば、顧客の記憶に残りやすくなり、良い印象を残すヒントとなりそうです。ちなみに、ピーク・エンドの法則はポジティブな印象だけに当てはまる法則では
Article・2024.02.19ピーク・エンドの法則とは?ユーザーの記憶に残る具体的な事例を紹介ピーク・エンドの法則とは、人間がある出来事を記憶する際には、感情が大きく動いた「ピーク」と全体の終わり「エンド」が最も強く印象に残り、ほとんどそれらだけでその出来事の全体の印象が形作られるという法則です。1999年にダニエル・カーネマンが提唱しました。「終わりよければすべてよしの理論」ともいわれることがあります。ピーク・エンドの法則をうまくビジネスに活用すれば、顧客の記憶に残りやすくなり、良い印象を残すヒントとなりそうです。ちなみに、ピーク・エンドの法則はポジティブな印象だけに当てはまる法則では Article・2024.02.11クレショフ効果とは?前後の視覚情報により解釈が変わる心理効果クレショフ効果とは、同じものでも前後に繋がる映像情報の違いにより、生じる印象や解釈が変わるという心理効果のことです。前後の情報に直接的な繋がりがなかったとしても、無意識に関連づけてしまうという人の心理にもとづいています。全ロシア映画大学で、映画作家・理論家であるレフ・クレショフが実験内で示したため、クレショフ効果と呼ばれています。レフ・クレショフは、認知心理学の視点からクレショフ効果を研究しました。実験では、ロシアの俳優イワン・モジューヒンのアップの映像を使い、この映像を下記3つの背景と組み合わ
Article・2024.02.11クレショフ効果とは?前後の視覚情報により解釈が変わる心理効果クレショフ効果とは、同じものでも前後に繋がる映像情報の違いにより、生じる印象や解釈が変わるという心理効果のことです。前後の情報に直接的な繋がりがなかったとしても、無意識に関連づけてしまうという人の心理にもとづいています。全ロシア映画大学で、映画作家・理論家であるレフ・クレショフが実験内で示したため、クレショフ効果と呼ばれています。レフ・クレショフは、認知心理学の視点からクレショフ効果を研究しました。実験では、ロシアの俳優イワン・モジューヒンのアップの映像を使い、この映像を下記3つの背景と組み合わ Article・2024.02.12ヴェブレン効果とは?高いものに魅力を感じる心理効果ヴェブレン効果とは、見せびらかすために高価なものを欲しがるといった心理効果です。自己顕示欲を満たすために高価なものを購入して見せびらかすことから、「見せびらかし消費」や「顕示的消費」とも呼ばれます。この効果は所得が高い人ほど働きやすく、高い商品ほど需要が増すのが特徴です。例えば、飛行機のファーストクラスやブラックカードなどは価値と希少性が高いため、ヴェブレン効果が働きやすいです。優先搭乗やラウンジなどの特典があることで、他の人たちと差別化することができ、自分のステータスの高さを強調できるからです
Article・2024.02.12ヴェブレン効果とは?高いものに魅力を感じる心理効果ヴェブレン効果とは、見せびらかすために高価なものを欲しがるといった心理効果です。自己顕示欲を満たすために高価なものを購入して見せびらかすことから、「見せびらかし消費」や「顕示的消費」とも呼ばれます。この効果は所得が高い人ほど働きやすく、高い商品ほど需要が増すのが特徴です。例えば、飛行機のファーストクラスやブラックカードなどは価値と希少性が高いため、ヴェブレン効果が働きやすいです。優先搭乗やラウンジなどの特典があることで、他の人たちと差別化することができ、自分のステータスの高さを強調できるからです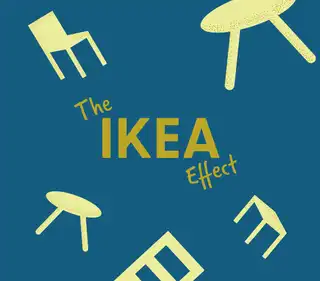 Article・2024.02.16イケア効果とは?自分で作ることで生まれるモノへの特別な愛着イケア効果とは、自分で作って完成させたものには特別な愛着が生まれ、より価値が高く感じられるという認知バイアスのことです。イケア効果は、自分で家具を組み立てて完成させる「IKEA」のビジネスモデルに由来しています。IKEAの家具を購入する際、ほとんどの商品が分解された状態で販売されています。分解されている家具を消費者自身が組み立てることで、完成した家具への愛着が増して特別な価値を感じるのがイケア効果です。イケア効果について、実際の研究より読み解いていきましょう。Michael I. Norton氏
Article・2024.02.16イケア効果とは?自分で作ることで生まれるモノへの特別な愛着イケア効果とは、自分で作って完成させたものには特別な愛着が生まれ、より価値が高く感じられるという認知バイアスのことです。イケア効果は、自分で家具を組み立てて完成させる「IKEA」のビジネスモデルに由来しています。IKEAの家具を購入する際、ほとんどの商品が分解された状態で販売されています。分解されている家具を消費者自身が組み立てることで、完成した家具への愛着が増して特別な価値を感じるのがイケア効果です。イケア効果について、実際の研究より読み解いていきましょう。Michael I. Norton氏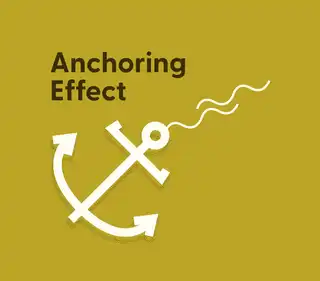 Article・2024.02.16アンカリング効果とは?初めに見た数値がその後の判断を変える心理現象アンカリング効果とは、人が最初に得た情報にその後の判断が影響されてしまう心理現象です。その人のそれまでの経験や先入観が影響して、合理的でない判断をしてしまう「認知バイアス」の1つです。「アンカリング・バイアス」と呼ばれることもあります。ちなみに、アンカリング効果の語源となる「アンカー(人が一番最初に受け取る情報)」には「錨(いかり)」という意味があります。「アンカリング」は「船舶を錨を使って係留すること」という意味です。錨を海に降ろして船がその場にとどまる様子と、人間の判断が最初に得た情報の一��定
Article・2024.02.16アンカリング効果とは?初めに見た数値がその後の判断を変える心理現象アンカリング効果とは、人が最初に得た情報にその後の判断が影響されてしまう心理現象です。その人のそれまでの経験や先入観が影響して、合理的でない判断をしてしまう「認知バイアス」の1つです。「アンカリング・バイアス」と呼ばれることもあります。ちなみに、アンカリング効果の語源となる「アンカー(人が一番最初に受け取る情報)」には「錨(いかり)」という意味があります。「アンカリング」は「船舶を錨を使って係留すること」という意味です。錨を海に降ろして船がその場にとどまる様子と、人間の判断が最初に得た情報の一��定 Article・2024.02.16フレーミング効果で印象はガラッと変わる!効果的なマーケティング手法を解説フレーミング効果とは、同じ情報であっても表現の仕方が違うと、その情報にもとづいた受け手の意思決定内容が変わるといった認知バイアスのことです。損失を避けたいという心理的な傾向により、フレーミング効果の認知バイアスが働きます。B J McNeil氏らが行った以下の研究を具体例としてあげてみましょう。被験者には、自分が肺がんにかかっていると想像してもらい、治療に「手術」と「放射線治療」のどちらかを選択してもらうという実験です。実験では、被験者を2つのグループに分け、それぞれのグループに「手術をした場合
Article・2024.02.16フレーミング効果で印象はガラッと変わる!効果的なマーケティング手法を解説フレーミング効果とは、同じ情報であっても表現の仕方が違うと、その情報にもとづいた受け手の意思決定内容が変わるといった認知バイアスのことです。損失を避けたいという心理的な傾向により、フレーミング効果の認知バイアスが働きます。B J McNeil氏らが行った以下の研究を具体例としてあげてみましょう。被験者には、自分が肺がんにかかっていると想像してもらい、治療に「手術」と「放射線治療」のどちらかを選択してもらうという実験です。実験では、被験者を2つのグループに分け、それぞれのグループに「手術をした場合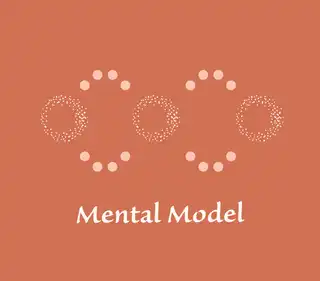 Article・2024.02.11メンタルモデルとは?ユーザー心理の調査方法や活用シーンを解説メンタルモデルとは、個人の頭の中に存在��する実世界に対する認識や解釈に関する認知モデルで、認知心理学の用語です。メンタルモデルは個人の過去の経験などに結びつき、価値観に基づいてできあがるものとされています。たとえば「犬は可愛い動物」というメンタルモデルを持っている人もいれば、「犬は怖い動物」というメンタルモデルを持っている人がいます。後者の場合、もしかすると子どもの頃、犬に追いかけられて噛まれた経験があるのかもしれません。この違いは、今まで犬とどのように触れ合ってきたか、という経験によって変わるこ
Article・2024.02.11メンタルモデルとは?ユーザー心理の調査方法や活用シーンを解説メンタルモデルとは、個人の頭の中に存在��する実世界に対する認識や解釈に関する認知モデルで、認知心理学の用語です。メンタルモデルは個人の過去の経験などに結びつき、価値観に基づいてできあがるものとされています。たとえば「犬は可愛い動物」というメンタルモデルを持っている人もいれば、「犬は怖い動物」というメンタルモデルを持っている人がいます。後者の場合、もしかすると子どもの頃、犬に追いかけられて噛まれた経験があるのかもしれません。この違いは、今まで犬とどのように触れ合ってきたか、という経験によって変わるこ Article・2024.02.21心の奥に眠る「深層心理」とは?本音がわかるニューロマーケティング深層心理とは、心の表面上(表層心理)では気付かない、つまり無意識に存在する心理状態です。深層心理は自覚しづらく、心の奥底に存在するとされています。深層心理に関する研究や学問を「深層心理学」と呼びますが、この分野ではジークムント・フロイトやカール・グスタフ・ユングなどの研究者が活躍しました。彼らは、深層心理が人間の行動や決定に大きな影響を及ぼしているという発見をしたのです。この発見は、心理学の分野だけでなく、文学・哲学など多岐にわたる分野に大きな影響を与えました。深層心理と潜在意識は同じものだと思
Article・2024.02.21心の奥に眠る「深層心理」とは?本音がわかるニューロマーケティング深層心理とは、心の表面上(表層心理)では気付かない、つまり無意識に存在する心理状態です。深層心理は自覚しづらく、心の奥底に存在するとされています。深層心理に関する研究や学問を「深層心理学」と呼びますが、この分野ではジークムント・フロイトやカール・グスタフ・ユングなどの研究者が活躍しました。彼らは、深層心理が人間の行動や決定に大きな影響を及ぼしているという発見をしたのです。この発見は、心理学の分野だけでなく、文学・哲学など多岐にわたる分野に大きな影響を与えました。深層心理と潜在意識は同じものだと思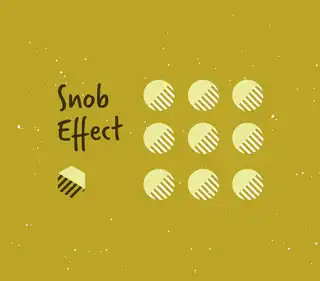 Article・2024.02.21スノッブ効果とは?他人と被るのは嫌という心理が需要に与える影響スノッブ効果(snob effect)とは “他の人が持っているものと同じモノは欲しくない”という心理から、大勢の人が所有するモノに対して個人の購買意欲や需要が減少してしまうという現象です。主に行動経済学やマーケティングの領域で用いられている用語です。提唱したのは、アメリカの理論経済学者であるハーヴェイ・ライベンシュタインです。彼が1950年に発表した論文「消費者需要理論におけるバンドワゴン効果、スノッブ効果、及びヴェブレン効果(Bandwagon, Snob and Veblen Effect
Article・2024.02.21スノッブ効果とは?他人と被るのは嫌という心理が需要に与える影響スノッブ効果(snob effect)とは “他の人が持っているものと同じモノは欲しくない”という心理から、大勢の人が所有するモノに対して個人の購買意欲や需要が減少してしまうという現象です。主に行動経済学やマーケティングの領域で用いられている用語です。提唱したのは、アメリカの理論経済学者であるハーヴェイ・ライベンシュタインです。彼が1950年に発表した論文「消費者需要理論におけるバンドワゴン効果、スノッブ効果、及びヴェブレン効果(Bandwagon, Snob and Veblen Effect Article・2024.02.11ディドロ効果とは?身の回りのものを一新したくなる心理効果ディドロ効果(diderot effect)とは、新しく購入した商品やサービスによって理想的な価値を得たとき、その価値に合わせてこれまでの生活環境や身の回りのものを一新したくなるような、連鎖的な消費喚起を生じさせる心理現象のことです。たとえば何か新しいものを購入したとき、その商品に合わせてほかのものも一緒に買い替えたという経験はありませんか。これまでもっていなかったような少し高価なソファが気に入って新しく購入してみたところ、今まで部屋にあったカーテンやほかの家具が急に見劣りして見えてきてすべて買
Article・2024.02.11ディドロ効果とは?身の回りのものを一新したくなる心理効果ディドロ効果(diderot effect)とは、新しく購入した商品やサービスによって理想的な価値を得たとき、その価値に合わせてこれまでの生活環境や身の回りのものを一新したくなるような、連鎖的な消費喚起を生じさせる心理現象のことです。たとえば何か新しいものを購入したとき、その商品に合わせてほかのものも一緒に買い替えたという経験はありませんか。これまでもっていなかったような少し高価なソファが気に入って新しく購入してみたところ、今まで部屋にあったカーテンやほかの家具が急に見劣りして見えてきてすべて買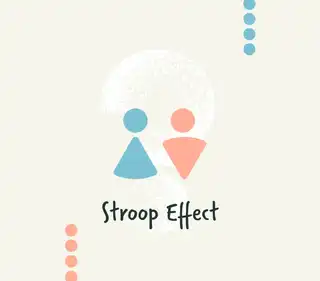 Article・2024.02.11ストループ効果とは?色と文字が一致しないと脳が混乱するのはなぜ?ストループ効果(stroop effect)とは、色から得られる情報と文字から得られる情報が一致せずにくい違って表示されている場合、情報を処理して理解するために時間がかかり、すぐに反応することが難しくなる現象のことです。たとえば赤インクでプリントされた「赤」という文字を呈示されて、「文字の色を答えてください」と聞かれたら、私たちはすぐに「赤です」と答えることができるでしょう。しかし、赤インクでプリントされた「青」という文字を呈示されて、文字の色を答えようとする場合には、文字と色が一致している場合
Article・2024.02.11ストループ効果とは?色と文字が一致しないと脳が混乱するのはなぜ?ストループ効果(stroop effect)とは、色から得られる情報と文字から得られる情報が一致せずにくい違って表示されている場合、情報を処理して理解するために時間がかかり、すぐに反応することが難しくなる現象のことです。たとえば赤インクでプリントされた「赤」という文字を呈示されて、「文字の色を答えてください」と聞かれたら、私たちはすぐに「赤です」と答えることができるでしょう。しかし、赤インクでプリントされた「青」という文字を呈示されて、文字の色を答えようとする場合には、文字と色が一致している場合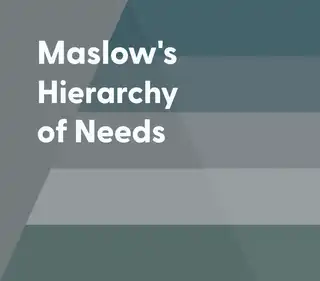 Article・2024.03.22マズローの欲求5段階説とは?分類の図解とビジネスでの活用事例紹介マズローの欲求5段階説は、心理学者アブラハム・マズローによって提唱された理論です。人間の欲求を「生理的欲求」「安全の欲求」「社会的欲求」「承認欲求」「自己実現の欲求」の5段階に分けたもので、人々が生きていく上で感じる欲求やニーズが、特定の順序で満たされるという前提で考えられました。この欲求はピラミッド状になっており、低い階層の欲求が満たされることによって次の段階の欲求を求めるようになります。この理論を理解することで、人々の行動や心理背景を深く掴むことができ、ビジネスやマーケティングの現場でも有効
Article・2024.03.22マズローの欲求5段階説とは?分類の図解とビジネスでの活用事例紹介マズローの欲求5段階説は、心理学者アブラハム・マズローによって提唱された理論です。人間の欲求を「生理的欲求」「安全の欲求」「社会的欲求」「承認欲求」「自己実現の欲求」の5段階に分けたもので、人々が生きていく上で感じる欲求やニーズが、特定の順序で満たされるという前提で考えられました。この欲求はピラミッド状になっており、低い階層の欲求が満たされることによって次の段階の欲求を求めるようになります。この理論を理解することで、人々の行動や心理背景を深く掴むことができ、ビジネスやマーケティングの現場でも有効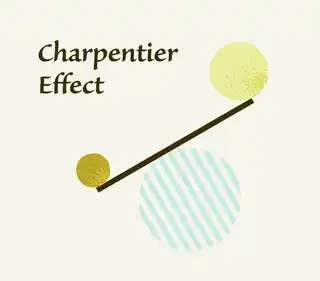 Article・2024.02.11シャルパンティエ効果とは? 人の知覚と物理的な世界にズレを生む心理現象シャルパンテイエ効果(Charpentier effect)とは、”重さに対する感覚”が“見ための大きさ”に影響されて、体積が大きいものを軽く、小さいものを重いと感じてしまう心理的な錯覚のことです。たとえば同じ重さの大きな箱と小さな箱をそれぞれ持ち上げたとき、物理的に重さが等しい物であっても、私たちは視覚的に大きく見える箱のほうを軽く感じ、小さい箱のほうを重たく感じてしまいます。これは同じ質量の小さな物体と比較したときに大きな物体のほうの重さを過小評価してしまう、人の知覚と物理的な世界にズレが生
Article・2024.02.11シャルパンティエ効果とは? 人の知覚と物理的な世界にズレを生む心理現象シャルパンテイエ効果(Charpentier effect)とは、”重さに対する感覚”が“見ための大きさ”に影響されて、体積が大きいものを軽く、小さいものを重いと感じてしまう心理的な錯覚のことです。たとえば同じ重さの大きな箱と小さな箱をそれぞれ持ち上げたとき、物理的に重さが等しい物であっても、私たちは視覚的に大きく見える箱のほうを軽く感じ、小さい箱のほうを重たく感じてしまいます。これは同じ質量の小さな物体と比較したときに大きな物体のほうの重さを過小評価してしまう、人の知覚と物理的な世界にズレが生 Article・2024.02.11ゴルディロックス効果とは?真ん中の選択肢に人気が集中してしまう理由ゴルディロックス効果とは、選択肢が3つあった場合、多くの人が無意識のうちに真ん中の選択肢を選んでしまう傾向があるという心理現象のことです。たとえば同じ商品を異なる3つの価格帯で販売すると、真ん中の価格帯の商品が最もよく売れる傾向があります。1500円、1200円、980円と3つの価格のお弁当が並んでいたとしたら、いちばんよく出るのは真ん中の1200円になります。日本ではゴルディロックス効果は「松竹梅の法則」と呼ばれています。松竹梅の法則とはマーケティング業界などで用いられる用語で、松・竹・梅と3
Article・2024.02.11ゴルディロックス効果とは?真ん中の選択肢に人気が集中してしまう理由ゴルディロックス効果とは、選択肢が3つあった場合、多くの人が無意識のうちに真ん中の選択肢を選んでしまう傾向があるという心理現象のことです。たとえば同じ商品を異なる3つの価格帯で販売すると、真ん中の価格帯の商品が最もよく売れる傾向があります。1500円、1200円、980円と3つの価格のお弁当が並んでいたとしたら、いちばんよく出るのは真ん中の1200円になります。日本ではゴルディロックス効果は「松竹梅の法則」と呼ばれています。松竹梅の法則とはマーケティング業界などで用いられる用語で、松・竹・梅と3 Article・2024.02.11人が自分の能力を過大評価してしまうのは「平均以上効果」のせい?平均以上効果とは、「自分は他の人と比べて平均以上である」と過大評価してしまう心理傾向をさします。別名「レイク・ウォビゴン効果」とも呼ばれています。この名前はアメリカの執筆家であるギャリソン・キーラが作品『レイク・ウォビゴンの人々』で描いた架空の村「レイク・ウォビゴン」の記述に由来しています。『レイク・ウォビゴンの人々』は、村の住民は容姿が平均以上の美男美女であり、彼らの子どもたちも平均以上に優れているなどの「錯覚した意識をもっている」という設定の小説です。実際に人は誰でも自己評価�をするときは無意
Article・2024.02.11人が自分の能力を過大評価してしまうのは「平均以上効果」のせい?平均以上効果とは、「自分は他の人と比べて平均以上である」と過大評価してしまう心理傾向をさします。別名「レイク・ウォビゴン効果」とも呼ばれています。この名前はアメリカの執筆家であるギャリソン・キーラが作品『レイク・ウォビゴンの人々』で描いた架空の村「レイク・ウォビゴン」の記述に由来しています。『レイク・ウォビゴンの人々』は、村の住民は容姿が平均以上の美男美女であり、彼らの子どもたちも平均以上に優れているなどの「錯覚した意識をもっている」という設定の小説です。実際に人は誰でも自己評価�をするときは無意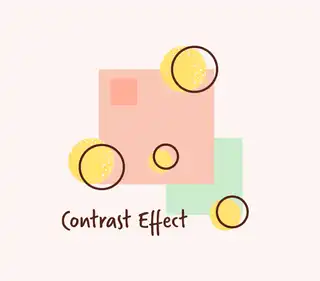 Article・2024.02.11対比効果とは?わざと売れにくい選択肢を生産する「捨て色」に見る応用例対比効果とは、人がものごとを評価する際に、同じものでも比較対象が変わると、その評価や印象に変化が生じる現象のことです。たとえば同じ色でも、背景の色が違うと明るさや彩度が違って見えたり、同じ大きさのアイテムでも、周囲の比較��物の大きさが変われば相対的な見た目の大きさが異なって映ります。また猛暑の炎天下で冷たい飲みものを飲むと、気温と飲みものの対比でのどごしの冷たさがよりいっそう際立って感じられることがあるでしょう。それも対比効果のひとつといえます。対比効果は別名コントラスト効果(Contrast e
Article・2024.02.11対比効果とは?わざと売れにくい選択肢を生産する「捨て色」に見る応用例対比効果とは、人がものごとを評価する際に、同じものでも比較対象が変わると、その評価や印象に変化が生じる現象のことです。たとえば同じ色でも、背景の色が違うと明るさや彩度が違って見えたり、同じ大きさのアイテムでも、周囲の比較��物の大きさが変われば相対的な見た目の大きさが異なって映ります。また猛暑の炎天下で冷たい飲みものを飲むと、気温と飲みものの対比でのどごしの冷たさがよりいっそう際立って感じられることがあるでしょう。それも対比効果のひとつといえます。対比効果は別名コントラスト効果(Contrast e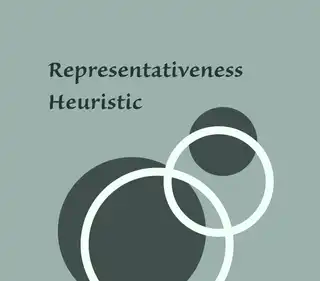 Article・2024.02.11��代表性ヒューリスティックとは?典型的イメージによる認知のバイアスヒューリスティック(Heuristic)とは、コンピュータ・サイエンスではアルゴリズム、行動経済学では意思決定をするときの理論を意味する言葉です。人は選択や意思決定をするとき、自分の経験則にもとづいて直感的な確率論で答えを出そうとする傾向をもっています。ヒューリスティックには種類があり、中でも重用視されているのが代表性ヒューリスティック(Representativeness heuristic)です。順を追って説明しましょう。人間は決して合理的な存在ではないため、直感や経験則をもとに意思決定をす
Article・2024.02.11��代表性ヒューリスティックとは?典型的イメージによる認知のバイアスヒューリスティック(Heuristic)とは、コンピュータ・サイエンスではアルゴリズム、行動経済学では意思決定をするときの理論を意味する言葉です。人は選択や意思決定をするとき、自分の経験則にもとづいて直感的な確率論で答えを出そうとする傾向をもっています。ヒューリスティックには種類があり、中でも重用視されているのが代表性ヒューリスティック(Representativeness heuristic)です。順を追って説明しましょう。人間は決して合理的な存在ではないため、直感や経験則をもとに意思決定をす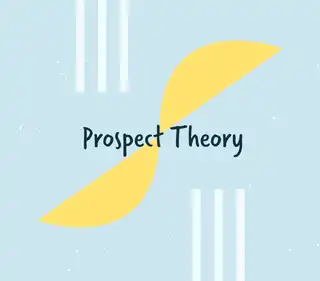 Article・2024.02.11人は「損失を嫌う」心の法則、プロスペクト理論についてプロスペクト理論(Prospect theory)とは、「富をめぐる人の心理」について分析した意思決定理論で、行動経済学の基礎に位置づけられる有名な研究です。プロスペクトは英語で見込みや可能性を意味する言葉で、人は不確かなリスクのある状況下では利益や損失に対する意思決定に認知のバイアスがかかりやすくなることが指摘されています。私たちは「利益はできるだけ早く確定したい」と願う一方で、「損失は先送りしたい」と考える傾向をもっており、得をしたときよりも損をしたときのほうが2〜3倍重く感じてしまうことが
Article・2024.02.11人は「損失を嫌う」心の法則、プロスペクト理論についてプロスペクト理論(Prospect theory)とは、「富をめぐる人の心理」について分析した意思決定理論で、行動経済学の基礎に位置づけられる有名な研究です。プロスペクトは英語で見込みや可能性を意味する言葉で、人は不確かなリスクのある状況下では利益や損失に対する意思決定に認知のバイアスがかかりやすくなることが指摘されています。私たちは「利益はできるだけ早く確定したい」と願う一方で、「損失は先送りしたい」と考える傾向をもっており、得をしたときよりも損をしたときのほうが2〜3倍重く感じてしまうことが Article・2024.02.11未完了のタスクが人の脳にもたらすツァイガルニク効果とは?ツァイガルニク効果(Zeigarnik effect)とは、未完了のタスクが人の脳に強い関心を引き起こす現象のことをさします。人は自分が達成できた事柄より、達成できなかった事柄や中断した事柄のほうが記憶に残りやすい傾向をもっています。またあるタスクを完了する前にやめてしまった場合、タスクが頭の中に残り続けてそれを完了することが強く求められるというのです。この現象は発見した心理学者の名前にちなんで、ツァイガルニック効果、ゼイガルニク効果、ゼイガルニック効果と呼ばれています。ツァイガルニク効果は、1
Article・2024.02.11未完了のタスクが人の脳にもたらすツァイガルニク効果とは?ツァイガルニク効果(Zeigarnik effect)とは、未完了のタスクが人の脳に強い関心を引き起こす現象のことをさします。人は自分が達成できた事柄より、達成できなかった事柄や中断した事柄のほうが記憶に残りやすい傾向をもっています。またあるタスクを完了する前にやめてしまった場合、タスクが頭の中に残り続けてそれを完了することが強く求められるというのです。この現象は発見した心理学者の名前にちなんで、ツァイガルニック効果、ゼイガルニク効果、ゼイガルニック効果と呼ばれています。ツァイガルニク効果は、1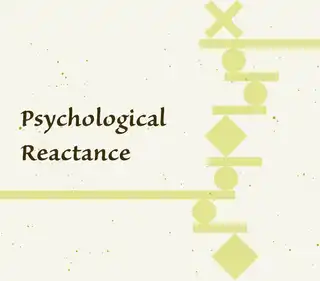 Article・2024.02.11心理的リアクタンスが教えてくれる、人が反発したくなるメカニズム心理的リアクタンス(Psychological reactance)とは、1966年にアメリカの心理学者であるジャック・ブレームが提唱した心理学理論で、人は自分が自由に選択できると思っていることに対して制限や強制をされてしまうと、抵抗や反発感情が生じる現象のことをさします。リアクタンスの語源は抵抗や反発を意味するリアクトという物理用語です。この現象にはどのような心理的な背景があるのでしょうか。人は生まれながらにして、自分の行動や選択は自分自身で決めたいという欲求をもっています。それを他人に決めら
Article・2024.02.11心理的リアクタンスが教えてくれる、人が反発したくなるメカニズム心理的リアクタンス(Psychological reactance)とは、1966年にアメリカの心理学者であるジャック・ブレームが提唱した心理学理論で、人は自分が自由に選択できると思っていることに対して制限や強制をされてしまうと、抵抗や反発感情が生じる現象のことをさします。リアクタンスの語源は抵抗や反発を意味するリアクトという物理用語です。この現象にはどのような心理的な背景があるのでしょうか。人は生まれながらにして、自分の行動や選択は自分自身で決めたいという欲求をもっています。それを他人に決めら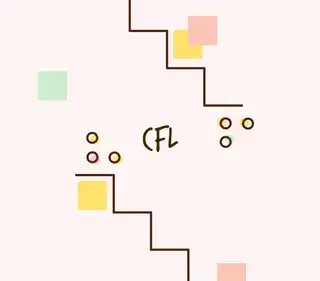 Article・2024.02.09ヒトは苦労して手に入れたものに価値を感じる?コントラフリーローディング効果を利用したデザイン私たちは「面倒くさいこと」が嫌いだ。 できることならなるべく早く、簡単に、苦労せず、欲しいものを手に入れたいと願っている。しかし、実際私たちの脳内はこれと全く逆なのです。今回は、そんな矛盾した脳の認知バイアスであるコントラフリーローディング効果(CFL) を上手く利用しているデザイン事例をご紹��介します。まず、コントラフリーローディング効果(CFL) について解説しましょう。ある実験で、レバーを押すと食事がでてくる仕組みを学習させたマウスの前に、皿に入った餌とレバーを押すと出てくる仕組みを設けた餌
Article・2024.02.09ヒトは苦労して手に入れたものに価値を感じる?コントラフリーローディング効果を利用したデザイン私たちは「面倒くさいこと」が嫌いだ。 できることならなるべく早く、簡単に、苦労せず、欲しいものを手に入れたいと願っている。しかし、実際私たちの脳内はこれと全く逆なのです。今回は、そんな矛盾した脳の認知バイアスであるコントラフリーローディング効果(CFL) を上手く利用しているデザイン事例をご紹��介します。まず、コントラフリーローディング効果(CFL) について解説しましょう。ある実験で、レバーを押すと食事がでてくる仕組みを学習させたマウスの前に、皿に入った餌とレバーを押すと出てくる仕組みを設けた餌 Article・2024.02.11ジョハリの窓とは?4つの自己を分析するワークのやり方ジョハリの窓とは、1955年にアメリカ・サンフランシスコ州立大学の心理学者、ジョセフ・ルフトとハリー・インガムが発表した、対人関係における気づきのグラフモデルのことです。人は4つの自己をもっているとして、4象限で図式化しました。自分が思っている自分の性格と人からみたときの印象にズレがあることに気づくことができる手法です。のちに提案者ふたりの名前を組み合わせてジョハリの窓と呼ばれるようになりました。その定義は次のとおりです。ジョハリの窓は、「自分が知っていることかどうか」をヨコ軸に、「他者が知って
Article・2024.02.11ジョハリの窓とは?4つの自己を分析するワークのやり方ジョハリの窓とは、1955年にアメリカ・サンフランシスコ州立大学の心理学者、ジョセフ・ルフトとハリー・インガムが発表した、対人関係における気づきのグラフモデルのことです。人は4つの自己をもっているとして、4象限で図式化しました。自分が思っている自分の性格と人からみたときの印象にズレがあることに気づくことができる手法です。のちに提案者ふたりの名前を組み合わせてジョハリの窓と呼ばれるようになりました。その定義は次のとおりです。ジョハリの窓は、「自分が知っていることかどうか」をヨコ軸に、「他者が知って