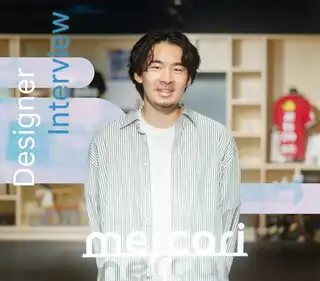私たちは日々、さまざまなプロダクトやサービスを利用しています。そして多くのデザイナーや開発者は、ユーザーの「ニーズ」や「ペインポイント(痛み・不満)」を発見し、解消することを目指しています。
ところが、ユーザーの要求は必ずしも単純ではありません。 たとえばAという機能が欲しい一方で、Bという条件も大事にしたい。コストを抑えたいが品質は妥協したくない。時間をかけて比較検討したいが、早く決めて楽になりたい ―。
このような相反する欲求や価値観が衝突する状態が、ユーザー体験の複雑性として存在します。
学生時代にWebデザイン会社を経験後、新卒で行政機関に勤務。ワークスアプリケーションズ、TERASSなどのITベンチャー、自身のデザイン会社などを通じ、プロダクトデザイン、ブランディング、開発、PMなどを経験したのち、株式会社マイベストでデザイン責任者としてデザイン組織、デザインリサーチ、リブランディング、アプリ開発などを推進。グロービス経営大学院卒業。 現在はスキマバイトサービスの運営企業にてプロダクトデザインマネージャー。
ユーザーが直面するジレンマ
ここで、ジレンマとはなにかについて考えてみます。
ジレンマは、2つの相反する選択肢の板挟みになる状況をさします。より分解すると、次のような主観的かつ複雑な状況と位置づけられます。
同時に選べない二者択一の状況
選択肢によって異なる感情がおきる状況
選択肢に関連して衝突する複数の価値観
注目すべきことは、ジレンマをとりまく選択肢自体だけでなく、個人の感情や複数の価値観がジレンマの複雑さを構成している点です。ジレンマは、事柄の大小を問わず、誰の中にも生じうるものです。
たとえば旅行予約サイトを使うとき、ユーザーは「少しでも費用を抑えたい」と思いつつ、「旅先では快適なホテルに泊まりたいし、ちょっと贅沢もしてみたい」と感じることがあります。
このような矛盾したインセンティブは一つの決断の中にいくつも浮かび上がります。
「安く済ませたい」 vs. 「妥協しない旅にしたい」
「のんびり過ごしたい」 vs. 「新しい発見がしたい」
「短時間で予約を終えたい」 vs. 「たくさんのプランを比較してベストを探したい」
「自由度を高めたい」 vs. 「トラブルを避けるため計画をしっかり立てたい」
そして、こうした葛藤は旅行に限らず日常のさまざまな場面で発生します。
また、ジレンマは必ずしもはっきりと自覚されるとは限りません。
ユーザーが直感的にもっている志向には、実は反対側の選択肢が存在することもジレンマ構造の一つと捉えることができます。さらには、目に見える選択肢だけではなく、何かをしないこと(不作為)も選択肢の一つであることに注意が必要です。
このようなジレンマ構造の発見�こそが、解く価値のある課題提起につながる可能性があります。
「ジレンマドリブンデザイン」とは?
ここで、今回ご紹介するデザインメソッドが「ジレンマドリブンデザイン(Dilemma-Driven Design)」です。 ユーザーの「相反する関心事(concerns)」をあえてあぶり出し、その衝突構造をデザインの基点とするアプローチです。いいかえると、「ユーザーが"これをしたい”一方で、"別のことも譲れない”と感じている摩擦を可視化したうえで、それをいかに解決あるいは緩和するかを考える」というものです。
たとえば旅行サイトで「費用を抑えたい」一方で「そこそこ豪華にもしたい」と感じるユーザーの希望を両立させる仕組みは作れないか。あるいは両立は難しいことを前提に後悔や罪悪感を少なくするUIを考えるか。ユーザー自身にジレンマを再認識させ、旅の目的を改めて考えてもらうアプローチもあるでしょう。
このように"ユーザーの葛藤”を起点にアイデアを展開する点に、ジレンマドリブンデザインの特徴があります。
ジレンマドリブンデザインは、こうしたジレンマの発見と解決策の型を提供し、効果的な体験設計をサポートします。
ジレンマドリブンデザインのプロセス
ここからは、実践にあたっての流れをみていきます。大きくDiscovery(発見)・Definition(定義)・Application(適用)の3ステップです。
Discovery: ユーザーが抱えるジレンマの発見
まずはユーザーがどんなジレンマを抱えているかを見つけます。インタビューや観察、ユーザビリティテストなどで「迷ったシーン」「二者択一に困惑した場面」を掘り下げ、感情と背景を聞き出します。
ジレンマを捉える際は、ユーザーのConcern(関心事)・Choice(選択肢)・Emotion(感情)の3つの要素で考えることが有効です。
Choice(選択肢) : 同時に選ぶことができない相互排他的な選択肢。
Concern(関心事) : その人の幸福にとって重要なもの。ユーザーが「なぜそれを望むのか」「どんな背景や価値観があるのか」を掘り下げる。
Emotion(感情) : 選択肢AまたはBを選んだ場合の得失を考えることで生じるポジティブ・ネガティブ感情。
たとえば「豪華なホテル(選択肢)を選ぶとワクワクする(感情)が、普段から節約して�いるので(関心事)費用面で罪悪感を抱く(感情)」といった形で、感情が複合的に表出することが多々あります。こうした構造を可視化することが、ジレンマドリブンデザインの出発点です。この3要素を明確化することで、「ユーザーは何に喜び、何を惜しみ、どんな未来を想定しているのか」をよりリアルに描き出すことができます。
注意しなければいけないのは、こうした矛盾したインセンティブはユーザーインタビューやユーザー行動観察のなかで、ときに顕在化しない場合がある点です。たとえば、「ホテルの費用を気にする」といった感覚は、ユーザーの社会的自覚に沿わずに明言されにくいかもしれません 。そうしたバイアスがないかを点検します。
Definition: デザインに値するジレンマの定義
Discoveryで見つけたジレンマの中から、「デザインに値するジレンマ」を選定します。
ここで参考になるのが、Pieter Desmet らの研究(2017)で提案された下記の7項目です(Is this a design-worthy dilemma? Identifying relevant and inspiring concern conflicts as input for user-centred design, Journal of Design Research 15(1):17)。
Relevance: 目標ユーザーにとって重要か
Potential to inspire design ideas: アイデア創出の可能性があるか
Impact on user well-being: ユーザーの幸福につながるか
Role products might play: 製品・サービスが解決に寄与できるか
Surprising elements or unexpected concerns: ユーザーにとって意外性があるか
Rarely strictly opposing choice alternatives: 完全に二分しない、多面的なアプローチが可能か
Abstract enough but also concrete enough: 抽象的すぎず、具体的すぎず、デザインに活かしやすいか
これらの視点で評価し、複数のジレンマを優先度づけして1〜2個に絞り込みます。たとえば「コスト vs. クオリティ」が多くのユーザーに共通する重要テーマであれば、そこにフォーカスしてデザインを深めます。
Application: ユーザーのジレンマへの介入
焦点を当てたジレンマに対して、どんなソリューションが考えられるかを具体化します。
ジレンマに対する介入策はその性質上、次の3点に類型化することができます。これらそれぞれにわけてソリューションの発散をおこないます。
1. Resolving(両立を図る)
これまでは相反していた2つの価値を同時に満たす仕組みを探る。AIレコメンドによる「低価格&そこそこ快適」プランの抽出や、割引キャンペーンを活かした宿泊候補の提示など、ユーザーの迷いを解消する方法を考える。
2. Moderating(折衷やバランスを取る)
どちらかを優先しつつ、もう一方もある程度満たす落としどころを設計する。UI上で「譲れない要素」と「妥協できる要素」をユーザーに選ばせ、コストとクオリティの配分を可視化する機能などが考えられる。
3. Triggering(あえて自覚を促す)
ジレンマを直接解決しようとするのではなく、ユーザーに「どちらを重視したいのか」を再認識してもらう仕組みを用意する。心理テストの仕組��みやスコアリングなどで、本人が自分の価値観を再認識するきっかけを与える。これは、ジレンマが解決されなくともユーザーに納得感を醸成させることを通じて体験をつくりあげるアプローチです。
このように、ジレンマに対処するためのUXは、必ずしもダイレクトに解決することだけではないことがわかります。
Airbnbを題材にした例
旅行サイトで「費用をできるだけ抑えたい」一方で「快適さにも妥協したくない」というジレンマは多くの人が経験すると思います。Airbnbの場合、この費用と安心感の衝突をどのように扱っているのでしょうか。実際にAirbnbが取り入れている機能を、3つの方向から見てみます。
Resolving(両立を図る): レビュー&スーパーホスト制度による「安さと信頼性」の見える化
Airbnbでは、ホストとゲストが互いにレビューを残すしくみを持っています。特に“スーパーホスト”のステータスは、高評価やホスト活動実績などの基準を満たしたホストに与えられる称号で、ゲストは検索画面でバッジを確認できます。これによって「費用は抑えたいが、まったく未知の物件は不安だ」という葛藤を、ある程度両立する方向で解消する仕組みを提供しています。
Moderating(折衷・バランスを取る): 補償プログラムでリスクを最小化
AirbnbはAirCover(エアカバー)という包括的な補償プログラムを提供し、ホスト都合の突然のキャンセルや部屋に重大な問題がある場合に、代わりの宿泊先手配や返金サポートなどを約束しています。リスクが起きた際のダメージを最小化することで、ユーザーは費用の抑制に挑戦しやすくなります。これによって「安く予約はしたいけど、リスクが高いのは困る」という人の不安をある程度緩和できます。
Triggering(あえて自覚を促す): フィルタ機能で本当に重視する条件を考え直す
Airbnbの検索UIには、価格帯のスライダーやアメニティ条件などを細かく�絞り込むフィルタが用意されています。ユーザーは「洗濯機は必要」「キッチン付きがいい」「でも予算はなるべく抑えたい」という複数の願望を入れてみることで、自分がどこまで価格を下げられて、どこからは譲れないのかを自然に考え直します。結果的に「自分は安さ6割・安心感4割だな」「多少高くてもレビュー点が8割以上の物件がいいかも」といった自己認識を促し、ジレンマの中でも納得できる選択をすることができるようになります。
ここまで、AirbnbのUXをジレンマドリブンデザインの枠組みで考察してみました。このように考えて気づくことがあります。機能一つ一つが具体的な特定の目的をもっているものでも、UXを構成するのは大小さまざまな要因の組み合わせであることです。
おわりに
ジレンマは「解決されるべき問題」というより、「複数の大切な価値が同時に存在している状態」です。デザイナーの役割は、どれか一つの選択肢へ誘導するだけではなく、ユーザーが自分の中にある葛藤をうまく扱い、よりよい選択をできるようサポートすることです。
旅行サイトの例で言えば、「安く抑えたい」と「満足度も高めたい」という両立困難な願望を正面から扱うからこそ、新しいアイデアが生まれます。
ジレンマドリブンデザインは、ユーザーの感情や内面を深く見つめるパワフルな枠組みです。日常のUX検討でこそ、ユーザーが持つ相克するインセンティブを丁寧に拾い上げ、それを起点にデザインを構築してみましょう。そうすることで、より深いインサイトに根ざしたユーザー体験をつくることができると思います。
参考記事
https://medium.com/illumination/dilemma-driven-design-e43a450f2676
https://uxdesign.cc/embrace-dilemmas-design-with-dilemmas-451d07d1ead9

学生時代にWebデザイン会社を経験後、新卒で行政機関に勤務。ワークスアプリケーションズ、TERASSなどのITベンチャー、自身のデザイン会社などを通じ、プロダクトデザイン、ブランディング、開発、PMなどを経験したのち、株式会社マイベストでデザイン責任者としてデザイン組織、デザインリサーチ、リブランディング、アプリ開発などを推進。グロービス経営大学院卒業。 現在はスキマバイトサービスの運営企業にてプロダクトデザインマネージャー。
yasuhiroyokota.today