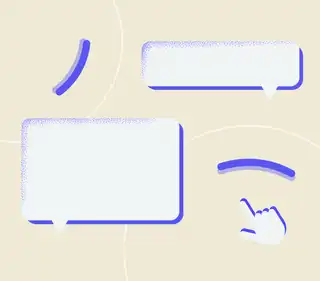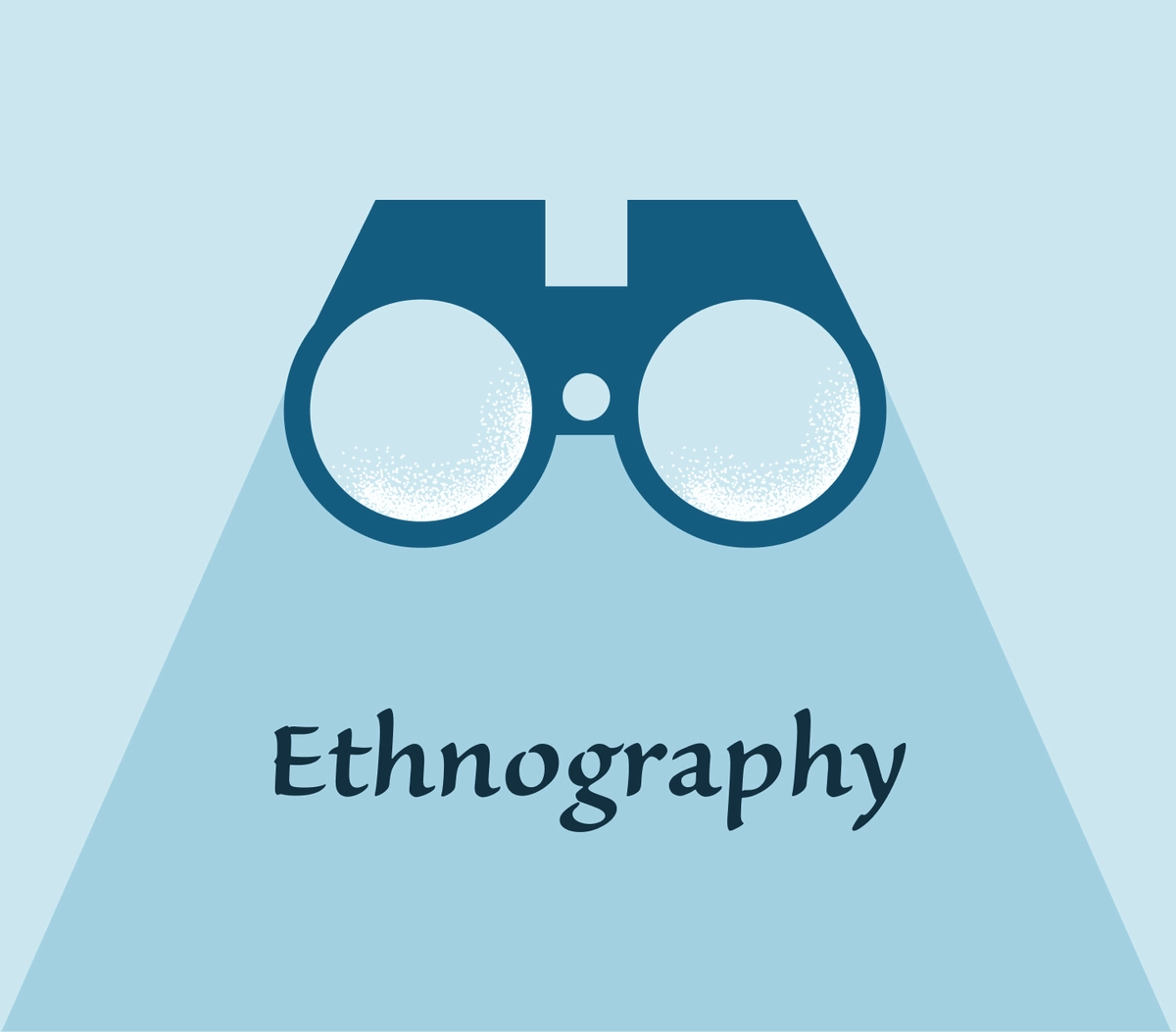
エスノグラフィとは?
エスノグラフィとは、文化人類学や心理学の研究における学術的な調査をルーツにもつ、ユーザーリサーチ(主に定性)の手法です。ユーザーの生活環境に身を置いて行動を観察するだけでなく、ときに生活を共にすることで、ユーザーの行動について深く理解することができます。
その手法が生まれた文化人類学は、異文化(主に未開の地)の衣・食・住・家族などを対象に、フィールドワークを通じて人類の文化の共通性、異質性、多様性を知る学問でした。みなさんも映画やドキュメンタリーなどで、欧米の探検家がアフリカやアジアの少数民族と時間を共にし、人々の生活様式について記録したり研究しているような描写を見たことあるかもしれません。
UXリサーチにおけるエスノグラフィでは、人類学者のように何年も調査対象の人々と時間を過ごすことはありませんが、プロジェクトの制限に合わせる形で同様のアプローチをとることができます。それによりユーザーテストなどと比較したときに、より自然な状況下でユーザーがどのような行動をとっているのか知ることができるのです。
ユーザーが普段のコンテクストでどのような行動をしているか理解することは、その人の人間像について知るだけでなく、周りの環境・文化について知ることにもつながります。そのため、ユーザーについて知ることがキーとなるUXデザインやデザイン思考のプロセスにおいて、非常に有効な手法の一つとなっています。
エスノグラフィのメリット
エスノグラフィの��メリットは大きく以下の3つです。
「ラボの外」でのユーザーの行動を知ることができる点
ユーザーの発言と行動のギャップを理解できる点
さまざまな文脈を「異なるレンズ」で見ることを可能にしてくれる点
1. 「ラボの外」でのユーザーの行動を知ることができる
じっくりとユーザーと向き合うエスノグラフィには多くのメリットがありますが、前述したように「自然な状況下」でのユーザーの行動を知ることができるという点が大きな特徴です。
UXリサーチにおいて、ユーザーテストやデプスインタビューなどは広く知られており、実践されることも多い手法だと思います。ユーザーの声を直接聞くという点では有効なリサーチ手法ではありますが、このような手法では知ることができない情報があります。
それは、普段の生活環境の中でのユーザー行動の傾向・特徴です。
例えば、ユーザーテストを実施する際、リサーチチームはどうしてもユーザーが使用する環境を自ら用意をしたり、タスクを課すことをしなくてはいけません。そのような環境の中でも多くの発見ができることは間違いありませんが、それは普段ユーザーが使っている環境と同じとは限りません。このように「コントロールされた」環境でのリサーチでは、実生活で起こり得るできごとや複雑なコンテクストを再現することはほぼ不可能と言って良いでしょう。
エスノグラフィでは、自分自身が被験者として日常生活に溶け込み、ユーザーやその環境を観察することができます。もちろん、その分時間やコストはかかってしまいますが、いままでに顕在化していないニーズを捉えたり、実生活に直面したからこそのデータの分析ができるなど多くのメリットがあります。
2. ユーザーの発言と行動のギャップを理解できる
また、エスノグラフィではリサーチャー自らがその環境に身を置くからこそわかることがあります。
それは、ユーザーの発言と実際の行動のギャップです。
デプスインタビューでの発言などユーザーから得た情報は、必ずしも正しいとは限らないというのはみなさんもよくご存知だと思います。エスノグラフィでは、実際の場所に訪れることで、ユーザーの記憶があいまいだったり、回答しにくく感じていた部分に関する情報を得ることができます。
同じように、定量リサーチや統計データの裏側で起きているユーザーの行動を理解することもできるでしょう。
3. さまざまな文脈を「異なるレンズ」で見ることを可能にしてくれる
最後に、エスノグラフィがリサーチチームにもたらす効果についてもう一つ紹介すると、それはさまざまなコンテクストを他の人の世界の中で見ることを可能にしてくれることです。
どんなに訓練を受けたリサーチャーでもバイアスをゼロにすることは不可能です。私たちは、知らないうちに自らの文化的規範やこれまでの経験を通して世界を見る癖があります。ユーザーと一緒に行動することで、普段の自分達では見ることのできなかったものの見方をすることができるようになります。
特に、インクルーシブの文脈であったり、ダイバーシティといった観点がより強調される現代社会において、エスノグラフィのこの側面は非常に重要な役割を果たしてくれます。
エスノグラフィ調査の事例
ここで、いくつかエスノグラフィの事例を紹介したいと思います。
アメリカの路上標識に関するリサーチ
もっとも有名なのは、認知心理学者のエレン・アイザックスとパロアルト研究所のチームが行った、アメリカの路上のパーキングに関する標識のリサーチです。
チームがリサーチを行ったエリアでは、パーキングに関する細かいルールが書かれた標識が路上にいくつもありました。例えば「午前7時〜9時と午後4時〜6時の間は停車禁止(no stopping)」と書かれた標識のすぐ隣に「午前9時から午後4時まで駐車禁止(no parking)」といった標識が設置されています。
彼女たちは、現地でパーキングに関する行動を観察する中で、運転中の人々が数秒でわかりにくい標識から情報を読み取り、判断を下すのはほぼ不可能だということを発見しました。このように瞬間的な判断をサポートするべき道路標識において重要なことは、「何ができないか」ではなく「何ができるか」を示すことです。
面白いことに、インタビューで人々に路上でのパーキングについての不満を聞いても、標識の難しさについて不満を述べる人々はいませんでした。エレンたち自身もこの事象を発見するまでに、4つの都市でのリサーチを経て1000以上の写真や動画を撮ってはじめて気づいたと言います。
こういった発見こそが、オフィス内などの「コントロールされた」環境下でなく、実際の環境や複雑な文脈が絡み合った現地に行くことで出会うことができる気づきの良い例と言えるでしょう。
Heinzのケチャップボトル
次に、世界的食品メーカーであるHeinz(ハインツ)の事例について紹介します。
2000年代前半、売上低迷に陥っていた同社は、立て直し策として主力商品であるボトル入りケチャップを復活させるため、商品の開発を開始しました。当時は、卓上瓶入りケチャップが主流となっていたため、ボトルをどのようなものにするかがこのプロジェクトの最大のポイントでした。
そこで、社会学者も含んだチームを編成し、ユーザーの日常生活に密着するエスノグラフィ調査を実施しました。 調査の中で、残り少なくなった瓶を逆さにして、底を叩いてケチャップを出そうとする行為が見られました。もしかしたら多くの人が経験のある行為かもしれませんが、改めて考えるとこの行動は効率的とは言えません。
ハインツの濃厚なケチャップは、少なくなるにつれてドロドロな部分だけが残ってします。このような状況で底を叩いてケチャップを出そうとすると、勢い余ってケチャップが出過ぎてしまったりするなど、非常に使いにくい状態になってしまうのです。そのためなのか、調査の中でケチャップを冷蔵庫に保管する際に瓶を逆さにするといった行動が多く見られました。
この調査の結果、リサーチチームと�開発チームはキャップを逆さにしたプラスチック製のボトルを生み出します。また、逆さでも立てられるようにキャップを大きくしたり、逆さの状態でラベルが読めるようにするなどの工夫もし、結果ビジネス的な成功も収めます。
自分自身がユーザーだと当たり前と感じるこのような現象も、ビジネスの文脈では私たちは意外と見落としがちです。それでも、エスノグラフィで現地の環境に溶け込むことで、ユーザーの立場になって考えたり、世界を見ることが再びできるのです。このハインツの例は、ユーザーのペインやニーズに寄り添ったデザインの良い例です。
UXデザインにおけるエスノグラフィの実践方法
では、次に実際のエスノグラフィの実践方法について見ていきましょう。まず何よりも重要なことは、この調査方法をいつ・どのタイミングで実践するべきかを知ることです。
結論からいいますと、デザインプロセスのどのフェーズにおいても、エスノグラフィを実践することは可能です。しかしながら、「思いがけない発見」をより後続に効果的に活かすことができる、デザインプロセスの初期に力を発揮します。エスノグラフィの強みは、「コントロールされた」オフィスの環境を飛び出し、実際にユーザーが置かれている環境に身を置くことで、ユーザーへの共感を高めることができる点です。ユーザー起点での商品企画やデザインをする上で、ユーザーのことをまずはじめに深く知ることは有用です。
では具体的に調査の流れについて見ていきます。
1. 調査設計
エスノグラフィを実施することが決まったら、まずは調査設計を行いましょう。 プロジェクトに適した調査目的を設定し、それを達成できるような調査対象(場所・ユーザーなど)を洗い出し、リサーチ期間やリクルーティング、結果のまとめに費やす時間などスケジュールを決めます。調査によっては仮説がある場合もありますが、仮説がなくてもエスノグラフィは実践することが可能です。調査の目的を決めるためには、現在知ろうとしているトピックについて、デスクトップリサーチをすると良いでしょう。
成功するために重要なポイント:デスクトップリサーチをして、自然に湧き上がってきた疑問を大事にしましょう。そのようなテーマは一人一人のメンバーの好奇心を刺激し、最後までドライブしてくれます
2. リクルーティング
ユーザーへの同行調査を行う場合は、リクルーティングが必要となります。リクルーティングには、専門のエージェンシーを利用する方法とチームメンバーの機縁によるリクルーティング方法があります。前者の場合、後者と比べてより大きな予算が必要になるので、プロジェクトの予算に応じて方法を選ぶ必要がありますが、より多くの人にアプローチすることができます。同じユーザーに対してのデプスインタビューと同行調査を行うとユーザーの発言がどれくらい本当なのか、またそれが実際の環境の中でどのように行われているか知ることができるのでより効果的です。
成功するために重要なポイント:リクルーティングの「質」と「スピード」の兼ね合いを考えましょう。リクルーティングがうまく行かないとリサーチ自体の実施に大きな影響を与えます。その反面、スピードが担保されているエージェンシーなどは、登録しているユーザーの属性に偏りがある場合があります。ここはバランスになります。
3. 調査の準備
当日のチーム編成や各メンバーの動き方をまとめた香盤表などを作成しましょう。チームメンバーの規模が多い場合は、同時に複数の場所に赴いたり、複数のユーザーへの同行調査を行いましょう。調査中は、思いもがけないことが起こることがあるので、(それが目的でもあるのですが)さまざまな事態を想定して準備する必要があります。パソコン・スマホ・カメラの充電やデータ容量の確認や、何かあったときの連絡先など当日調査に集中できるよう抜かりなく準備をしましょう。
成功するために重要なポイント:リストを作成し、リサーチをするごとにアップデートしておきましょう。また同様のリサーチを経験した他のチームに助けを求めましょう。
4. 調査の実施
調査する現場に��赴き、人々の行動を観察しましょう。録音や録画、写真などあらゆる方法で記録を残します。同行調査でユーザーが気なる行動をした場合、その場で理由などを聞くようにしましょう。調査中は「善を行い、害を与えない」ことを意識しましょう。現場にいるユーザーを騙すような行動など、非倫理的な行動を取らないように注意します。
成功するために重要なポイント:なるべく現場に溶け込み、調査対象にあまり影響を与えないようにしましょう。例えば、あるユーザーのショッピング体験を同行リサーチしている場合、立ち位置などを工夫するなどして普段通りの行動を促しましょう。
5. 調査内容の振り返り
なるべく早い段階でチームで集まって調査内容を振り返ります。特に気になった行動やデザインへのヒントになりそうな事柄など重要な発見を忘れないようにメモをしておきます。また、ノー�トはのちほど振り返ってもわかるようにまとめておきましょう。
成功するために重要なポイント:あらかじめまとめ用のノートを作成しておきましょう。メンバー間のメモが統一されてより議論がしやすくなります。
6. 調査データの分析
調査データが集まったら、データを分析し実用的なインサイトを導く作業に移ります。定性調査におけるデータ分析の方法��にルールはありませんが、代表的な方法に以下のようなものがあります。
親和性ダイアグラム: データポイント間の意味のある関係を整理して特定することができる。
タスクフロー: 参加者の行動の流れを整理するためのもので、タスクを完了するために必要なツールや情報など、参加者がどこから始めるかを示す。
ジャーニーマップ: ユーザーの体験を視覚的に表現したもので、すべての主要なタッチポイント、ペインポイント、アクションを順を追って記載する
このような分析方法を通じて、
調査中多くのユーザーに共通して見られたパターン
重要なユーザーの行動・意思決定とそれに影響を与えたもの・要素
ユーザーが抱えるペイン・ゲイン
意外だったユーザーの行動・現場で起こっていた現象
などを見出すようにしましょう。
成功するために重要なポイント:多くの人が、インサイトは「面白い」発見であれば十分と思いがちですが、それと同じくらい重要なことはそのインサイトが「使える」ものであることです。デザインプロセスのインパクトを考えた上で、面白いだけでなくより使えるようなインサイトの発見を目指しましょう。
まとめ
文化人類学を起源にもち、ユーザーをよりリアルな状況で観察するエスノグラフィは、ユーザー中心のデザインプロセスを進めていく上で強力なツールとなります。
より多くの予算・時間を要しますが、その情報のリッチさゆえ、エスノグラフィはデザインプロセスで大きな影響力をもつことになるでしょう。そのため、正しい設計とチーム編成を行いリサーチ結果に偏りのないようにすることが求められますので、その点は注意が必要です。
しかし、もっとも大事なのは、ユーザーの行動に注目したり、その動機を知りたいと思う好奇心です。エスノグラフィの経験がなく、調査設計が困難に感じた場合でも、まずは現場に出て自分の目で見てユーザーについて学ぶことからはじめてはいかがでしょうか。