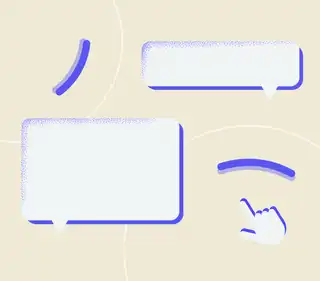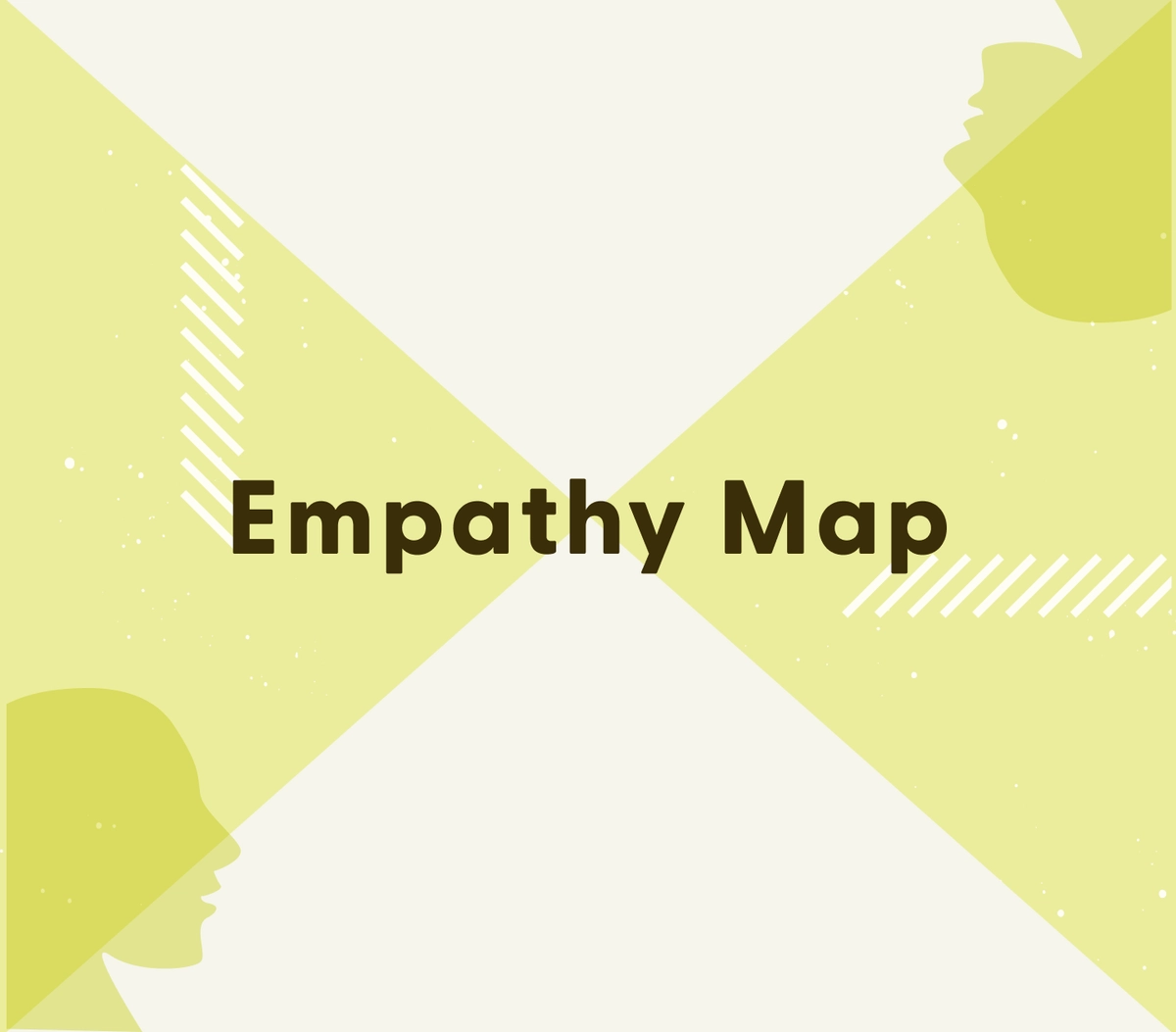
共感マップとは?ユーザーの環境や感情、思考を理解するためのフレームワーク
共感マップの例
共感マップとは、ユーザーの置かれた環境やその中で抱く感情・思考などについて理解するためのフレームワークです。UXデザインやサービスデザインにおいて最も使われることの多いフレームワークの一つでもあり、デザイン思考の産みの親であるIDEO創業者のデビッド・ケリーがスタンフォード大学に設立したd.schoolのカリキュラムでも採用されています。また、過去にはハーバードビジネスレビューでも掲載されたことがあり、ビジネスにおいてもユーザーや消費者の感情面がより重視されるようになるにつれ、その役割もデザインの文脈を超えて一層重要となってきています。
共感マップの役割は、ユーザーについて理解することはもちろん、それに加えてチーム内で共通認識を作り上げることを促進することです。また、共感マップはユーザーや消費者を対象にしたものだけでなく、組織内の従業員に対しても利用することができるので、組織変革の際にも活用することが可能です。今回は、現代ビジネスにおける最も重要なキーワードの一つである「共感」を、さまざまなビジネスやデザインのプロセス内に組み込むことを可能にする共感マップについて紹介したいと思います。
共感マップの目的。ペルソナの心理の深いところまで理解する。
共感マップは、顧客視点でサービスをより良いものにするためのヒントを与えてくれるツールです。最大の目的は、ユーザーやペルソナの体験や感情を彼らの目線で理解し、文字通りより深く「共感」することにあります。それにより、ユーザーの感情面も考慮したニーズに応えるようなUX戦略を立てたり、それに即したサービスの設計・改善が可能になります。
ペルソナは、ユーザーインタビューやマーケティングに関連する情報などから作成される空想上の人物です。典型的なターゲットユーザーについて、年齢・性別・居住地・職業・年収といった基本情報だけ�でなく、価値観やライフスタイルなど具体的な行動を描くことで、チーム内で顧客視点を伴ったディスカッションを可能してくれます。ただし、ペルソナをサービス開発やデザインプロセスで使う上で注意すべき点があります。それは、ペルソナは実際に存在する人間ではないという点です。だからこそ、チームメンバー全員がペルソナのことを本気で考え、理解する機会となる共感マップが重要となります。より具体的なユーザー像をチームメンバーが共有することができれば、UX戦略やサービスの設計・改善案は自ずと顧客視点のものになるでしょう。
そのため、ユーザーやペルソナに関するチーム内での認識のずれを防いでくれることも共感マップの大きな役割の一つとなっています。ペルソナの情報は限られているため、これまでの経験値や知識から、各チームメンバーがペルソナをどう理解するかは異なります。そのため、チームで一緒にユーザー像を作り上げていくことが、共通認識を持ってその後のプロセスを進める上でのキーとなります。
プロジェクトによっては、リサーチとデザインまたは開発のフェーズでチームメンバーが異なることがあります。その場合、ユーザーやペルソナに関する理解や共感度合いは、インタビューなどリサーチフェーズから参加するメンバーとそうでないメンバーでギャップが生まれます。プロジェクトの途中から参加するメンバーでも、共感マップのワークに参加することができればユーザーやペルソナに対して共感を持って向き合うことができます。共感マップの主な目的は、ペルソナ心理の深いところまで理解をすることです。デザインの共創的なプロセスにおいて、ユーザー視点・ニーズに関する共通認識を作り上げる共感マップの役割は非常に重要なものと言えるでしょう。
共感マップを構成するの6つの要素
次に共感マップの6つの構成要素について紹介します。共感マップを作成する際には、ユーザーの性格や属性などを踏まえてどのような行動をしているか、どのような思考・感情を抱いているかをチームで考えながら以下の6つの要素を埋めていきます。
See: 見ていること
Hear: 聞いていること
Say and Do: 言っていること、行っていること
Think and Feel: 考えていること、感じていること
Pain: 悩みやストレスに感じていること
Gain: 幸福に感じていること、あったら嬉しいこと
See: 見ていること
ユーザーが普段の生活の中で目にしているものについて考えましょう。文字通り「目にしているもの」に当てはまるものであればとりあえず書いてみることがよりアイデアを拡散するコツです。どのようなウェブサイトをよく閲覧しているか、テレビやYoutubeなどでどのような動画を見ているか、また職場や生活の特定の場面でどのようなシーンを目にしているか。ユーザーになった気持ちで考えましょう。
見ていることの例
昼休みにYoutubeでお気に入りのクリエイターの最新動画をチェック
帰りの電車で新しい化粧品の中吊り広告を見かけた
寝る前にスマホで好きなブランドの新商品を閲覧
Hear: 聞いていること
ユーザーが普段の生活の中で耳にしているものについて考えましょう。「見ていること」と同じくここでも当てはまるものをなるべく多く書きましょう。もっともわかりやすいのは、周囲の人している話だったり、聞いている音楽だったりだと思います。
聞いていることの例
会社の先輩から好きなブランドの新商品が出たと聞いた
1日の終わりはジャズを聴きながらリラックスする
Say and Do: 言っていること、行っていること
ユーザーが普段の生活の中での行動や言葉にしているものについて考えましょう。「言っていること」はユーザーの口癖や友人・同僚に対してどのような言葉をかけることが多いか考えるとわかりやすいでしょう。行動に関しては、「見ていること」「聞いていること」「言っていること」では説明できないような、ユーザーの特徴的な行動です。いつ・どのようなことをしているか考えることがそのヒントになるはずです。
言っていることの例
休み時間に好きなYoutubeチャンネルについて同僚に共有する
何かにつけて「なんとかなるだろう」と言うのが口癖
友達との待ち合わせにはいつも少しだけ遅れてしまう
Think and Feel: 考えていること、感じていること
これまでとは違��い、今度はユーザーが内面で考えていること・感じていることを考えましょう。これまでの3つと比べて、客観的に観察するできないユーザーの「内側」の部分になります。ここでのコツは、必ずしも開発しようとしているサービスやデザインに関わらないことも含めて一旦広く書き出すことです。
考えていること、感じていることの例
新商品は欲しいけど今月は余裕がないと感じる
いつか自分自身でもブランドを立ち上げてみたい
Pain: 悩みやストレスに感じていること
ユーザーが悩みやストレスに感じていることについて考えましょう。ユーザーにとってネガティブとなる要素は、新たなデザインやサービスのヒントにつながります。特定のサービスやビジネスについてワークしている場合はそのサービスや商品についても少し念頭に入れつつ考えましょう。
悩みやストレスに感じていることの例
ブランド立ち上げのために何からはじめたら良いか検討がつかない
お金のことには気をつけているはずなのに月末にはいつも余裕がなくなってしまう
Gain: 幸福に感じていること、あったら嬉しいこと
ユーザーがすでに幸福に感じていることや今はないけどあったら嬉しいと感じることです。ペインと同じように、特定のサービスやビジネスについてワークしている場合はそれに関連したものを考えましょう。すでに幸福に感じていることを阻害しないようなサービス作りや、ペルソナが潜在的に欲しているものを理解するために書き出します。
幸福に感じていること、あったら嬉しいことの例
気に入っているYoutubeチャンネルは毎週金曜日に更新されるので、それが週末の楽しみになっている
自分自身でデザインしたTシャツが気に入っている
以上が共感マップの基本的な6要素になります。
共感マップ�は人物像を感情面と共に描くことを可能にするのでユーザーやペルソナをよりリッチにしてくれます。コツは、ユーザーのキャラクターが出る象徴的な瞬間を考えることです。例えば「友達との待ち合わせにはいつも少しだけ遅れてしまう」ということから、少しだけだらしないユーザー像が想像できませんか?このように共感マップでは、基本情報のようなタンパクな情報にカラーを与え、ユーザーのキャラクターを理解した上でサービスをデザインすることを可能にしてくれます。
共感マップの作り方を4ステップで解説
次に実際に共感マップを作成していく手順について紹介します。
ユーザーインタビューでターゲットユーザーの情報を集める
ペルソナの設定とテンプレートの準備
共感マップに6つの要素を書き出す
必要に応じて内容を精査
1. ユーザーインタビューでターゲットユーザーの情報を集める
共感マップを作成する上で、ユーザーインタビューは必須のものではありません。しかし、ペルソナを設定していく上で、インタビューを実施するとより精度の高いペルソナを作ることができますので、予算や時間に余裕がある場合やより精度の高いペルソナが求められる場合は、インタビューからはじめるのをおすすめします。インタビューの質問リストは、ペルソナ作成に必要な情報はもちろん、すでに紹介した共感マップの6つの要素、また開発中のサービス・商品のジャーニーから作成していきます。
2. ペルソナの設定とテンプレートの準備
次に、ユーザーインタビューやターゲットユーザーの情報からペルソナを設定します。インタビューやマーケットリサーチなどによるユーザーに関するインプットから、ペルソナの属性情報や行動特性を考え設定していきます。グループワークで共感マップを作成する際には、このペルソナの情報を常に参照することになります。
オンライン・対面問わず、わかりやすいフォーマットで設定することや、あまり詳細まで書きすぎて想像力を阻害しないようにするなどを注意して設定しましょう。また、共感マップのテンプレートも可能であれば準備しましょう。対面の場合は、A1やA2サイズなどで印刷をすると付箋が入る大きさになり、グループでテンプレートに付箋を貼りながら議論できるサイズとなります。余裕がある場合は、自分達の好みに合わせてテンプレートをカスタマイズしたり、デザインを少し変えたり、当日のワークが盛り上がるような工夫をすることもコツの一つです。ここまでできたら、先ほど紹介した6つの要素をグループで書き出すワークを行う下準備は完了です。
「いつ」実施するか?
チームメンバーのスケジューリングもありますが、日中の中でどの��時間帯にやるのがベストか少し工夫しましょう。例えば、自分が参加者だということを想定して朝9時からセッションを行うのと、ランチ後にセッションを行うのとどちらがより意味のあるものになりそうでしょうか。
「どこで」実施するか?
共感マップのワークでは、自分ではないペルソナに関してのライフスタイルを広くイメージする必要があります。例えば、窓のない会議室より開放的な空間の方が、さまざまなインスピレーションを受けることができます。
「だれと」実施するか?
共感マップを行う上での注意点は、視点が偏らないようにすることです。主観的な情報を多く扱うため、参加者の属性に考慮し、より多くの視点を取り入れることを注意しましょう。共感マップのようなユーザーの感情面について考えるワークにおいては、ワーク参加者の感情面にも考えた設計をすることでよりリッチなペルソナ像を作成することができます。準備は大変ですが、精度の高い共感マップを作成するために、しっかりと準備をしましょう。
また、共感マップの6つの要素を埋める順番も工夫が必要です。一般的に、ペイン・ゲインは他の4要素を記入してから行われることが多いです。ユーザーの置かれている環境や思考・感情を想像した上で、どのようなこと�に困っているか・喜びに感じているか考える方がより自然な流れとなります。また、セッション中はただテンプレートを埋めることだけでなく、チームメンバー間の議論の時間も大切にしましょう。自分とは全く異なる視点を持っている人の意見を聞いたり、議論をすることでより共感マップの内容が磨き上げられていきます。それぞれが書いた内容について共有し、議論をしましょう。
4. 必要に応じて内容を精査
共感マップを作成するセッション中は、アイデアの「発散」に集中し「収束」することはあまり考えないようにします。チームで集まって共感マップを作成する際の目的は、より多くのアイデアを発散することですセッション終了後に、作成した共感マップの内容を改めて見直し、精査する時間をとるとより精度の高い共感マップを作成することができますので、セッション中はなるべく、否定的な意見を言わないようにも気をつけます。


Figma版 & PDF版 『共感マップテンプレート』
unprintedオリジナルの共感マップテンプレートは、Figma CommunityからFigmaファイルをコピーして使うことも、PDFを印刷して手書きで使うこともできるよう2種類のフォーマットで配布しています。どちらも登録やメールアドレスの入力は不要。個人・商用に関わらず自由に使用することができます。
共感マップテンプレートの使い方
共感マップテンプレート
まとめ
今回は、ユーザーの置かれている環境やその中で抱いている感情についてより深く理解し、ユーザー目線での課題について考えるフレームワークである共感マップについて紹介しました。
「共感」がより重視されるビジネスやUXデザインの文脈において、誰でも使いやすく、かつチームでの共通認識を作り上げることができる共感マップは強力なツールとなります。しかし、共感マップもあくまでフレームワークであることに注意が必要です。各項目を埋めることや共感マップを作成すること自体が目的化してしまい、ユーザーのことを考えるのを疎かにしないようにしましょう。はじめてのワークであっても、ユーザーの目線で環境や感情を理解し、課題について考えることを常に忘れないようにしながら、チームでより意義のあるディカッションを行いましょう。