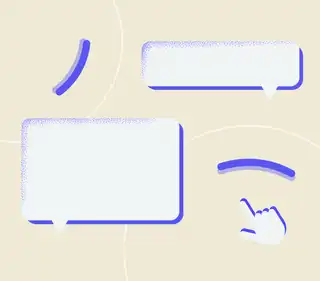ユーザーインタビューとは?ユーザー行動の「なぜ」に迫るUXデザイン手法
ユーザーインタビューとは、プロダクトやサービスのユーザーとの対話を通して、その課題やニーズ、現状のプロダクトへの反応などを分析する手法です。ユーザーインタビューは、定性分析の手法の一つであり、行動データの分析などの定量分析と比べて、ユーザー行動の「なぜ」に迫ることができるという強みがあります。
デジタルサービスの世界では、データ分析ツールが充実し、簡単にユーザーの行動データを分析することができるようになりました。このような定量データをもとにサービス改善を繰り返していくようなケースも多いでしょう。しかしながら、より広い視点でサービスにとって重要となってくる
ユーザーは、なぜそのサービスを使っているのか?
ユーザーは、サービスのどのような点に魅力を感じているのか?
ユーザーは、サービスのどのような点に不満を感じているのか?
といった情報はデータ分析からは見えてきません。このようなサービスの提供価値に関するユーザーの認知・反応を分析する際には、ユーザーインタビューが有効な手段となります。
ユーザーインタビューの3分類
ユーザーインタビューにはその特徴から、大きく「構造化インタビュー」「半構造化インタビュー」「非構造化インタビュー」の3種類があります。
構造化インタビュー: アンケートでも代替可能
構造化インタビューとは、すべての質問を前もって準備した上で、一問一答形式でインタビューを進めるインタビュー手法です。この手法のメリットは、定量分析に近い一貫性のあるデータの取��り方ができるという点です。集めたデータを集計しやすいため、明確なアウトプットが欲しい場合などに利用されます。
しかし、構造化インタビューでは、ユーザーと対話しながら行うことによるメリットはほとんどほとんど無いと言えます。一問一答形式となるため、より時間やコストのかからない「アンケート」として行うことが適切な場合は多いでしょう。この、インタビューとアンケートの使い分けについては、「アンケートとインタビューの適切な使い分け: そのユーザーインタビュー、アンケートでも良いのでは?」にて詳しく解説します。
半構造化インタビュー: 回答を深掘りして深層心理に迫る
半構造化インタビューは、質問を前もって準備する点は構造化インタビューと同じですが、インタビュー実施時にインタビューアーが相手の回答や反応をもとに、話を広げて解答の意図や深層心理に迫る手法です。イメージとしては、5回「なぜ?」という質問を繰り返すことで、ものごとの本質に迫れるという「5 Whys(なぜなぜ分析)」に近いです。もちろん、単純にインタビューで「なぜ?」と5回も質問しても鬱陶しいだけなので、ロジカルに状況を分析して即興で質問を行えるインタビューアーのスキルが求められる手法となります。回答を深掘りするためのポイントは、「それぞれの質問�で明らかにしたいこと」を前もって明確にしておくことです。詳しくは、後の「ユーザーインタビューの準備: 聞きたい質問をリストアップするのではダメ?」にて解説します。
非構造化インタビュー: 実施環境を工夫すると効果的
非構造化インタビューとは、質問を事前に準備せずにテーマのみを決めてユーザーと自由に対話をするインタビュー手法です。まだサービスの明確なコンセプトや方向性が決まっていない場合や、新たな課題を発見して新機能を提供したい場合などに有効となります。非構造化インタビューを行う場合には、テーマに沿った場所や環境でインタビューできると効果的です。例�えば、「料理を行うときの悩み」を聞く場合は、実際に普段利用しているキッチンにて料理をしてもらいながらインタビューを進めるなどです。ユーザーは、自分の抱える課題についてあまり強く意識していない場合も多いです。そのため、課題の起こる環境に実際に身を置くことで、会議室などのインタビューの場では思い出せないような点についても発言してもらえる可能性が高まります。
「なぜ」を明らかにできることがユーザーインタビューの利点
効果的なインタビューを行うために、改めてユーザーインタビューの利点について述べておきたいと思います。なぜなら、この利点を最大限に活かせるかどうかがユーザーインタビューのポイントとなるからです。ユーザーインタビューの最大の利点は、「なぜ?」に迫れることです�。これは、サービスの改善にとってとても重要な情報でありながら、なかなか他の手法では得ることのできない情報です。例えば、Instagramのアプリ1つを見ても、サービスが提供している価値はさまざまです。
写真を投稿すること
フォロワーが増えること
他の人の投稿を見ること
他の人と交流すること
などのInstagramが提供する価値の中で、どの提供価値に魅力を感じている人が何%くらいいるのかといったデータについては定量的なデータの分析だけではなかなか見えてきません。また、「他の人と交流すること」に魅力を感じる人が多いとわかった場合にも、その背景として「なぜInstagram上での交流が魅力的なのか?」といった情報を得るためには直接ユーザーに聞く以外に良い方法はあまりありません。このような、ユーザーの体験を根本的な動機から理解することができると、デザインやUX改善のための大きな手がかりとなります。
アンケートとインタビューの適切な使い分け: そのユーザーインタビュー、アンケートでも良いのでは?
直接ユーザーに意見を聞く手法としては、ユーザーインタビューの他に「アンケート」があります。アンケートは、インタビューと比べて時間やコストを抑えることができる上、より多��くの人からデータを集めやすいという利点があります。一見、定性調査はアンケートだけで十分と思われるかもしれません。しかし、アンケートには大きな欠点があります。それは、
回答の選択肢を前もってすべてリストアップする必要がある
「なぜ?」を深掘りしにくい
の2点です。ユーザーの「なぜ?」に迫る定性分析では、ユーザーとの対話を通して初めて得られる新たな発見が多くあります。しかし、アンケートのために前もって回答の選択肢を準備するとなると、選択肢がサービス提供者側が考え得る回答のみに制限されてしまいます。アンケートでは「その理由を自由に書いてください」といった設問を設けることで、一見「なぜ?」の深掘りができそうに見えますが、この設問に対してユーザーがどの程度本質的な理由を回答してくれるかは分かりません。多くの場合、「楽しいから」などのとても表面的な理由しか得られない場合が多いです。その点、ユーザーインタビューでは、相手の回答が本質的ではない場合は、追加の質問をすることで本来得たかった情報を正確に得ることができます。
また、ユーザーインタビューで一問一答的な進め方をしてしまう例も多く見受けられます。しかし、これではユーザーインタビューの利点を活かすことができず、アンケートでも得られるような情報しか集まりません。効果的なユーザーインタビューを行うためには、ユーザーインタビュー設計時に「アンケートでも代用できるようなインタビューになっていないか?」という点を都度確認してみても良いかもしれません。
では、アンケートはどのような場合に有効なのでしょうか?アンケートが有効なケースの一つに、「ユーザーインタビューで得たデータの統計的な信頼度を確認したい場合」があります。ユーザーインタビューでは、5 ~ 10人ほどへのインタビューである程度の傾向が掴めることが多いです。例えば、インタビューを通して「サービス利用動機には大きく2種類ありそうだ」ということがわかったとします。しかし、10人へのインタビューだけでは、それぞれの利用動機を持つユーザーが、サービス全体の何%ずついるのかは分かりません。そこで、インタビューにて明確になった主な利用動機を回答の選択肢として、より多くの人数にアンケートを行うことで統計的に有効なデータを得ることができるようになります。つまり、ユーザーインタビューとアンケート両方を行うのであれば、まずユーザーインタビューで方向性を掴んだ上で、アンケートにて統計的な情報を得るといった順番で実施すると効果的でしょう。
ユーザーインタビューの準備: 聞きたい質問をリストアップするのはダメ?
ユーザインタビューの成否は、9割方準備段階で決まるといっても過言ではありません。失敗するユーザーインタビューの設計で一番多いパターンとしては、始めに「ユーザーに聞きたいことをリストアップしていく」という進め方です。特に、サービスに関わるメンバーの人数が多い場合などは、「社内から質問を募る」というケースもあるかもしれません。この進め方の問題点は、「次のアクションにつながりにくい」という点です。例えば、「ユーザーの利用動機を聞いてみたい」という意見をもとにインタビューを設計したとして、インタビューを実施した後に集まった意見が思いのほか表面的すぎて「回答は得られたものの、次にどうしたら良いのかはわからない」といった状態に陥ってしまいます。
聞きたいことベースの進め方だと、
どのような仮説を検証したいのか?
どのようなアクションに繋げたいのか?
という2つの重要な視点が欠けてしまいます。例えば、同じく「ユーザーの利用動機」がテーマとなるユーザーインタビューであったとしても、仮説をもとに設計すると以下のようになります。
仮説: サービス利用者は「他のユーザーとの交流」に魅力を感じているのではないか?
アクション: この仮説が検証できれば、「コメント機能の強化」に取り組みたい
設問設計: この仮説を検証する入り口として、「サービスの利用動機は?」という質問をする
インタビュー実施: インタビュー時に、「交流には魅力を感じているかどうか」が検証されるまで回答を深掘りする
結果の分析: 得られた結果をもとにサービスを改善
この進め方だと、インタビュー実施時にはそれぞれの質問を通してどの程度の粒度と方向性で深掘りをすれば良いのかが明確になる上、得られた結果が必ず次のアクションにつながるようになります。
仮説思考でのユーザーインタビューの設計方法
この仮説思考でのユーザーインタビューの設計方法をさらに詳しく紹介していきます。仮説思考でのインタビュー設計の手順をまとめると以下のようになります。
目的とテーマを明確に設定する
検証したい仮説を洗い出す
仮説が検証された場合のアクションプランを準備する
仮説を検証するための質問を考える
インタビューを実施
1. 目的とテーマを明確に設定する
まずは、そのユーザーインタビューを通して達成したい目的を明確に設定しましょう。ここで目的を設定しておくと、後のステップでそれぞれの仮説や設問がインタビューの目的から逸れていないかの確認が行いやすくなります。半構造化インタビューでは、それぞれの回答について深掘りをしていくため思いのほか実施に時間がかかってしまいます。そのため、あれもこれも聞こうと考えるのではなく、一つの明確なテーマを設定して行うことが望ましいです。また、インタビュー結果を反映したUX改善施策の効果を測定できるように、ここで設定する目標は「変化を計測することが可能な指標」を設定しましょう。
2-3. 検証したい仮説とアクションプランを洗い出す
ステップ2とステップ3は同時に行います。まず、設定したテーマに関して考え得る仮説を洗い出しましょう。そして、それぞれの仮説が正しかった場合と正しくなかった場合それぞれのアクションプランを書き出します。仮説といっても幅広い�ですが、「次のアクションにつながる仮説」という視点で洗い出すと進めやすくなります。ユーザーインタビューの設計段階で、次のアクションプランまで考慮して設計することで、インタビュー実施後にしっかりと次の施策や提案に繋げることができるようになります。また、アクションプランでは具体的なUX改善案を考えることが求められるため、デザイナーとしての強みを活かすことができるポイントでもあります。もし、インタビュー設計者がデザイナーではない場合は、ぜひチームのデザイナーを巻き込んでアクションプランを考えてみると良いでしょう。
4. 仮説を検証するための質問を考える
ここまできてやっと、インタビューでの質問を考えることになります。半構造化ユーザーインタビューにおける質問は、あくまでも「�話題への入り口」として捉えると良いでしょう。入り口となる質問を一つ準備した上で、関連して確認したいポイントを記載しておきます。関連して確認したいポイントについては、「5W1H」を基本として書き出すと様々な観点から情報が得やすくなります。特に、「なぜ?」という部分を確認しておくと、インタビュー後のUX改善に役立つ情報が得られるでしょう。
5. インタビューを実施
これまでの手順に沿ってインタビューを設計すると、インタビュー実施時には「検証したい仮説」「アクションプランの有効性」を意識してインタビューを進めやすくなります。それぞれの質問を入り口として、仮説に関して得られた情報をメモしながらアクションプランの有効性を探りましょう。インタビューの目的と、それぞれの質問に紐づいた仮説が明確になっていることで、どのよう��な方向性でどの程度深掘りするべきかについても分かりやすくなったと思います。
Figma版 & PDF版『ユーザーインタビュー設計テンプレート』
unprintedでは、仮説思考でユーザーインタビューの設計を行うためのテンプレートを提供しています。ユーザーインタビュー設計テンプレートは、Figma CommunityからFigmaファイルをコピーして使うことも、PDFを印刷して手書きで使うこともできるよう2種類のフォーマットで配布しています。どちらも登録やメールアドレスの入力は不要。個人・商用に関わらず自由に使用することができます。
テンプレートに沿ってインタビュー設計を進めることで、仮説思考でインタビュー設計を進めるために必要なステップを辿ることができます。ワークショップのために冊子として印刷してご利用頂くためにも最適な形となっています。
Figma版テンプレートの使い方
印刷用PDF版テンプレートの使い方
インタビュー参加者募集のポイント: サービスに無関心の人にインタビューしても意味がない?
インタビューの設計と同じく、インタビュー参加者として「どのような人を集めるか?」も有益な情報を得るためには大変重要なポイントとなります。端的にいうと、「そのサービスに興味を持っている人」や「そのサービスが解決する課題を抱えている人」に対してインタビューを行うと良いでしょう。単純に、広い意味でのターゲット属性(性別・年代)などで参加者を集めても、サービスの提供価値にはそれほど興味を持っていない人が集まりやすく、表面的なインサイトしか得られません。既存サービスの場合、最も理想的なのは実際のサービス利用者からユーザーインタビュー参加者を募ることです。この場合の募集方法としては、
サービス内でインタビュー対象スクリーニング用のアンケートを行う
インタビュー対象に当てはまるユーザーに対して、アンケートの最後に「ユーザーインタビュー参加」の依頼をする
といった方法をとることが多いです。サービスを普段使っているユーザーであれば、サービスに対する理解やサービスが扱うトピックについての理解も深いため、有用な情報が得やすいでしょう。
ユーザーインタビュー参加の謝礼は支払うべき?
ユーザーインタビューの参加者を募る際に、もう一つ気になるのが「謝礼の設定」ですね。謝礼を設定する場合、1時間程度のインタビューで¥3,000 ~ ¥5,000程度のAmazonやスターバックスのギフトカードを渡すケースが多いです。一般の人から広く参加者を募る場合には、謝礼の設定がないと参加�者が集まらない場合も多いでしょう。しかし、前述のように「サービスに興味を持っている人」や「そのサービスが解決する課題を抱えている人」を対象とする場合は、謝礼ではなく「課題解決への協力」がインタビューへの参加動機となりやすいです。サービス利用者の中からインタビュー参加者を募る場合も同様で、「サービス改善に協力したい」という内的な動機から協力してくれる人を募った方が、効果的に参加者が集まりやすい場合が多いです。このような人を対象として参加者を募る場合、謝礼を設定すると逆に参加者のモチベーションを下げてしまう結果につながることもあります。これは、心理学の分野で「アンダーマイニング効果」として知られる心理現象です。
どこでインタビュー参加者を見つけると良いのか?
参加者を集める方法として、一番簡単なのはインタビュー参加者のリクルーティングサービスを使うことでしょう。この場合には、前述の「サービスに興味を持っていない人」が集まりやすいというデメリットがあるため、しっかりと目的に合ったターゲティングができるかどうかを見極める必要があります。また、このようなサービスを利用する場合には、参加者はモニター登録者であり、謝礼が主なインセンティブになっているという点にも注意が必要です。
では、その他の方法で効果的に参加者を募るためにはどのような方法があるのでしょうか?ここでは、UXデザインの現場で取り入れられているいくつかの方法を紹介します。
1. サービス内で参加者を募る
一つ目は、前述の通りサービス内で参加者を募る方法です。メリットとしては、「実際のサービス利用者を集められる」「ユーザーの定量分析データと紐付けられる」という点があります。この場合は、謝礼の設定も必要なく、一定数の参加者を集めることができるでしょう。ただし、サービス内から被験者募集をするための動線がない場合は追加で開発をする必要が出てきます。簡単にこのような機能を実装する方法としては、「運営からのお知らせ」から「Googleフォーム」で作ったスクリーニングアンケートへの導線を設けるやり方などがあります。
2. Slackなどのコミュニティがある場合はそこで参加者を募る
対象者となるような人が集まるコミュニティがオンライン上にある場合は、そこでインタビュー参加者を探すという方法があります。例えば、フロントエンドエンジニアを対象としたサービスであれば、フロンエンドエンジニアのSlackやDiscordコミュニティなどに入ってみるのも一つの手です。このようなコミュニティを利用する場合、全体向けの投稿としてインタビュー参加者を募ることもできますが、より詳細に対象者を絞りたい場合(経験年数など)には、直接DMなどで一人ずつ声をかけてみた方が良いでしょう。このようなコミュニティでは、自己紹介用のチャネルが設けられていて、それぞれのユーザーに関してある程度の情報が得やすい場合も多いです。
3. Twitterで特定のトピックに関心を持っている人を探してDMを送る
新規サービス開発時で、さらにニッチなトピックに関して関心を持つ人を集める必要がある場合には、インタビュー参加者の募集はさらに難しくなります。このような場合には、やや時間がかかるものの、Twitterで「特定のトピックについてツイートしている人」をターゲティングして声をかけるという方法が有効です。Twitterの検索機能や、APIを使って特定のトピックに関心のあるユーザーをリストアップし、DMを通してインタビュー参加依頼をしてみると良いでしょう。この場合は、あまりにも突然の依頼連絡となるので、ある程度謝礼を設定して募集しても良いでしょう。
ユーザーインタビュー参加者は何人集めれば良い?
しっかりとトピックとの関連性の高い参加者を集められれば、ユーザーインタビューの参加人数は、一般的に5 ~ 6人ほどである程度の傾向が掴めるようになります。多くの人数で一度だけ行うよりは、少人数でも頻繁に行う方がより効果的かつ、継続的にインサイトを得ることができるでしょう。
インタビュー実施: ファシリテーションのポイントは、とにかくリラックスした雰囲気を作ること
仮説ベースでインタビューを設計し、サービスに関心のある参加者を募ればユーザーインタビューの成功は9割方見えているといっても過言ではありません。ここでは、実際にインタビューを実施する際のファシリテーションのポイントを簡単にまとめます。
基本的には、準備段階で設定した
目的とテーマ
検証したい仮説
アクションプラン
の3つを意識してインタビューを実施することで自然と効果的なインタビューを行うことができます。この他��にファシリテーションを行う際の重要なポイントは、「参加者に話してもらうための環境づくり」です。ユーザーインタビューという特殊な環境では、参加者はどうしても緊張しやすく、積極的に話しにくいものです。会社の面接のような雰囲気では、率直な意見は引き出せません。ユーザーインタビューでは、ファシリテーターも堅苦しくなることなく、リラックスしたカジュアルな雰囲気で行うことを意識すると良いでしょう。この、リラックスした雰囲気づくりがインタビュー実施時の一番重要なポイントです。また、インタビューを実施する際に、インタビューアー以外の人が参加することも望ましくないです。対話的な場を作るためにも、可能な限りインタビューはインタビューアーと参加者の一対一で行い、メモについても録音で代用するなどの方法をとることをおすすめします。
その他、よく知られているファシリテーションの技術的なポイントとしては、
回答を誘導しないように注意する
オープンエンド型の質問をする
などの点があります。しかし、この辺りを意識しすぎて堅苦しくなってしまうよりは、自然な雰囲気でインタビューが行えるように努めることの方が重要だと言えるでしょう。
インタビュー結果の分析・改善策実施・効果測定
今回紹介したような仮説ベースでのインタビュー設計を行うと、テーマに沿ったインサイトを得ることができるため、分析と改善策の実施に繋げやすいです。ユーザーインタビューを通して、ユーザーのニーズや課題を明確に把握することができていれば、改善施策による効果が見られなかったとしても、改善の方向性自体を見直す必要はなく、別のデザインやマイクロコピーを試してみるなど、より具体的な実施施策に近い部分でPDCAサイクルを回すことができるようになります。
まとめ
今回は、UXリサーチの最大の武器といっても過言ではない、ユーザーインタビューについて、その効果的な実施方法について紹介しました。インタビューというと、人に意見を聞くだけであるため簡単に思えますが、その設計次第でその効果は大きく異なります。今まで、ユーザーインタビューを行ったもののいまいち次のアクションに繋がらなかったという方も、今回紹介した仮説思考でのインタビュー設計を参考に、今一度インタビューの設計と実施してみてはいかがでしょうか?